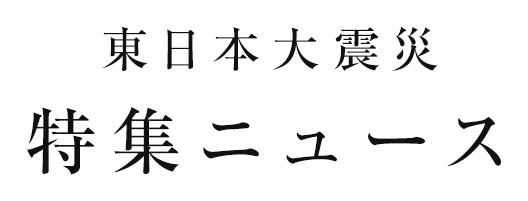電力供給 大災害に備える

オール電化の住宅に電気自動車。私たちの生活はますます電気なくして成り立たなくなっています。それだけに災害時にもどう安定的に電力を供給するか。東日本大震災で大規模な停電を経験した被災地では、この10年間、災害に備えた供給体制を整えてきました。(仙台放送局記者 高垣祐郷)
停電解消に3か月 命脅かされる事態に

東日本大震災の発生直後、東北地方では全体の8割にあたる486万戸が停電しました。すべての停電が解消されたのは、3か月以上たった6月18日。

宮城県石巻市の病院では、患者のたんを吸引する機械も使えなくなり、看護師が注射器を使って処置しました。
交代で24時間看護を続け、夜には懐中電灯とランタンに頼りました。
岩手県釜石市では、停電などの影響で医療機器が使えなくなり、患者8人が死亡しました。
電気がないことで被災者の命が失われる事態が起きていたのです。
長期化の理由は発電所でなく○○○

このとき東北電力では、何が起きていたのか。
宮城県にある女川原子力発電所や太平洋側にある火力発電所の多くが運転を停止していました。
日本海側の発電所は無事でしたが、電力の供給力は半分以下に落ち込み、地域ごとに停電する「計画停電」が検討されました。
首都圏では実際に計画停電が実施されましたが、東北では地震と津波の被害で経済活動がとまり、電力の需要も減っていたことから、計画停電は回避されました。

実は停電が長引いたのは、発電所が運転を停止したからではなく、「変電所」が被災したことが要因のひとつだと言われています。
変電所は、電気を適切な電圧に戻して各家庭に分配する地域の電力供給の拠点です。
しかし配電盤などの重要な設備が水に浸かり、電気を届けられない状況になりました。
対策1 津波に強い施設へ

震災後、東北電力はこの教訓をいかそうと、変電所の津波対策に力を入れてきました。
わたしが訪れたのは、宮城県石巻市の重吉変電所です。
震災前はハザードマップで津波の高さは0メートルと予想されていました。しかし実際には6メートルの津波に襲われました。
そこで平屋だった建物を3階建てにし、ほとんどの設備を震災で起きた津波以上の高さに移しました。

また建物の形も工夫しました。1階部分には津波を受け流すスペースを設けました。
このほかの変電所も、高台に移すなどそれぞれの土地にあった対策を講じています。
対策2 送電網を充実

また地域間で電気をやりとりする送電網も充実させました。
2017年、山形県と新潟県をつなぐ送電線の運用が始まりました。

震災時、山形県では宮城県からの供給が途絶え停電が起きました。
このため新潟県からも電気を送れるようにしたのです。

東北電力ネットワークの阿部智主査は「震災の被害は想定をはるかに上回るものだった。自分の経験を震災を知らない若い社員に伝えていく必要がある。さらなる対策についても前向きに検討したい」と話していました。
対策3 自衛隊との連携
さらに設備が被災した際に復旧にかかる時間を短くする取り組みも進めています。
そのための切り札が自衛隊との連携です。
震災の2年後に協定を結び、年1回は合同で訓練を行うようにしました。
なぜ自衛隊との連携なのか、それは自衛隊の大型ヘリで、被災地にいち早く、電源復旧に必要な車を送れるようになるからです。
自衛隊と何度も打ち合わせを重ね、東北電力は大型ヘリに載せることができる小型の電源車を開発しました。
訓練では孤立した集落や島で停電が起きたことを想定し、運用の手順を確認しています。
こうすることで迅速に電力を復旧できる体制を整えようとしています。

こうした連携の効果は、2019年の台風19号の際に発揮されました。
被害が大きかった宮城県南部の丸森町筆甫地区では、土砂崩れや道路の陥没で、作業用の車両が現場に入れませんでした。

このとき東北電力の状況を知った自衛隊が筆甫地区に向かい、道路の整備にあたりました。
この道路を使って東北電力の車両が現場に入り、停電の復旧作業にあたったのです。

当時、自衛隊とやりとりした東北電力ネットワークの高橋充広副長は「当時は道路の被害もひどく、電気をいつ届けられるのかという不安があったが、自衛隊から協力してもらったことが早期復旧につながった。今後も訓練などを通して意思疎通がはかれる環境を維持していきたい」と話していました。
自前の発電所で災害に備える

一方、自前の発電所で災害に備える自治体も出てきています。
福島第一原発の事故で住民が5年以上避難生活を余儀なくされた福島県葛尾村です。
第三セクターの電力会社を立ち上げ、今年度から運用を始めました。

発電に使う太陽光パネルは休耕田に設置しました。
アメリカの電気自動車メーカー、テスラ社の蓄電設備を購入し、およそ100戸の住宅とつないでいます。

自前で供給できる電力は全体の半分ほどですが、災害時に外部からの電力供給が途絶えても、最低3日間は避難所や役場に供給できるといいます。
発電所の整備にはおよそ8億円かかり、国からの補助金を除くと3億円を第三セクターの会社が負担しています。
それでも発電した電気を売ることで、費用は20年以内に回収できる見通しだということです。

会社の社長を務める葛尾村の松本弘副村長は「まず3日間耐えしのぐことができれば、外からの電力供給が再開される可能性がかなり高くなる。初期投資の負担はあるが、地元の会社にお金が落ちることで経済活性化にもつながる」と話していました。
震災から10年、あの時のような事態を引き起こしてはならないという関係者の思いが、それぞれの対策につながっていました。
いまや日本のどこかで毎年のように「被災地」と呼ばれる場所ができています。
人々の生活になくてはならない電気を途絶えさせない取り組みは、ますます重要になっていると強く感じました。

仙台放送局記者
高垣 祐郷
平成26年入局
山口局、秋田局を経ておととしから仙台局で経済担当