東北のすごいいちご

真っ赤に熟れた大粒の甘いいちご。大好きなフルーツの1つです。「東北にすごい、いちご農家がいる」と聞き、現地に向かいました。どんないちごでしょう。(経済部記者 池川陽介)
デパ地下の“センター”に

東京 新宿のデパート「伊勢丹」の“デパ地下”。
そのいちごは、和歌山産「まりひめ」や熊本産の「あその小雪」といった高級いちごとともに、フルーツ売り場の中央に構えていた。

「MIGAKIーICHIGO」(ミガキイチゴ)。
形はきれいな逆三角すい。1粒1粒丁寧に包装されている。
もっとも高いものは12個入りで税込み8640円。軽い気持ちで買える価格ではない。

最先端技術でいちご栽培

このいちごは宮城県山元町産。生産しているのは農業ベンチャー「GRA」。
2月下旬、現地のハウスを訪ね、社長の岩佐大輝さん(43)に話を聞いた。

外は寒かったが、ハウスの室温は、15度から20度に保たれ、上着を着ていると暑いくらいだった。ハウスは、温度や湿度、二酸化炭素の濃度、それに日照時間まで、すべて自動管理されているという。
いちごをつくって40年という地元のベテラン農家から詳しく聞き取ったノウハウや経験をデータベース化したシステムだ。

「いちごの栽培といっても、全国一律ではありません。九州と東北では、気候や環境が全く異なり、栽培方法も違います。システムの力で、地元のベテランしかできなかった高品質ないちご栽培を誰でもできるようにしたいと思ったのです」
被災した故郷でできること

山元町は岩佐さんの故郷。
いちご栽培をはじめたきっかけは、東日本大震災だった。当時は33歳。東京でITベンチャーを経営していた。
「10年前、変わり果てたふるさとの姿を見て、価値観が大きく変わりました。震災前から衰退が始まっていた故郷をもとに戻すだけの復興なら意味は無い。どうせやるなら、日本一、世界一を目指そうと考えた時、地元特産のいちごならできると思ったんです」
いちご栽培の常識に挑む
故郷に戻って、津波の被害を受けた農地を借りハウスを建て、一からいちご栽培を学んだ。
農業は全くの素人。だからこそ「いちご生産の常識」にびっくりすることも少なくなかった。例えば、次のような話だ。
「店に並ぶいちごの多くは、完熟でない」
いちごは、生産者が摘み取ってから消費者の手にわたるまで、通常3日~5日かかる。農協や市場を通し消費地まで運ばれるためだ。
その間に、悪くならないよう実が固いうちに収穫するのが慣例だった。摘み取った後、追熟で色は赤くなるけれども、甘みは増さない。

「いちご狩りのときのような甘いいちごを消費者に届けたい」
岩佐さんは、完熟いちごの出荷を始めた。摘み取ってすぐ販売店に直送するようにしたいちごは「甘さが違う」と評判になった。
素人が普通にやってもゲームには勝てない

ブランドいちごといえば、どんなイメージだろうか。栃木の「とちおとめ」、佐賀の「さがほのか」などが有名だが、これらは品種名だ。
岩佐さんは、品種にはこだわらず、一定以上の大きさや色つきのいちごを「ミガキイチゴ」というブランドとして売り出した。
大きくて甘い実をつける「とちおとめ」「もういっこ」といった5つの品種をローテーションし高品質のいちごを11月から5月まで長期間、安定出荷できるようにした。
「素人が普通にやってもゲームには勝てない。まず小さくても成功のモデルをつくることができれば、そこからチャンスが生まれると考えたんです」
失敗の共有で、経験値“上げる”
岩佐さんは、いま仲間づくりを進めている。苦労して開発したハウス栽培のシステムを、熱意ある新規就農者に惜しみなくシェアしている。

「いちごの収穫って、ITの世界のようなデジタルと違い、いわゆるPDCA(計画→実行→評価→改善)のサイクルが1周するのに21か月かかる。1社だけでやっていたんでは改善のスピードが遅いのです。だから多くの経営体で集団主義で農業をやっていくのがいいと思った。きょうどれぐらいいちごが採れたか、糖度がどれぐらいだったかっていう情報をみんなで共有すれば、テンポよく成長できる」
自分1人だと、成長のスピードには限界がある。
できるだけ多くの成功体験、失敗体験を共有すればスピードはあがる。単純計算で、2人いれば、2倍の、3人なら3倍の経験が積めるということだ。
岩佐さんのもとでいちご作りを学んだ13人がいま、各地で高級いちごの栽培を始めている。その1人、高橋俊文さん(44)は、こう言う。

「仲間の話を聞き、肥料のやり方や、湿度などを工夫する。互いに切磋琢磨できるので、やる気がわく」
いい意味の競争も生まれていると話してくれた。
震災前より地域の魅力を高めたい。
2011年、小さなハウス2棟から始まった岩佐さんのいちご栽培。13人の仲間を含めると、およそ130倍にあたる6.6ヘクタールに拡大した。
販売先もデパートや洋菓子店など全国280店舗、グループ全体の売り上げはおよそ10億円になった。
生産だけでなく、2017年から都内で直営のカフェを開始。いちごを使ったスイーツなどを販売している。

さらに、海外展開を目指して、インドやカナダなどで現地で試験生産も始めた。
「震災前より地域の魅力を高めることが『復興』だと思うんです」
岩佐さんはそう話した。

経済部記者
池川陽介
平成14年入局
仙台局、山形局などを経て現所属


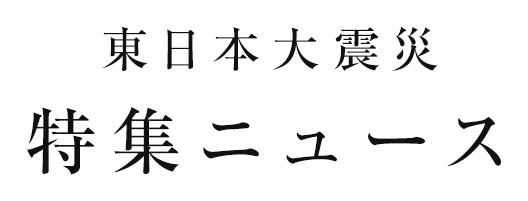
「ミガキイチゴは、個包装で高級感を出すなど、新しい手法で、大きな注目を集めています。新しい高級品種が毎年、次々と売り出されていますが、ミガキイチゴには固定ファンが多く、安定した人気のブランド。売り場には欠かせない商品です」