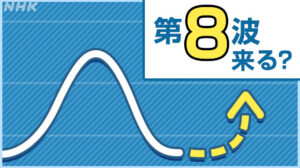科学と文化のいまがわかる
文化
文化の灯を絶やさない

“映画文化を絶やさない” 河瀨直美監督の思い
2020.11.19
カンヌ国際映画祭のグランプリなど数々の賞を獲得した奈良出身の映画監督、河瀨直美さん。
河瀨さんが運営に関わる、「なら国際映画祭」が9月に世界文化遺産の東大寺などを舞台に開催されました。
新型コロナウイルスの感染拡大で、映画産業が岐路に立ついま、どのような思いで映画祭の開催にこぎ着けたのか。
そして、映画づくりにどのような思いを込めているのか、聞きました。
心の中に、光をポッとともす
新型コロナウイルスの影響が続く中、第6回目となることしの「なら国際映画祭」の開催は危ぶまれていました。河瀨さんも多くの仕事が制限され、無気力の状態にさいなまれていましたといいます。
「東京オリンピックも延期になり、自分の映画も公開できなくなり、さまざまなイベントなんかも全部中断してしまって。一体、答えがどこにあるのか分からなくなって。いっときは家の中で、ずっとぼんやりしているという時間だったんですけど。すごくつらかったですね」
それでも“ウイルスには負けたくない”と気力を奮い立たせ、映画祭メンバーとリモートで開催実現にむけて話し合い続けました。

「『なら国際映画祭』を開催するためには、どうすればいいかって。自分一人ではできない、本当にたくさんの人たちの力と、何かが寄せ集まらないとできないこと。やらないというのは、ある意味、コロナに持っていかれちゃっているということなので、やっぱり、そこで、行動を起こしていく。対処しながら行動を起こしていくということが必要なんだろうなと」
議論の末、チケットの販売数を半分に減らし、観客の距離を確保するようにしました。映画祭入場時にはマスクの着用、検温、アルコール消毒など感染予防を徹底。インターネットでの配信も行い、映画祭の新たな形を模索しました。
河瀨さん自身にも変化が訪れていました。
「河瀨というと本当にリアリティーを追求する、実際に会うということを重要視しているから、配信とかはないだろうと思われていた。今回、『えいや』、という感じにせざるをえなかったということですが、新しいチャレンジをすることで次につながる。考え方の転換ができました。やらないよりやるということですね。やるということは、みんなの心の中に、光をポッと、ともすことにもなると思いました」
世界中の映画祭が中止に追い込まれる中での英断に、海外の映画界の重鎮たちから、続々と期待の声が集まったといいます。

「世界三大映画祭の代表、カンヌ、ベネチア、ベルリン。それからトロント、釜山、中国という、もう本当、世界の主要な映画祭の代表からメッセージが来ているんですよ。私が『なら国際映画祭』に寄せる思いに、向き合ってくださって、ものすごく共感していただいていてですね。そこに対してメッセージをくださっている、とても感動的です」
奈良から世界へ

奈良を世界にアピールしたいと10年前に立ち上げ、2年に1回のペースで開催されてきた「なら国際映画祭」。河瀨さんを開催へと後押ししたのは、連綿と受け継がれてきた奈良の歴史でした。
「東大寺の大仏様もそうですし、興福寺の中金堂もそうですし。いつも再建する人がいる。地震とか災害によって、屋根がなくなっちゃうとか、まあ、そういうこともあるんですけど、でも、そういうときを乗り越えて必ず再建されるんですよ。何かあっても未来を思って再建するという心が奈良の精神かなって思っていて。それを今、私も自分のアートの世界でやりたいなと」
河瀨さんは今も暮らしの拠点を奈良に置いています。映画作りの合間をぬって奈良の自然や人々の営みを記録するのがライフワークとなっています。

「20代の前半ぐらいって、やっぱり、どんどん出ていきたいじゃないですか? 都会とかに出ていきたいし、海外にも行きたいと思うけど、そう思いながら奈良で暮らすと、『あ、きれいだな』って思うものは、そこにあるんです。どうしてこの場所じゃない所に行かなきゃいけないのかっていうぐらい。映画を撮り始めてから私たちは何かを見失っているのかもしれないって気付かされた。カメラのまなざしを通して、何か生きていく豊かさを感じることができた」

映画文化を絶やさない
この夏は奈良を舞台に13歳から18歳の若者たち11人と短編映画を製作しました。
作品で描くテーマは「生きる」「つながる」。
若者たちが奈良の人々に話を聞き、決めました。
河瀨さんは、新型コロナは若者たちのまなざしにも大きな影響を与えていると感じたといいます。

製作過程で河瀨さんが意識したのは、自分の価値観を押しつけるのではなく、若者たちの感性に寄り添うこと。
できあがった作品は、映画祭で上映し、観客からは「この時代にこそ必要な取り組み」「10代だからこそ撮れたとも思える作品」という感想がありました。

「つくりたいもの、伝えたいことが彼らにはあるんですよ。これまでのワークショップって、大人が『こうしたほうがいいよ』みたいなことを結構、言っちゃって、その枠の中に彼らをはめていこうとするものが多かったんですけど、私たちの映画制作ワークショップは、完全に放置するんですよね。私自身、学んできた、この日本の学校教育とか、その社会の中では、どうしても敷かれたレールとか、限られた箱の中、時間の中でしか、学べなかった印象があってですね。育てたいというよりも、そういった場を、もっとたくさん創出したい」
「将来映画に就く仕事がしたいと思えるようになった」と語る若者もいました。
河瀨さんは地元で映画を作り続ける自らの責任として、これからも新たな映画文化を奈良から発信していきたいと言います。

「若いときは何もできないと思っていたのは、やっぱり、その何かができる自分に、まだなってないということ。それに気付かされたかなという感じ。今も全然できてないと思うんですけど、ある種の役割として、次に何かを渡していく。中堅世代というか、50代に突入したんですけど、ここまで生きてくると、やっぱり、ある意味、人のつながりが、いかに大切かということを本当に目の当たりにするんですね。決して『自分が、自分が』、じゃなくて、自分たちの役割をしっかりと持ちながら、つながり合えるということ、何かそういう場を、なら国際映画祭は創出したいなというふうに思っています」
そして、最後に、新型コロナウイルスの感染拡大で、社会の姿が大きく変わろうとしている中、映画や芸術をどう守っていくか、模索し続けていると語りました。

「伝統芸能からコンサート、演劇、映画、美術展まで、さまざまな分野で発表の場を奪われているということは、そういうものによって心が温かくなったりとか、人に優しくしようと思ったりとか、そういう機会も奪っていくことになるんですね。一足飛びに何かが解決するわけじゃないんですが、こういうことは必ずまた起こるから、今回のような有事のときにだけ何かをやるんじゃなくて、平時のときにも、なにかが起こったときに何とかできる、そのシステムをつくっておかないと駄目だよね、というふうに感じています。
日本のアートに対する支援などは、明らかに諸外国より、まだまだ、できてないという現状があります。なぜ、それが日本でできないのか、いま、そういうところを考え始めている感じです。
アートに関わる人たちみんなで、芸術を守る社会に導いていくということを一歩一歩なんですけど、探し始めています」