いないなら育てよう!
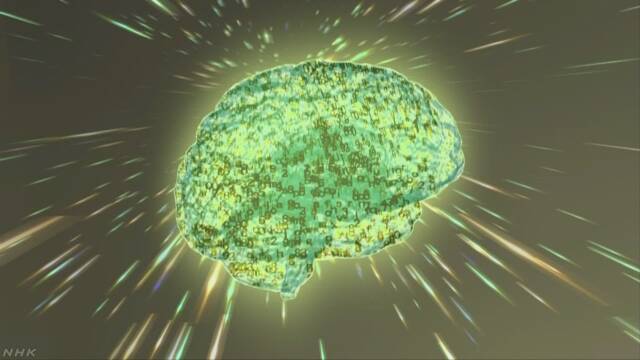
AI(人工知能)の活用が広がり、企業の間で専門性の高い技術者の獲得競争が激しくなっています。どうやって人材確保を図るのか。お給料アップかと思いきや、東芝はほかの会社とは少々異なる戦略を打ち出したそうなんです。どのような戦略なのか、経済部の猪俣英俊記者、教えてください!

少々異なる戦略ってどういうものでしょうか?
 猪俣記者
猪俣記者
「足りないなら育てよう!」
ひと言で言うとそういう戦略です。

東京大学大学院の情報理工学系研究科と連携して、今いる社員にAIの専門的な技能を身につけてもらうための独自の育成プログラムを開発したんです。
東大の研究者を講師に招き、社員がおよそ3か月間、講義や演習を受けます。
例えば、ロボット化によって工場の生産効率がどう変わるか?蓄電池の性能を図るテストのデータから商品開発にどうつなげるか?東芝が持つ現場の“生のビッグデータ”を活用することで実践的な技術を短期間で習得してもらおうというのがポイント。
実は大学の研究者にとっても、機密性が高い大手企業のビッグデータに触れられることはメリットになるんだそうです。

技術者の育成ってそれほど簡単ではない気もしますが、リアルなデータを使うことがカギなのですね。
 猪俣記者
猪俣記者
そうです。このプログラムを始めるのは12月から。専門性の高い人材を、年間100人規模で育成したい考えです。
今、会社には750人のAI技術者がいるんですが、プログラムの導入に加えて、新卒や中途の積極的な新規採用も続け、2022年度までに3倍近い2000人規模に増やす計画です。

ここまで育成に力を入れなきゃいけないほど、AIの技術者っていないんですか?
 猪俣記者
猪俣記者

AIなどの先端分野に通じた専門性の高い人材は、世界的に不足しています。特に日本では、人口減少で労働人口も減るため、人材の獲得がさらに難しくなっていくとみられています。
経済産業省の調査(2016年公表)では、2020年の時点で、国内ではおよそ4万8000人の人材が不足すると推計されています。人材不足を補うことができなければAI市場も拡大しないし、日本の成長率にも影響すると思うので、デジタル時代がどこまで進んでも、やはりカギになるのは「人の力」なんです。

ほかの企業はどうやって人材獲得に力を入れているのでしょうか?
 猪俣記者
猪俣記者
やはり報酬の引き上げです。
例えば富士通は、AIなどの先端分野で高い専門性を持つ社員を「高度人材」と位置づけ、勤続年数にかかわらず、能力しだいで3000万円から4000万円の年収を得られるようにする仕組みを年度内に導入することを目指しています。
NECは、研究職の社員を対象に、新卒であっても大学時代に論文が高い評価を受けるといった実績があれば、年収が1000万円を超えるという新たな制度を10月から導入しました。
ソニーも、AIなどの分野で高い能力を持つ新入社員の給与を最大で2割増やす取り組みを始めています。
東芝は、今の時点では報酬の引き上げは考えていないとしていて、今の戦力の育成に軸足を置くことになります。高度な技術を持つAI人材の確保はどの企業にとっても待ったなしの課題ですから、貴重な自社の人材をいかに育成していくかも、大事な戦略になりそうです。
# 注目のタグ
- # 新型コロナ (51件)
- # 暮らし・子育て (34件)
- # 銀行・金融 (34件)
- # 環境・脱炭素 (33件)
- # 自動車 (28件)
- # AI・IT・ネット (27件)
- # 財政・経済政策 (24件)
- # 働き方改革 (21件)
- # 給与・雇用 (21件)
- # 日銀 (19件)
- # 企業の合従連衡・業界再編 (18件)
- # 消費税率引き上げ (17件)
- # エネルギー (17件)
- # 農業・農産品 (15件)
- # 原油価格 (14件)
- # 人手不足 (14件)
- # 物価高騰 (13件)
- # 外食 (13件)
- # 旅行・インバウンド (12件)
- # 株式市場・株価 (12件)
- # 景気 (12件)
- # 経済連携・貿易 (12件)
- # ウクライナ侵攻 (11件)
- # 携帯料金 (10件)
- # コンビニ (10件)
- # お酒 (10件)
- # 携帯電話 (9件)
- # 鉄道 (9件)
- # キャッシュレス決済 (9件)
- # 為替 (9件)

