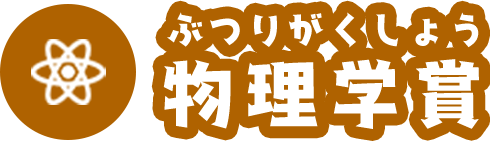次のノーベル賞を目指せ 「KAGRA」の挑戦

今から100年余り前、アインシュタインが「一般相対性理論」の中で存在を予言しながら、長い間、観測されなかった「重力波」。初めて観測に成功したアメリカの研究チームを主導した3人の研究者におととし(2017年)、ノーベル物理学賞が授与されました。今後も未知の天体現象を観測することができると考えられていて、日本でも巨大な施設が完成し、「KAGRA(かぐら)」と名付けられて、ことし中の本格稼働を目指しています。
KAGRAとは
「KAGRA」は、岐阜県飛騨市の山中にことし(2019年)10月に完成した重力波の観測施設です。
施設は、長さ3キロの2本のパイプをL字型に組み合わせた構造で、地下200メートルの振動や温度変化の少ないトンネルの中に設置されています。
重力波は、質量のある物体が動くと空間のゆがみが波となって伝わる現象で、宇宙で星が爆発するなどの激しい現象が起きて地球に到達すると空間がゆがみ、「KAGRA」の2本のパイプの長さがごくわずかながら変化すると考えられています。

「KAGRA」のパイプの中には、レーザー光線が通っていて、パイプの長さのわずかな変化を捉え、重力波を観測する仕組みです。
重力波は、すでに、アメリカのチームが4年前に初観測を果たし、ノーベル賞を授与されていますが、「KAGRA」の研究代表者を務める、2015年のノーベル物理学賞受賞者、東京大学宇宙線研究所所長の梶田隆章さんは、その意義について、「重力波でなければ調べられない宇宙の現象を世界と協力して調べていく上で日本のKAGRAの存在意義はすごく大きい」と話しています。
重力波は未知の天体現象を観測するための新たな観測手段として、「マルチメッセンジャー天文学」という新しい分野で、盛んに利用されるようになっているのです。
おととし(2017年)8月にはアメリカの観測施設「LIGO」と、ヨーロッパの観測施設「Virgo」が共同で重力波を捉え、初めて2つの中性子星の合体という天体現象を観測することに成功しました。
“いま、新しい天文学が生まれている。まさにその瞬間に立ち会っている”
「KAGRA」は、ことし中の本格稼働を目指して、観測装置の最終的な試験や調整を進めていて、10月4日には現地で完成記念式典が予定されています。
今後、ブラックホールの合体のような光では見ることが難しい現象の観測や、超新星爆発が起きる仕組みなどを理解することに役立つと考えられています。
梶田さんは「本当に今、新しい天文学が生まれている、まさにその瞬間に立ち会っているので研究者として非常に良い時期に生きていると思います。新しい予期しないことが出てくると思うのでそれを楽しみに待ちたい」と話していました。

科学文化部
春野 一彦(はるの かずひこ)
平成15年入局。鹿児島放送局を経て、平成21年から科学文化部で主に宇宙分野の取材を担当。小惑星探査機「はやぶさ」の地球帰還をオーストラリアの砂漠で目の当たりにした。平成27年から3年間、京都放送局で「iPS細胞」の取材などを担当し、平成30年から再び科学文化部で取材。