高校生の長女は、どこの大学に進学しようか悩んでいました。
そんなとき父親は、長女と一緒に都内の大学のオープンキャンパスを訪れました。
春にたくさんの桜が咲く、きれいなキャンパス。
案内してくれた親切な学生との出会いもあり、長女はこの大学への進学を決めました。
教師になることを目指して。
でも、それは叶いませんでした。
よく晴れた日の朝、歩道を歩いていただけなのに。
(横浜局 横須賀支局記者 米澤直樹)

2021年5月20日事故
高校生の長女は、どこの大学に進学しようか悩んでいました。
そんなとき父親は、長女と一緒に都内の大学のオープンキャンパスを訪れました。
春にたくさんの桜が咲く、きれいなキャンパス。
案内してくれた親切な学生との出会いもあり、長女はこの大学への進学を決めました。
教師になることを目指して。
でも、それは叶いませんでした。
よく晴れた日の朝、歩道を歩いていただけなのに。
(横浜局 横須賀支局記者 米澤直樹)

父親は職場にかかってきた電話で、その知らせを受けました。
家族ぐるみで付き合いのあった同僚が泣きながらこう言いました。
「娘さんが意識不明の状態で運ばれた」
何を言っているんだ…
すぐには理解できなかったし、信じたくもなかったといいます。
父親
「仕事の話かと思って電話に出ると『娘さんが意識不明で病院に運ばれた』と言われ、頭が真っ白になりました。冗談なのかなと。相手が泣いていて訳がわかりませんでしたが、タクシーが拾える場所ではなかったので、急いで電車で向かいました」
病院に駆けつけ、長女と対面した父親。
ほおにそっと手を当てると、まだ温かく感じたといいます。
なぜこんなことに。
どうして娘が死ななければならないのか。
それを明らかにしたいと、「お父さんがかたきをとるから」というような言葉をつぶやいたのを覚えています。

事故が起きたのは、去年2月5日の午前8時ごろです。
神奈川県逗子市の住宅地にある道路脇の斜面が、突然崩落。
およそ66トンの土砂が一気に崩れ落ち、下の歩道を歩いていた18歳の女子高校生の命を奪いました。
都内に遊びに行く途中で起きた悲劇でした。

亡くなった女子高校生には、妹がいます。
父親は今回、多感な年頃の妹の心に負担をかけたくないと、家族の名前や顔写真などを出さないことを条件に、取材に応じてくれました。
父親によりますと、亡くなった長女は小学生のとき、東日本大震災の復興支援の活動に携わりました。
そのころの夢は、保育園の先生でした。
父親
「争いごとが嫌いで、ひと言で言うと優しい子でした。誰にでも平等に接する子だったので、『先生とかいいね』と家族で話していました」
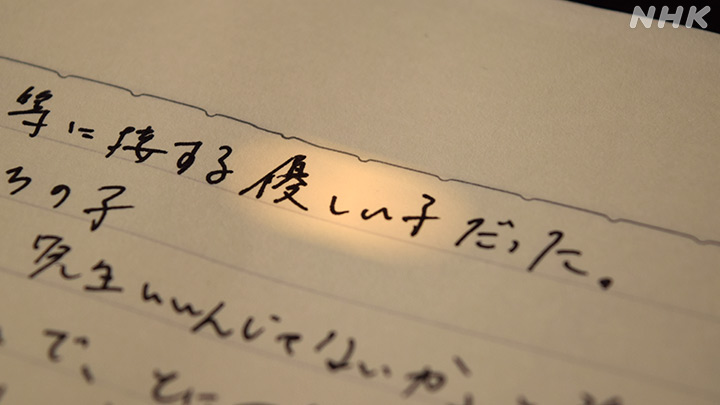
高校に入る頃には、マスコミ関係の仕事にも関心が出て、大学選びに迷っていたそうです。
そんなとき一緒に訪れた、大学のオープンキャンパス。
それがきっかけとなり、この大学に教師を目指して進学することを決めたといいます。
父親
「案内してくれた学生が『自分もジャーナリスト志望だったけど、この学校に来てから学校の先生を目指すようになった』と話してくれたんです。そんな出会いもあり、最終的に『この大学を受けたい。教師になりたい』と決めたようです」
「長女は妹思いで、アルバイトで稼いだお金で妹をディズニーランドに連れて行く約束をしていました。葬儀には、たくさんの友だちが来てくれて、これだけの人に慕われていたのかと、親の私たちもびっくりしました」
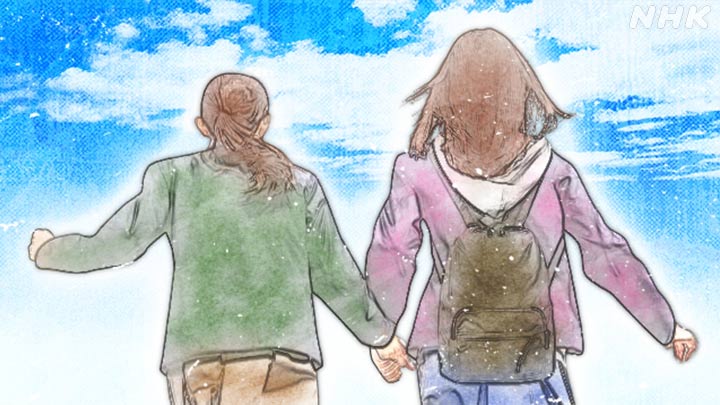
事故はなぜ起きたのか。
県の調査で、崩落の原因は、“岩の層の激しい風化”によるものとされています。
崩れた斜面は、「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」に指定されていましたが、逗子市によりますと、喫緊の対策を講じなければならない場所という認識はなかったということです。
ただ崩落の前日、斜面の上に建つマンションの管理人が亀裂を見つけ、管理会社に報告していました。

亀裂は、長さおよそ4メートル、幅およそ1センチ。
その日のうちに管理会社から県の土木事務所などに連絡がありましたが、「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の指定に向けた調査日程を教えてほしい」といった内容にとどまり、亀裂については具体的に報告されなかったということです。
神奈川県の担当者は会見で、次のように話しました。
県の担当者
「できることは限られ、非常に難しかったと思うが、危険だと判断できていたら市道を管理する逗子市に情報を提供して通行止めにするなど、対応を取れた可能性もある」

崩れた斜面の所有者は、区分所有者であるマンションの住人たちです。
住人や管理会社は、この斜面についてどういう認識だったのか。
インターフォン越しに話を聞かせてくれたマンションの住人の1人は、言葉少なに、次のように話しました。
住人の1人
「自分の住むマンションの敷地に斜面が含まれていることは知っていたものの、まさか崩れるとは思いませんでした。しかも雨でもない日に崩れるなんて想像もしませんでした」
女子高校生の命を奪った崖崩れ。
取材を進めると、神奈川県、とりわけ横浜市の南部から横須賀市や逗子市などが位置する三浦半島にかけて、繰り返し起きていたことがわかりました。
2012年、横須賀市で私鉄沿線の斜面が大雨で崩れ、車両が脱線する事故が発生。
50人以上が重軽傷を負いました。

2014年には、台風による大雨で横浜市内で斜面が崩れ、住宅などに土砂が押し寄せて2人が亡くなりました。

なぜ、これらの地域で被害が相次いだのか。
高度経済成長期、人口の急増に伴って住宅需要が高まり、丘陵地を切り開いて宅地が造成されました。
その結果、斜面や崖の上に建てられる住宅やマンションが林立し、被害も増えたのです。
県のまとめでは、去年1年間に起きた土砂災害は104件(風雨が原因も含む)。
実に全国で3番目に多い数です。
繰り返されてきた被害に、行政はどう対応してきたのか。
横浜市では、2014年に相次いだ土砂崩れを受けて、市内の斜面およそ1万か所を調査し、対策を進めようとしました。
ところが、ある問題に直面したといいます。
それは、「民有地」の壁です。
崩落の危険がある斜面や崖のほとんどが、個人や企業などが所有していたのです。
行政としては、所有者の同意なしに対策を進めることはできないため、所有者に対策を取るよう促す手紙を送ることしかできないのが実情でした。

横浜市 成田充 建築防災課長
「危険度が高い場所については、極力機会を捉えて改善を促していますが、民有地ではどうしてもお願いベースになってしまいます。所有者が抜本的な対策に踏み切れるだけの十分な財政支援をする余裕もないため、行政としてできることには限界があると感じています」
では、所有者は、崩落のリスクについてどう考えているのか。
事故が起きた現場とは別の斜面の所有者に、話を聞くことができました。

逗子市に住む大野智樹さん(49)は、10年前に父親から実家の土地を相続した際、高さ17メートルの崖が敷地に含まれていることを初めて知りました。
その崖は風化が進んでいたため、何らかの対策が必要と考えた大野さんは、県の対策事業に応募しました。
しかし、県の回答は「工事までは7~8年程度かかる」というものでした。
大野智樹さん
「工事は順番待ちの状態で、あとから『さらにあと10年くらいかかるかもしれない』と言われました。税金を使って工事を行う以上、遅いとも言えないですし、一方で気象が凶暴化するなかで、崖はいつ崩れるかも分からない。どうしたらいいか困っています」

県の事業を待つ中、去年、実際に崖の一部が崩れました。
そして崖の下に住む人たちの不安を取り除くため、応急的な対策工事を余儀なくされました。
市の助成制度を利用したものの、これまでに200万円近くの費用がかかっています。
これ以上の出費は厳しく、いつ始まるか分からない工事を待たざるを得ないのが現状だといいます。
県によりますと、安全対策は「原則、所有者が行う」としていますが、各地域から要望が寄せられる中で、優先順位をつけて年間200件ほど工事や調査を行っているということです。
◎個人で対策するには、負担が大きい。
◎行政は、所有者の同意なしに対策できない。財政面で限界も。
こうした状況を踏まえて何が求められるのか、地盤工学の専門家に話を聞きました。

専門家は「土地の所有者に、“リスクを含めて所有している”ということを認識してもらうのが第一歩となる」と指摘した上で、次のように話しました。
関東学院大学 規矩大義 教授
「喫緊で対策が必要な土地については、行政がバックアップや補助を強化できる仕組みがあってもいい。差し迫った危険を除去したり、二次災害を少なくしたりする対策もある。莫大なお金がかかる対策がすべてではないので、さまざまな情報や選択肢を所有者に示すことが重要」
長女を亡くした父親は、ことし2月5日の命日に「斜面の管理責任を明確にしたい」とマンションの住人や管理会社などに対し、賠償を求める裁判を起こしました。
食卓には、いまも長女の分の食事を欠かさず用意しているという父親。
裁判への思いをこう語りました。
父親
「率直に言って人災だと思っています。18歳ですよ。なんでこんな死に方をしなければならなかったのかというのが親としては一番なので、親の責任としてきちんと対応したい」
「単純に娘を返してほしいけど、帰ってこないじゃないですか。それならば娘のために何をしてあげられるのかを考えて、自分を鼓舞というか、自分自身に言い聞かせてやっていこうと。長女も『お父さん頑張って』と言ってくれていると思います」

土砂によって未来を絶たれた、ひとりの女子高校生。
「ただ返してほしい。長女がいたときに戻りたい」
父親は、悲しみや怒りを押し殺すように冷静な語り口で、話を聞かせてくれました。
今後、同じような悲劇を繰り返さないために、斜面のリスクをどう把握し、安全を担保していくのか。
取材を続けていきたいと思います。

横浜放送局 横須賀支局 記者
米澤直樹 2014年入局
札幌局・北見局を経て2019年から現所属


「どうして代わってあげられなかったんだろう」能登半島地震 珠洲市で土砂崩れに巻き込まれ、家族4人を亡くした警察官の大間圭介さんは
2024年2月1日