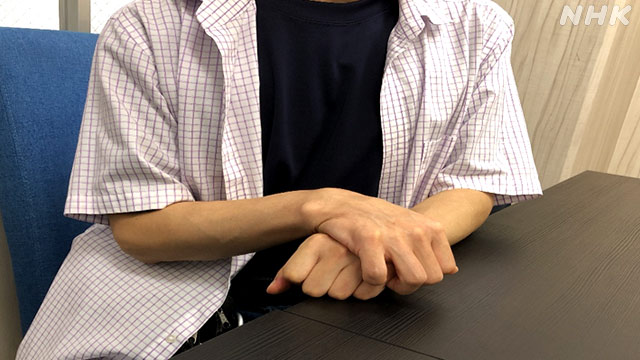「もう自分には生きている意味がない。将来の不安は、死に損なったことだ」
82歳の母親を亡くした40代の男性の言葉です。
男性は20年以上にわたってひきこもってきました。
ひきこもりの末、頼ってきた家族を亡くし、直面した孤独と絶望。
その胸の内を話してくれました。
(ネットワーク報道部記者 秋元宏美 管野彰彦)
母の死
長崎県内に住む山崎和人さん(仮名・40代後半)
去年6月、長年、一人で育ててくれた82歳の母親を亡くしました。
母を失った悲しみと心の痛みが、今も心を占めているという山崎さん。
NHKのひきこもりの特設サイト「ひきこもりクライシス」に投稿を寄せてくれました。
(山崎さん)
「生きる意味はもうない。今から何かをやるなんて、もう無理ですよね」
会って話をしてもいいと言って下さり、直接お会いしてみると、暗い印象はなく、
ことば数は少ないながらも1つ1つの質問に答えてくれました。
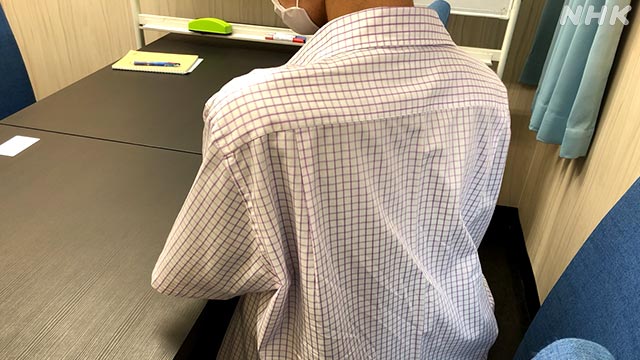
ひきこもりのきっかけは
小さな頃から他人とのコミュニケーションがうまくいかなかった山崎さん。
クラスメイトとの会話のテンポや話の盛り上がりについて行けず、その度に苦しい思いをしてきたと言います。
家にこもるようになったきかっけは中学2年の時でした。
いじめを受け、不登校になりました。
その後、通信制の高校に進学しましたが、続かずに退学。
自宅からほとんど出ずに、家で好きなSFの本を読んだりテレビを見たりして過ごすだけの生活が続きます。
そして、16歳の時、アルコール依存症だったという父親が体を壊して亡くなりました。
家庭の経済状況は、苦しくなりました。
母親は、不登校の子どもがいる親の会に参加するなど、ひきこもる山崎さんのことを気にかけていましたが、ひきこもりが長引くにつれて、次第に何も言わなくなったと言います。
母親に対する気持ちをたずねると、伏し目がちになり、しばらくの沈黙のあと、少し早口になって、こう答えてくれました。
(山崎さん)
「母親に対しては、すごく申し訳ないと感じていました。自分が情けないと思う気持ちでした」
そして、山崎さんは「昔からこんな感じですから・・・」と突然腕を突き出しました。
“普通の生活”を送っていない自分自身のことや、複雑な家庭状況などさまざまなストレスから苦しさに耐えきれず、発作的に、リストカットを繰り返したと言います。
(山崎さん)
「痛みで現実から逃げられる、逃げたいというか・・・。気がつくとやっていました。
母親はもしかしたら気づいていたかもしれません」
支えてくれる人は、誰もいない。そう感じる日々が続きます。

40歳を手前に転機も…
転機が訪れたのは、40歳を過ぎようとしていたころでした。
ひきこもり始めてから20年以上たち、母親は70代になっていました。
洗濯や食事などの家事をこなし、自分を支えてくれる、その姿を見て、ふと、自分も高齢になった母親を支えなければいけない、という思いが強く芽生えたと言います。
働こうと思い立ち、アルバイトに応募。人生で初めてのことでした。
(山崎さん)
「40手前で無職というのもこのままじゃいけないと思ったし、母親も年で、自分がしっかりしないといけないと思いました」
思い切って始めたアルバイト。当初は順調だったと言いますが、ある日、金属加工の作業中に手に大けがを負ってしまいます。
働きづめの状態も続き、患っていたうつ病も悪化。結局、1年ほどで退職しました。
ちょうどこのころ、みずから受診した病院で発達障害の1つのアスペルガー症候群(自閉スペクトラム症)と診断されましたが、「何一つ自分の生活が変わったことはなかった」と話す山崎さん。
この時も、自分に寄り添ってくれる人や支援はなかったといいます。
一方で、働きたいという気持ちを持ち続けていた山崎さん。
その後、知人の紹介でパン屋で働き始めましたが、職場の勤務管理や衛生環境などに疑問を感じ、再び1年ほどで退職。
そうした中、母親は80歳を超え、体調を崩すことも多くなっていきました。
そして去年、すい臓がんが見つかり、入院します。
長年、一緒に暮らしてきた母親の病気を知ってショックを受けた山崎さんは、毎日母親の病室に通い、朝から晩までそばにいて看病しましたが、2か月後の去年6月、母親は息を引き取りました。

たった1人の肉親だった母親を亡くした山崎さん。
孤独にさいなまれている今の心境を、ポツリポツリとつぶやくように打ち明けてくれました。
(山崎さん)
「放心状態で当時のことは記憶がありません。母親のために生きねばと思って生きていたのにその母親を失ってしまってはもう生きる意味はない。今から何かをやるなんて、もう無理ですよね。絶望、無、今の不安といえば死に損なったことだけです」
これまで周囲の支援をほとんど受けずに生きてきたと語る山崎さん。
大切な母親との死別を経験し、自分も消えてしまいたいと思うほどの苦しい思いを抱えていました。
そのうえで、将来が見通せない自らの今の状況については、「他人に迷惑をかけられない」「自分の中で解決しなきゃいけない」と思い詰めている様子でした。
最後に社会に伝えたいことを尋ねたさい、「誰もがいつでもその人なりのペースでやり直せる社会になってほしい」とまっすぐに目を見つめ訴えていた山崎さん。
たった1人の肉親を亡くしたことで、一段と深まった自身と社会との間の溝に苦しんでいるように見えました。
少しでも周囲とのつながりを
長年ひきこもってきた人が、生活を支えてきた家族を失うことで直面する問題。
中高年のひきこもりの問題に詳しい宮崎大学の境泉洋准教授は、ひきこもりの人たちにとって、独りで取り残されることが与える影響は大きいといいます。

「家族の死は、これまでの生活が終わるということを突き付けられるということです。
解決の見通しが持てないために、先延ばしにしたりしてきたさまざまな課題が立ちはだかることで、自分の人生も終わりに近づいているのではないかと、落ち込み途方に暮れてしまうというのは当然起こりうることだと思います」
そして、支援が届いていない人ほど、その思いを強くするとしたうえで、家族が健在な間に、社会との繋がりをもてるようにしておくことが重要だと指摘しています。
「独りになってしまうと、本人が助けを求めないかぎり、周りがSOSに気が付くチャンスは無くなってしまいます。親御さんがいるうちに、細くてもいいので支援との繋がりを持つことができていれば、孤立を防ぐことができます。そのためには、家族が早いうちから 行政や支援団体などとの関わりを持っておくことが大事ですし、支援する側もひきこもりの解決を就労などに限定するのではなく、いざという時に助けを求めてもらえるよう、ゆるやかでもいいので繋がりを維持するという視点をもつことが重要になってくると思います」