東京パラリンピックの恩恵
多くのパラアスリートが夢見た建物が東京 品川区にあります。
民間の財団が運営する「パラアリーナ」です。

東京パラリンピックに向けて、国内では数少ないパラスポーツ専用の体育館として、おととしオープンしました。
ここで練習している車いすラグビー日本代表の島川慎一選手に話を聞くことができました。

島川慎一選手
「東京パラリンピックに向けてこの施設ができて本当にありがたい。ここなら一日中、何の不自由もなく、練習ができる」

実は島川選手が喜びをあらわにするのには訳があります。
パラアリーナができるまでは、ほとんどの体育館で門前払いにあい、東京のチームにいながら栃木県足利市まで通って練習していたというのです。
床の「傷」が危ない?
問題となったのは、床にできる「傷」です。

車いすラグビーは激しいぶつかり合いが魅力の人気競技ですが、車いすが転倒して床に傷がつくので、次に使う人がけがをする危険があると懸念されたのです。
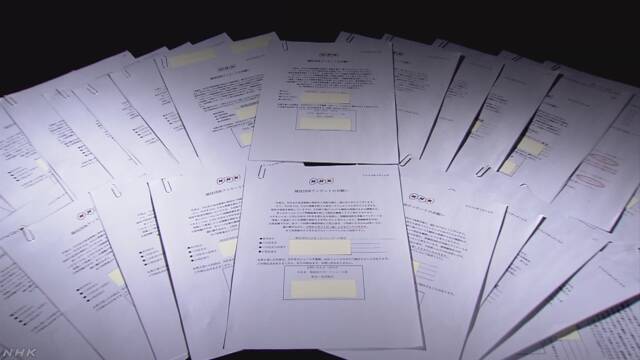
NHKのアンケートでは、島川選手のように日本代表の選手でも施設の利用を断られた経験があると答えた団体は、7つにのぼりました。
深刻な“競技施設不足”
そこでいま、懸念されているのが“パラバブル崩壊”です。
島川選手が練習するパラアリーナは、実は東京パラリンピックの1年後、来年末で閉鎖されるのです。

島川選手も、パラリンピックのあとはどうやって練習場所を確保するのか不安を抱えています。
NHKのアンケートでも「競技施設の不足」を訴えた競技団体は26団体のうち、およそ70%にのぼりました。
東京パラをレガシーに!
せっかく東京パラリンピックが盛り上がってもプレーできる場所がなければ、「その先」にはつながりません。
このため、思い切った対応に乗り出した自治体があります。

東京 江戸川区です。
ことし1月、東京パラリンピックで行われる22競技すべてを区内でプレーできるようにすると宣言しました。

ポイントは、区立体育館など誰もが使える施設にパラスポーツの用具を導入することです。
担当職員の塩田光明さんが今、施設を回ってその方策を探っています。

たとえば車いすフェンシングの場合、重さ100キロに達する車いすの固定器具が必要ですが、ひとりで動かすことができ、立てかけると場所をとらずに保管できるため、区内の施設でも置けることがわかりました。
また、馬術も馬を新たに購入すれば、区が運営に参加する子ども向けのポニーランドにあるスペースや飼育施設をそのまま活用して競技ができることもわかりました。

さらにパワーリフティングや自転車競技も民間のフィットネスクラブにバーベルなどの用具が十分そろっていて、台を付け足したりベルトで補助するなど少しの工夫を加えるだけで、障害がある人もすぐに使えるようになります。

塩田光明さん
「2020年のあと何を残すかが重要だ。東京大会をバブルで終わらせず、レガシーとして競技施設を残し、維持していきたい」
バブルの先へ 課題は…
“パラバブル”の「その先」を見つめるとき、もう1つ避けて通れないのが競技の未来を担う「若手選手の発掘」です。ところがNHKのアンケート調査ではそこに大きな課題があることがわかりました。
東京パラリンピック以降を見据えた若手選手の発掘について尋ねたところ「不十分」と「やや不十分」と回答した競技団体が76%にのぼったのです。

実は、東京大会で金メダルが期待される車いすラグビー日本代表の主力は島川選手をはじめ、40歳前後とベテランが多く、10代の選手は橋本勝也選手(17)ただ1人だけです。

橋本勝也選手
「もっと車いすラグビーの選手を増やしてできるなら、若手の選手と一緒に切磋琢磨していきたい」
若手発掘への動き
人気と実力を兼ね備えた競技にもかかわらず、若手選手の発掘はなぜ進まないのか。
日本車いすラグビー連盟は、大きな理由の1つとして、子どもが競技を楽しめる環境が整っていないことをあげました。
特に子ども用の車いすがないことが大きく影響してきたといいます。

競技に使う車いすは1台100万円以上するため、子ども用の車いすはこれまで作ることができず、体験会でも子どもたちはサイズの合わない大人用でプレーせざるをえませんでした。
これではタックルなど、車いすラグビーのだいご味を十分に味わうことができません。

実は橋本選手も、競技を始めた中学生の頃は、大人の選手から譲ってもらった車いすを改造して使っていました。
「10年、20年先の日本代表を作りたい」
現状を憂えた日本車いすラグビー連盟が動いたのは、2か月前でした。
子ども用の車いすを作るために、製作費用をネットで募るクラウドファンディングを始めたのです。

180万円を超える資金が集まり、待望の子ども用の車いすを作るめどがようやく立ちました。

日本車いすラグビー連盟 三阪洋行理事
「車いすがなくて最初の情熱がくじける可能性もある。どんな年齢でも合わせられるものを準備したい。2020年以降に向けて大きな意義があると思う」
“バブル”で大きな恩恵
そして、“パラバブル”がもっとも如実にあらわれるのが、競技団体に入る「お金」の問題です。
東京パラリンピックに向けて注目が集まるにつれ、スポンサーからの協賛金などで収入が大幅に増える、まさにバブル状態となっているのです。

例えば、シッティングバレーボールの日本パラバレーボール協会には今年度9000万円の収入があり、大会公式ボールを、練習用に一気に100個、買いそろえることができました。
“バブル崩壊”に募る危機感
そうした“バブル状態”にある競技団体がいま最も恐れているのが、東京パラリンピックのあとに起きるであろう“バブルの崩壊”です。
NHKのアンケートでは、大会終了後に予想される助成金やスポンサーの減少に「不安を感じている」と答えた団体は、実に95%以上にのぼりました。
アンケートで競技団体からは…
「スポンサー離れが進み、強化や普及の継続が困難」
「国際大会への選手の派遣や国内大会の開催も危ぶまれる」
悲痛な訴えが相次ぎました。
安定した財源確保へ
そんな中、日本パラバレーボール協会は、スポンサーとなる企業が得られる将来的なメリットをアピールして安定した財源を確保しようとしています。

スポンサーとなっている外資系保険会社と大手証券会社との定例会議を取材することができました。
真野嘉久会長が強調したのは、東京パラリンピックのあと、パラスポーツが子どもからお年寄りまで楽しめる「生涯スポーツ」として普及が進む可能性があるということ。
それは、すなわち幅広い年代を顧客とする企業側にもメリットがあるということです。

真野会長はスポンサーに「協会が学校で行っているバレーボール教室と合わせて金融や保険の授業ができるのではないか」と具体的な提案を行いました。
スポンサーの担当者は「一企業が学校にアプローチするのとは反応が全く違う。協会のビジョンは応援していきたいので、スポンサーの継続を前向きに検討したい」と、将来的に期待している様子でした。

こうした働きかけの結果、協会は企業13社といずれも10年間のスポンサー継続を約束、東京パラリンピックのあとも継続的に財源を手にすることができているのです。

日本パラバレーボール協会 真野嘉久会長
「企業とは互いにメリットのあるウィンウィンの関係をつくることができる。10年後、20年後、100年後のメリットを考えてスポンサーになってもらっているからこそ、2020年以降が勝負だ」
2020の「その先へ」
東京パラリンピックの目標として掲げられているのが「誰もがパラスポーツができる環境をつくる」こと、そして「違いを受け入れ認め合う共生社会を育む」ことです。
ここまで見てきた「施設」「選手」「お金」は、いずれもその目的を実現するためには欠くことができません。

“パラバブル”をピンチのまま終わらせるか、チャンスに転換できるのか。
2020の「その先」を見据えた時、どちらの道を選択するかは競技団体だけでなく、これから東京パラリンピックにふれて、楽しむ、私たち自身にもかかっているのではないかと感じています。




