“タワマン文学” 麻布競馬場さんが描くZ世代の本音とは
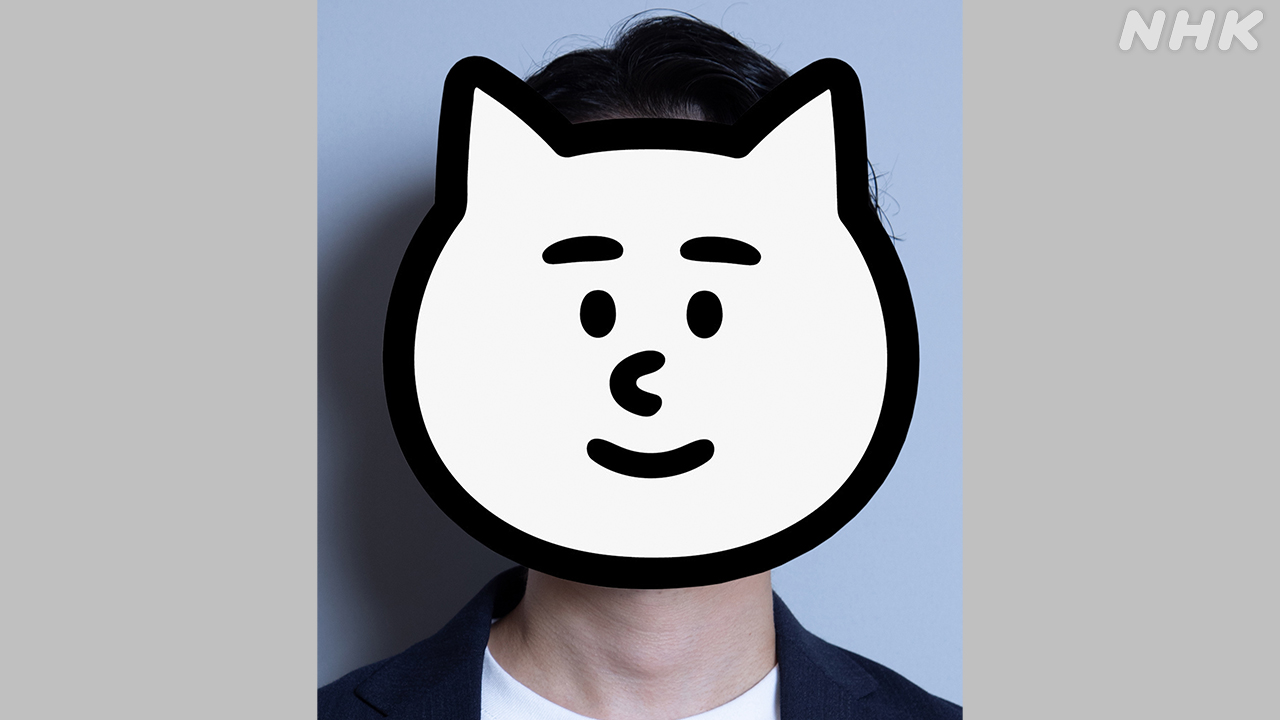
“Z世代の取扱説明書”という挑発的な宣伝文句で注目された小説、「令和元年の人生ゲーム」。
作者のペンネームは“麻布競馬場”。
覆面作家として活動し、ふだんは、フルタイムで働く会社員です。
コロナ禍でSNSに投稿した小説が大バズリしたことが作家デビューのきっかけでした。
デビュー2作目、32歳の若さで、ことしの直木賞の候補にも選ばれた、謎多き作家の麻布さん。
同じ32歳の私は(記者)どんな人なのかと興味を持ち、インタビューを申し込みました。
(科学文化部・堀川雄太郎)
作者のペンネームは“麻布競馬場”。
覆面作家として活動し、ふだんは、フルタイムで働く会社員です。
コロナ禍でSNSに投稿した小説が大バズリしたことが作家デビューのきっかけでした。
デビュー2作目、32歳の若さで、ことしの直木賞の候補にも選ばれた、謎多き作家の麻布さん。
同じ32歳の私は(記者)どんな人なのかと興味を持ち、インタビューを申し込みました。
(科学文化部・堀川雄太郎)
直木賞の候補に“びっくり”
7月17日に選考会が行われる第171回芥川賞・直木賞。
歴史ある直木賞の候補作に選ばれたのが、麻布競馬場さんの「令和元年の人生ゲーム」です。
麻布さんがインタビューの場所に指定したのは出版社の会議室。
覆面作家ということもあって緊張して待っていると、白いTシャツに綿のパンツという出で立ちに、はっきりした声で「よろしくお願いします!」と挨拶する爽やかな青年が登場。
歴史ある直木賞の候補作に選ばれたのが、麻布競馬場さんの「令和元年の人生ゲーム」です。
麻布さんがインタビューの場所に指定したのは出版社の会議室。
覆面作家ということもあって緊張して待っていると、白いTシャツに綿のパンツという出で立ちに、はっきりした声で「よろしくお願いします!」と挨拶する爽やかな青年が登場。

その人こそが麻布競馬場さんでした。
親しみやすい人柄ですぐに緊張の糸もほぐれ、まずは、デビュー2作目にして直木賞の候補に選ばれた感想を聞いてみました。
親しみやすい人柄ですぐに緊張の糸もほぐれ、まずは、デビュー2作目にして直木賞の候補に選ばれた感想を聞いてみました。
麻布競馬場さん
「普通に職場で働いていたところに知らない番号から電話がかかってきて…。感慨深いというよりまずはびっくりしました。元々、作家になりたいとか文学賞を取りたくて書き始めたわけではないんです。(候補に選ばれ)自分の書いていたものがちゃんとおもしろいものだと評価されたように感じ、ようやく息継ぎができたと思いました」
「普通に職場で働いていたところに知らない番号から電話がかかってきて…。感慨深いというよりまずはびっくりしました。元々、作家になりたいとか文学賞を取りたくて書き始めたわけではないんです。(候補に選ばれ)自分の書いていたものがちゃんとおもしろいものだと評価されたように感じ、ようやく息継ぎができたと思いました」
平成から令和 迷走する若者たち

候補作の「令和元年の人生ゲーム」。
平成の終わりから令和の初めにかけて東京の有名大学に進学した、20代を中心とする「Z世代」と呼ばれる若者の学生時代から就職活動、社会人となってからの姿を通して、その本音をリアルに描いた群像劇です。
平成の終わりから令和の初めにかけて東京の有名大学に進学した、20代を中心とする「Z世代」と呼ばれる若者の学生時代から就職活動、社会人となってからの姿を通して、その本音をリアルに描いた群像劇です。
「自分や他人に期待しちゃって、最後の最後に裏切られたりしたら、死にたくなるほどみっともないでしょう?そうなるくらいなら、僕はやっぱり何もしないほうがマシだと思います」
(第2話 平成31年より)
(第2話 平成31年より)
「ソーシャルグッドへの情熱を失わない強さをZ世代は持ってるんですよ」
「早く正しいことがしたい!そうしないと不安で仕方がない」
(第3話 令和4年より)
「早く正しいことがしたい!そうしないと不安で仕方がない」
(第3話 令和4年より)
「仕事だけが人生じゃない」と言われ、明確なゴールのない時代に、どうすれば幸せになれるのか分からず、迷走する若者の姿が赤裸々に描かれています。

麻布さんは、2010年、慶應義塾大学への進学を機に地方から上京し、その後は、厳しい就職活動を勝ち抜き、都内の企業に就職。
平成の競争社会を生き抜いてきました。
麻布さんたちの世代にとって成功の証しは“タワーマンション”での暮らしでしたが、その価値観は、1つ下の世代である「Z世代」の若者たちと違うことに気づいたと言います。
平成の競争社会を生き抜いてきました。
麻布さんたちの世代にとって成功の証しは“タワーマンション”での暮らしでしたが、その価値観は、1つ下の世代である「Z世代」の若者たちと違うことに気づいたと言います。
麻布競馬場さん
「僕自身は平成3年生まれで、自分の“地元”は明確に平成なんです。平成での“人生のゲーム”って、いい大学に入っていい会社に入って、いい給料をもらってきれいな奥さんをもらって、タワマンに住みながら頭のいい子を育てて、労働者を再生産していく。ある種の経済的成功を目標としたゲームだと思っているし、その象徴がタワマンだったと思うんです」
「しかし、今の20代、いわゆるZ世代と呼ばれる人たちと話すと『もう東京にもタワマンにも憧れない』と彼らは言う。『では、皆さんはタワマンなきあとにどこに行くんですか』と聞くと、『いや実はそれは分からないです』と。タワマンの時代は終わったけれど、次に僕たちはどこへ行くのかという惑いと不安、これはこれからの時代の空気になるのではないか。その気づきが今回の執筆の発端になっています」
「僕自身は平成3年生まれで、自分の“地元”は明確に平成なんです。平成での“人生のゲーム”って、いい大学に入っていい会社に入って、いい給料をもらってきれいな奥さんをもらって、タワマンに住みながら頭のいい子を育てて、労働者を再生産していく。ある種の経済的成功を目標としたゲームだと思っているし、その象徴がタワマンだったと思うんです」
「しかし、今の20代、いわゆるZ世代と呼ばれる人たちと話すと『もう東京にもタワマンにも憧れない』と彼らは言う。『では、皆さんはタワマンなきあとにどこに行くんですか』と聞くと、『いや実はそれは分からないです』と。タワマンの時代は終わったけれど、次に僕たちはどこへ行くのかという惑いと不安、これはこれからの時代の空気になるのではないか。その気づきが今回の執筆の発端になっています」
365日ほぼ飲み歩いています

東京・港区在住の麻布さんがよく出没するのは、麻布十番や白金高輪。
いろんな年代や職業の人と交流したいと、365日ほぼ毎日のように飲み歩き、そこで出会った人たちに聞いた話などが、AIの機械学習のようにデータとして頭の中に蓄積されて、作品に投影されていると言います。
作家であることは酒の席で出会う人たちや会社の同僚、家族にすら明かしていません。
いろんな年代や職業の人と交流したいと、365日ほぼ毎日のように飲み歩き、そこで出会った人たちに聞いた話などが、AIの機械学習のようにデータとして頭の中に蓄積されて、作品に投影されていると言います。
作家であることは酒の席で出会う人たちや会社の同僚、家族にすら明かしていません。
麻布競馬場さん
「何か一つの人生を生きていない事が好きだし、創作活動にも生きてるなって思うんです」
「何か一つの人生を生きていない事が好きだし、創作活動にも生きてるなって思うんです」
ユニークなペンネームの由来には、東京を生きる人たちへの風刺が込められています。
「東京の人は、すごく生き生きと、自分の人生を自分で描いたとおりに自由に生きているような顔をしていますけど、実際のところ、頑張って働いて、フルローンでマンションを買って、子どもの教育費を払いながらローンを返すみたいな、同じような暮らしの中で苦しんでいるなという感覚がありました。結局、同じルートをみんなでぐるぐる走らされて、一番になろうともがく光景が競馬場みたいだと思って、麻布競馬場という名前にしました」
小説を書き始めたのはコロナ禍
麻布さんが小説を書き始めたのは、飲み会も難しかったコロナ禍の2021年。
SNSに短いストーリーを投稿したのがきっかけでした。
SNSに短いストーリーを投稿したのがきっかけでした。

「3年4組のみんな、高校卒業おめでとう。最後に先生から話をします。大型チェーン店と閉塞感のほかに何もない国道沿いのこの街を捨てて東京に出て、早稲田大学の教育学部からメーカーに入って、僻地の工場勤務でうつになって、かつて唾を吐きかけたこの街に逃げるように戻ってきた先生の、あまりに惨めな人生の話をします。」
(「この部屋から東京タワーは永遠に見えない」『3年4組のみんなへ』より)
(「この部屋から東京タワーは永遠に見えない」『3年4組のみんなへ』より)
東京に疲弊しながらも東京に生きることをアイデンティティーとせざるを得ない人たちを描いたシニカルな作品群は“タワマン文学”とも呼ばれて話題を呼び、2022年には1冊の本にまとめて出版され、瞬く間に作家デビューとなりました。
一方で、当時は「これは文学ではない」といった批判も受けました。
一方で、当時は「これは文学ではない」といった批判も受けました。
麻布競馬場さん
「コロナ禍の緊急事態宣言で完全に生活が自分の家の中だけに閉じてしまった時期に、インターネットに深く没頭していきました。いわゆる有名大学に通って有名企業に就職して、それなりに高い給料をもらって暮らしている。一見すると恵まれた人たちの苦悩、都市生活者の苦悩という、僕にとってはすごく身近な人たちの話のつもりで書いていました。たくさんの人に届けようとか、理解してもらおうという気持ちで書いていなかったので、自分が想定していない読者に広がったのはすごくおもしろかったです」
「コロナ禍の緊急事態宣言で完全に生活が自分の家の中だけに閉じてしまった時期に、インターネットに深く没頭していきました。いわゆる有名大学に通って有名企業に就職して、それなりに高い給料をもらって暮らしている。一見すると恵まれた人たちの苦悩、都市生活者の苦悩という、僕にとってはすごく身近な人たちの話のつもりで書いていました。たくさんの人に届けようとか、理解してもらおうという気持ちで書いていなかったので、自分が想定していない読者に広がったのはすごくおもしろかったです」
デフォルメした極端な人物を書いたと語るとおり、作品では、“人に見せたくない嫌な自分”がテーマとなっていて、そこには幼少時代の経験や、尊敬する作家の影響もあると言います。
「中学生のとき、最初にいいなと思ったのが大江健三郎さんの小説でした。『他人の足』という短編の作品で描かれていた人間のすごく嫌な一面というのは、僕の内面にある人間性や、家族・友人の中にかいま見る部分とも共通しているところがあったんです。もともと小学校のときに、親が担任の先生から『おたくのお子さんは他人に対する共感性が低い』と言われ、親からもずっと『他人の気持ちを考えて生活しなさい』と言われていました。いまだにそれが分からなくて、自分のことも他人のことも分からない。“人間って何だ”、“他人って何だ”とかをずっと考え続けていて、そういったところから、あまり世間に見せたくない自分、人間の嫌な部分を見つめることが多かったです」
正しさに戸惑う若者

平成の終わりから令和にかけて、長時間労働による過労死の問題やコロナ禍など、働き方や生活は大きく変わりました。
小説では、そんな時代に有名大学に進学、就職活動を勝ち抜いて、憧れの企業に入った主人公が、ある同期の発言に衝撃を受けます。
小説では、そんな時代に有名大学に進学、就職活動を勝ち抜いて、憧れの企業に入った主人公が、ある同期の発言に衝撃を受けます。
「総務部あたりに配属になって、クビにならない最低限の仕事をして、毎日定時で上がって、そうですね、皇居ランでもしたいと思ってます」
(「令和元年の人生ゲーム」第2話 平成31年より)
(「令和元年の人生ゲーム」第2話 平成31年より)

急速に広がる「仕事だけが人生ではない」という価値観にうなずく一方で、時代ごとに変わる“正しさ”に戸惑う若者たち。
麻布さんは、今回の小説を「すごく近くて狭い時代小説」と語ります。
そこに込めたのは、“自身の地元である平成を成仏させたい”という思いでした。
そこに込めたのは、“自身の地元である平成を成仏させたい”という思いでした。
麻布競馬場さん
「『たくさん働いて自己実現しよう』とか『圧倒的に成長しよう』といったこれまでの価値観に対し、急に『これからは定時で帰れ』と言われて戸惑った若手社員って、たくさんいたと思います。今回の本で書いたのは、時代によって正しさというものがすごく移り変わった10年間だと思っていて、変化する時代に振り回された若者たちの鎮魂歌、新しい一歩を踏み出せず悩んでいる主人公を書きたいと思いました」
「『たくさん働いて自己実現しよう』とか『圧倒的に成長しよう』といったこれまでの価値観に対し、急に『これからは定時で帰れ』と言われて戸惑った若手社員って、たくさんいたと思います。今回の本で書いたのは、時代によって正しさというものがすごく移り変わった10年間だと思っていて、変化する時代に振り回された若者たちの鎮魂歌、新しい一歩を踏み出せず悩んでいる主人公を書きたいと思いました」

人生ゲームは続く 若者へのメッセージ
2019年の5月1日を境に、令和に時代を移した日本。
「令和元年の人生ゲーム」と名付けた作品のタイトルは、時代を反映したあのボードゲームをヒントにしたといいます。
「令和元年の人生ゲーム」と名付けた作品のタイトルは、時代を反映したあのボードゲームをヒントにしたといいます。
麻布競馬場さん
「僕がやっていた頃の平成版のゲームはすごくシンプルで、ルーレットを回して出た目に応じて、就職して、結婚して子どもを産んでと、一番早く目的のゴールにたどり着くことを競いながら、その途中でたくさんお金を集める、まさしく平成のゲームというか、タワマン文学的なゲームだったと思います。驚くことに、その後リリースされた令和版では決まったゴールがなくなったんです。プレイヤーたちは盤面をさまよいながらフォロワーを増やしていく。これからはお金の時代ではなくて、いかにいい人生を送っているか、それが令和のゲームだと宣言された気がして、すごく皮肉だと思い、タイトルに入れたんです。それに加え、敬愛する大江健三郎先生の『万延元年のフットボール』へのリスペクトもあります」
「僕がやっていた頃の平成版のゲームはすごくシンプルで、ルーレットを回して出た目に応じて、就職して、結婚して子どもを産んでと、一番早く目的のゴールにたどり着くことを競いながら、その途中でたくさんお金を集める、まさしく平成のゲームというか、タワマン文学的なゲームだったと思います。驚くことに、その後リリースされた令和版では決まったゴールがなくなったんです。プレイヤーたちは盤面をさまよいながらフォロワーを増やしていく。これからはお金の時代ではなくて、いかにいい人生を送っているか、それが令和のゲームだと宣言された気がして、すごく皮肉だと思い、タイトルに入れたんです。それに加え、敬愛する大江健三郎先生の『万延元年のフットボール』へのリスペクトもあります」
作品を通して、正しくありたいともがくZ世代の若者たちに伝えたいことを聞きました。
「僕自身もいわゆる優等生をやって30年間生きてきたので、今これをするのが正解だというのは何となく感覚として分かります。『今はこう言っておくのが正しいだろう』、『こう言っておけば損することはないだろう』と、自分の人生を損したくない、自分の人生を傷つけたくないという一心で、時代の正しさをなぞってしまう。そこに自分の意思があってもなくてもです」
「平成がもし競争の時代だとしたら、令和の正しさというのは、優しさに満ちあふれつつも、その裏側にどこか残酷性とか人を傷つける恐怖、可能性も抱えていると思います。若者たちが、Z世代的価値観にしがみついて生きていくのが正しいと思ってソーシャルグッドなことをやっているのだとしたら、『じゃあ本当にそれはあなたのしたいことですか』と一度自分の胸に手を当てて立ち止まってもいいから考えてほしいというのがメッセージです」
「平成がもし競争の時代だとしたら、令和の正しさというのは、優しさに満ちあふれつつも、その裏側にどこか残酷性とか人を傷つける恐怖、可能性も抱えていると思います。若者たちが、Z世代的価値観にしがみついて生きていくのが正しいと思ってソーシャルグッドなことをやっているのだとしたら、『じゃあ本当にそれはあなたのしたいことですか』と一度自分の胸に手を当てて立ち止まってもいいから考えてほしいというのがメッセージです」

取材後記 “若者は常に正しい”
取材中、終始物腰柔らかな姿が印象的だった麻布競馬場さん。
その発言や文章は、冷静な目で社会を見つめているようにも見えますが、今回の作品でコロナにはほとんど触れなかった理由を尋ねると、「あの数年間はただただ空白で奪われた時間だったから、何か意味があるものとして書きたくないという世代としての抵抗というかプライドがあったと思います」と語気を強め、コロナにより大切なものを喪失したことを伺わせました。
そして、同世代として麻布さんの話で印象に残ったのが「若者は常に正しい」ということばです。
その発言や文章は、冷静な目で社会を見つめているようにも見えますが、今回の作品でコロナにはほとんど触れなかった理由を尋ねると、「あの数年間はただただ空白で奪われた時間だったから、何か意味があるものとして書きたくないという世代としての抵抗というかプライドがあったと思います」と語気を強め、コロナにより大切なものを喪失したことを伺わせました。
そして、同世代として麻布さんの話で印象に残ったのが「若者は常に正しい」ということばです。

麻布競馬場さん
「『今どきの若い者は』というのはこれまでは僕自身も言われる側でしたけど、気づけば自分たちの周りが言い始めてるんですよね。大学時代の同期と会ったときに話題になるのは、『最近の後輩が働かない。あいつらをどうしたら定時以降働かせられるだろう』とか、『怒ったらすぐ病むんだよな』とか。30代に入ったらすぐ“今どきの若い者は”をやるんだというのがすごく衝撃でした。僕は『若者は基本的に正しい』、時代が新しくなればなるほど、世の中は必ずよくなっていくと信じています。若い人たちのためにわれわれ年上の人間ができることは、自慢することでも愚痴を言うことでもなく、自分たちの世代がいかに失敗をして、なぜ幸せになれなかったのか。僕たちが抱えている傷を共有することだと思っています」
「『今どきの若い者は』というのはこれまでは僕自身も言われる側でしたけど、気づけば自分たちの周りが言い始めてるんですよね。大学時代の同期と会ったときに話題になるのは、『最近の後輩が働かない。あいつらをどうしたら定時以降働かせられるだろう』とか、『怒ったらすぐ病むんだよな』とか。30代に入ったらすぐ“今どきの若い者は”をやるんだというのがすごく衝撃でした。僕は『若者は基本的に正しい』、時代が新しくなればなるほど、世の中は必ずよくなっていくと信じています。若い人たちのためにわれわれ年上の人間ができることは、自慢することでも愚痴を言うことでもなく、自分たちの世代がいかに失敗をして、なぜ幸せになれなかったのか。僕たちが抱えている傷を共有することだと思っています」
入局11年目の私もギクッとしてしまいましたが、これからの世代や若者たちが幸せになるためには、私たちも前の世代の経験について、いいところはいい、間違っていることは間違っていると、しっかり分析することが大事だと感じました。
次回作は「全共闘」の時代がテーマだという麻布競馬場さん。
その作品にこれからも注目したいと思います。
(7月17日「おはよう日本」放送予定)
次回作は「全共闘」の時代がテーマだという麻布競馬場さん。
その作品にこれからも注目したいと思います。
(7月17日「おはよう日本」放送予定)

科学文化部記者
堀川雄太郎
岡山市出身、2014年入局。
山形、鹿児島を経て22年から科学文化部。
現在は出版のほか将棋やロケットも担当。
堀川雄太郎
岡山市出身、2014年入局。
山形、鹿児島を経て22年から科学文化部。
現在は出版のほか将棋やロケットも担当。