森林環境税は、自治体が森林整備などの財源に充てるために、年に1回、徴収される税金です。
1人あたり年間1000円で、今月から初めての徴収が始まりました。
給与所得者で徴収が7月からになる人もいるほか、公的年金を受給している人は10月からとなります。
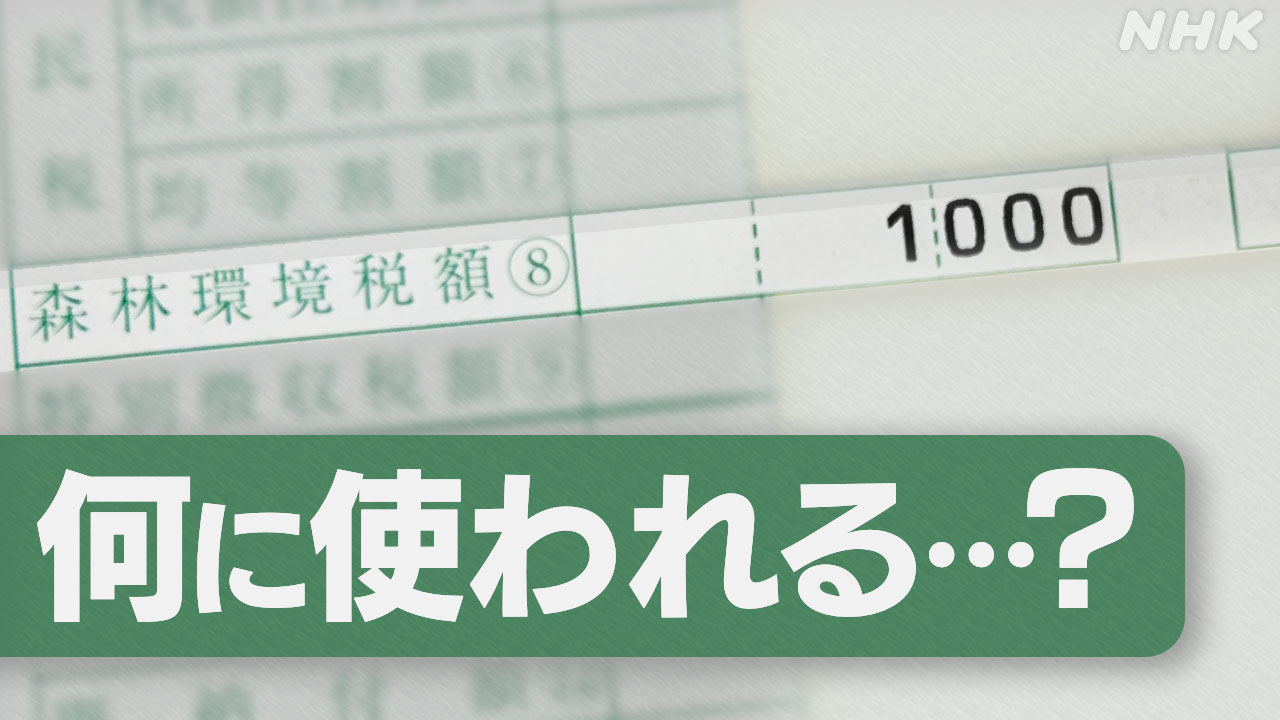
一律の1000円徴収 “森林環境税” なぜ?
今月、職場で手渡された住民税を知らせる紙。その中に見慣れない文字が…。
「森林環境税 1000円」
SNSでは「わけの分からない税金多すぎる」とか「何に使われるのか」といった声もあがっています。
そもそもどういうものなのか。森林がない地域の人にも関係することなのでしょうか。
森林環境税って?
どうして徴収されるの? ギモンが
この森林環境税について、SNSでは疑問の声が出ています。
「森ない都会なんのために取るのよ」
「なんで森ない渋谷区まで分配金」
徴収の対象は納税者およそ6200万人で、住民税非課税の人は対象となりません。
自治体が住民税とあわせて徴収し、年間約620億円の税収が見込まれています。
それを国が「森林環境譲与税」として自治体に分配し直します。

交付されるのは森林がない自治体も。
国から交付される額は、個人や会社などで管理されている「私有林人工林」の面積と林業の就業者数、それに人口によって決められます。

人口も交付の基準に入っているので、私有林人工林の面積がゼロでも、東京23区などにも交付されるのです。
森林環境譲与税は森林環境税の徴収に先立って、2019年度からすでに、国庫から捻出する形ですべての都道府県と市区町村に交付されています。
総務省の資料によると、東京・世田谷区には4年間でおよそ2億8300万円、大阪市には18億8900万円あまり、兵庫県尼崎市にはおよそ1億3900万円が交付されました。
どう活用?
集められた森林環境税は何に使われるのでしょうか。
目的は、森林を育てることで、温室効果ガスの排出削減目標を達成することや災害を防止することです。
使用実績を見てみます。
総務省と林野庁によりますと、2022年度までの4年間で、全国の都道府県と市区町村に交付された額は、あわせておよそ1500億円。
たとえば、私有林人工林の面積が5万6000ヘクタールあまりと、市区町村の中で最大の静岡県浜松市は4年間でおよそ9億6400万円の交付を受け、伐採や伐採した場所に再び森林を作る事業、それに林業に携わる人材の育成といった事業などに活用したということです。

活用されていないケースも
では、私有林人工林がない都市部の自治体では、交付された森林環境譲与税をどんな用途で使っているのでしょうか。
林野庁が示した具体的な活用例では、公共施設での木製の備品の購入や建て替えに国産木材を使うこと、それに都市部の子どもが植林を行う体験などが挙げられています。
一方で、基金に積み立てるケースも。
4年間でおよそ2億2000万円の交付を受けた東京・大田区は、全額を「公共施設整備資金積立基金」に積み立てました。
教育施設や福祉施設などの建て替えや増改築のタイミングで国産の木材を使う際に活用するということです。
実は、4年間に交付された森林環境譲与税の3分の1ほどにあたる525億円ほどは活用されていません。
中には、大田区のように基金として積み立てているケースもあるということです。
森林ない都市部にも交付の理由は
こうした状況について環境経済学が専門の東京経済大学の佐藤一光教授は。

「この税金は、どのように使うかを自治体が判断するという制度になっています。どうやって使うか、交付が始まったときから考え始めたので、最初は困って未活用、ためておいたという事例が多かったです。いまは活用の事例がたまってきていて、2023年度まででみると、未活用は25%くらいで、利用が進んできています」
そのうえで、佐藤教授は、森林がない都市部でも森林を守るうえで果たせる役割があると指摘しています。
「森林環境税の目的に、木材の利活用というのも入っています。国産の木材を使うことが巡りめぐって森林整備に資するという理解です。私は都市部で国産材を使うことは非常に重要だと考えています」
森林・林業を持続可能に
唐突に徴収され始めたようにも感じる森林環境税。
佐藤教授は、実は、長い間議論されてきたと言います。
日本の林業は1970年代まで盛んで、植林が多く行われてきましたが、その後、衰退して、林業の従事者が減り、90年代には間伐もできないという問題も起きました。
10年ほど前からは、1970年代に植えた木が建築の材料として利用する時期になってきていて、どう活用し、その後どう植林するかが課題になっているとしています。
佐藤教授は、木材の価格はまだ安く、林業では厳しい労働が必要なのに賃金が低いとしていて、森林を守るためにも、こうした状況を変える必要があるとしています。
森林環境税もこうした議論から出てきたものだということです。

佐藤教授
「林業は産業としての状況が極めて悪く、その根本原因は木材が安いことなんです。国産材をきちんと利用していくことや、安く買いたたくのではなくフェアな価格で買い取ること、それが日本の森林を持続可能なものにしたり、林業を持続可能なものにしていく上では極めて重要なポイントです」
一律1000円、どう受け止めれば?
一律に年間1人1000円を徴収されることについて、どう受け止めればよいのか、税金や財政にも詳しい佐藤教授は。
佐藤教授
「低所得の人ほど負担が重く、高所得ほど負担が軽い1人1000円という徴収の仕方では納得感が得られないのは当然だと思います。本来であれば所得に応じた形にすべきだった。また、使われ方が、植林や伐採にしたあとに植林することにきちんとつながっているのか、林業に従事する人の労働環境の改善につながっているのかといったことを国がしっかりと調査をして、その結果を見える化していくことが必要だと思います」
総務省は都道府県や市区町村に対し、森林環境税として集められたお金の使いみちをインターネットなどで公表するよう義務づけています。
これを機に、日本の森林や林業、それに私たちの税金が有効に活用されているか考えてみるのもいいかもしれません。