歴史的な円安の引き金を引いたのは、日銀の金融政策を決めるメンバーが青森市で行った講演での発言だった。
講演したのはメガバンク出身の田村直樹審議委員。
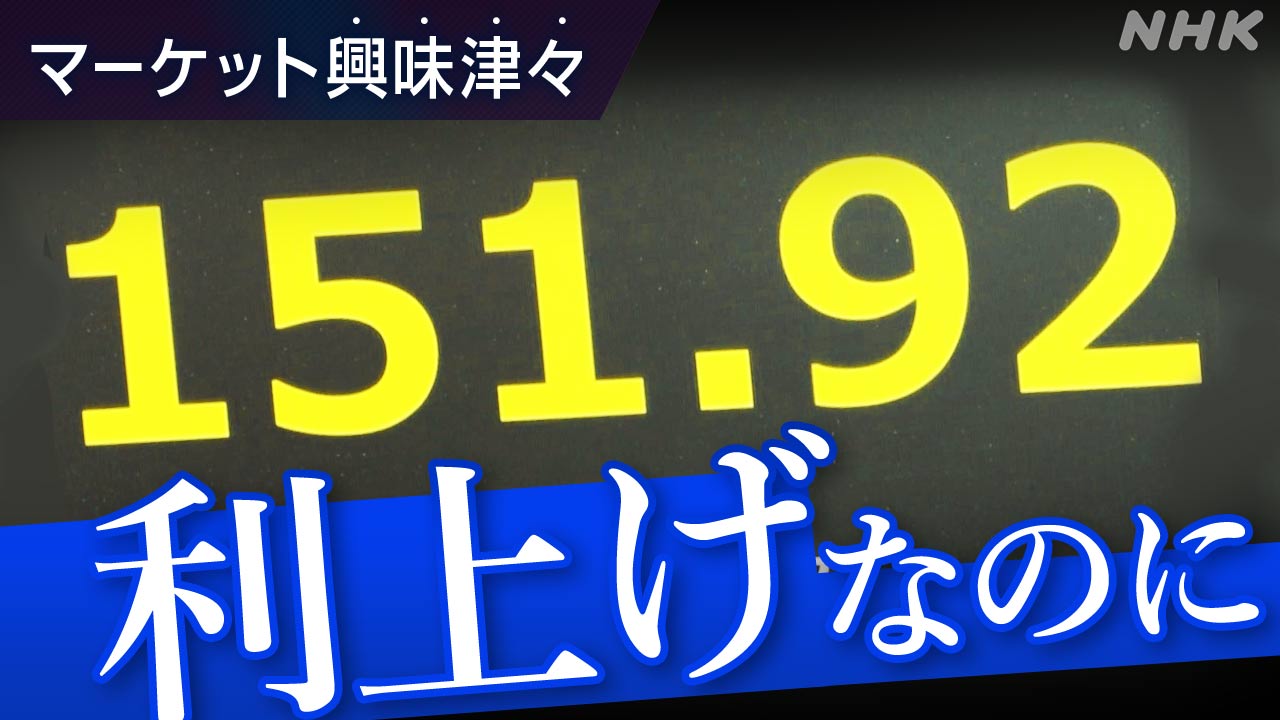
“利上げ”なのに“円安” 日銀のジレンマ?【経済コラム】
為替市場で加速する円安。日銀が17年ぶりの利上げに踏み切ったにもかかわらず、3月27日には1ドル=152円台に迫り、1990年7月以来、33年8か月ぶりの円安ドル高水準をつけた。
なぜ、“利上げ”と同時に“円安”なのか。背景を探ると、日銀のジレンマとも言える状況が見えてきた。
(経済部記者 西園興起)
円安加速の引き金は“ゆっくり”

日銀の大規模な金融緩和策の副作用と金融政策の正常化の必要性を早くから指摘していたことから、市場では利上げに積極的なタカ派と受け止められてきた人物だ。
早くも日銀の追加利上げの時期に市場の関心が集まる中、今後の金融政策について田村委員はこう発言した。
田村直樹 審議委員
「先行き、経済・物価・金融情勢に応じて、ということが大前提ではありますが、ゆっくりと、しかし着実に金融政策の正常化を進め、異例の大規模金融緩和を上手に手仕舞いしていくために、これからの金融政策の手綱さばきは極めて重要だと考えています」
今後も金融政策の正常化を進めていく姿勢を示した内容だと感じたが、市場が大きく反応したのは“ゆっくり”ということばだった。
タカ派のイメージがある田村委員が追加の利上げについて踏み込んだ発言をせず、“ゆっくり”ということばを使ったことで、利上げまでの道のりは遠いと受け止められたのだ。
講演を受けて円相場は急落。
政府・日銀は三者会合を実施し、円安をけん制しなければならなくなった。
講演後の記者会見で、“ゆっくり”の真意を問われた田村委員は「現在の経済物価見通しを前提にすれば、米国のように1年で5%利上げといったようなことになるとは考えていない」と語った。
日銀の緩和姿勢で“利上げ”後も“円安”
田村委員の発言が急速な円安のきっかけとはなったが、為替市場ではその前から円安基調が続いてはいた。
日銀が「当面、緩和的な金融環境が継続すると考えている」として、マイナス金利を解除しても、金融環境は緩和的だという見方を示していたからだ。
日銀が17年ぶりの利上げを決めた3月19日も会合の結果が公表されると、円相場は1ドル=150円台半ばまで下落し、その後の海外市場でも151円台後半まで円安が進行した。

日銀が緩和的環境が続くという見方を示しているとはいえ、なぜ、ここまで円安が加速するのか。
「為替市場は日米の金利差はもちろん、それがどこまで続くかを見ている」こう指摘するのは、あおぞら銀行の諸我晃チーフ・マーケット・ストラテジストだ。
日銀はマイナス金利政策を解除したものの、政策金利はまだまだ低く「0.0%~0.1%」。
一方のアメリカは「5.25%~5.50%」と、その金利差は圧倒的だ。
金利が高い通貨の方が投資家にとっては魅力的で、今の金利差であれば、ドル資産を持ちたい人も多いだろう。
さらにこうした状況では、金利が低い円で資金を借り入れ、より金利が高いドルなどの通貨で運用して利ざやを稼ぐ「円キャリートレード」と呼ばれる取り引きがしやすくなる。
その際には円を売ってドルを買う動きが増えるので、円安要因として働くことになる。
一方、この取り引きで利益を稼ぐ投資家にとって、最大のリスクは急激な円高だ。
ドル資産などで運用して利ざやを稼ぐため、為替が円高に大きく動くと、一気に評価損が出かねないからだ。
このため、日米の金利差が“安定的に”大きく開いていることが重要となる。
諸我さんは日銀やFRBの姿勢に変化がなければ、今の状況が続くとみている。
諸我晃チーフ・マーケット・ストラテジスト
「アメリカではインフレ懸念が根強く、すぐには利下げしないという見方が強い。こうした中、日銀が『当面は緩和的環境が続く』と発信していることで、市場では日米の金利差が一気に埋まることへの警戒感が薄くなっている状況だ。従って、両者のいずれかが動かない限りは、ドル資産への人気が高まり、円安を招きやすい状況が続くことになる」
日銀のジレンマ?
日銀が緩和的環境が続くと説明する背景には、政策の連続性を強調することで長期金利が跳ね上がるのを抑える狙いがあるとみられる。
長期金利が急上昇すれば、実体経済の冷え込みなどの悪影響につながりかねないからだ。
こうした説明が奏功したのか、日銀がマイナス金利の解除を発表したあとも債券市場は落ち着いていた。
一方で、こうした説明は為替市場では円安を加速させる要因となり、日銀の内部からは「為替の先行きを読むのは不可能だ」と当惑する声や「経済へのショックを抑えるため仕方のない説明だが、国民の暮らし向きにどう影響するか心配だ」という声も聞かれる。
また、日銀が追加利上げについて、慎重なコミュニケーションを取ろうとすれば取ろうとするほど、その時期は早まる可能性があるという指摘もある。
三菱UFJ銀行 井野鉄兵チーフアナリスト
「『当面は緩和的環境が続く』と言い過ぎると円安が進みやすくなる。足元では円安要因で輸入物価が上がってきていて、今後も円安が続けば、輸入物価の上昇を通じて消費者物価が上振れする可能性がある。そうなると、日銀は物価の見通しを引き上げざるをえなくなり、遠くない将来の追加利上げが視野に入ってくることになる」
実際、足元では輸入物価が上昇してきている。
輸入物価の上昇は時間差で消費者物価の上振れ要因になる。
どうなる? 日銀の追加利上げ
それでは、日銀が追加利上げに動くのはいつなのか。
複数の市場関係者にタイミングについて見立てを聞くと、まだ自信がないという声も聞かれたものの、おしなべてことし7月や10月という意見が多かった。
7月は春闘の最終的な集計がまとまること、10月は短観や支店長会議もあり、経済や物価に関するデータも集めることができるということが、それぞれの根拠として挙げられていた。

為替市場や債券市場の安定に目配りしつつ、いかにして金融政策の正常化を推し進めていくのか。
ある日銀関係者は「政策判断は難しい。難しいが、それが日本銀行の仕事だ。何かシナリオがあるわけではない。データを見て、金利を動かす。それをひたすらにやっていくだけだ」と話す。
日銀のナローパスは続く。
今後も取材を続け、見届けたい。
正常化はこれからだ。
注目予定

4月1日には日銀の短観=企業短期経済観測調査の結果が公表されます。
民間の予測では一部の自動車メーカーが出荷を停止した影響などで、大企業・製造業の景気判断は4期ぶりに悪化すると見込まれていますが、企業の設備投資の姿勢など、どういった結果が出るか注目です。
また、4月4日には日銀の支店長会議が開かれます。
日銀はマイナス金利政策を解除し、17年ぶりの利上げに踏み切りましたが、地方の中小企業の賃上げや価格転嫁の状況について、どのような声が集まっているか注目です。