能登半島地震 地元に根ざす信用金庫 地域産業の復興に向き合う
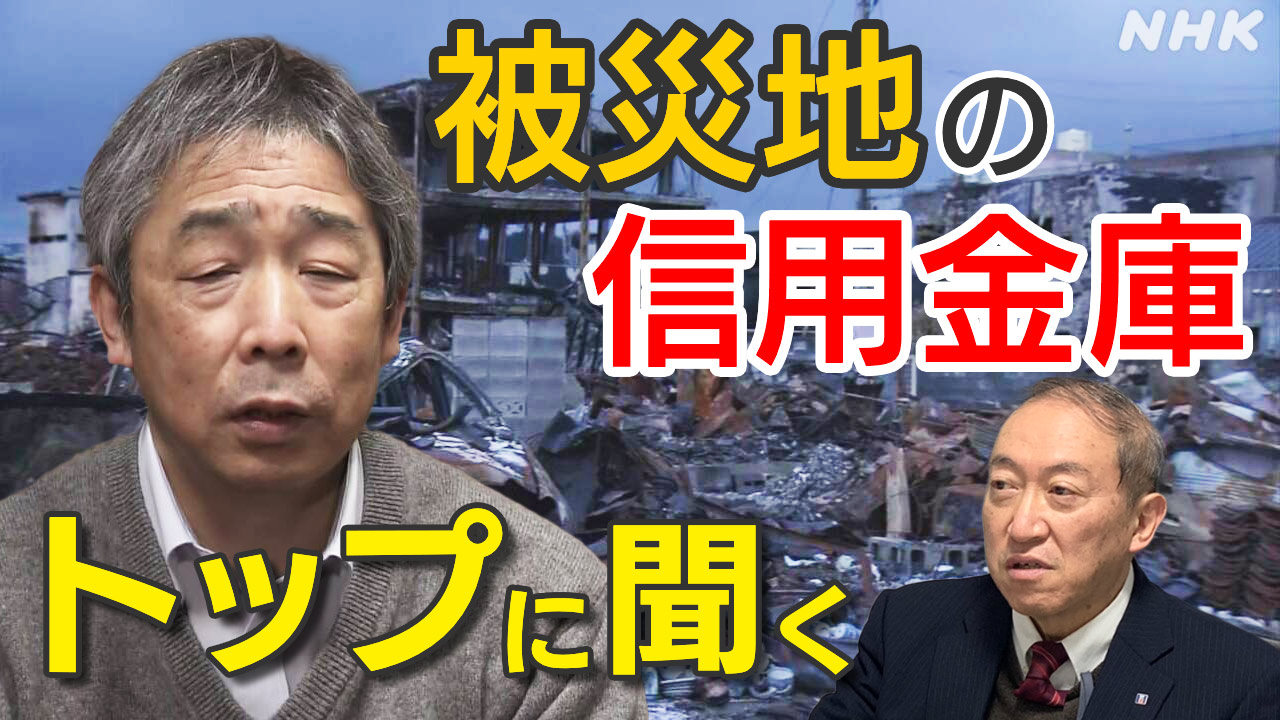
輪島塗、珠洲焼、能登牛、能登ワイン…
能登半島地震では、伝統工芸や特産品の生産者が大きな被害を受けました。
その多くは個人事業主や中小企業で、きめ細かい支援が求められています。
こうした中、資金面をはじめとする経営支援に重要な役割を果たすのが金融機関です。
地元に根ざす「信用金庫」の理事長に、被害の実態や産業の再生について聞きました。
(経済部記者 榎嶋愛理・金沢放送局記者 竹村雅志)
能登半島地震では、伝統工芸や特産品の生産者が大きな被害を受けました。
その多くは個人事業主や中小企業で、きめ細かい支援が求められています。
こうした中、資金面をはじめとする経営支援に重要な役割を果たすのが金融機関です。
地元に根ざす「信用金庫」の理事長に、被害の実態や産業の再生について聞きました。
(経済部記者 榎嶋愛理・金沢放送局記者 竹村雅志)
6割が「営業できる状況にない」
「地震の影響はどうですか?」
「建物は大丈夫だったけど、断水の影響がまだ残っていて」
被災地の取引先を1軒1軒訪ねているのは、「興能信用金庫」(こうのう)の職員です。
「建物は大丈夫だったけど、断水の影響がまだ残っていて」
被災地の取引先を1軒1軒訪ねているのは、「興能信用金庫」(こうのう)の職員です。

この信用金庫は能登町に本店があり、輪島市や珠洲市などが営業エリアです。
地元に根ざし、個人事業主や中小企業を相手に融資や経営支援を行ってきました。
地震直後から、すぐに訪問や電話での聞き取りを始め、見えてきたのは深刻な実態でした。
輪島市の2支店と珠洲市の1支店が取り引きしている1600余りの事業者のうち、工場などの建物に被害があったのは、少なくとも7割以上にあたる1200。
地元に根ざし、個人事業主や中小企業を相手に融資や経営支援を行ってきました。
地震直後から、すぐに訪問や電話での聞き取りを始め、見えてきたのは深刻な実態でした。
輪島市の2支店と珠洲市の1支店が取り引きしている1600余りの事業者のうち、工場などの建物に被害があったのは、少なくとも7割以上にあたる1200。

さらに「営業できる状況にない」と答えたのは、6割以上にあたる980に上りました。(2月8日時点)
信用金庫の田代克弘理事長がまず語ったのは、1か月以上が経過しても、事業の再開や復興を考えることができない厳しい現実でした。
信用金庫の田代克弘理事長がまず語ったのは、1か月以上が経過しても、事業の再開や復興を考えることができない厳しい現実でした。

興能信用金庫 田代克弘理事長
「地震から数日後に奥能登地域に入りましたが、今までに見たことのない状況でした。崩落した道、倒壊した建物…。再建していくためにはとても長い時間が必要になるだろうと思いました。災害発生後は、緊急・再開・復興とフェーズが変わってくると思います。でも、奥能登地域は、緊急事態のままなんです。事業主の中には避難している人もいて、被災の全体像がつかみづらい状況です。今はまだ事業を再開できるフェーズではないというのが正直なところです」
「地震から数日後に奥能登地域に入りましたが、今までに見たことのない状況でした。崩落した道、倒壊した建物…。再建していくためにはとても長い時間が必要になるだろうと思いました。災害発生後は、緊急・再開・復興とフェーズが変わってくると思います。でも、奥能登地域は、緊急事態のままなんです。事業主の中には避難している人もいて、被災の全体像がつかみづらい状況です。今はまだ事業を再開できるフェーズではないというのが正直なところです」

産業復活へ必要なこととは
まだ「緊急」の段階だという言葉どおり、事業者の中には、避難生活を続けている人も多くいます。
建物の被害や長引く断水が、大きな壁となって立ちはだかっています。
中には、年齢的な理由で廃業を決める人も出ています。
建物の被害や長引く断水が、大きな壁となって立ちはだかっています。
中には、年齢的な理由で廃業を決める人も出ています。

田代理事長は、いま重要なことは、経営者が事業継続のマインドを保てるかどうかだといいます。
この信用金庫では、被災者向けの生活再建資金として、融資期間15年以内、上限1000万円の「災害復旧ローン」を用意しています。
すでに実行した融資の返済猶予なども合わせて、事業者の足元を支えていくつもりです。
この信用金庫では、被災者向けの生活再建資金として、融資期間15年以内、上限1000万円の「災害復旧ローン」を用意しています。
すでに実行した融資の返済猶予なども合わせて、事業者の足元を支えていくつもりです。
田代克弘理事長
「毎年のように地震が起こり、直しても直してもという状況の中で、どの程度、動機づけができるのかが重要だと思います。長期化したコロナ、原材料の高騰など、経営の範囲外からの負担を抱えている中で、さらに今回の災害による負担を重ねていくのは非常に厳しい状況です。融資や補助金による調達も考えながら組み合わせをしっかりやっていく必要があると考えています」
「毎年のように地震が起こり、直しても直してもという状況の中で、どの程度、動機づけができるのかが重要だと思います。長期化したコロナ、原材料の高騰など、経営の範囲外からの負担を抱えている中で、さらに今回の災害による負担を重ねていくのは非常に厳しい状況です。融資や補助金による調達も考えながら組み合わせをしっかりやっていく必要があると考えています」
そのうえで、インフラが復旧し、再開・復興の段階に入れば、より信用金庫らしい支援の出番が来ると考えています。
地域密着で個々の事業者の強みを把握しているからこその経営アドバイスや全国の信用金庫のネットワークを通じた販路の確保。
こうした取り組みで、産業を再生させることこそが地域の再生につながると考えています。
地域密着で個々の事業者の強みを把握しているからこその経営アドバイスや全国の信用金庫のネットワークを通じた販路の確保。
こうした取り組みで、産業を再生させることこそが地域の再生につながると考えています。

田代克弘理事長
「奥能登の2市2町には非常に魅力的な資源があって、その資源によって地域の生産性が支えられています。能登の魅力を引き出しているのが、地域の事業者さんで、その事業者さんたちが再生していかないと、地域の再生・復興はやはり難しいと思うんです。事業者の全員が諦めるわけではないです。『なんとか取り戻したい』『なんとか続けたい』という方がいらっしゃれば可能なかぎり応援すること、それがわれわれの使命だと思ってます。不安はもちろんありますが、希望を持てる地域だとも思っています」
「奥能登の2市2町には非常に魅力的な資源があって、その資源によって地域の生産性が支えられています。能登の魅力を引き出しているのが、地域の事業者さんで、その事業者さんたちが再生していかないと、地域の再生・復興はやはり難しいと思うんです。事業者の全員が諦めるわけではないです。『なんとか取り戻したい』『なんとか続けたい』という方がいらっしゃれば可能なかぎり応援すること、それがわれわれの使命だと思ってます。不安はもちろんありますが、希望を持てる地域だとも思っています」
復興へのビジョンを
この地域には、もう1つ信用金庫があります。
「のと共栄信用金庫」
七尾市に本店を構えています。
「のと共栄信用金庫」
七尾市に本店を構えています。

近くに和倉温泉があることもあって、取引先の多くは宿泊業や飲食業です。
取引先の3分の1は小規模事業者だといいます。
こちらの信用金庫でも、上限1000万円の個人向けの生活再建の融資制度や被災した事業者向けの上限3000万円の特別融資枠などを設けています。
鈴木正俊理事長も、被災した事業者が、前に進む気持ちになれるかどうかが重要だとしたうえで、そのためのカギとして、地域のこの先のビジョンを掲げ共有することを挙げました。
取引先の3分の1は小規模事業者だといいます。
こちらの信用金庫でも、上限1000万円の個人向けの生活再建の融資制度や被災した事業者向けの上限3000万円の特別融資枠などを設けています。
鈴木正俊理事長も、被災した事業者が、前に進む気持ちになれるかどうかが重要だとしたうえで、そのためのカギとして、地域のこの先のビジョンを掲げ共有することを挙げました。

のと共栄信用金庫 鈴木正俊理事長
「日々の生活を続けているときはよいのですが、次第に、今後どうなるんだろう仕事どうなるんだろうとなってきます。早め早めに復興ビジョンを示していかないと、経営者の気持ちが途絶えてしまう可能性があります。ビジョンを示し、それを地域で共有していくことが大事だと思います。さらに、単に元どおりの姿に戻すのではなく、付加価値をつける必要もあります。時間はかかるかもしれませんが、新しいコンセプトのもとに持続可能性のある復興の姿を示せるようにしたいですね。そのために、われわれもアイデアを出し、金融機関としての使命を果たしていきたいです」
「日々の生活を続けているときはよいのですが、次第に、今後どうなるんだろう仕事どうなるんだろうとなってきます。早め早めに復興ビジョンを示していかないと、経営者の気持ちが途絶えてしまう可能性があります。ビジョンを示し、それを地域で共有していくことが大事だと思います。さらに、単に元どおりの姿に戻すのではなく、付加価値をつける必要もあります。時間はかかるかもしれませんが、新しいコンセプトのもとに持続可能性のある復興の姿を示せるようにしたいですね。そのために、われわれもアイデアを出し、金融機関としての使命を果たしていきたいです」
被災地の信金 手をたずさえて
実は、この2人の理事長は、地震のあと、毎日のように連絡を取り合っているといいます。
ふだんであればライバル関係ですが、未曽有の事態を前に、協力して地域を盛り上げたいという思いは同じです。
ふだんであればライバル関係ですが、未曽有の事態を前に、協力して地域を盛り上げたいという思いは同じです。

興能信用金庫 田代克弘理事長
「金融機関や商工会議所、行政が連携して支援につなげていくことが重要になります。われわれにできることは限られていますが、どんどん使っていただきたい。そのために私たちは存在しているので」
「金融機関や商工会議所、行政が連携して支援につなげていくことが重要になります。われわれにできることは限られていますが、どんどん使っていただきたい。そのために私たちは存在しているので」
のと共栄信用金庫 鈴木正俊理事長
「お客さんの経済的な支柱になるとともに、この地域で今後も生活や仕事を続けられるよう、サポートしていく体制があるということをしっかり伝えていきたいです」
「お客さんの経済的な支柱になるとともに、この地域で今後も生活や仕事を続けられるよう、サポートしていく体制があるということをしっかり伝えていきたいです」
今回、取材で訪れた信用金庫の支店の中には、建物が壊れ、社員寮の一角に相談スペースを設けて対応しているところもありました。
避難先から出勤し、制服ではなく私服姿で働く職員もいます。
避難先から出勤し、制服ではなく私服姿で働く職員もいます。

興能信用金庫の田代理事長が言う「日頃お客さまと密に接しているからこそ対応しなければならないという使命感」というものを強く感じました。
一方、事業者の被害の全容はまだ見えず、これだけ取引先が厳しい状況になれば、信用金庫自体の経営に影響が出ることも避けられません。
被災地の産業はどう再生に向かっていくのか、地元に根ざした信用金庫はどう役割を果たしていくのか、これからも取材を続けたいと思います。
一方、事業者の被害の全容はまだ見えず、これだけ取引先が厳しい状況になれば、信用金庫自体の経営に影響が出ることも避けられません。
被災地の産業はどう再生に向かっていくのか、地元に根ざした信用金庫はどう役割を果たしていくのか、これからも取材を続けたいと思います。

(2月12日「ニュース7」などで放送)

経済部記者
榎嶋愛理
2017年入局
広島局を経て経済部。金融分野を担当。
榎嶋愛理
2017年入局
広島局を経て経済部。金融分野を担当。

金沢放送局記者
竹村雅志
2019年入局
金沢局で経済分野を担当。
能登半島地震の直後から、連日、被災地に通い、取材を続ける。
竹村雅志
2019年入局
金沢局で経済分野を担当。
能登半島地震の直後から、連日、被災地に通い、取材を続ける。