日本環境感染学会によりますと、避難所には
▽多くの人が集まり、密な環境になりやすいほか
▽水やアルコールが不足して衛生管理が難しくなることから
感染症が広がりやすい環境になり、過去に起きた大きな災害ではインフルエンザなどの集団感染が起きたことがあるということです。
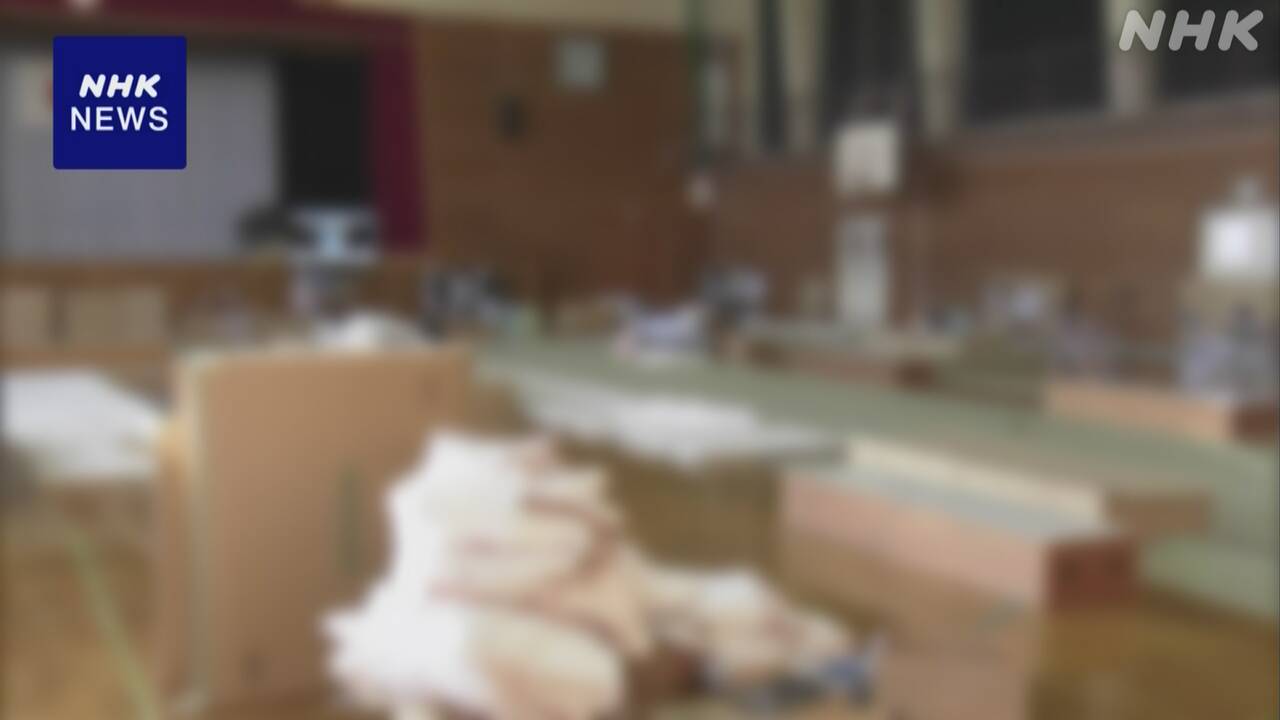
“避難所生活 集団感染に注意 できる範囲で感染対策を”
今回の能登半島地震の被災地では、被災した人の多くが避難所での生活を余儀なくされています。専門家はこうした環境では、1週間ほどするとインフルエンザなどの感染症が増える傾向があると指摘していて、水が不足している環境では手をティッシュで拭いたり、体調の悪い人はマスクを着用したりといった、できる範囲での感染対策を取るよう呼びかけています。

学会の元理事長で、感染症に詳しい東北医科薬科大学の賀来満夫特任教授は、避難生活が始まって1週間ほどすると感染症が増える傾向があると指摘しています。
感染症をきっかけに肺炎で亡くなる人もいるということで、できる範囲での感染対策を求めています。
賀来特任教授は感染症を防ぐためには、まず、食事と排せつの際の手洗いが重要だとしたうえで、せっけんを使って流水で手を洗うことが望ましいものの、被災地では清潔な水が手に入らないこともあるため、「消毒用のアルコールやウェットティッシュ、それが無ければ少量の水やお茶で湿らせたティッシュで手を拭くことでも感染症のリスクを下げることができる」としています。
また、発熱したり、のどの痛みやせきなどの症状が出たりしたときは、感染性の胃腸炎やインフルエンザ、新型コロナに感染している可能性も考えられるため、感染を広げないためにも、可能なかぎり周囲の人から離れた場所で過ごすよう呼びかけています。
また、体調が悪いことを自分から言い出せない人もいるため、体調の悪い人がいないか周りを気にかけて、必要に応じて別室を確保するなどの配慮をすることも重要だとしています。
賀来特任教授は「被災地で感染症対策を徹底することは難しいが、できる範囲で感染対策を進めてほしい。特に、体調が悪いときにはがまんせずに、周囲に助けを求めることが大切だ。医療支援のチームも入り始めているので、なるべく外部の力を頼ってほしい」と話しています。
感染予防のための8か条
東日本大震災が起きた当時、避難所の感染症対策にあたった東北医科薬科大学の賀来満夫特任教授は当時の経験を踏まえて、被災地での感染対策で気をつけてほしいことを「感染予防のための8か条」としてまとめています。
それによりますと、
▼可能なかぎり守ってほしいこととして
1.加熱した食事をとること
2.安心して飲める水を飲むことと、きれいなコップを使うこと
3.食事の前やトイレのあとに手を洗うこと
4.おむつは決められた場所に捨てて、手を洗うことの4つを挙げています。
また
▼症状が出たときの対応として
5.せきが出るときは口を覆い、マスクがある場合はマスクを着用する
6.熱っぽいときやのどが痛いといった症状があるときや、周りに同じような症状の人が増えているときには、医師や看護師、避難所の代表の人に伝える。
7.熱やせきが出ている人や介護する人はなるべくマスクを着用する
8.せきがひどく、黄色いたんが多い場合など、肺炎が疑われるときは早めに医療機関を受診できるよう、医師や看護師、避難所の代表の人に伝えるといった4つを挙げています。
一方、避難生活では、水が十分に無かったり、感染対策に使うマスクやアルコールが不足していたりして、十分な感染対策を取ることが難しいことも多くあり、賀来特任教授は状況に応じて、できる範囲で対策を取ってほしいと呼びかけています。
賀来特任教授によりますと、まずは食事と排せつの際の手洗いが重要だとしたうえで、せっけんを使って流水で手を洗うことが望ましいものの、被災地では清潔な水が手に入らないこともあるため、消毒用のアルコールやウェットティッシュを使ったり、ペットボトル飲料の少量の水やお茶でティッシュを湿らせて手を拭いたりするだけでも、感染症のリスクを下げることができるということです。
また、避難所での履物はトイレで使うものと、ふだんの生活スペースで使うものを分けることができれば、感染対策につながるということです。
次に意識してほしいのは体調の変化への対応だということで、かぜをひいたり、感染性の胃腸炎やインフルエンザ、新型コロナに感染したりすることも考えられるため、発熱したりのどの痛みやせきなどの症状が出たりしたときは、離れた場所や別室で過ごしてほしいとしています。
また、自分から体調不良を言い出せない人もいるため、避難している人も周囲に体調が悪い人がいないか気にかけるとともに休める場所や、保護するスペースを確保してほしいとしています。
また、小さな子どもがミルクを飲まなくなったり、高齢者が食が進まなくなったりすると、肺炎が悪化する兆候の可能性もあるとして、周囲の人が異変に気付くことが大切だと話しています。
さらに、口の中を清潔に保つことが高齢者の誤えん性肺炎を防ぐことにつながるとして、歯磨きができなくても、水やお茶がある場合には定期的に口をゆすぎ、無い場合には水で湿らせたティッシュで寝る前には口の中を拭うようにしてほしいとしています。
このほか、今後、壊れた家屋の片づけに入る場合には、傷口から感染する「破傷風」に注意が必要だとしています。
賀来特任教授は「高齢者を中心に破傷風のワクチンを接種していない人がいるので、厚手の手袋や長靴を履いて作業してほしい。早く片づけをしたい気持ちも分かるが、そうした資材がそろうまでは待ってほしい」と話していました。
そのうえで、賀来特任教授は「東日本大震災のときは何もない状態で、いろいろな工夫をしながらできることを考え、現場の状態に即した感染対策を考えてきた。ひと言で感染対策と言っても、手洗い用品がないのか、清掃のための物品がないのか避難所の状態はさまざまだ。状況をよく把握して、どのような支援が必要なのか見極めて、現場を支えるネットワークを作らなければいけない」と話していました。
日本環境感染学会はDICTを派遣
被災地の感染症対策を支援するために、日本環境感染学会は感染症の対策にあたる医師や看護師のチームを石川県内に派遣しました。
DICT=災害時感染制御支援チームと呼ばれるこのチームは、東日本大震災の際の避難所での感染症対策の経験をもとに作られ、これまで2016年の熊本地震などで感染対策を行ったということです。
チームは石川県七尾市にある公立能登総合病院に常駐して、各地の避難所運営を支援する方針だということです。
学会では今後、感染症対策に使う消毒薬やマスクといった物資の支援も合わせて行うことにしています。
看護師による住民の健康状態の確認

石川県七尾市の避難所では、県の看護協会から派遣された看護師による住民の健康状態の確認が始まりました。
石川県看護協会は看護師3人をそれぞれ七尾市と珠洲市の避難所に5日から派遣しました。
このうち、七尾市の中島小学校では、到着した看護師たちが、糖尿病などの持病がある人の数や、過ごしている部屋などの情報を市の職員と共有しました。
そして、1人ずつ声をかけ、健康状態のほか、薬など不足しているものがないか聞き取りを行っていました。
今後、医療機関での対応が必要なケースがあれば、搬送の調整を行うということです。
また、感染症が広がるのを防ぐためのこまめな消毒や、エコノミークラス症候群を予防するための定期的なストレッチなども呼びかけていくということです。
派遣された看護師の虎本三佳恵さんは「これから長丁場になることが予想されるので、避難している方の健康状態を守れるよう環境整備を進めていきたい」と話していました。
看護協会は要請があれば、派遣する看護師を増やしたいとしています。
仮設トイレの設置進む
石川県は避難所で断水によって衛生環境が悪化しているなどという避難している人の声を受けて、仮設トイレの設置を順次、進めています。
このうち、輪島市では5日と6日で、合わせて30基が設置され、市によりますと5日、設置される避難所は次のとおりです。
▽輪島高校、サンアリーナ、健康センターでそれぞれ3基
▽輪島中学校、河井小学校、鳳至小学校、大屋小学校でそれぞれ2基
▽鳳至公民館、港公民館、大屋公民館でそれぞれ1基です。
また、6日は
▽剱地原子力災害防護施設で4基
▽黒島公民館、諸岡公民館で
それぞれ3基が設置されます。
石川県によりますと、仮設トイレは4日までに国から少なくとも200基程度が届けられていて、被害の大きかった能登半島の自治体の避難所で設置が進められています。
県は今後も自治体の要請に応じて、随時、設置を進めることにしています。
輪島市副市長「トイレに困っていた」
石川県輪島市内の避難所に国が提供した仮設トイレが設置されることについて、中山由紀夫副市長は「避難所ではトイレに困っており、仮設トイレを提供いただき大変ありがたい。感謝申し上げます」というコメントを発表しました。
60代女性「とてもありがたいです」
石川県輪島市の60代の女性は「トイレがとても大変でした。特に女性はすごく困っていました。30台も仮設トイレが来るということもそうですし、個室でできるのもとてもありがたいです」と話していました。
また、金沢市内から実家に帰省していて被災したという20代の男性は「水がでないので、やりっぱなしの状態でしたし、手もアルコール消毒だけでした。仮設トイレがあることはとてもうれしいです」と話していました。