東京・東久留米市に住む秋山耕介さん(28)は重度の知的障害と自閉症があり「強度行動障害」の状態にあります。
平日の日中は自宅から30分余り離れた作業所に通っていますが、気持ちが不安定になると、壁紙をはぎ取ったり、職員を叩いたりしてしまうことがあるといいます。
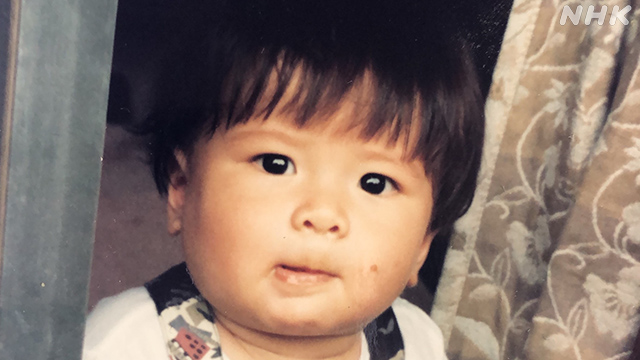
「息子が幸せに暮らす環境を」強度行動障害ある人の支援強化へ
1歳になる前の写真です。
歩くのがとても速く、目を離すと1人でどんどん遠くへ行ってしまう子どもでした。
「問題となる行動を取ることはありますが、不満も言わず家事を手伝ってくれる優しくて素直な息子です」(母親)
今、28歳になった耕介さんは、自分や周りの人を傷つけたりものを壊したりといった行動が頻繁にみられる「強度行動障害」の状態にあり、日中は作業所に通いながら過ごしています。
国は、来年度から支援を強化することになりました。
耕介さんの生活は

また、作業所を抜け出して近くのコンビニに入り、まだ購入していない商品を口にしたり、病院の非常ボタンを押してしまったりして警察に通報されたこともあったということです。
母親のつぐみさん(61)はそのたびに、店員や警察官に本人の障害について説明するなどの対応にあたらなければならず、ヘルパーなどの福祉サービスを利用している時間帯以外は、目が離せないといいます。
福祉サービスの利用にも制約が
さらに、週末に耕介さんが外出する際にはヘルパーに付き添いを頼んでいますが、本人の特性を理解して対応できるスタッフは限られるため利用を断られることがたびたびあります。
本来であれば月に30時間利用できるサービスを、現在は月に1度6時間程度しか利用できていないということです。

ここ数年、体力的な衰えを感じるようになり、耕介さんの面倒をみていけるか不安を感じるようになったつぐみさんは、耕介さんが暮らせるグループホームなどを探し始めています。
なじみのある社会福祉法人のグループホームはいっぱいで、これまで空きが出た際に2度利用を申請しましたが、いずれも入居がかないませんでした。

重度の知的障害がある子どもがいる知人の中には、自宅近くのグループホームなどに空きがなく遠く離れた他県の施設に入居させざるをえなかった人もいます。
つぐみさんは、耕介さんが将来安心して暮らせる場を得られるのか、不安を感じ始めています。
母・つぐみさん
以前は1日かけて耕介と出かけることもありましたが、最近は体力と気力が落ちて半日見ているのが限界だと感じるようになりました。日中、作業所に通えているので、まだ自分は恵まれている方だと思いますが、高齢になればいつ病気になるかわかりません。

その上で、次のように話しています。
耕介は問題となる行動を取ることはありますが、家では不満を口にすることなく家事を手伝ってくれるような優しくて素直な息子です。高度な支援ではなくとも、好きなときに音楽を聴けたり散歩に出かけられたり、楽しく幸せに暮らせる環境があってほしいです。
「強度行動障害」とは
「強度行動障害」とは、自分自身や周りの人を傷つけてしまったり、ものを壊したりといった行動が頻繁にみられる状態で、もともとある障害ではありません。
重度の知的障害を伴う自閉症の人に多いとされていて、全国に少なくとも延べ7万8000人以上いるとみられています。
厚生労働省などによりますと、こだわりが強かったり感覚が過敏だったりする特性があり、周りの人の対応や環境などにストレスや不安を感じて引き起こされるということです。
そのため、その特性をふまえて声かけをしたり、生活環境を整えたりすることで状態を改善させることができるということです。
しかし、おととし(令和3年)国の事業として行われた調査で施設などの利用を中断した「強度行動障害」のある人の家族に理由を尋ねたところ「職員にけがをさせるなどして利用を断られた」といった回答が寄せられ、十分な支援を受けられていないケースも明らかになっています。
「サービス十分提供されず家族に重い負担」
また、全国の市区町村を対象に「強度行動障害」のある人の福祉サービスの利用状況を尋ねたところ、739の自治体が次のように回答しました。
▼「ニーズが満たされているか把握していない」・・・49%
▼「福祉サービスなどにつながっているがニーズが満たされていない人を1人以上把握している」・・・27%

「受け入れ体制が整わず、サービスが十分に提供されないことで、同居する家族にとって重い負担になっている」
「強度行動障害」に関する国の検討会は、ことし3月にまとめた報告書で、このように指摘し、支援にあたる人材のさらなる専門性の向上に向けた人材育成が重要だとしています。
支援の現場では離職相次ぐ
「強度行動障害」のある人を多く受け入れる福祉サービスの事業所では、支援の難しさなどを背景に離職する職員もいて、人手を確保するための対策を国に求める声が聞かれました。

大阪・吹田市にある日中の作業所の「集いの場ふりーばーど」では、39人の利用者のほとんどが重度の知的障害者で、「強度行動障害」のある利用者が22人います。
利用者は商品となる小物を作るなどしていますが、その日の体調によって他の利用者や職員を叩いたり物を壊したりしてしまう人も多く「強度行動障害」のある利用者に対しては職員が1対1で支援にあたっています。
また、気持ちが不安定になって作業を続けられなくなった利用者が落ち着きを取り戻せるように専用の休憩室を設けるなど、過ごしやすい環境を整えています。

人手の確保が課題
一方で、課題となっているのは人手の確保だといいます。
30人の職員のうちおよそ20人は非正規雇用で、パートのスタッフなどによって支えられていますが、作業所によりますと利用者から目を離すことができないなど責任や体力が求められ、離職してしまう人も少なくないといいます。

去年は5人が離職して、中には1か月ほどで辞めてしまう人もいたということです。
「強度行動障害」のある利用者の支援では障害の特性を学ぶだけではなく、本人と長期間接することで性格や考えを理解することが求められることから、長期的に安定して人手を確保できるような国の対策が必要だといいます。
施設長 山下徹さん
支援は簡単ではありませんが、その分、本人の気持ちを理解できたときなどのやりがいは大きいです。国の対策のひとつの『強度行動障害』に関する研修などを通じて知識を蓄えられるというのはとても大事なことだと思いますが、現場は人手の確保が難しいのが現状です。
賃金に反映できるだけの報酬を加算するなどして人手を確保し、職員が余裕をもって働けるような職場環境を整えることも大切です。
国は事業所への報酬加算など支援強化へ
厚生労働省は来年度行われる3年に1度の障害福祉サービスの報酬改定に向けて、6日に専門家会議を開き「強度行動障害」に関する専門的な知識を持つ人材を育成・配置した事業所への報酬を加算するなど支援を強化することを決めました。

具体的には、
▽「強度行動障害」がある利用者の行動を詳しく分析して支援内容を決めるリーダー役の「中核的人材」を配置した場合
▽「強度行動障害」に関する専門的な知識を持った「広域的支援人材」を配置し支援が難しくなっているグループホームなどに繰り返し足を運んで指導や助言を行うなどした場合に加算の対象とする方針です。
厚生労働省は来年度の予算編成をふまえて、今後、具体的な報酬の改定案を取りまとめることにしています。
専門家「チームで一貫した支援体制を」
「強度行動障害」のある人の支援に詳しく、国の検討会でも委員を務めた鳥取大学大学院の井上雅彦教授に聞きました。

鳥取大学大学院 井上雅彦 教授
『強度行動障害』のある子どもがいる親たちの中には、子どもを福祉サービス事業所に送ったものの、問題を起こしてクレームを受けたり、利用を断られたりする経験が重なって、孤立してしまう人が少なくない。重度の知的障害や自閉症の強い方に関する知識を身につけて、本人の特性を理解した上で支援にあたることが非常に大切だ。
一方で、支援の現場で人手不足が深刻化していることについて、「専門性に見合った給料を支払える報酬体系や、メンタルヘルスなど困ったときに相談できる体制を作り、 最前線で支援にあたる人たちを守る仕組みも求められている」と話しました。その上で。
『強度行動障害』はライフステージを通して支援する必要があり、ひとつの事業所だけで対応できるレベルの話ではない。学校や医療機関を含め、地域がチームで一貫した支援をできる体制を作っていくことが欠かせない。そのためにも、まずは自治体が福祉サービスが十分に届いていないケースがどれほどあるのかを把握することが非常に重要だ。
【詳報】障害者福祉サービス報酬改定の基本的な方針
来年度の障害福祉サービスの報酬改定に向けて、6日に開かれた専門家会議では福祉サービスや障害の特性などの項目ごとに改定の基本的な方針が取りまとめられました。以下、項目ごとに内容を紹介します。
入所施設
今回の改定では、障害者が郊外などにある大規模な入所施設ではなく、希望する地域での生活を実現するための支援の強化が重点的なテーマとなっています。
これを受けて、入所施設では、すべての入所者に対し、施設以外での暮らしの場について意向を確認した上で、希望に応じて地域のグループホームの見学を調整するなどした施設に対して報酬が加算されます。
また、入所者の意向を確認する責任者の選任や地域のグループホームに移るための個別計画の策定などを令和8年度から義務付け、これらを行っていない施設への報酬を減額することにしています。
グループホーム
地域での生活の主な受け皿となるグループホームについては、1人暮らしを希望している利用者の意向を確認した上で住宅の確保のための支援などを行った事業所への報酬を加算します。
また、グループホームの運営の透明性を確保するため、来年度から地域の住民や障害福祉の専門家などで作る会議を設置し、定期的に事業所を訪れて支援の状況を確認したりアドバイスをしたりするということです。
訪問系サービス
判断能力が制限されている障害者の外出などを支援する「行動援護」のヘルパーに「強度行動障害」のある人など、障害の程度がより重い利用者の対応にあたらせた場合や、「強度行動障害」に関する専用の研修を受けさせた場合に事業所への報酬が加算されます。
相談支援
障害者やその家族などからの相談に応じ、適切な福祉サービスとつなげたりサービスの利用計画を作成したりする「相談支援専門員」については、障害福祉サービスのニーズの高まりに伴い人手不足が課題となっています。
これを解消するため「相談専門員」という新たな制度を立ち上げます。
一定の職員体制が確保され、高度な専門的な知識がある「相談支援専門員」をすでに配置している事業所は、常勤の社会福祉士や精神保健福祉士を新たに「相談支援員」と位置付けて利用計画の作成などにあたることができるようします。
処遇改善加算
福祉サービスの職員の賃上げを実現するため、要件を満たした事業所は3種類の「処遇改善加算」を受け取ることができますが、厚生労働省によりますとそれぞれの加算に対して申請を行う必要があることなどから、事務作業が煩雑で業務を圧迫し、加算を取得していない事業所も少なくないということです。
このため、来年度からは3種類の処遇改善加算を1本化することで事務作業を軽減させることにしています。
児童発達支援・放課後等デイサービス
障害児通所支援事業所が、子どもの状態やニーズに応じて地域の保育所などに移ることを支援する取り組みに新たに報酬が加算されます。
また、事業所で医療的ケアを行う看護師の人手不足が課題となるなか、必要な研修を受けてたんの吸引などを行えるようになった介護職員などが子どもの支援を行った場合の報酬をこれまでよりも引き上げる方針です。
さらに子どもの発達や日常生活、それに家族を支える観点から、日常的にたんの吸引や人工呼吸器などが必要な「医療的ケア児」や重症心身障害児に対して発達支援とあわせて入浴支援を行った場合に、新たに報酬が加算されるということです。
保育所等訪問支援
障害のある子どもたちを地域の保育所などで受け入れる体制を整備するため、子どもが保育所や幼稚園での集団生活に適応できるよう訪問支援員が専門的な支援を行う「保育所等訪問支援」について、より専門的な支援が必要な「医療的ケア児」や重症心身障害児などに対応した場合に新たに報酬を加算するということです。
また、障害の特性などに応じた支援につなげるため、職種の異なる複数の人で連携して支援を行った場合にも報酬が加算されるということです。