NHKプラス
配信期限 :10/17(火) 午前7:45 まで
CODA 知っていますか? “耳が聞こえない”親がいる子どもたち

「CODA(コーダ)」ということば、皆さん、ご存じでしょうか?
「Children of Deaf Adults」の略です。耳が聞こえない、または聞こえにくい親がいる「子どもたち」のことを表します。
「CODA」と呼ばれる子どもたち自身は、耳が聞こえます。あくまで「親が耳が聞こえない」という「子どもたち」のことを表すのですが、近年、専門家の推計で、国内におよそ2万2000人いることが明らかになりました。
子どもたちの中にはみずから手話などを使って、親の手伝いを日常の中ですることがあります。取材を進めると、時に、子どもたちに大きな負担がかかっている現状が見えてきました。
(首都圏局 記者 喜多美結、おはよう日本 ディレクター 棚橋大樹)
「Children of Deaf Adults」の略です。耳が聞こえない、または聞こえにくい親がいる「子どもたち」のことを表します。
「CODA」と呼ばれる子どもたち自身は、耳が聞こえます。あくまで「親が耳が聞こえない」という「子どもたち」のことを表すのですが、近年、専門家の推計で、国内におよそ2万2000人いることが明らかになりました。
子どもたちの中にはみずから手話などを使って、親の手伝いを日常の中ですることがあります。取材を進めると、時に、子どもたちに大きな負担がかかっている現状が見えてきました。
(首都圏局 記者 喜多美結、おはよう日本 ディレクター 棚橋大樹)
両親が耳が聞こえない「CODA」のきょうだい
大阪府貝塚市に住む、小学5年生の松下理音(まさね)さんと、小学4年生の妹の佳冬(かふゆ)さんです。2人ともテニスが大好きです。


彼女たちを見守る父親の哲也(てつや)さんと母親の恵(めぐみ)さんです。
ふたりは生まれたときから耳が聞こえないため、手話で会話しています。
ふたりは生まれたときから耳が聞こえないため、手話で会話しています。

子どもたち、理音さんと佳冬さんは耳が聞こえますが、耳が聞こえない両親との会話は手話が中心です。

母・恵さん(手話で)
「次は浅いボールを打ってみたら」
「次は浅いボールを打ってみたら」
理音さんたちのように、『聞こえない親のもとで育つ、聞こえる子どもたち』は、CODA(コーダ)と呼ばれています。

理音さん
「危ない」
佳冬さん
「裏がえさな」
理音さん
「もうやめてー」
「危ない」
佳冬さん
「裏がえさな」
理音さん
「もうやめてー」
理音さんと佳冬さんは、きょうだいでは声を出して会話しています。
両親とは手話で会話していますが、どちらも“自分たちの日常だ”といいます。
両親とは手話で会話していますが、どちらも“自分たちの日常だ”といいます。

松下理音さん
「手話は絶対必要になるけど、聞こえない場所と聞こえる場所ではどっちも同じかな」
「手話は絶対必要になるけど、聞こえない場所と聞こえる場所ではどっちも同じかな」
きょうだいが担う「ある役割」
親子が日常生活を送るなかで、耳が聞こえる理音さんたちきょうだいは『ある役割』を担います。
それは、通訳の役割です。
それは、通訳の役割です。

スーパーの店員
「袋無くて大丈夫ですか?」
「袋無くて大丈夫ですか?」
母・恵さん
「いらない」
佳冬さん
「いらない」
「いらない」
佳冬さん
「いらない」
母親とスーパーに買い物にやってきたこの日、理音さんたちが、店員と母親の恵さんの間に入って、店員さんの問いかけに答えていました。

母・恵さん
「(レジで)時間がかかると後ろに並んでいる人が気になるので、その時に子どもがすぐに通訳してくれると助かります」
「(レジで)時間がかかると後ろに並んでいる人が気になるので、その時に子どもがすぐに通訳してくれると助かります」
“お手伝い”が時に大きな負担に
自然と母親のお手伝いをする子どもたち。
しかし、取材を進めると、「時には大きな負担がかかっていること」が見えてきました。
9月、理音さんは、地元の祭りの運営に関する話し合いに、母親と一緒に急きょ参加することになりました。
しかし、取材を進めると、「時には大きな負担がかかっていること」が見えてきました。
9月、理音さんは、地元の祭りの運営に関する話し合いに、母親と一緒に急きょ参加することになりました。

母親の恵さんは、いつもは事前に行政に申請して手話通訳を派遣してもらっていますが、この日は急だったため、娘の理音さんに通訳の役をお願いせざるをえなかったのです。
しかし、話し合いの中で、理音さんが知らない言葉もたびたび登場します。
地元の祭りの会長が話した「救護班」の意味がわからなかった理音さんは、母親に、ひと文字ひと文字、伝えました。
しかし、話し合いの中で、理音さんが知らない言葉もたびたび登場します。
地元の祭りの会長が話した「救護班」の意味がわからなかった理音さんは、母親に、ひと文字ひと文字、伝えました。

祭りの会長
「救護班ね」
「救護班ね」
理音さん
「キ・ュ・ウ・ゴ・ハ・ン」
母・恵さん
「ああ、救護班ね」
「キ・ュ・ウ・ゴ・ハ・ン」
母・恵さん
「ああ、救護班ね」
そして、およそ1時間の会議が終わるころ。
地元の祭りの会長が、「母親の恵さんから何か質問はないか」理音さんに聞きました。
地元の祭りの会長が、「母親の恵さんから何か質問はないか」理音さんに聞きました。
祭りの会長
「ききたいことはない?」
「ききたいことはない?」

恵さん
「何?」
理音さん
「ききたいことはない?って」
恵さん
「さっきのむすびって?」
理音さん
「むつみ」
恵さん
「むすび?」
「何?」
理音さん
「ききたいことはない?って」
恵さん
「さっきのむすびって?」
理音さん
「むつみ」
恵さん
「むすび?」
自分が知らない言葉を、ひと文字ひと文字、伝えるにも難しさがあります。
この時、祭りのはっぴのサイズ『6』を表す『むつみ=六つ身』という言葉を母親にうまく説明をすることができませんでした。
この時、祭りのはっぴのサイズ『6』を表す『むつみ=六つ身』という言葉を母親にうまく説明をすることができませんでした。
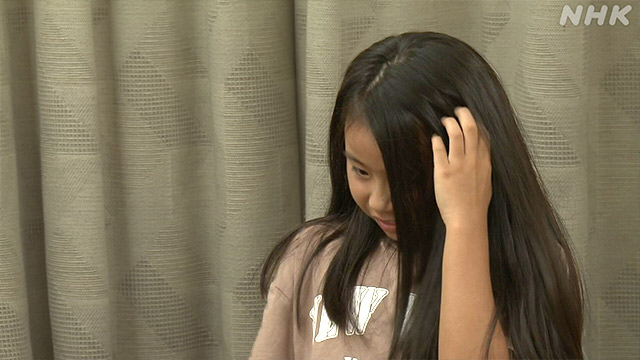
松下理音さん
「伝えられなかったところがちょっと悔しかった。分からない言葉を言われたから、どうやって伝えればいいのかわからなかった」
「伝えられなかったところがちょっと悔しかった。分からない言葉を言われたから、どうやって伝えればいいのかわからなかった」
母親の恵さんは、日ごろの娘たちの姿に感謝する一方で、子どもたちに負担をかけていることが心苦しいといいます。

母・恵さん
「子どもに通訳をしてもらうというプレッシャーを与えてしまったかなと、申し訳ない気持ちがあります。(理音さんが)テニスと関係がある学校に行きたいというのがあって、これからもっと勉強をすることになるかもしれません。そう考えると、子どもの時間を作ってあげたいなと思います」
「子どもに通訳をしてもらうというプレッシャーを与えてしまったかなと、申し訳ない気持ちがあります。(理音さんが)テニスと関係がある学校に行きたいというのがあって、これからもっと勉強をすることになるかもしれません。そう考えると、子どもの時間を作ってあげたいなと思います」
専門家「周りの大人たちは 直接親と会話して」
親子同士のほうが話しやすいのかなと、周りの大人たちが遠慮して、耳の聞こえない親に話しかけるのではなく、耳の聞こえる子どもの方に話しかけてしまうことがありますが、その遠慮が、親子にとって負担になる面もあると、取材を通して感じました。
CODAの子どもたちに大きな負担をかけないためのポイントは、周りの大人たちが、耳が聞こえない大人、この場合は、お母さんと直接話すことです。
専門家は、こう指摘しています。
CODAの子どもたちに大きな負担をかけないためのポイントは、周りの大人たちが、耳が聞こえない大人、この場合は、お母さんと直接話すことです。
専門家は、こう指摘しています。

東京大学バリアフリー支援室 中津真美 特任助教
「聞こえるコーダを頼るのではなくて、直接(聞こえない親と)会話をしてほしい。手話がわからなくても、筆談だったり指さしや身ぶり、または口元を大きく開けて会話をするだけでもずいぶんと伝わるのではと思います」
「どうしたら目の前にいる自分と異なるコミュニケーション手段を持つ人に伝えることができるか思い巡らせて、まずはやってみる」
「聞こえるコーダを頼るのではなくて、直接(聞こえない親と)会話をしてほしい。手話がわからなくても、筆談だったり指さしや身ぶり、または口元を大きく開けて会話をするだけでもずいぶんと伝わるのではと思います」
「どうしたら目の前にいる自分と異なるコミュニケーション手段を持つ人に伝えることができるか思い巡らせて、まずはやってみる」
たとえば、「六つ身」のような言葉を、耳の聞こえない人にどう伝えたらいいか。
「六つ身」は音だけではわかりにくいことばなので、ホワイトボードや紙などに文字で書く。
また、祭りの「はっぴ」は、『はっぴ』と服を指さしながらジェスチャーするなど、いろいろな手段があります。
よりわかりやすいことばを使ったり、より口を大きくしたり、よりゆっくり話すということも有効です。
なぜなら音ではなく、目から得られる情報が大切だからです。
中津さんは、「フラットな関係性のなかで、“ちょっとした工夫”でお互いをわかり合うことが大事だ」と指摘しています。
「六つ身」は音だけではわかりにくいことばなので、ホワイトボードや紙などに文字で書く。
また、祭りの「はっぴ」は、『はっぴ』と服を指さしながらジェスチャーするなど、いろいろな手段があります。
よりわかりやすいことばを使ったり、より口を大きくしたり、よりゆっくり話すということも有効です。
なぜなら音ではなく、目から得られる情報が大切だからです。
中津さんは、「フラットな関係性のなかで、“ちょっとした工夫”でお互いをわかり合うことが大事だ」と指摘しています。
社会全体で支えるには
そして、社会全体の仕組みとしては、行政に申請して手話通訳者を派遣してもらう『制度』や、聞こえない人と聞こえる人をつなぐ『電話リレーサービス』といったものがあります。こうした仕組みの利用が、CODAの子どもたちを支えることにつながります。

こういったサポートがあることを当事者だけではなくみんなで知ると、誰もが歩み寄りやすくなって、より暮らしやすい社会につながります。

CODAの子どもたちが、私たちの周りにもいること。そして、お互いの会話の方法は、声と手話だけではないことを広く知ってもらい、CODAを社会全体で支えていくことにつながっていってほしいと思います。そして、みんなが想像力を持って、すべてのひとに優しい世界になっていってほしいと感じました。
10月10日(火) おはよう日本で放送

首都圏局 記者
喜多美結
2023年入局
共生社会やスポーツ、教育に関心があります。
喜多美結
2023年入局
共生社会やスポーツ、教育に関心があります。

おはよう日本 ディレクター
棚橋大樹
2015年入局
初任地は大阪局。歴史、国際に関心があります。
棚橋大樹
2015年入局
初任地は大阪局。歴史、国際に関心があります。