企業などに勤め、厚生年金や健康保険に加入している配偶者の扶養に入っている人は、みずから社会保険料を支払わなくても、基礎年金を受給できるほか、保険診療を受けることができます。
ただ、パートなどで働き一定の年収を超えると扶養を外れてみずから保険料を支払う必要があり、手取りが減ることから「年収の壁」と呼ばれています。
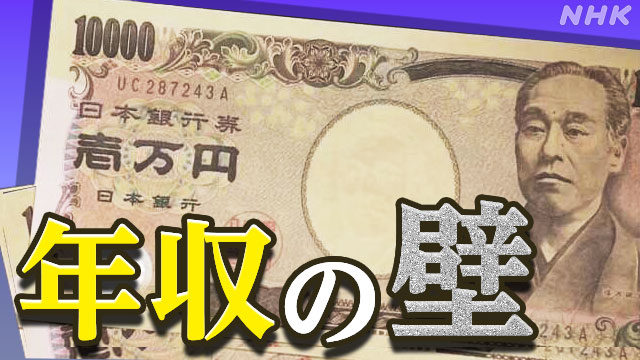
“時給上がったから働く時間減らさないと”「年収の壁」対策へ
一定の年収を超えると、配偶者の扶養を外れて社会保険料の負担が生じ、手取りが減ってしまう、いわゆる「年収の壁」をめぐり、岸田総理大臣は、手取りが減らないように取り組んだ企業に対し、従業員1人当たり最大で50万円を助成する対策を来月から実施する方針を明らかにしました。
「年収の壁」を超えると手取りの収入が減るため働く時間を抑える人がいて、人手不足の要因とも指摘されています。こうした懸念の声を払しょくできるのでしょうか。
目次
「年収の壁」とは

従業員が101人以上の企業などで働く人は、年収が106万円を超えると扶養を外れ、厚生年金や健康保険の保険料の支払いによって手取りが減り、おおむね125万円まで、その状態が続きます。
- 注目
スーパーでは人手不足への懸念
パートタイムの従業員が多く働くスーパーの業界からは、「年収の壁」を意識して従業員が労働時間を減らすことによる人手不足への懸念の声があがっています。
「月収8万8000円を超えないように…」
山梨県を中心に15店舗のスーパーを展開する「いちやまマート」は、従業員1400人余りのうち、およそ8割にあたる1100人ほどがパートタイムで働く人です。
商品の陳列などを担当する従業員の齋藤麻衣さん(34)は、スマートフォンのアプリで出退勤の時間や、日当などを毎日記録しています。
年収の壁を越えないよう徹底して管理し、1週間の労働時間が20時間を超えないように抑えています。

齋藤麻衣さん
「夫の扶養から外れないように、毎月8万8000円を超えないように気にしています。今の時給で社会保険料を引かれてしまうと生活が厳しい。正直年金などで返ってくると言われてもどこまで返って来るのか分からないので毎月管理したほうがいいと思っています」
実際どれぐらい“損”する?
「年収の壁」を超えると、世帯でどれくらい“損”をするのか?
条件は住んでいる地域や勤めている会社の規模によって異なります。
野村総合研究所が条件を設定して、次のような試算をしています。

[条件]
●二人世帯(他に扶養者なし)
●夫の年収 500万円(家族手当含まず)
●税金や保険料が引かれる
●妻はパートタイムで働く
●妻の年収が…
・100万円超で住民税がかかる
・103万円超で月額1万7000円の会社の「家族手当」支給停止
・106万円超で社会保険加入
妻の年収が100万円のときは世帯の手取り額が「513万円」ですが、妻の年収が106万円に上がると社会保険料などの支払いが増え、手取り額は「489万円」に減ってしまうのです。この差額の「24万円」がいわば“働き損”です。
「年収の壁」を超えて手取りを増やすには、妻は年収の4割増しにあたる138万円以上になるまで働かないといけないということです。
賃上げの影響 「年収の壁」に早く到達するから…

さらに人手不足の要因と考えられるのが、最低賃金の引き上げです。
山梨県の最低賃金は、来月から時給898円から938円まで上がります。
このスーパーでは、パートタイムで働く多くの人たちの時給を、この3年間は毎年30円程度あげ、来月からさらに上げる予定です。
しかしその分、106万円とされる「年収の壁」に早く到達することから、配偶者の扶養の範囲内に収めようと労働時間を減らす人が増えているということです。
山梨県中央市の店舗では、毎週木曜の安売りの日には、客が増えるものの従業員の数が足りないためレジを十分に開けられず、稼働できないレジの前には休止中の看板が置かれていました。
また、パンのコーナーでも一日に何回もパンを焼き、焼きたてを提供してきましたが、従業員不足の影響で午後早い時間までにすべて作り終え、夕方以降に焼くのを取りやめざるをえなくなったということです。

いちやまマート 辻隆元 取締役
「扶養の範囲で働きたい人の時給単価が上がり、労働時間を減らしてほしいと依頼されるが、減らした分は新しく人を採用する必要がある。しかし、昨今の人手不足で採用も困難となっていて、厳しい状況となっている」
賃上げも 多くの人が就業調整か
「年収の壁」をめぐっては最低賃金の大幅な引き上げが続くなか、パートタイムで働く人たちなどが年収を配偶者の扶養の範囲内に収めようと働く時間を減らす「就業調整」を行うことが、企業の人手不足を加速させていると指摘されています。

最低賃金は、今年度までの10年間で4回にわたって引き上げ幅が過去最大を更新し、10年前の2014年に全国平均で時給780円でしたが224円上昇し、今年度は時給1004円となりました。
内閣府によりますと、最低賃金の影響が時給に直結しやすいパートタイムの時給は2021年までの過去25年間でおよそ30%上昇した一方で、年収の伸びはおよそ5%にとどまっていて、時給が上がっても必ずしも年収アップにつながらない状況が続いています。
また、パートタイムで働く人の1か月の総実労働時間の平均は1997年には96.8時間でしたが、減少傾向が続き、2021年には78.8時間と減少しています。
厚生労働省が2021年に行った調査では、配偶者がいるパートタイムで働く女性のうち、21.8%の人が「就業調整」をしていると回答しています。
その理由については、複数回答で聞いたところ、
▽「一定の年収を超えると配偶者の健康保険、厚生年金保険の被扶養者からはずれ、自分で加入しなければならなくなるから」と回答した割合は57.3%、
▽「一定の労働時間を超えると雇用保険、健康保険、厚生年金保険の保険料を払わなければならないから」と回答した割合は21.4%となっています。
「就業調整」している > していない
民間のシンクタンク、野村総合研究所が去年9月に行った調査では、配偶者がいてパートタイムやアルバイトとして働く全国の20歳から69歳の女性およそ3000人のうち、61.9%が「就業調整」をしていると回答し、38.1%の「調整していない」を大きく上回りました。

また、59.4%が時給の上昇によって以前より「就業調整」をせざる得なくなったと感じた経験があると回答しています。
さらに年収の壁を超えても手取りが減らないのであれば年収が多くなるよう働きたいかと尋ねたところ、「とてもそう思う」が36.8%、「まあそう思う」が42.1%と、あわせて80%近くが年収が多くなるように働きたいと考えていることがわかりました。
こうした調査結果などから、スーパーの業界や宿泊業界などパートタイムで働く人を多く雇用する企業からは、年収の壁を意識した就業調整が人手不足の要因となっているとして、対策を求める声があがっていました。
- 注目
週内に「支援強化パッケージ」決定へ

岸田総理大臣は25日夜、総理大臣官邸で記者団に対し「若い世代の所得向上や人手不足への対応の観点から『年収の壁・支援強化パッケージ』を週内に決定し、時給1000円超えの最低賃金が動き出す来月から実施していく」と述べました。
《106万円の「壁」》
厚生年金が適用される企業などで、働く人が扶養を外れる「106万円の壁」について、年収がおおむね125万円を超えると手取りが増え始めるため、その水準まで手当を支給したり、賃上げを行ったりした企業に対し、従業員1人当たり最大で50万円を助成するとしています。
今回の助成金は手取りが減らないようにするためのものですが、期限を設ける予定で、いわば当面の対策です。
先週開かれた厚生労働省の審議会では根本的な解決策として、保険料を減免して手取りが減らないようにする案について議論されましたが、委員からは、そもそも扶養に入っていない人との公平性に欠けるなどと異論が相次ぎました。
厚生労働省は再来年に行う予定の年金制度改正に向けて、引き続き議論していくことにしています。
《130万円の「壁」》
一方、従業員が100人以下の企業や業種により、厚生年金の適用対象になっていない職場で働く人は、年収が130万円を超えると扶養を外れ、国民年金や国民健康保険の保険料を支払うようになりますが、国民年金の制度上、将来受け取ることができる年金額は、自身で支払っていない時と変わりません。
このため今回の対策では、130万円を超えても、一時的な増収であれば2年まで扶養にとどまれるようにする方向で調整しています。
また厚生労働省は今後、厚生年金に加入できる要件を緩和して、年金の保険料を支払えば受け取れる年金が増える対象を増やし、「壁」を意識せずに働いてもらえるようにしていきたいとしています。
《「壁」を超えるメリットも》
厚生年金や健康保険に加入することで、将来受け取ることができる年金が増えるほか、けがや病気で休んだ際の「傷病手当金」や「出産手当金」を受け取れるといったメリットもあります。
そうした点をいかに周知していくかも課題となります。
専門家 “制度の抜本的見直し必要”

社会保障制度に詳しい日本総合研究所の西沢和彦理事はNHKの取材に対し、「130万円の壁」への対策について「これから年末にかけて繁忙期も迎える中で、残業できたり、労働時間の延長に事業主が賞与で報いたりしやすくなり、即効性はある」と評価しました。
一方で「扶養の範囲が拡大することは、恩恵を受けていない人からは不公平にも映る」と指摘したほか、「子育てや介護など、自分の時間と働く時間のバランスの中で、こうした働き方をパートの人が望んでいるのか疑問がある」と述べ、対策の実効性には不透明な点もあると指摘しました。
そのうえで「今回の対策は、あくまで人手不足対策という経済対策にとどまっているが、正社員の夫とそれを支える専業主婦の妻という過去の価値観で作られている現行の制度を、新しい価値観で見直していく視点が重要だ」と述べ、扶養のあり方を含め、抜本的な見直しが必要だという考えを示しました。