国家公務員をめぐっては、いわゆる「キャリア官僚」となる「総合職」の来年春の採用に向けた試験の申し込み者数が、過去2番目に少なくなるなど、人材が集まりにくくなっていて、なり手不足が課題となっています。
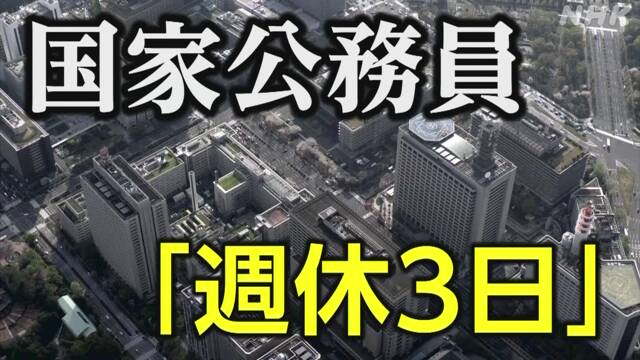
国家公務員の「週休3日」導入を勧告 “官僚離れ” 解消なるか
国家公務員のなり手不足が課題となる中、人事院は「週休3日」の働き方を可能とするよう、内閣と国会に勧告しました。休みを取った分は、ほかの勤務日に働く時間を長くすることで、総労働時間は維持するということです。
国家公務員 東大生のイメージは

キャリア官僚のイメージについて、国家公務員「総合職」の合格者数が例年もっとも多い東京大学の学生に聞きました。
(学生)
「休みもそんなにしっかり取れていないのかなと。漠然としたイメージで」
「公務員は選択肢に入っていませんでした。大学の先輩から残業が多い、大変だって話を聞きます」

志望者数の減少に加え、採用されたあとの離職者数も増加傾向にあり、総合職のうち採用後10年未満で退職した職員の数は、3年連続で100人を超えています。
「週休3日」の働き方とは
こうした状況を受けて人事院は、フレックスタイム制を活用して、週に1日を限度に、土日以外に休みを取り、「週休3日」の働き方を可能とするよう内閣と国会に勧告しました。

休みを取った分は、ほかの勤務日に働く時間を長くすることで、4週間で合わせて155時間となっている総労働時間は維持するということです。
これまで、こうした働き方は、育児や介護を行っている職員などに限定されて認められていましたが、希望するすべての職員を対象にすることで、人事院は、国家公務員の多様な働き方を拡大させたいとしています。
人事院は、再来年、令和7年4月1日から施行できるよう、必要な法改正などを実施するよう求めています。
人事院総裁 “人材確保は依然厳しく危機的状況”
人事院の川本総裁は、記者会見で「人材確保は、応募者の減少や若手職員の離職の増加などにより依然として厳しい、危機的とも言える状況にある。『ブラック』というイメージがなかなか払しょくされず、こうした状況を打開しないといけないことは、霞が関の共通の思いだ」と述べました。
そのうえで「この国の利益や生活を守り、世界最高水準の行政サービスを提供し、活力ある社会を築くため、国家公務員がいきいきと働けるよう、制度や運用の面から、よりよくしていくことが人事院の役割だ」と述べました。
そして、今後の働き方改革の具体的な内容として、
▽職員の健康を確保するため、次の勤務までに一定の休憩時間を設ける勤務間のインターバルを確保することや、
▽職員の成長や組織力の向上につながる兼業の在り方などについて、検討を進める考えを明らかにしました。

霞が関の働き方改革について提言を行ってきた専門家は導入にはメリットも大きいと指摘します。
(働き方改革のコンサルティングを行う小室淑恵さん)
「週休3日制というのは、取得の理由を問わず、家庭的な事情以外の人でも使えるようになる休みで非常に意味があります。来年の春に効果があるような単純なことではないですが、新しい働き方ができるようになったらそこで働きたいと思うのでは」