私たちはどう生きればよいのか 安倍元総理銃撃事件1年 識者は

安倍元総理大臣の銃撃事件から1年。
山上徹也被告が「動機は旧統一教会だ」とする中、教団が抱える問題が改めて注目を集め、政治家とのつながりも明らかになった。
また、被告の刑を軽くするよう求める署名など、一部で被告の境遇に思いを寄せる動きもある。
今年4月、岸田総理大臣の近くに爆発物が投げ込まれる事件も起きた。
暴力の連鎖を生まないため、私たちはどうすればよいのか。
作家、歴史家、社会学者らのことばから、この時代を生きるヒントを探す。
(大阪放送局ディレクター 白瀧愛芽 馬宇翔 山岸聖也)
山上徹也被告が「動機は旧統一教会だ」とする中、教団が抱える問題が改めて注目を集め、政治家とのつながりも明らかになった。
また、被告の刑を軽くするよう求める署名など、一部で被告の境遇に思いを寄せる動きもある。
今年4月、岸田総理大臣の近くに爆発物が投げ込まれる事件も起きた。
暴力の連鎖を生まないため、私たちはどうすればよいのか。
作家、歴史家、社会学者らのことばから、この時代を生きるヒントを探す。
(大阪放送局ディレクター 白瀧愛芽 馬宇翔 山岸聖也)
作家・高村薫が語る “銃撃事件1年と日本社会”
7月上旬、私たちは大阪府内で暮らす作家・高村薫さんのもとを訪ねた。
高村さんは純文学やミステリーなど数々の小説を世に送り出すかたわら、新聞の時評などを通じてみずからの考えを発信してきた。
事件直後「民主主義がきちんと機能していない。そういうところにテロが起きる。根本的に危うさを私たちはこの事件でのぞきみた」と指摘していた高村さんに改めて話を聞いてみたいと思った。
高村さんは純文学やミステリーなど数々の小説を世に送り出すかたわら、新聞の時評などを通じてみずからの考えを発信してきた。
事件直後「民主主義がきちんと機能していない。そういうところにテロが起きる。根本的に危うさを私たちはこの事件でのぞきみた」と指摘していた高村さんに改めて話を聞いてみたいと思った。
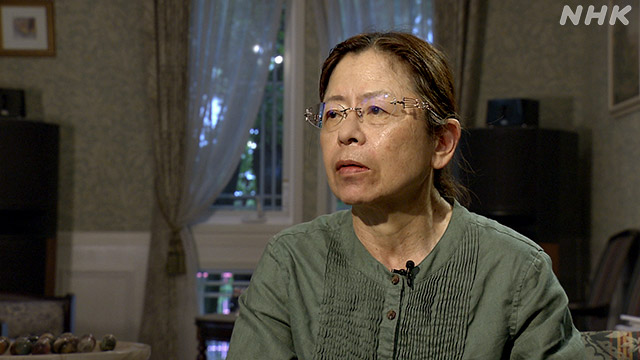
1年がたち、事件をどう捉えているのか尋ねると、高村さんはことばを探しながらゆっくりと語り始めた。
作家 高村薫さん
「ああいう大きな事件ですね。しかも手製の銃を作って、それで生身の人間に向けて至近距離でそれを発射するというようなことを、おそらく日本人はほとんど見たことがなかったと思います。そういう暴発のしかたがあるということを山上という人が一つ見せてしまった。こういう直接体験は恐ろしい形で反復されることがあるなと思います」
「ああいう大きな事件ですね。しかも手製の銃を作って、それで生身の人間に向けて至近距離でそれを発射するというようなことを、おそらく日本人はほとんど見たことがなかったと思います。そういう暴発のしかたがあるということを山上という人が一つ見せてしまった。こういう直接体験は恐ろしい形で反復されることがあるなと思います」
銃撃事件から9か月、岸田総理大臣の演説会場が狙われた事件が起きていた。
高村さんは暴発が続くことに恐ろしさを感じるようになったという。
高村さんは暴発が続くことに恐ろしさを感じるようになったという。
「衆人環視の場で要人、有名な大物の政治家を襲撃するという暴発ですね。それをまねたとは言わないが、一度こういうことができるんだと社会が知ってしまうと、二度三度と続くことはあり得ると思います。そのことは恐ろしいことだと思います」
“政治と旧統一教会”の関係は変わったのか?
暴発が続く社会に変わりつつあるという感覚を抱く一方で、高村さんがこの1年で変わったようには見えないと語ったのが“政治と旧統一教会”との関係だ。
高村薫さん
「この1年を眺めていて、国民の目にさらされて政治が変わることを期待しましたが、そうはならなかったですね。旧統一教会との、主に自民党との関係が取り沙汰されはしたけれども、そのあと政治家たちはそれを清算もしない。私たちは一つは山上容疑者の動機の中に旧統一教会に対するいろんな思いがあることを知りながら、それを真剣にどうにかしようとかしたことはなかった。結局、消費して終わり。何も変わっていない。この1年、何かが解決したか。何も解決していませんでしょう。別に信仰の自由は否定しませんが、その信仰が社会正義に反するようなことであっては困るんです。信仰の自由と社会正義と厳しく峻別(しゅんべつ)しなければいけない。それが日本社会はできないんですね」
「この1年を眺めていて、国民の目にさらされて政治が変わることを期待しましたが、そうはならなかったですね。旧統一教会との、主に自民党との関係が取り沙汰されはしたけれども、そのあと政治家たちはそれを清算もしない。私たちは一つは山上容疑者の動機の中に旧統一教会に対するいろんな思いがあることを知りながら、それを真剣にどうにかしようとかしたことはなかった。結局、消費して終わり。何も変わっていない。この1年、何かが解決したか。何も解決していませんでしょう。別に信仰の自由は否定しませんが、その信仰が社会正義に反するようなことであっては困るんです。信仰の自由と社会正義と厳しく峻別(しゅんべつ)しなければいけない。それが日本社会はできないんですね」
政治と旧統一教会の関係は、この1年で変わったのかー。

教団との接点がある議員が最も多かった自民党は党運営の方針を改訂し、旧統一教会や関連団体とは一切、関係を持たないことなどを徹底させているとしている。
しかしNHKの取材によると、地方議会では自民党議員が旧統一教会の信者だと公表した議員と同じ会派を組むなど、方針が徹底されているのか疑問視されるケースも明らかになっている。
野党も含め、政治は旧統一教会との関係を本当に断っているのか問われている。
しかしNHKの取材によると、地方議会では自民党議員が旧統一教会の信者だと公表した議員と同じ会派を組むなど、方針が徹底されているのか疑問視されるケースも明らかになっている。
野党も含め、政治は旧統一教会との関係を本当に断っているのか問われている。
“小さな社会正義がきちんと働く社会に…”
インタビュー中、高村さんが繰り返し口にしたことばがあった。
「社会正義」だ。
「社会正義」だ。
高村薫さん
「例えば山上被告という人でも、もし社会正義が適切に実現されていたり、あるいは小さな声が拾われていたり、いろんな相談ができたり、母親の問題で社会的に助けがあったりしたら、彼の苦しみもここまでひどくならず、あんな暴力を暴発させることはなかったかもしれない。公正でないことに対してきちんと正していくような力がいろんなところで働く、そういう社会であればテロリズムのような暴発はそうそう起こるものではないと思いますが、日本ではそういう力が非常に弱いと思っています。私たちが今でもなお、この社会に求めなければいけないのは公正で公平であることだと思います。いわゆる『小さな社会正義』がきちんと働くような社会であれば、暴力の温床が少しでも減るのかなと思います」
「例えば山上被告という人でも、もし社会正義が適切に実現されていたり、あるいは小さな声が拾われていたり、いろんな相談ができたり、母親の問題で社会的に助けがあったりしたら、彼の苦しみもここまでひどくならず、あんな暴力を暴発させることはなかったかもしれない。公正でないことに対してきちんと正していくような力がいろんなところで働く、そういう社会であればテロリズムのような暴発はそうそう起こるものではないと思いますが、日本ではそういう力が非常に弱いと思っています。私たちが今でもなお、この社会に求めなければいけないのは公正で公平であることだと思います。いわゆる『小さな社会正義』がきちんと働くような社会であれば、暴力の温床が少しでも減るのかなと思います」

“暴力が連鎖した時代”と重なる今の日本社会
「社会が暴発のしかたを知ってしまったことは恐ろしいことだ」
そう語った高村さんのことばを受け、次に話を聞いたのが日本の近現代史を研究する帝京大学・筒井清忠教授だ。
筒井さんは、過去に日本で暴力が連鎖した時代があり、それを踏まえると銃撃事件後の日本社会が危うい道を歩いているのではないかと警鐘を鳴らしていた。
そう語った高村さんのことばを受け、次に話を聞いたのが日本の近現代史を研究する帝京大学・筒井清忠教授だ。
筒井さんは、過去に日本で暴力が連鎖した時代があり、それを踏まえると銃撃事件後の日本社会が危うい道を歩いているのではないかと警鐘を鳴らしていた。

筒井さんは銃撃事件が起きた直後、大正時代に起きたある事件が頭に浮かんだという。
帝京大学 筒井清忠教授
「1921年に朝日平吾という人が財閥の安田善次郎という人を暗殺し、自殺したという事件があったんですけれど、それをすぐ思い浮かべました。大正時代の日本は財閥が台頭し、それに対しいろんな資本主義の競争で敗れていった人たちが相当貧困な状況に追いやられ、社会全体に非常に閉塞感(へいそくかん)が広まっていることもあり、この暗殺事件が起きたというふうにいえると思います。個人に問題があって政治的にも経済的にもうまくいかなかったときに、ほとんど是正するやり方もないということで、暗殺のような形で訴えて実行する人が現れました。その意味で今回の安倍さんの事件と非常に共通していると思いました」
「1921年に朝日平吾という人が財閥の安田善次郎という人を暗殺し、自殺したという事件があったんですけれど、それをすぐ思い浮かべました。大正時代の日本は財閥が台頭し、それに対しいろんな資本主義の競争で敗れていった人たちが相当貧困な状況に追いやられ、社会全体に非常に閉塞感(へいそくかん)が広まっていることもあり、この暗殺事件が起きたというふうにいえると思います。個人に問題があって政治的にも経済的にもうまくいかなかったときに、ほとんど是正するやり方もないということで、暗殺のような形で訴えて実行する人が現れました。その意味で今回の安倍さんの事件と非常に共通していると思いました」

1921年に起きた無名の青年・朝日平吾が、実業家・安田善次郎を殺害した事件。
朝日は財閥など富裕層が資金をため込んでいることが社会の不平等の原因だとして犯行に及んだとされている。
第一次世界大戦が終わって間もなかった当時、不況だった日本では財閥など富裕層と庶民との格差が生まれ、閉塞感が漂っていた。
事件が起きると社会には朝日を賛美する空気が広がっていく。
朝日は財閥など富裕層が資金をため込んでいることが社会の不平等の原因だとして犯行に及んだとされている。
第一次世界大戦が終わって間もなかった当時、不況だった日本では財閥など富裕層と庶民との格差が生まれ、閉塞感が漂っていた。
事件が起きると社会には朝日を賛美する空気が広がっていく。
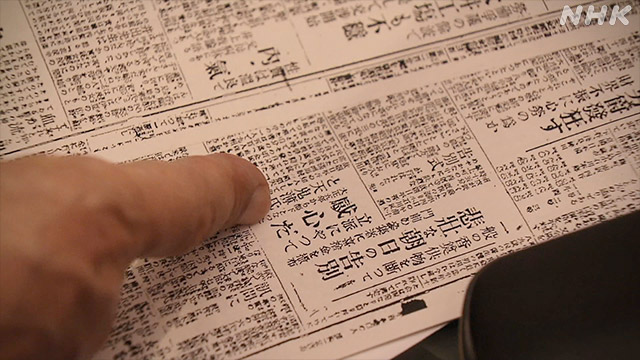
そして1か月後、影響を受けた別の青年が時の総理大臣・原敬を暗殺。
暴力が連鎖していくことになった。
暴力が連鎖していくことになった。
“危うい共感” 暴力の連鎖をどう断ち切るか
筒井さんが注視しているのが、社会の一部で生まれている山上被告の境遇に対する共感だ。
親族によると、山上被告の元には全国から洋服や菓子などの差し入れが届き、これまでに総額100万円以上の現金も送られているという。
インターネット上では、山上被告の刑を軽くするよう求める署名活動も起きている。
親族によると、山上被告の元には全国から洋服や菓子などの差し入れが届き、これまでに総額100万円以上の現金も送られているという。
インターネット上では、山上被告の刑を軽くするよう求める署名活動も起きている。

山上被告が改めて「事件の動機は旧統一教会への恨みだ」とする一方で、一部ではあっても被告への共感が生まれる状況に警鐘を鳴らし、暴力をどう食い止めていくのか考えていく必要があると筒井さんは語った。
帝京大学 筒井清忠教授
「大正時代に起きるような時の閉塞(へいそく)状況が現代もあるかなと思います。暗殺事件を起こした人に対して、同情的になってはいけないんですが、『事件を起こした犯人にも事情があったんだから聞いてあげなければいけないんじゃないか』という感じが非常に強いので、そういう空気が生まれやすい国で、われわれは非常に難しい状況に今、立ち会っているといえると思います」
「大正時代に起きるような時の閉塞(へいそく)状況が現代もあるかなと思います。暗殺事件を起こした人に対して、同情的になってはいけないんですが、『事件を起こした犯人にも事情があったんだから聞いてあげなければいけないんじゃないか』という感じが非常に強いので、そういう空気が生まれやすい国で、われわれは非常に難しい状況に今、立ち会っているといえると思います」
“個人化”が生み出す “名前のない不幸せな穴”
どうすれば人々が暴発しない社会を築くことができるのか。
私たちは現代社会の構造から、暴発が続く日本社会を捉えようとしてきた大阪大学 吉川徹教授のもとを訪ねた。
吉川教授はこれまで社会階層や格差の問題について調査・研究を行ってきた。
私たちは現代社会の構造から、暴発が続く日本社会を捉えようとしてきた大阪大学 吉川徹教授のもとを訪ねた。
吉川教授はこれまで社会階層や格差の問題について調査・研究を行ってきた。

吉川教授が暴発が続く社会の背景にあるものとして考えているのが、現代社会で進む「個人化」。
そして、それによって生み出される「名前のない不幸せな穴」ともいえる状況に陥ってしまう人々の存在だ。
そして、それによって生み出される「名前のない不幸せな穴」ともいえる状況に陥ってしまう人々の存在だ。
大阪大学 吉川徹教授
「今まであった家族や地域、友人関係、職場という所属している組織から離れて人々がバラバラになっていく。これを『個人化』といいますが、社会との絆が切り離されていった時に、誰がどんな位置にいるのかが見えにくくなっている。すると何かのきっかけで人生の歩み方に不利な状況になり、人に説明できるような、よくある状況ではない状況に人知れず陥る『名前のない不幸せな穴』に落ちてしまっている人が生まれる。理解もされないし、手助けの力も加わってこないという状況になるわけですね。そういう状況にあって、誰もが事件を起こすことだとは私は思いません。ですが、その中からごくまれに特別な事情があって暴発的に事件が起きた。この状態に対する危機感は持っておいてもいいかなと思います」
「今まであった家族や地域、友人関係、職場という所属している組織から離れて人々がバラバラになっていく。これを『個人化』といいますが、社会との絆が切り離されていった時に、誰がどんな位置にいるのかが見えにくくなっている。すると何かのきっかけで人生の歩み方に不利な状況になり、人に説明できるような、よくある状況ではない状況に人知れず陥る『名前のない不幸せな穴』に落ちてしまっている人が生まれる。理解もされないし、手助けの力も加わってこないという状況になるわけですね。そういう状況にあって、誰もが事件を起こすことだとは私は思いません。ですが、その中からごくまれに特別な事情があって暴発的に事件が起きた。この状態に対する危機感は持っておいてもいいかなと思います」
山上被告が抱えていた旧統一教会をめぐる苦しみも、事件が起こるまでは「名前のない不幸せな穴」だったのではないかと指摘する吉川教授。
興味深いデータを見せてくれた。
去年、吉川教授自身が行った、社会的に立場が異なる人々が抱える不安について調べたアンケート調査の結果だ。
興味深いデータを見せてくれた。
去年、吉川教授自身が行った、社会的に立場が異なる人々が抱える不安について調べたアンケート調査の結果だ。

全国2300人が回答。
「社会から取り残されているという不安感があるか」という質問に対し、全体の約2割が「ある」と答え、「名前のない不幸せな穴」に陥っている可能性が否定できない層が一定数いることを裏付ける結果だった。
「社会から取り残されているという不安感があるか」という質問に対し、全体の約2割が「ある」と答え、「名前のない不幸せな穴」に陥っている可能性が否定できない層が一定数いることを裏付ける結果だった。
大阪大学 吉川徹教授
「宗教2世のこととか、そういうことが事件として起きる、表面的に表れてくると、それに対して対応するという形で制度や法律は作られるわけです。しかし、それはイタチごっこのような対処療法を続けているだけで、根本のところ『名前のない不幸せの穴』を生まない方向には必ずしもいっていないと考えています。視野の狭い理解のしかたで事件の固有性に注目して『こういうことが起きないようにしましょう』と見ていたのでは、また思いもよらないところから、思いもよらない事件が起きる可能性はある」
「宗教2世のこととか、そういうことが事件として起きる、表面的に表れてくると、それに対して対応するという形で制度や法律は作られるわけです。しかし、それはイタチごっこのような対処療法を続けているだけで、根本のところ『名前のない不幸せの穴』を生まない方向には必ずしもいっていないと考えています。視野の狭い理解のしかたで事件の固有性に注目して『こういうことが起きないようにしましょう』と見ていたのでは、また思いもよらないところから、思いもよらない事件が起きる可能性はある」
私たちは事件後の日本社会をどう生きればよいのか
暴力による暴発を防いでいくために、私たちには、いま何が必要なのか。
事件後の社会をどう生きればよいのか。
吉川さんは「簡単な答えがあるわけではない」としながら、社会で生きる私たちにはなすべきことがあるという。
事件後の社会をどう生きればよいのか。
吉川さんは「簡単な答えがあるわけではない」としながら、社会で生きる私たちにはなすべきことがあるという。

大阪大学 吉川徹教授
「少しでも自分ではない立場の人たちに思いをはせるということが重要ではないかなと思います。今の日本社会の問題は、上層の人たちが自分たちではない人たちがどのようなことをしているのか関心がないし、理解もしていない。自分とは関係ない、社会の形が分からないといったままでは、何が起こるか分からない不安に全員がさらされるということになる。助けを求めている、絆を求めている、居場所を求めている人たちについて知っておくのは、同じ社会を構成する人の強く言えば義務であるかと思います」
「少しでも自分ではない立場の人たちに思いをはせるということが重要ではないかなと思います。今の日本社会の問題は、上層の人たちが自分たちではない人たちがどのようなことをしているのか関心がないし、理解もしていない。自分とは関係ない、社会の形が分からないといったままでは、何が起こるか分からない不安に全員がさらされるということになる。助けを求めている、絆を求めている、居場所を求めている人たちについて知っておくのは、同じ社会を構成する人の強く言えば義務であるかと思います」
そして、作家・高村薫さんも「非常に難しいと思うが…」と前置きをしたうえで、こう語った。
作家 高村薫さん
「客観的になることだと思います。みんな生きづらさとか、息苦しさを感じているし、うまくいかないことや、イライラするとか自分の人生の先が見えないとか、いっぱい抱えているのが現代人だと思います。だから暴発することに対しても、できれば自分だってしたいよという、そういう感情が渦巻いていてもおかしくないと思います。今はSNSがこれだけ発達していますから、あちこちで瞬時に感情が爆発する。それをそうはさせない、ならないことですね。自分自身がそのことで本当に起きている状況を客観視する、それだけの一歩引いた姿勢と精神的な余裕、冷静さを個々人が持つことで事態は少し悪化を防げるのかなと思います」
「客観的になることだと思います。みんな生きづらさとか、息苦しさを感じているし、うまくいかないことや、イライラするとか自分の人生の先が見えないとか、いっぱい抱えているのが現代人だと思います。だから暴発することに対しても、できれば自分だってしたいよという、そういう感情が渦巻いていてもおかしくないと思います。今はSNSがこれだけ発達していますから、あちこちで瞬時に感情が爆発する。それをそうはさせない、ならないことですね。自分自身がそのことで本当に起きている状況を客観視する、それだけの一歩引いた姿勢と精神的な余裕、冷静さを個々人が持つことで事態は少し悪化を防げるのかなと思います」

動機がなんであれ、暴力に訴えることは断じて許されるものではない。
今回、話を伺った3人のメッセージからは、この事件が社会に突きつけたことを、私たち一人一人が立ち止まって冷静に見つめること。
そして暴力を生まないために、自分ではない他の立場の人に少しでも思いをはせることの大切さを感じた。
私たち一人一人が、この社会で、どう生きていくのかが問われている。
今回、話を伺った3人のメッセージからは、この事件が社会に突きつけたことを、私たち一人一人が立ち止まって冷静に見つめること。
そして暴力を生まないために、自分ではない他の立場の人に少しでも思いをはせることの大切さを感じた。
私たち一人一人が、この社会で、どう生きていくのかが問われている。
作家・高村薫さんが語る 銃撃事件と日本社会のいま
作家・高村薫さんのインタビューの詳しい内容はこちら


大阪放送局 ディレクター
白瀧愛芽
平成21年入局
高村薫さんの取材を担当
これまで小児医療、被害者遺族などを取材し、ドキュメンタリー番組を制作
白瀧愛芽
平成21年入局
高村薫さんの取材を担当
これまで小児医療、被害者遺族などを取材し、ドキュメンタリー番組を制作

大阪放送局 ディレクター
馬宇翔
平成30年入局
山上被告の境遇への共感者や社会学者への取材を担当
新たなライフスタイル「FIRE」を目指す若者たちなどを取材、番組を制作
馬宇翔
平成30年入局
山上被告の境遇への共感者や社会学者への取材を担当
新たなライフスタイル「FIRE」を目指す若者たちなどを取材、番組を制作

大阪放送局 ディレクター
山岸聖也
令和2年入局
山上被告の親族や関係者などを取材
若者の起業や「スタートアップ」、地方の政治や医療の取材を続ける
山岸聖也
令和2年入局
山上被告の親族や関係者などを取材
若者の起業や「スタートアップ」、地方の政治や医療の取材を続ける