※「チケット不正転売禁止法」で、主催者の同意なしに、定価を上回る高値で繰り返しチケットを転売することは禁止されています。購入者側も、チケットが無効となって、会場への入場ができないケースがあります。業界団体では転売チケットにはリスクがあることを認識し、主催者側や正規のルートからチケットを入手してほしいと呼びかけています。
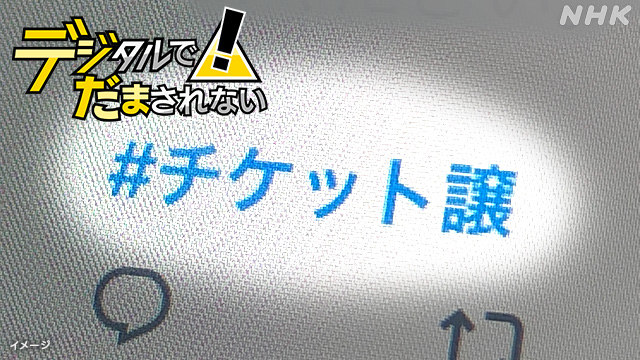
ファン心理につけ込む“チケット詐欺” SNS悪用の手口とは
入手が困難な人気イベントのチケット。諦めきれずSNSで検索すると、定価より少し高い金額でしたが、譲りたいという投稿が見つかりました。
これって詐欺?でもひょっとしたら入手できるかも…。
「推しに会いたい」「どうしても試合が見たい」というファン心理につけ込み、SNSを悪用してお金をだまし取るチケット詐欺。いま増えています。
(デジタルでだまされない取材班 吉村啓)
「大谷翔平を見せたい」親心が

都内に住む40代の女性です。ことし3月、野球部に所属する高校生の息子のためにWBC=ワールド・ベースボール・クラシックの観戦チケットを探していました。
息子は大谷翔平選手の大ファン。
ふだんはプロ野球の試合のチケットはファンクラブの公式サイトで購入していますが、WBCのチケットは非常に人気が高く、一般販売はすべて売り切れ。再販するリセール情報なども見つかりませんでした。
女性
「公式サイトでもリセールサイトでもチケットは見つかりませんでした。WBCは基本4年ごとで、次の大会のときは息子も高校野球を離れて大学生になって、こんな機会はもうないんじゃないかと思いました。今まさに高校野球をやっている息子に、なんとか見せてあげたいという親心でした」

そんなとき、目にとまったのはSNSの投稿文。
「WBC 3/9 チケット譲 一階指定席」
大谷選手がマウンドに上がる初戦のチケットを譲りたいという内容でした。
「今夜には試合が始まる…」
女性は投稿したアカウントに「まだ残っていますか」とダイレクトメッセージを送りました。返信が来たのは、わずか1分後。そこにはチケットはまだ手元にあり、譲ることが可能だと書かれていました。
女性は詐欺の可能性も疑い、実際のチケットや本人証明書の提示を求めました。

相手からはすぐにチケットの半券や免許証の画像が送られてきました。たしかに3月9日の初戦の観戦チケットでした。
チケットを受け取れる保証がないことへの不安を伝えると、相手からは「半額を前払いし、チケットを受け取った後に残りの支払いでも大丈夫です」と連絡がありました。さらにお互いに悪用を防ぐためにと、女性にも証明書を提示するよう求めてきました。
半額の支払いや丁寧なことばづかいでのやりとり、それに試合の当日という焦りから、女性は「予定があって、日本戦を見られなくなった人なのだろう」と思い、信じて購入することを決めました。

女性は半額の1万1000円を指定されたキャッシュレス決済で支払い、息子を東京ドームへと向かわせました。
しかし、お金を支払ったとたん、相手からの連絡は途絶え、その後は何を送っても返信が来なくなりました。最後はメッセージもブロックされ、チケットは手に入りませんでした。
警察や決済会社にも被害を相談しましたが、だまし取られたお金は返ってきていません。

「やはり信頼できるところ、保証がある公式のサイトを使うべきで、そこで手に入らない場合は諦めるべきでした。私の証明書が悪用されるんじゃないかといまも不安に思いますし、SNSを通じて購入しようとしたことを後悔しています」
チケットトラブル 再び増加傾向

国民生活センターによると、インターネットでのチケット転売をめぐるトラブルの相談は2019年度をピークに、新型コロナの感染拡大で減少。2020年度には322件にまで減りました。
しかしコンサートやスポーツイベントなどが再開され、昨年度の相談は1628件と再び増加傾向に転じています。SNSでは「代金を振り込んだら連絡が取れなくなった」など、チケット詐欺の被害を訴える投稿が相次いでいます。
個人間でのチケット転売 法律は?
そもそもチケットの転売は、どのような行為が違法となっているのでしょうか。
2019年に施行された「チケット不正転売禁止法」で、主催者の同意なしに、定価を上回る高値で繰り返しチケットを転売することが禁止されました。
一方、購入者側は試合やコンサートに入場する意思をもって、転売者からチケットを購入する場合は法律に違反しません。ただ、トラブルに巻き込まれるケースは相次いでいます。
チケット販売会社などで作る「チケット適正流通協議会」によりますと、金銭をだまし取られるケースだけでなく、イベントによっては、購入した際に登録した情報の本人確認ができない場合、チケットが無効となって会場への入場ができないこともあるということです。
安全な“推し活”に向けて
チケット詐欺の被害やトラブルに遭わないためにどうすればいいのか。ポイントは3つです。

チケット適正流通協議会では、一番の対策として、SNS経由での購入はせずに、公式のリセールサイトなどを利用してほしいと呼びかけています。

公式サイトの見分け方としては、音楽業界では、「FTマーク」と呼ばれる公式マークを一部の販売サイトに掲載しているほか、アーティストなどの公式ページを経由して購入することを勧めています。
ただ、そうはいっても、ファンであればあるほど、どうしても行きたいという気持ちがおさえられず、公式で手に入らなかったときには、別の入手方法はないかと検索してしまうもの。
SNSでチケットを譲りますという甘いことばを見つけても、無視する。とくに比較的新しいアカウントでの投稿や、今回の記事で紹介した被害事例のように、一部でも先払いを求めてくる手口には、注意が必要です。
そして万一、被害にあった場合には、すぐに警察や消費生活センターなどに相談しましょう。

チケット適正流通協議会 東條岳 弁護士
「チケットがなかなか当たらないという不満があるのは重々承知していますが、さまざまなリスクが潜んでいることを改めて認識して、主催者側や正規のルートからチケットを入手するようにしてほしいです。そして転売が禁止されているチケットをSNS経由で買うことをアーティストや競技団体が喜ぶのか、一歩立ち止まって考えてほしいと思います」