戦地に残してきたのは親友でした

日本から遠く離れたアフリカの地で、彼女はありふれた日常をおくっていました。
平日は懸命に仕事をして、休日には親友とおしゃべりをしながらお茶をしたり、お気に入りの場所でピクニックを楽しんだり。
街を歩く若者たちの間には、この国の未来は自分たちで作るんだという希望があふれていました。
その国が突然、紛争の激戦地に。
そして彼女は、あの日の親友との約束を果たせないまま帰国しました。
(社会部記者 勝又千重子)
平日は懸命に仕事をして、休日には親友とおしゃべりをしながらお茶をしたり、お気に入りの場所でピクニックを楽しんだり。
街を歩く若者たちの間には、この国の未来は自分たちで作るんだという希望があふれていました。
その国が突然、紛争の激戦地に。
そして彼女は、あの日の親友との約束を果たせないまま帰国しました。
(社会部記者 勝又千重子)
スーダンに魅せられて
仲佐かおいさん(37)は、日本の支援団体、JICA=国際協力機構のスーダン担当の職員です。

子どものころから発展途上国での支援に興味があった仲佐さんは、大学でイスラムを研究。卒業後、アフリカのケニアやソマリアの国際機関で働いてきました。
転機となったのが2015年。スーダンの首都ハルツームの大学への留学でした。
当時、スーダンは独裁政権下。イスラム教の戒律に基づき、生活では多くの制約がありました。
ほとんどの女性が髪を覆うヒジャブを身につけ、特に女性は体のラインが出る服を着ることは禁止され、ジーパンをはくこともできなかったといいます。
それでも仲佐さんは、10か月の滞在中、スーダンの人たちと親しくつきあううちに、次第にスーダンという国の魅力にひきつけられていきました。
転機となったのが2015年。スーダンの首都ハルツームの大学への留学でした。
当時、スーダンは独裁政権下。イスラム教の戒律に基づき、生活では多くの制約がありました。
ほとんどの女性が髪を覆うヒジャブを身につけ、特に女性は体のラインが出る服を着ることは禁止され、ジーパンをはくこともできなかったといいます。
それでも仲佐さんは、10か月の滞在中、スーダンの人たちと親しくつきあううちに、次第にスーダンという国の魅力にひきつけられていきました。

仲佐さん
「スーダンの人たちは、『友達の友達は家族』といった感じの国民性です。電気が壊れて大家さんとの交渉に私のアラビア語が通じなくて困っていたら、友達がすぐに駆けつけてくれたり、一緒に留学していたルームメイトが帰国し、家賃が安い部屋を探していたら友達の親戚が空いている部屋を無償で提供してくれたり。あるときには、バスで運賃を出すのに手間取っていたら私の分まで出してくれたおばあちゃんもいて、助けが必要な人には自然と手を差し伸べる、本当に温かい、人のつながりを大切にする人たちなんです。『あなたは家族よ』とよく言われましたが、本当にそう思って助けてくれました」
「スーダンの人たちは、『友達の友達は家族』といった感じの国民性です。電気が壊れて大家さんとの交渉に私のアラビア語が通じなくて困っていたら、友達がすぐに駆けつけてくれたり、一緒に留学していたルームメイトが帰国し、家賃が安い部屋を探していたら友達の親戚が空いている部屋を無償で提供してくれたり。あるときには、バスで運賃を出すのに手間取っていたら私の分まで出してくれたおばあちゃんもいて、助けが必要な人には自然と手を差し伸べる、本当に温かい、人のつながりを大切にする人たちなんです。『あなたは家族よ』とよく言われましたが、本当にそう思って助けてくれました」
念願の派遣 親友との出会い
次は、スーダンのために働きたい。その思いを募らせた仲佐さんは、去年10月、JICAに転職。念願だったスーダン事務所に派遣されました。
早速、ハルツームを拠点に、スーダンの人たちが医療を受けやすくするため保険制度の普及を担当し、申請書の電子化や保険料の支払いの仕組み作りに懸命に取り組みました。
早速、ハルツームを拠点に、スーダンの人たちが医療を受けやすくするため保険制度の普及を担当し、申請書の電子化や保険料の支払いの仕組み作りに懸命に取り組みました。

そんなスーダンは、6年前とは大きく変わっていました。独裁政権は崩壊し、民主化の議論が行われる中で、街なかではヒジャブをつけずに歩く女性も増えました。
若者たちの間にも、自分たちの国は、自分たちが作るんだという希望にあふれていました。
若者たちの間にも、自分たちの国は、自分たちが作るんだという希望にあふれていました。
仲佐さん
「これだけ変わった様子を見て、この国の未来は明るいなという感じはありました。仕事で知り合うスーダンの人も国をよりよくしようと希望をもって働いていて、1つの国が変わっていくプロセスの中に自分もかかわって仕事ができるということに、私自身もやりがいを感じていました」
「これだけ変わった様子を見て、この国の未来は明るいなという感じはありました。仕事で知り合うスーダンの人も国をよりよくしようと希望をもって働いていて、1つの国が変わっていくプロセスの中に自分もかかわって仕事ができるということに、私自身もやりがいを感じていました」
そんな中で出会ったのが、エラフ・イブラヒムさん(26)です。
アラビア語の先生として週2回、レッスンを受けている間に、明るく前向きな人柄もあって親しくなっていきました。
アラビア語の先生として週2回、レッスンを受けている間に、明るく前向きな人柄もあって親しくなっていきました。

数年前に父親を亡くし、一家の大黒柱として母親と妹4人を養っていたエラフさん。それでも、いつも仲佐さんの生活を気にかけてくれ、いつのまにか親友と呼べる関係になっていました。
仲佐さんは、休日にもエラフさんと会い、一緒に食事をしたり、お気に入りの場所でピクニックをしたり、たわいもない話をして笑い合うのがなによりの楽しみだったといいます。
仲佐さんは、休日にもエラフさんと会い、一緒に食事をしたり、お気に入りの場所でピクニックをしたり、たわいもない話をして笑い合うのがなによりの楽しみだったといいます。
仲佐さん
「私も1人でスーダンに赴任して仕事をしていたけれど、彼女も自分で生計を立てて自立しているのもあって、この国の政治の話をすることもありました。それだけじゃなく、過去のお互いの恋愛の話やスーダンの男性の話など“恋バナ”をして盛り上がることもあって、何でも話せる間柄でした」
「私も1人でスーダンに赴任して仕事をしていたけれど、彼女も自分で生計を立てて自立しているのもあって、この国の政治の話をすることもありました。それだけじゃなく、過去のお互いの恋愛の話やスーダンの男性の話など“恋バナ”をして盛り上がることもあって、何でも話せる間柄でした」
突然失われた日常
そんな日常が、急変したのが4月15日のことでした。この日、仲佐さんはエラフさんお気に入りのレストランで、夕食を共にする約束をしていました。
この日は、イスラム教徒が日中に断食を行うラマダンの最中で、日没とともに家族など親しい人と一緒にとる食事を共にしようと、エラフさんから誘われていたのです。
午前9時ごろ、身支度をして、エラフさんに待ち合わせの時間を尋ねるメッセージを送った直後、窓の外から「パン、パン」という乾いた銃声が聞こえてきました。
職場から自宅待機の連絡を受け、不安な1日を過ごした仲佐さん。夕食の約束はキャンセルせざるを得なくなりました。
この日は、イスラム教徒が日中に断食を行うラマダンの最中で、日没とともに家族など親しい人と一緒にとる食事を共にしようと、エラフさんから誘われていたのです。
午前9時ごろ、身支度をして、エラフさんに待ち合わせの時間を尋ねるメッセージを送った直後、窓の外から「パン、パン」という乾いた銃声が聞こえてきました。
職場から自宅待機の連絡を受け、不安な1日を過ごした仲佐さん。夕食の約束はキャンセルせざるを得なくなりました。

その後も散発的に銃声が聞こえる中、自宅待機を続けた仲佐さん。電気も止まったため、発電機で携帯電話を充電し、エラフさんと互いに安否の確認を続けました。
仲佐さん
「毎日、生きているよとか、きのうは眠れたかとか、時にはきょうは何を食べたとか、たわいもないやり取りもしていました。突然始まった自宅での待機で緊張状態でしたが、彼女とやり取りすることで、不安が和らぎました。とてもありがたかったです」
「毎日、生きているよとか、きのうは眠れたかとか、時にはきょうは何を食べたとか、たわいもないやり取りもしていました。突然始まった自宅での待機で緊張状態でしたが、彼女とやり取りすることで、不安が和らぎました。とてもありがたかったです」
早く事態が収束してほしい、その願いとは裏腹に、戦闘は日に日に激化。4月20日、退避のための自衛隊機の派遣が決まり、日本への退避が決まりました。
一番に仲佐さんの胸に浮かんだのはスーダンに残る同僚たち、そしてエラフさんのことでした。
退避を伝えた時、エラフさんから、届いたメッセージです。
一番に仲佐さんの胸に浮かんだのはスーダンに残る同僚たち、そしてエラフさんのことでした。
退避を伝えた時、エラフさんから、届いたメッセージです。

直接お別れが言えなくてとても悲しい。けれど、こんなにも優しい心を持ったあなたに会えてとてもとてもうれしかった。神の導きがあり、お互い安全で状況がよくなったらほかの国で会えますように。
仲佐さん
「当時は退避が無事に終わるか分からない状況だったので、再会できる確証はないんだなというのをこのメッセージを見て実感しました。それと同時に自分だけが安全なところに行くというのは、他の人もどうなるか分からない状況で心苦しい気持ちもありました。彼女には『15日は夕食を一緒に食べる約束だったよね。私たちはきっと再会して、どこかで何事もなかったようにあの日の夕食を食べているよ』と返信しました」
「当時は退避が無事に終わるか分からない状況だったので、再会できる確証はないんだなというのをこのメッセージを見て実感しました。それと同時に自分だけが安全なところに行くというのは、他の人もどうなるか分からない状況で心苦しい気持ちもありました。彼女には『15日は夕食を一緒に食べる約束だったよね。私たちはきっと再会して、どこかで何事もなかったようにあの日の夕食を食べているよ』と返信しました」
退避断念の危機 その時スーダン人が
「いつか必ずエラフさんと再会し、あの日できなかった夕食の約束を果たす」
その思いを胸に、退避の準備を始めた仲佐さん。
その思いを胸に、退避の準備を始めた仲佐さん。

しかし、いきなり壁に突き当たります。自衛隊機が待つ沿岸部のポートスーダンまで国連の車列に加わることになりましたが、そのためのガソリンを集める必要があったのです。
戦闘が始まって1週間がすぎ、退避する人たちでガソリンは不足していました。
このままでは退避を断念せざるをえないかもしれない…。そんな時、確保に奔走してくれたのは、支援の現場で顔を合わせていたスーダン人たちでした。
戦闘が始まって1週間がすぎ、退避する人たちでガソリンは不足していました。
このままでは退避を断念せざるをえないかもしれない…。そんな時、確保に奔走してくれたのは、支援の現場で顔を合わせていたスーダン人たちでした。
仲佐さん
「今、退避しないと逃げられなくなるかもしれないから、あなたたちは逃げるべきだと、ガソリンをかき集めてくれました。今後、彼らも避難することになれば絶対に必要になってくる本当に貴重なガソリンなのに、何の迷いも無く『使ってくれよ』と。こんな危機の時でも、自分のことを顧みず、ふだんと同じようにやれることをしてくれたのが、本当にスーダンの人らしい優しさだなと。本当に感謝してもしきれないです」
「今、退避しないと逃げられなくなるかもしれないから、あなたたちは逃げるべきだと、ガソリンをかき集めてくれました。今後、彼らも避難することになれば絶対に必要になってくる本当に貴重なガソリンなのに、何の迷いも無く『使ってくれよ』と。こんな危機の時でも、自分のことを顧みず、ふだんと同じようにやれることをしてくれたのが、本当にスーダンの人らしい優しさだなと。本当に感謝してもしきれないです」
残されたスタッフも命の危機に
スーダンの人たちに、少しでも恩返しができないか。仲佐さんは帰国した今も、スーダンへの支援を模索しています。

この日、退避したほかの職員とともに話し合っていたのは、現地で銀行の送金システムが止まる中で残された現地スタッフへ、なんとか別の手立てで給料を支払えないかということでした。
現地の物価は4倍以上に跳ね上がっているとも言われています。現金が手に入らなければ、武力衝突の影響を受ける以前に、水や食料すら手に入らない可能性があるのです。
現地の物価は4倍以上に跳ね上がっているとも言われています。現金が手に入らなければ、武力衝突の影響を受ける以前に、水や食料すら手に入らない可能性があるのです。

さらに懸念されているのが、これまでJICAが行ってきた支援が継続できるかということです。
JICAが、スーダンで活動を開始したのは40年近く前になります。現地政府と協力しながら、安定的にきれいな飲み水を供給するための浄水施設の建設や医療保険制度の普及などの支援を続けてきました。
しかし、今回の武力衝突によって、事実上、支援を続けるのが難しくなり、再開の見通しすら立たない状態になっているのです。
JICAが、スーダンで活動を開始したのは40年近く前になります。現地政府と協力しながら、安定的にきれいな飲み水を供給するための浄水施設の建設や医療保険制度の普及などの支援を続けてきました。
しかし、今回の武力衝突によって、事実上、支援を続けるのが難しくなり、再開の見通しすら立たない状態になっているのです。
仲佐さん
「今の状況でスタッフの安全が確認できていない中で、システムが継続されているかが分かりません。この状況で医療ニーズは高まっていますが、薬も枯渇して病院も襲われて医薬品もとられているという情報がきていて、今の緊急の時点では何もできていないのが本当に心苦しいです」
「今の状況でスタッフの安全が確認できていない中で、システムが継続されているかが分かりません。この状況で医療ニーズは高まっていますが、薬も枯渇して病院も襲われて医薬品もとられているという情報がきていて、今の緊急の時点では何もできていないのが本当に心苦しいです」

坂根所長
「われわれがやってきたことは、人々の生活に無くてはならない水や保険に関わることで、それが止まることで生活に対する公的サービスが悪化していくことを心配しています。退避するとき、多くのスーダン人が支援をしてくれてわれわれは助かったので、今度は彼らの命をどこまで大切に思い行動できるのか、本気度が試されています。それは今後、事務所を再開できた時の日本との信頼関係にもつながるので、政府とも相談しながらできることはしていきたいと思っています」
「われわれがやってきたことは、人々の生活に無くてはならない水や保険に関わることで、それが止まることで生活に対する公的サービスが悪化していくことを心配しています。退避するとき、多くのスーダン人が支援をしてくれてわれわれは助かったので、今度は彼らの命をどこまで大切に思い行動できるのか、本気度が試されています。それは今後、事務所を再開できた時の日本との信頼関係にもつながるので、政府とも相談しながらできることはしていきたいと思っています」
親友もエジプトに避難
そんな中、仲佐さんのもとに、エラフさんから知らせが入ります。

5月5日、エラフさんが母親と妹たちを連れて、隣国のエジプトに避難したというのです。
エラフさんたちは、ハルツームからバスやフェリーなどを乗り継ぎエジプトまで、9日間かけてようやくたどりつきました。
エラフさんたちは、ハルツームからバスやフェリーなどを乗り継ぎエジプトまで、9日間かけてようやくたどりつきました。

以前は、1枚50ドルほどだった国境までのバスのチケットが700ドルまで値上がりし、家族全員分のチケットが買えずに途方に暮れたこともあったというエラフさん。それでも親族や家族からお金を借り、なんとかスーダンを出ることができたといいます。

エラフさん
「こんな形で母国を出ると思っていなかったので、まだこれが現実だと思えません。10歳の妹は持ってきていないものがたくさんあるから、また家に帰れるかなと聞いてきますが、自宅が元の状態で残っているのかもわからないし、帰れる見込みもないことを伝えられないでいます。私は運良く避難できたけれど、多くの友達がまだハルツームにいて過酷な状況にいます。お金がなくて避難できない人もいて、自分が避難できたこの状況に罪悪感を感じます」
「こんな形で母国を出ると思っていなかったので、まだこれが現実だと思えません。10歳の妹は持ってきていないものがたくさんあるから、また家に帰れるかなと聞いてきますが、自宅が元の状態で残っているのかもわからないし、帰れる見込みもないことを伝えられないでいます。私は運良く避難できたけれど、多くの友達がまだハルツームにいて過酷な状況にいます。お金がなくて避難できない人もいて、自分が避難できたこの状況に罪悪感を感じます」
スーダンに気持ちを寄せ続けて
涙ながらにエラフさんの話を聞いていた仲佐さん。エラフさんは、避難したエジプトに頼る親族はいないため、仲佐さんが、早速、日本からエジプトの友達たちを紹介しました。
その後、この友達のグループがエラフさん一家の住居を手配し、いまも生活の支援を続けています。
エラフさんのように、これまでにスーダンから国外に避難した人はUNHCR=国連難民高等弁務官事務所の推計でおよそ15万人にのぼります。友人や親戚など頼れる人もいないまま避難している人も少なくありません。
状況が悪化する中、周辺国に逃れた人たち、そして、今もスーダン国内にとどまる多くの人たちへの支援は大きな課題となっています。
スーダンに再び平和が訪れ、約束したあの日の夕食をエラフさんと共にできるその日まで、仲佐さんは、スーダンに心を寄せ、できる支援を続けるつもりです。
その後、この友達のグループがエラフさん一家の住居を手配し、いまも生活の支援を続けています。
エラフさんのように、これまでにスーダンから国外に避難した人はUNHCR=国連難民高等弁務官事務所の推計でおよそ15万人にのぼります。友人や親戚など頼れる人もいないまま避難している人も少なくありません。
状況が悪化する中、周辺国に逃れた人たち、そして、今もスーダン国内にとどまる多くの人たちへの支援は大きな課題となっています。
スーダンに再び平和が訪れ、約束したあの日の夕食をエラフさんと共にできるその日まで、仲佐さんは、スーダンに心を寄せ、できる支援を続けるつもりです。

仲佐さん
「スーダンの人は本当に温かく家族思いで友達思い。彼らにとって何が願いかというと、そのような家族と過ごして友人と過ごしてという元のスーダンの日常が1日でも早く戻るということ。私としてもそういった日が1日でも早くくることを願って、できることは何でもしていくつもりです」
「スーダンの人は本当に温かく家族思いで友達思い。彼らにとって何が願いかというと、そのような家族と過ごして友人と過ごしてという元のスーダンの日常が1日でも早く戻るということ。私としてもそういった日が1日でも早くくることを願って、できることは何でもしていくつもりです」
取材後記
今回取材した仲佐さんをはじめ、現地から退避した多くの人たちが口々に話していたのが、「日本人の退避が終わったことで、日本から遠く離れたスーダンという国への関心は薄れてしまうのではないか」という危機感でした。
ウクライナの戦争のようにひとたびどこかの国で紛争が起きれば、世界中にその影響は広がります。スーダンの軍事衝突もその例外ではありません。
私もこれからも日本から関心を持ち続けていきたいと思います。
ウクライナの戦争のようにひとたびどこかの国で紛争が起きれば、世界中にその影響は広がります。スーダンの軍事衝突もその例外ではありません。
私もこれからも日本から関心を持ち続けていきたいと思います。
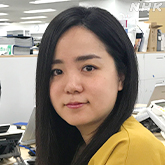
社会部記者
勝又千重子
平成22年入局
山口局、仙台局を経て現所属
仲佐さんは高校時代の同級生
帰国までとても心配でした
勝又千重子
平成22年入局
山口局、仙台局を経て現所属
仲佐さんは高校時代の同級生
帰国までとても心配でした