ずっと渡れない橋 なぜ?

「未着手」
私たちが気になったのは国が公開するリストにあったこの記述だ。
リストは、9人の命を奪った笹子トンネル天井板崩落事故(2012年)を契機に義務化された橋などのインフラの点検結果をまとめたもの。
それによると、点検で「緊急に措置が必要」とされた橋のうち300以上が「未着手」。つまり、緊急度が高いのに手がつけられていない橋が各地にあるのだ。
一体、何が起きているのか。
現場を取材すると、日本のインフラが抱える構造的な問題が見えてきた。
記事には地図も掲載している。お住まいの地域の橋も確認して欲しい。
私たちが気になったのは国が公開するリストにあったこの記述だ。
リストは、9人の命を奪った笹子トンネル天井板崩落事故(2012年)を契機に義務化された橋などのインフラの点検結果をまとめたもの。
それによると、点検で「緊急に措置が必要」とされた橋のうち300以上が「未着手」。つまり、緊急度が高いのに手がつけられていない橋が各地にあるのだ。
一体、何が起きているのか。
現場を取材すると、日本のインフラが抱える構造的な問題が見えてきた。
記事には地図も掲載している。お住まいの地域の橋も確認して欲しい。
「立入禁止」続く橋
ことし2月。
「未着手」の橋の実態を調べようと、私たちが向かったのは茨城県高萩市。
市街地から山間部へと延びる幹線道路から、車1台がようやく通れるほどの脇道に入ってしばらく進むと、目の前にフェンスに囲われた壊れた橋が現れた。
「未着手」の橋の実態を調べようと、私たちが向かったのは茨城県高萩市。
市街地から山間部へと延びる幹線道路から、車1台がようやく通れるほどの脇道に入ってしばらく進むと、目の前にフェンスに囲われた壊れた橋が現れた。

フェンスの前には赤い字で「立入禁止」と書かれた看板が立っている。
橋の名前は「菖蒲橋」。
長さ25メートルあまりの木製の橋で、半世紀以上前から地域の子供たちの通学路やお年寄りの散歩コースとして親しまれてきたという。
橋の名前は「菖蒲橋」。
長さ25メートルあまりの木製の橋で、半世紀以上前から地域の子供たちの通学路やお年寄りの散歩コースとして親しまれてきたという。

しかし、2016年に腐食が原因で一部が落橋。以降、通行止めの状態が6年半にわたって続いている。
周辺に住宅は多くないが、犬の散歩をする人もいて、通りかかる人は思っていたよりも多い。
周辺に住宅は多くないが、犬の散歩をする人もいて、通りかかる人は思っていたよりも多い。

通行人に声をかけたり住宅を回ったりして話を聞くと「架け替え」を求める声が相次いだ。
近くに住むトマト農家の沼田尚人さんは、2歳の息子・晴斗くんが小学校に通うまでに、橋を架け替えて欲しいという。
近くに住むトマト農家の沼田尚人さんは、2歳の息子・晴斗くんが小学校に通うまでに、橋を架け替えて欲しいという。

トマト農家/沼田尚人さん
「菖蒲橋が使えないと、学校まで遠回りする必要があって、子どもが歩いて通えるのか不安です。しかも、遠回りするときに使う道路はトラックがスピードを出して走っているので、親として正直通らせたくありません。小学生になる4年後までに直してもらえると安心できるのですが」
「菖蒲橋が使えないと、学校まで遠回りする必要があって、子どもが歩いて通えるのか不安です。しかも、遠回りするときに使う道路はトラックがスピードを出して走っているので、親として正直通らせたくありません。小学生になる4年後までに直してもらえると安心できるのですが」
橋が使えない状態が続いたことで稲作をあきらめたという男性にも出会った。

農業/大部淳さん
「菖蒲橋を使えなくなったら、反対側の田んぼに行くまでの時間が4倍近くになり、農業機械で移動すると30分も余計に時間がかかります。通行止めの後も4年くらいは頑張って続けましたが、毎日のことで大変で、橋の反対側での稲作は2年前に辞めました」
「菖蒲橋を使えなくなったら、反対側の田んぼに行くまでの時間が4倍近くになり、農業機械で移動すると30分も余計に時間がかかります。通行止めの後も4年くらいは頑張って続けましたが、毎日のことで大変で、橋の反対側での稲作は2年前に辞めました」
4度も要望したけど

長野市南部の「岡田川下橋」も「通行止めが続く橋」のひとつだ。
3年以上「通行止め」が続いていて、床板は抜け落ちている。
周辺の人に話を聞くと、実はこれまでに4度、市に「早く修理して欲しい」と要望を出しているものの、いっこうに修理は行われないという。
住民からは諦めや危険性を指摘する声が。
3年以上「通行止め」が続いていて、床板は抜け落ちている。
周辺の人に話を聞くと、実はこれまでに4度、市に「早く修理して欲しい」と要望を出しているものの、いっこうに修理は行われないという。
住民からは諦めや危険性を指摘する声が。

隣接地域で区長を務める男性
「以前は通行止めの柵を乗り越えて通る人もいたので、万が一、危険なことになったらいけないという思いで修理して欲しいと要望を出しています。ただ、難しいなら早く撤去して欲しいです。大きな被害が出た4年前の台風19号では、橋にいろいろなものが引っかかりました。もし橋ごと流されれば、下流域の人たちに迷惑をかけると思います」
「以前は通行止めの柵を乗り越えて通る人もいたので、万が一、危険なことになったらいけないという思いで修理して欲しいと要望を出しています。ただ、難しいなら早く撤去して欲しいです。大きな被害が出た4年前の台風19号では、橋にいろいろなものが引っかかりました。もし橋ごと流されれば、下流域の人たちに迷惑をかけると思います」
1年以上通行止め全国に265橋
全国の「未着手」の橋の中には、菖蒲橋のように「通行止めが続く橋」がもっとあるのではないか。
私たちは、国土交通省の「全国道路施設点検データベース(損傷マップ)」を元に、全国の実態を調べた。
点検の結果、「緊急に対応が必要」とされた橋のうち、2022年3月末時点で「未着手」の343橋を「損傷マップ」からピックアップ。対応状況を自治体に取材した。
その結果、2022年12月の時点で、全国41都道府県の265の橋で「1年以上通行止めが続いている」ことが判明した。
下の地図で、各地の状況を確認できるので、お住まいの地域を見て欲しい。
私たちは、国土交通省の「全国道路施設点検データベース(損傷マップ)」を元に、全国の実態を調べた。
点検の結果、「緊急に対応が必要」とされた橋のうち、2022年3月末時点で「未着手」の343橋を「損傷マップ」からピックアップ。対応状況を自治体に取材した。
その結果、2022年12月の時点で、全国41都道府県の265の橋で「1年以上通行止めが続いている」ことが判明した。
下の地図で、各地の状況を確認できるので、お住まいの地域を見て欲しい。
未着手の橋の7割以上で修理や撤去の対応が取られず、「通行止め」のままになっているのが現状なのだ。
通行止めの期間を見てみると、
▽5年以上が131か所(49.4%)
▽10年以上が33か所(12.5%)
単に通行止めになっているだけではなく、長期化していることもわかってきた。
通行止めの期間を見てみると、
▽5年以上が131か所(49.4%)
▽10年以上が33か所(12.5%)
単に通行止めになっているだけではなく、長期化していることもわかってきた。
橋が落ちた
通行止めが続く中、橋が流失したり、崩壊したりするケースも少なくとも3件確認された。

牛落橋(栃木市)
2018年8月から通行止め。およそ1年後の台風19号で橋の3分の2が流失
2018年8月から通行止め。およそ1年後の台風19号で橋の3分の2が流失

栄橋(山形県遊佐町)
通行止め後に橋の一部が崩壊し、今もその状態のまま
通行止め後に橋の一部が崩壊し、今もその状態のまま

大里沢橋(新潟県関川村)
10年ほど通行止めが続き、2022年8月の大雨で橋脚ごと流失
いずれのケースでも、これまでは人的な被害は確認されていないが、「この先も大丈夫」とは言い切れず、「利用者がいなければそのまま通行止めにしておけば良い」とは言えないのだ。
10年ほど通行止めが続き、2022年8月の大雨で橋脚ごと流失
いずれのケースでも、これまでは人的な被害は確認されていないが、「この先も大丈夫」とは言い切れず、「利用者がいなければそのまま通行止めにしておけば良い」とは言えないのだ。
「費用対効果を考えざるを得ない」
では、なぜ通行止めの状態が続くのか。
冒頭で紹介した茨城県高萩市の『菖蒲橋』。
市によると、木製の橋を頑丈なコンクリート製の橋にして架け替えた場合、費用はおよそ1億円かかるという。
壊れた橋台を直すだけでも3000万円の費用がかかる上、その後も、定期的に補修や点検などのランニングコストが必要になる。
冒頭で紹介した茨城県高萩市の『菖蒲橋』。
市によると、木製の橋を頑丈なコンクリート製の橋にして架け替えた場合、費用はおよそ1億円かかるという。
壊れた橋台を直すだけでも3000万円の費用がかかる上、その後も、定期的に補修や点検などのランニングコストが必要になる。
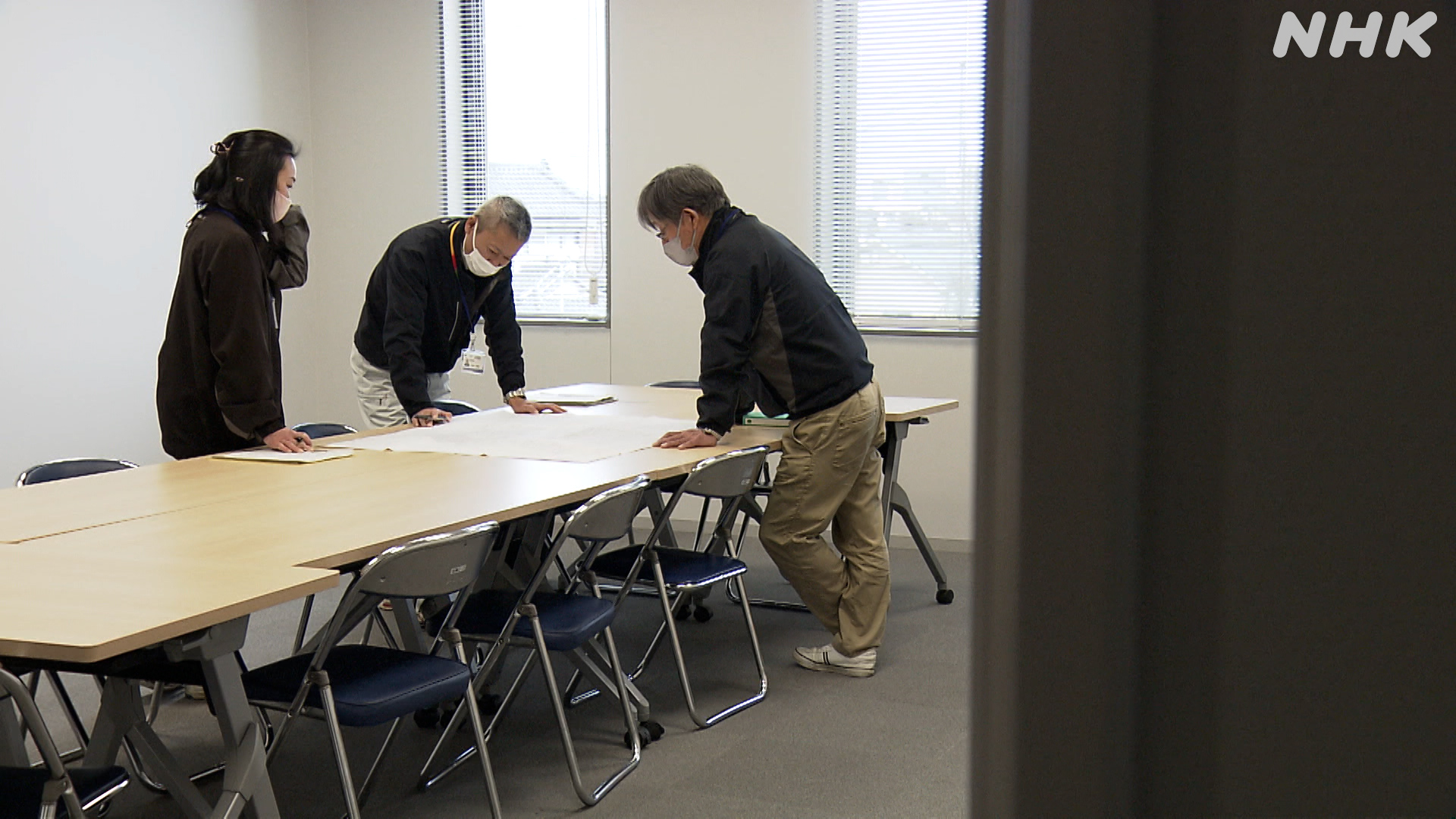
このため市は、近くにある「麦屋橋」という別の橋と一本化する計画を立てて、2019年に住民説明会を開いたものの、理解は得られなかった。
今も結論の出ない状態が続いている。
今も結論の出ない状態が続いている。
高萩市都市建設課 蛭野努 課長
「高度経済成長期は作って、壊して、また新しく作って…という時代でした。しかし、少子高齢化で人口が減少し、財源も限られる今の時代ではとてもできません。福祉事業などにも予算がかかる中、将来的なコストも見越して、管理する橋の数を減らすことも大事だと考えています。もちろん住民の理解は欠かせないので、しっかり説明を尽くしたいですが、費用対効果を考えざるを得ないのが現状です」
「高度経済成長期は作って、壊して、また新しく作って…という時代でした。しかし、少子高齢化で人口が減少し、財源も限られる今の時代ではとてもできません。福祉事業などにも予算がかかる中、将来的なコストも見越して、管理する橋の数を減らすことも大事だと考えています。もちろん住民の理解は欠かせないので、しっかり説明を尽くしたいですが、費用対効果を考えざるを得ないのが現状です」
他にも「通行止め」が続く理由は様々あった。

岡田川下橋(長野市)
修理要望はあるが市内に1750の橋があり、対応に手が回っていない。
修理要望はあるが市内に1750の橋があり、対応に手が回っていない。

和田浜橋(静岡県熱海市)
担当職員も不足し、修理か架け替えかの検討に時間を要している
担当職員も不足し、修理か架け替えかの検討に時間を要している

港歩道橋・港跨線橋(北海道稚内市)
関係機関との調整に時間がかかっている
取材する中で多くに共通していたのは、人口と財源が減る中では修理や架け替えは容易ではなく、かといって、撤去するにも住民の理解がハードルになる現状。
橋を管理する自治体は、一旦「通行止め」にする対応を取るが、状況は変わらないまま時間が経過しているのだ。
関係機関との調整に時間がかかっている
取材する中で多くに共通していたのは、人口と財源が減る中では修理や架け替えは容易ではなく、かといって、撤去するにも住民の理解がハードルになる現状。
橋を管理する自治体は、一旦「通行止め」にする対応を取るが、状況は変わらないまま時間が経過しているのだ。
橋を手放す
こうした状況のなか、ついに、もう管理は無理だと「橋を手放す」自治体も現れている。
山あいの自然に囲まれた愛知県新城市。
市が行ったのは「市道の廃止」という手続きだ。
そもそも道路にある「橋」は、道路法という法律で「道路」の一部に位置づけられている。このため5年に1度点検を実施し安全に保たなければならない。
ところが「市道の廃止」という手続きを取って、管理が必要な「道路」ではなくすことで、「橋」としての管理が不要になり、点検の手間やコストを削減できるのだ(構造物自体や土地は市の財産として財産管理部局が管理する)。
山あいの自然に囲まれた愛知県新城市。
市が行ったのは「市道の廃止」という手続きだ。
そもそも道路にある「橋」は、道路法という法律で「道路」の一部に位置づけられている。このため5年に1度点検を実施し安全に保たなければならない。
ところが「市道の廃止」という手続きを取って、管理が必要な「道路」ではなくすことで、「橋」としての管理が不要になり、点検の手間やコストを削減できるのだ(構造物自体や土地は市の財産として財産管理部局が管理する)。

廃止されたのは「5号橋」という鉄筋コンクリートと石造りの長さ3メートルほどの橋。
言われてみれば橋の形をしているが、利用者はほとんどなく、存在さえもほとんど知られていないという。
ただ、修理する場合には3750万円の費用がかかるうえ、5年に1度の点検で人を派遣するのにもコストがかかる。
言われてみれば橋の形をしているが、利用者はほとんどなく、存在さえもほとんど知られていないという。
ただ、修理する場合には3750万円の費用がかかるうえ、5年に1度の点検で人を派遣するのにもコストがかかる。
新城市建設部 天野充泰 部長
「橋はほぼ利用者はいませんが、市道に認定されているので、5年に1度の点検が義務づけられています。撤去するにも、重機を橋の場所まで持っていったり、橋を搬出したりすると相当な費用がかかります。建設から50年以上経つなど、古くなる橋の割合が多くなっている中で、利用の実態がないものについて市道の認定を外す対応は、今後、必要な橋を維持していく上でひとつの選択肢になるかなと考えています」
「橋はほぼ利用者はいませんが、市道に認定されているので、5年に1度の点検が義務づけられています。撤去するにも、重機を橋の場所まで持っていったり、橋を搬出したりすると相当な費用がかかります。建設から50年以上経つなど、古くなる橋の割合が多くなっている中で、利用の実態がないものについて市道の認定を外す対応は、今後、必要な橋を維持していく上でひとつの選択肢になるかなと考えています」
新城市のように橋を「手放す」ことを検討する動きは、山形県鮭川村の「深沢1号橋」や岡山県真庭市の「宗末上橋」でも確認できた。
まだ始まったばかり
全国各地に通行止めが続く橋が多数存在する。
この状況を専門家はどう見ているのか。
インフラの老朽化問題に詳しい東洋大学の根本祐二教授は、こうした状況は今後さらに広がっていくと警鐘を鳴らす。
この状況を専門家はどう見ているのか。
インフラの老朽化問題に詳しい東洋大学の根本祐二教授は、こうした状況は今後さらに広がっていくと警鐘を鳴らす。
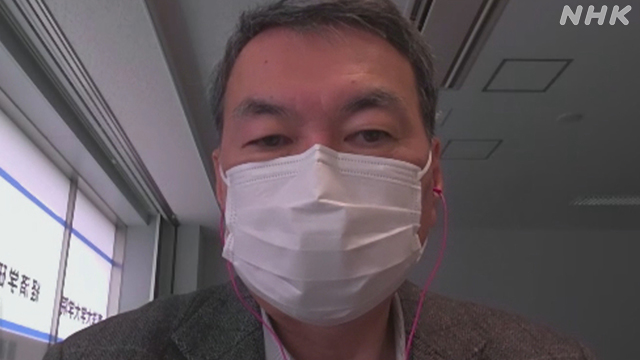
根本祐二 教授
「修理、撤去の予算がまったく確保できない状況が国全体で起きていて、予算を確保できない状態では通行止めにするしかありません。1970年代の高度成長期に橋は年間およそ1万本架けられていました。耐用年数を60年ほどと考えた場合、2030年にはこの1万本の橋を架け替えなければならない計算となり、老朽化はこれからもっと深刻になっていくと考えられます。点検や修理などに手をこまねいている間に、さらに老朽化が進む悪循環が非常に懸念されます」
「修理、撤去の予算がまったく確保できない状況が国全体で起きていて、予算を確保できない状態では通行止めにするしかありません。1970年代の高度成長期に橋は年間およそ1万本架けられていました。耐用年数を60年ほどと考えた場合、2030年にはこの1万本の橋を架け替えなければならない計算となり、老朽化はこれからもっと深刻になっていくと考えられます。点検や修理などに手をこまねいている間に、さらに老朽化が進む悪循環が非常に懸念されます」
根本教授によれば、アメリカでも1980年代にインフラの老朽化が集中したものの、人口が増加していた時期だったため、増税で乗り切ったが、人口減少が進む現在の日本では、そう簡単にはいかない。
日本の構造的な問題が解決を難しくしているのだ。
根本教授は「優先順位をつけていくこと」の重要性を指摘する。
日本の構造的な問題が解決を難しくしているのだ。
根本教授は「優先順位をつけていくこと」の重要性を指摘する。
根本祐二 教授
「これまでと同じようにすべてのインフラを維持するのは『不可能だ』と皆が認識する必要があります。その上で「では、どのようにたたんでいくのか」を真剣に議論する時期に来ています。そして、議論する時には、橋だけではなく、学校や図書館、文化ホールなどの公共施設も含め、インフラ全体の中で優先順位を付けて、予算を配分していくことが必要です」
「これまでと同じようにすべてのインフラを維持するのは『不可能だ』と皆が認識する必要があります。その上で「では、どのようにたたんでいくのか」を真剣に議論する時期に来ています。そして、議論する時には、橋だけではなく、学校や図書館、文化ホールなどの公共施設も含め、インフラ全体の中で優先順位を付けて、予算を配分していくことが必要です」
私たちのすぐそばに
通行止めが続く橋は、私たちの生活するすぐそばにある。
ただ、すべてを修理して、維持・管理を続けていくことは、限界を迎えつつある。
その現実から目を背けずに「どうやってたたむのか」。
これまで使ってきたものを無くす決断は簡単ではないが、自治体と住民が一緒に考えて、実行していく時期に来ているのではないだろうか。
ただ、すべてを修理して、維持・管理を続けていくことは、限界を迎えつつある。
その現実から目を背けずに「どうやってたたむのか」。
これまで使ってきたものを無くす決断は簡単ではないが、自治体と住民が一緒に考えて、実行していく時期に来ているのではないだろうか。
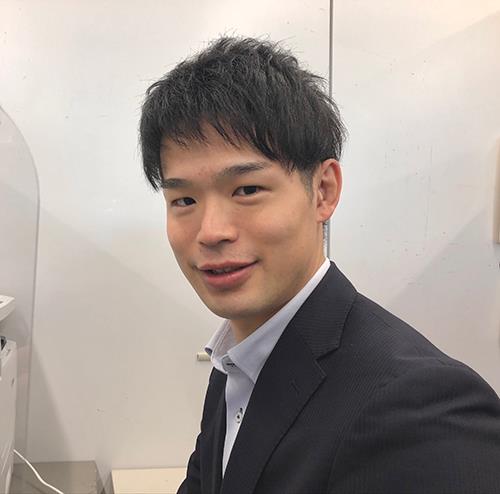
大阪放送局 記者
大野敬太
2018年入局(水戸)
2021年から現所属
現在は大阪府警担当
大野敬太
2018年入局(水戸)
2021年から現所属
現在は大阪府警担当
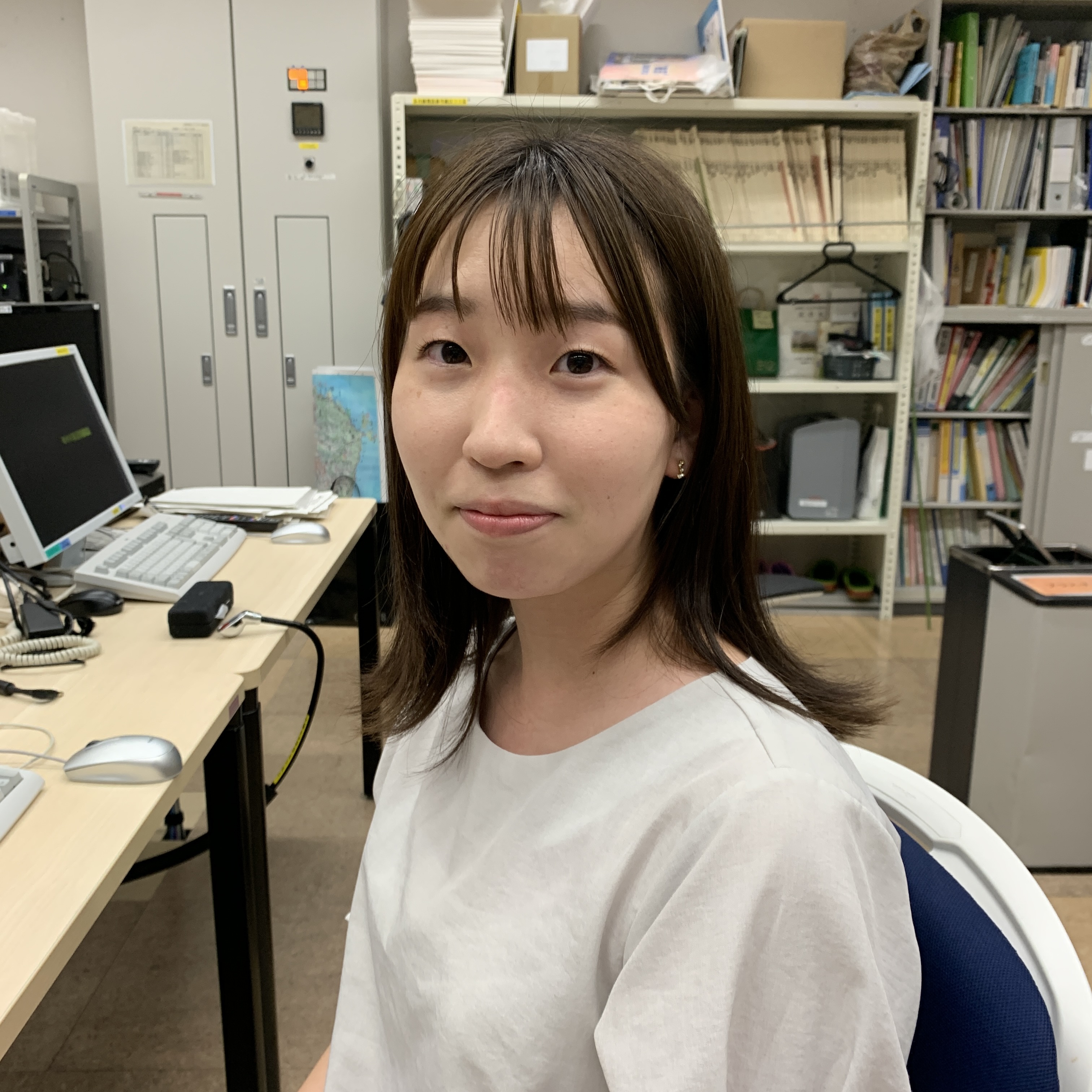
大阪放送局 記者
鈴椋子
2020年入局
2年間大阪府警を担当
災害や教育を取材
鈴椋子
2020年入局
2年間大阪府警を担当
災害や教育を取材
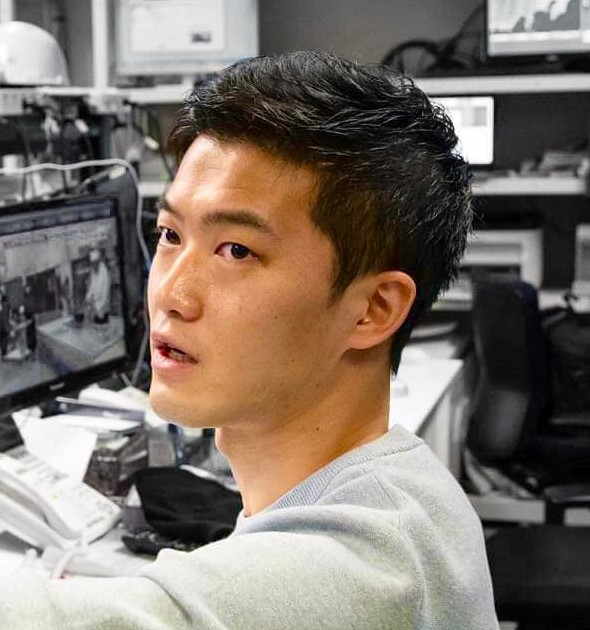
大阪放送局 記者
藤島新也
2009年入局(盛岡)
2022年から現所属
災害担当
藤島新也
2009年入局(盛岡)
2022年から現所属
災害担当

大阪放送局 カメラマン
福島浩晃
2003年入局(山口)
報道局、岡山などを経て
2020年から現所属
番組の取材・撮影も担当
福島浩晃
2003年入局(山口)
報道局、岡山などを経て
2020年から現所属
番組の取材・撮影も担当

和歌山放送局 記者
伊藤敬一郎
2021年入局
警察・司法を担当
スポーツや災害も取材
伊藤敬一郎
2021年入局
警察・司法を担当
スポーツや災害も取材

神戸放送局 記者
小田和正
2014年入局(金沢)
鹿児島を経て
2021年から現所属
現在は兵庫県警担当
小田和正
2014年入局(金沢)
鹿児島を経て
2021年から現所属
現在は兵庫県警担当

奈良放送局 記者
八代千歳
2016年入局(山形)
2020年から現所属
現在は橿原支局に勤務
八代千歳
2016年入局(山形)
2020年から現所属
現在は橿原支局に勤務