「書くことは生きることだった」
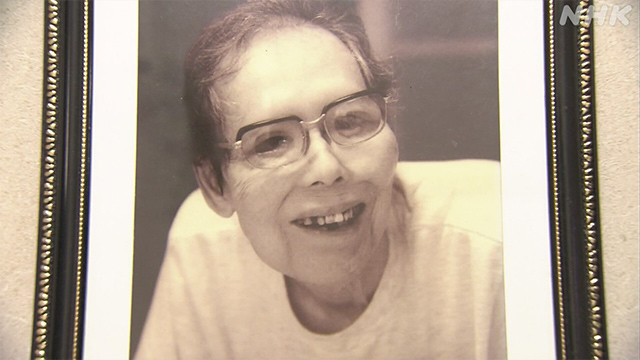
住まい、仕事場、郵便局、理髪店、それに火葬場まで…。
“小さな街”のような囲いの中に強制的に隔離された人たちにとって「書くことは生きること」でした。
この日本で平成に入っても続けられた誤った隔離政策。
その不条理の中でつづられた“幻の詩集”が70年ぶりによみがえりました。(社会部記者 背戸柚花)
※詩は、時代背景を考慮し原文のまま引用しています。
“小さな街”のような囲いの中に強制的に隔離された人たちにとって「書くことは生きること」でした。
この日本で平成に入っても続けられた誤った隔離政策。
その不条理の中でつづられた“幻の詩集”が70年ぶりによみがえりました。(社会部記者 背戸柚花)
※詩は、時代背景を考慮し原文のまま引用しています。
家族からも、社会からも、切り離された囲いの中で
妹は今でも 私の病を知らない
いつかはわかるだろう
兄は いくら待っても帰れないという事を
やがて
永遠に消えない悲しみの灯が
お前の心にも点るだろう。
妹よ 淋しくはないか
妹よ 悲しくはないか
(略)
「妹の手紙を見て」國本昭夫
いつかはわかるだろう
兄は いくら待っても帰れないという事を
やがて
永遠に消えない悲しみの灯が
お前の心にも点るだろう。
妹よ 淋しくはないか
妹よ 悲しくはないか
(略)
「妹の手紙を見て」國本昭夫
強制的に隔離された療養所で、離れた家族のことを思ってつづられた詩。
戻ることのできない故郷への思いをつづった詩も多く見られます。
戻ることのできない故郷への思いをつづった詩も多く見られます。

夕映えの海の向うには声がある。
忘れかけていた色色な声が一杯に拡がっている。
(略)
あのぼうせき工場のサイレンが鳴るのも今ごろであろうか。
幾重にも輪になって
夕雲を飛びこえ風に輝き
遠く谺しているあの声、あのかすかな轟き。
海の向うには、
甘い苺の取れる田舎町の
遠い日の想い出がはずんでいる。
「海の向うには」小島浩二
※谺(こだま)
忘れかけていた色色な声が一杯に拡がっている。
(略)
あのぼうせき工場のサイレンが鳴るのも今ごろであろうか。
幾重にも輪になって
夕雲を飛びこえ風に輝き
遠く谺しているあの声、あのかすかな轟き。
海の向うには、
甘い苺の取れる田舎町の
遠い日の想い出がはずんでいる。
「海の向うには」小島浩二
※谺(こだま)
70年ぶりに復刊した“幻の詩集”

今から70年前の1953年に出版され、ことし初めて復刊された詩集「いのちの芽」。
全国8か所のハンセン病療養所に入所していた73人がつづった227の詩が掲載されています。
全国8か所のハンセン病療養所に入所していた73人がつづった227の詩が掲載されています。

当時、ハンセン病の患者たちは、国の誤った政策により強制的に療養所に隔離されました。
患者や家族は激しい差別や偏見にさらされ、一家離散や心中に追い込まれることもあったといいます。
その後、感染力が極めて弱いことがわかり、治療法が確立されましたが、国は1996年まで隔離政策を続けました。
患者や家族は激しい差別や偏見にさらされ、一家離散や心中に追い込まれることもあったといいます。
その後、感染力が極めて弱いことがわかり、治療法が確立されましたが、国は1996年まで隔離政策を続けました。
詩集「いのちの芽」の復刊に尽力した国立ハンセン病資料館の学芸員、木村哲也さん。
入所者の「生きた証し」とも言える作品をよみがえらせ、後世に伝え続けていきたいと考えました。
入所者の「生きた証し」とも言える作品をよみがえらせ、後世に伝え続けていきたいと考えました。

木村哲也さん
「70年間一度も再刊されたことがなく、読みたくても手に入らない状態で“幻の詩集”と言われてきました。諦めの詩であるように見えても、外に向かって、このことばだけは隔離の壁を越える。誰かに聞いてほしい、自分を知ってほしいという思いに満ちた詩集と言っていいと思います」
「70年間一度も再刊されたことがなく、読みたくても手に入らない状態で“幻の詩集”と言われてきました。諦めの詩であるように見えても、外に向かって、このことばだけは隔離の壁を越える。誰かに聞いてほしい、自分を知ってほしいという思いに満ちた詩集と言っていいと思います」
絶望の中で見いだした希望も「生きるということ」
詩集には生きることへの揺るがぬ決意が感じられる詩も少なくないといいます。
私の手は曲っている。しかし掴まねばならない。
歯が抜けている。だが噛まねばならない。
眼球を失っても 見ねばならず、足を失っても
歩かねばならない。
(略)
あなたも生きているように私も生きる。
私も生きるようにあなたも生きる。
(略)
「生きるということ」志樹逸馬
歯が抜けている。だが噛まねばならない。
眼球を失っても 見ねばならず、足を失っても
歩かねばならない。
(略)
あなたも生きているように私も生きる。
私も生きるようにあなたも生きる。
(略)
「生きるということ」志樹逸馬
この詩を書いた志樹逸馬さん。
13歳で発症し、家族のもとを離れて療養所に入り戦前から詩を書き始めます。
13歳で発症し、家族のもとを離れて療養所に入り戦前から詩を書き始めます。

「いのちの芽」が出版された6年後に42歳で亡くなるまで、多くの詩を残しました。
戦後、日本でも治療薬「プロミン」が使用されるようになり、ハンセン病が“治る病気”になる中で、その作風も変わっていったといいます。
戦後、日本でも治療薬「プロミン」が使用されるようになり、ハンセン病が“治る病気”になる中で、その作風も変わっていったといいます。
木村哲也さん
「どんなに困難な状況にあろうとも、精いっぱい持てる力を発揮して生きるんだという意思表現であり、生きた痕跡というか、療養所の閉ざされた環境でありながら、外に向かって自分たちはこう生きたいんだという思いが込められている。治療薬ができて、完全に治癒してもなお隔離政策があるために、外には出て行けずに一生涯そこで閉じ込められてしまう。自分は何のためにここで生きてるんだと、誰しも自問自答したと思います。その答えが作品になっている」
「どんなに困難な状況にあろうとも、精いっぱい持てる力を発揮して生きるんだという意思表現であり、生きた痕跡というか、療養所の閉ざされた環境でありながら、外に向かって自分たちはこう生きたいんだという思いが込められている。治療薬ができて、完全に治癒してもなお隔離政策があるために、外には出て行けずに一生涯そこで閉じ込められてしまう。自分は何のためにここで生きてるんだと、誰しも自問自答したと思います。その答えが作品になっている」
「ふるさとの家は灯が消えた」“詩人”たちの人生をたどって
「いのちの芽」に詩を寄せた入所者たちは、どんな思いでことばを紡いだのか。その人生をたどりたいと、入所者の1人を知る人を訪ねました。
北九州市に住む岸上昭子さん、81歳。「いのちの芽」に詩を寄せた島比呂志さんと交流を続けてきました。
北九州市に住む岸上昭子さん、81歳。「いのちの芽」に詩を寄せた島比呂志さんと交流を続けてきました。
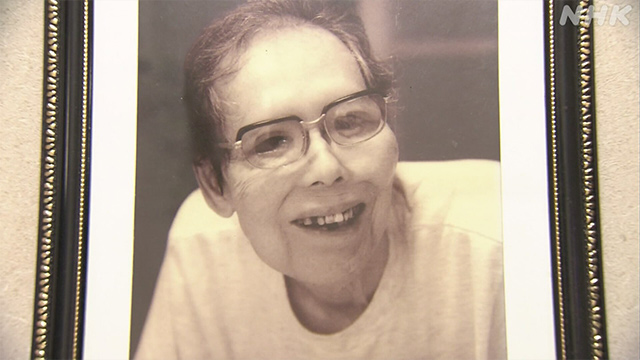
島さんは、20歳のころに発症し、その後、半世紀にわたり療養所で暮らしました。
作家としてハンセン病に対する差別や偏見を鋭く告発しただけでなく、国の責任を追及した裁判で原告団の名誉団長を務め、尊厳回復に尽力してきました。
作家としてハンセン病に対する差別や偏見を鋭く告発しただけでなく、国の責任を追及した裁判で原告団の名誉団長を務め、尊厳回復に尽力してきました。
岸上昭子さん
「島さんは生き方がシャープでいろんな人にまみれない自分の信念を貫く人。静かな人だけど静かな闘志を持った人だった」
「島さんは生き方がシャープでいろんな人にまみれない自分の信念を貫く人。静かな人だけど静かな闘志を持った人だった」
その島さんが寄せた詩です。
ふるさとの家を思う日
わたしの心は暗い
わたしが癩になった日から
ふるさとの家は灯が消えた
暗い空洞のような家の中で
父は
いつまでも顔をあげず
母は
愚痴にあけくれ
妹は
嫁にゆけぬ青春をのろい
弟は
みんなの不安にうちしおれ
ふるさとの家は
笑いを忘れてしまった
(略)
「ふるさとの家を思う」島比呂志
わたしの心は暗い
わたしが癩になった日から
ふるさとの家は灯が消えた
暗い空洞のような家の中で
父は
いつまでも顔をあげず
母は
愚痴にあけくれ
妹は
嫁にゆけぬ青春をのろい
弟は
みんなの不安にうちしおれ
ふるさとの家は
笑いを忘れてしまった
(略)
「ふるさとの家を思う」島比呂志
作品をきっかけに、島さんと手紙のやりとりを始め、療養所にも会いにいくようになった昭子さん。島さんからいろんな話を聞いたといいます。
島さんの父親は「息子は死んだ」と学校に言っていたこと。同級生に手紙を出した際には「ハンセン病患者の手紙はくださるな」と拒否されたこと。
また島さんは、ハンセン病を理由に断種手術を強いられ、子どもを持つこともかないませんでした。
島さんの父親は「息子は死んだ」と学校に言っていたこと。同級生に手紙を出した際には「ハンセン病患者の手紙はくださるな」と拒否されたこと。
また島さんは、ハンセン病を理由に断種手術を強いられ、子どもを持つこともかないませんでした。

岸上昭子さん
「島さんは悔しく悲しい思いをしながら生きてきたと思います。だからこそ『自分も人も大切にできるような人になってほしい』っていつも言っていましたね」
「島さんは悔しく悲しい思いをしながら生きてきたと思います。だからこそ『自分も人も大切にできるような人になってほしい』っていつも言っていましたね」
昭子さんは、結婚して3人の子どもを育てていましたが、あるとき夫が自ら命を絶ってしまいます。そのときに島さんからかけられたことばが今でも忘れられないといいます。
岸上昭子さん
「島さんに電話したら『子どもを連れてね、無理心中なんてしたらいけんよ。子ども3人タクシーに乗せてこっちにやんなさい。そうしたら面倒見てあげるからね』って言ってくれて。島さんのことを親のように大切にしようと思ったんです」
「島さんに電話したら『子どもを連れてね、無理心中なんてしたらいけんよ。子ども3人タクシーに乗せてこっちにやんなさい。そうしたら面倒見てあげるからね』って言ってくれて。島さんのことを親のように大切にしようと思ったんです」
後にこのときのことを島さんは、自身が子どもを持つことがかなわなかった中で、子どもは宝だという思いが強くあったからだと、話してくれたといいます。

1999年に療養所生活を終えて社会復帰した島さん。
昭子さんは養子縁組をし、「娘」として島さんを亡くなるまで支え続けました。
昭子さんは養子縁組をし、「娘」として島さんを亡くなるまで支え続けました。
「隔離の現場」火葬場まである“小さな街”で
その島さんが暮らした療養所、鹿児島県鹿屋市にある「星塚敬愛園」。

広さはおよそ37万平方メートル。東京ドームおよそ8個分の広大な敷地には、入所者の住まいが並び、学校や仕事場、郵便局、理髪店、それに火葬場まであり、そこはまるで“小さな街”のようだったといいます。
国立ハンセン病資料館によりますと、かつての療養所は「患者が病気を治して社会に戻っていくための施設ではなく、囚人同様の待遇のもとでそこで死んでもらうための場所」であり、入所者たちは食事や医療が十分に整っていない劣悪な環境の中で働かされたといいます。
島さんと交流のあった作家の立石富生さんが、案内してくれました。
国立ハンセン病資料館によりますと、かつての療養所は「患者が病気を治して社会に戻っていくための施設ではなく、囚人同様の待遇のもとでそこで死んでもらうための場所」であり、入所者たちは食事や医療が十分に整っていない劣悪な環境の中で働かされたといいます。
島さんと交流のあった作家の立石富生さんが、案内してくれました。

立石富生さん
「患者地帯、職員地帯ってわかれていて、患者たちは絶対に向こう側にいけなかった。基本的人権はない、人間扱いされていない。極端に言えばそういう時代があったんです」
「患者地帯、職員地帯ってわかれていて、患者たちは絶対に向こう側にいけなかった。基本的人権はない、人間扱いされていない。極端に言えばそういう時代があったんです」
「書くことは生きること」だった
「いのちの芽」が出版された5年後、その療養所の中で島さんは詩や小説などさまざまな作品が掲載された同人誌「火山地帯」を立ち上げ、40年にわたって編集長を務めました。

立石さんが編集長を引き継ぎ、今も活動を続けています。
療養所に通い、島さんとおよそ20年交流を続ける中で、ことばへの強い意志を感じてきました。
療養所に通い、島さんとおよそ20年交流を続ける中で、ことばへの強い意志を感じてきました。

立石富生さん
「島さんがいつも言っていたのは自分にとって『書くことは生きることだ』と。社会に向かって訴えるものはペンしかなかったんですよね。外に出て行けないから。でも、いいものを書けば認めてもらえる。ことばを変えて言うなら、文学には差別がない。そういうことで一生懸命励んだのだと思います」
「島さんがいつも言っていたのは自分にとって『書くことは生きることだ』と。社会に向かって訴えるものはペンしかなかったんですよね。外に出て行けないから。でも、いいものを書けば認めてもらえる。ことばを変えて言うなら、文学には差別がない。そういうことで一生懸命励んだのだと思います」
よみがえった「いのちの芽」今を生きる人たちへ

国立ハンセン病資料館では、「いのちの芽」の企画展がことし5月まで開かれています。
会場には、展示されたことばを静かに見つめる若い世代の姿がありました。
会場には、展示されたことばを静かに見つめる若い世代の姿がありました。

木村哲也さん
「コロナ禍で本当に人とのつながりが希薄になった何年間かだったと思います。そんな中で、それこそ本当に人とのつながりを求めて、隔離の壁を越えて発せられたことばを受け止める素地みたいなものは、それ以前に比べて増している気がするんですよね。70年前の話なので、自分とかけ離れているんじゃないかと思うかもしれませんが、時代を越えて心打つ作品、ことばがきっとあると思います」
「コロナ禍で本当に人とのつながりが希薄になった何年間かだったと思います。そんな中で、それこそ本当に人とのつながりを求めて、隔離の壁を越えて発せられたことばを受け止める素地みたいなものは、それ以前に比べて増している気がするんですよね。70年前の話なので、自分とかけ離れているんじゃないかと思うかもしれませんが、時代を越えて心打つ作品、ことばがきっとあると思います」
厚生労働省によりますと、去年5月末までに全国の療養所で亡くなった人は2万7501人。そして、現在も全国の療養所にはおよそ900人が暮らしています。

私自身、今回の取材で「いのちの芽」を初めて読み、一人一人の感情が心に迫ってくるように感じました。
同時にハンセン病の問題を遠い過去の話にしてはいけないと強く思いました。
この時代によみがえったことばが1人でも多くの人に届くことを願っています。
同時にハンセン病の問題を遠い過去の話にしてはいけないと強く思いました。
この時代によみがえったことばが1人でも多くの人に届くことを願っています。

社会部記者
背戸柚花
2022年入局
大学時代は被爆者について研究
今後は全国のハンセン病療養所を訪ね、取材を続けたい
背戸柚花
2022年入局
大学時代は被爆者について研究
今後は全国のハンセン病療養所を訪ね、取材を続けたい