ひきこもりの末に亡くなった弟 8050問題の当事者として語る
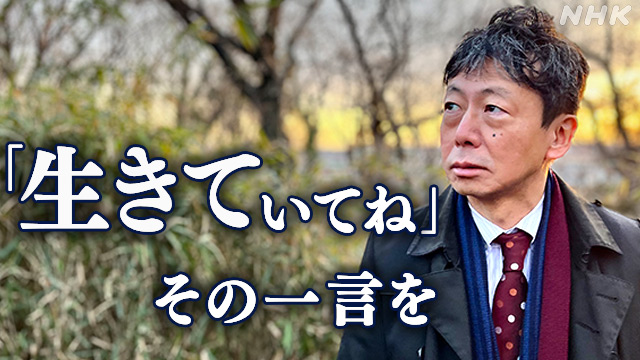
「あのとき、できることがあったのではないか」
ひきこもり当事者の声を25年以上にわたって取材している、ジャーナリストの池上正樹さんには、長年しまい込んできた思いがありました。
4つ下の弟は、仕事についても長続きせず、ひきこもりがちな生活を送っていました。弟は両親を看取り、その後アパートで一人暮らしをしていましたが、7年前に自宅で亡くなっているところを発見されました。
ジャーナリストとしてではなく、8050問題の“当事者”として。
兄弟姉妹の立場の人たちの役に立ててほしいと、池上さんはその過去を語り始めました。(#となりのこもりびと取材班 ディレクター 森田智子)
ひきこもり当事者の声を25年以上にわたって取材している、ジャーナリストの池上正樹さんには、長年しまい込んできた思いがありました。
4つ下の弟は、仕事についても長続きせず、ひきこもりがちな生活を送っていました。弟は両親を看取り、その後アパートで一人暮らしをしていましたが、7年前に自宅で亡くなっているところを発見されました。
ジャーナリストとしてではなく、8050問題の“当事者”として。
兄弟姉妹の立場の人たちの役に立ててほしいと、池上さんはその過去を語り始めました。(#となりのこもりびと取材班 ディレクター 森田智子)
封じ込めてきた過去
「僕の弟も、“ひきこもり死”でした。だから兄弟の立場の気持ちがよくわかります」
池上さんの弟がひきこもりの末に亡くなったという話を初めて聞いたのは、4年前の夏でした。
私は、高齢の親が亡くなったあと、残された本人が命の危険にさらされるケースが全国で相次いでいることを受け、亡くなった56歳の男性とそのご家族の取材を進めていました。
池上さんに“専門家”として話を聞いていた際に、不意に漏れた告白でした。
池上さんの弟がひきこもりの末に亡くなったという話を初めて聞いたのは、4年前の夏でした。
私は、高齢の親が亡くなったあと、残された本人が命の危険にさらされるケースが全国で相次いでいることを受け、亡くなった56歳の男性とそのご家族の取材を進めていました。
池上さんに“専門家”として話を聞いていた際に、不意に漏れた告白でした。
ジャーナリスト 池上正樹さん(60歳)
「この家族はうちとそっくりです…。ただ弟に生前、『お兄ちゃん、僕のことは(記事に)書かないで』と言われたことがありました。公にはしていないので、他言しないでくださいね」
「この家族はうちとそっくりです…。ただ弟に生前、『お兄ちゃん、僕のことは(記事に)書かないで』と言われたことがありました。公にはしていないので、他言しないでくださいね」
最近になって、池上さんは家族会などの場で、弟や家族について少しずつ語るようになっています。
その理由を尋ねると、8050問題が進行し、親が病気になったり亡くなったりする局面にさしかかる人が増える中、ひきこもり当事者の兄弟姉妹からの相談が次々と舞い込むようになったことがあると教えてくれました。
その理由を尋ねると、8050問題が進行し、親が病気になったり亡くなったりする局面にさしかかる人が増える中、ひきこもり当事者の兄弟姉妹からの相談が次々と舞い込むようになったことがあると教えてくれました。

池上正樹さん
「忘れていたわけではないのだけど、『弟も嫌がっていたし、あんまり出さないでおこう』と封じ込めてきました。けれど、相談を受けるたびに思い出されることが一つ一つあって。引き出しが気づかないうちに開いて、ああ、あのときそうだったなと思い出されることが続きました。
ジャーナリストとして少し離れた、安全地帯から見ている感覚がどうしてもあったのですが、“傍観者”でいていいのかな、と。
教訓というか、振り返ってみてもっと伝えておくべきことがいくつかあるのではないかなと思い始めました」
「忘れていたわけではないのだけど、『弟も嫌がっていたし、あんまり出さないでおこう』と封じ込めてきました。けれど、相談を受けるたびに思い出されることが一つ一つあって。引き出しが気づかないうちに開いて、ああ、あのときそうだったなと思い出されることが続きました。
ジャーナリストとして少し離れた、安全地帯から見ている感覚がどうしてもあったのですが、“傍観者”でいていいのかな、と。
教訓というか、振り返ってみてもっと伝えておくべきことがいくつかあるのではないかなと思い始めました」
“成功者”の家に生まれ

記憶のはじまりは、高度成長期まっただ中。
誰もがより良い暮らしを求めた時代にありふれた、ごく普通の家族でした。
語学が堪能で、外資系企業で上り詰めた父と、PTA会長を自ら進んで務めるような社交的な母。
父親は家のことには口を出さず、専業主婦である母親に任せきりでした。
母親は「公務員か教員になってほしい」というのが、口癖でした。
池上さんは幼い頃、弟と比較されて「できの悪い兄」として扱われているように感じていました。
今ではひきこもりの専門家としてテレビにも頻繁に出演していますが、子どもの頃は内気な性格で、幼稚園に行くことを拒んでは母親を困らせました。
小学校に上がると、学校では一切言葉を発することができない「場面緘黙(かんもく)症」になり、その状態は6年間続きました。
誰もがより良い暮らしを求めた時代にありふれた、ごく普通の家族でした。
語学が堪能で、外資系企業で上り詰めた父と、PTA会長を自ら進んで務めるような社交的な母。
父親は家のことには口を出さず、専業主婦である母親に任せきりでした。
母親は「公務員か教員になってほしい」というのが、口癖でした。
池上さんは幼い頃、弟と比較されて「できの悪い兄」として扱われているように感じていました。
今ではひきこもりの専門家としてテレビにも頻繁に出演していますが、子どもの頃は内気な性格で、幼稚園に行くことを拒んでは母親を困らせました。
小学校に上がると、学校では一切言葉を発することができない「場面緘黙(かんもく)症」になり、その状態は6年間続きました。

学校では、「なんでしゃべらないんだ」と問い詰められ、少しでも笑うと、「笑うんだね」とからかわれました。
友達もおらず、学校に行くのは嫌でしかたがなかったものの、「休む」という選択肢はありませんでした。
友達もおらず、学校に行くのは嫌でしかたがなかったものの、「休む」という選択肢はありませんでした。
池上正樹さん
「自分1人だけが変だと、おかしいのだと思い込まされていたので、そこはもう諦めの境地にいたような感じでした。僕はもともと作家になりたいというのが子どもの頃からの夢で。休み時間に、カーテンの陰に隠れてずっと窓の外を見ていたりしていました。どこか違う世界に行きたいという思いで、SFとかファンタジーを書いたりしていました。そこだけが自由…自分だけの世界でした。本当の自分を確認できる、大事な時間だったと思います」
「自分1人だけが変だと、おかしいのだと思い込まされていたので、そこはもう諦めの境地にいたような感じでした。僕はもともと作家になりたいというのが子どもの頃からの夢で。休み時間に、カーテンの陰に隠れてずっと窓の外を見ていたりしていました。どこか違う世界に行きたいという思いで、SFとかファンタジーを書いたりしていました。そこだけが自由…自分だけの世界でした。本当の自分を確認できる、大事な時間だったと思います」
一方で、4つ下の弟は成績が優秀で、スポーツ万能な優等生。
母親の期待に忠実に応えていきました。
両親にとってまさに、“希望の星”でした。
母親の期待に忠実に応えていきました。
両親にとってまさに、“希望の星”でした。
池上正樹さん
「社交的でたくさん友達がいて、エレクトーンとか水泳とか習い事をたくさんしていました。僕は嫌がって一切を拒否していたので、あ、もう何か僕のこと諦めたなっていうタイミングがあって、愛情は弟の方に注がれていきました。今考えれば、兄には期待できないから、親の期待感がもろに弟の方にいったのではないかなと思います」
「社交的でたくさん友達がいて、エレクトーンとか水泳とか習い事をたくさんしていました。僕は嫌がって一切を拒否していたので、あ、もう何か僕のこと諦めたなっていうタイミングがあって、愛情は弟の方に注がれていきました。今考えれば、兄には期待できないから、親の期待感がもろに弟の方にいったのではないかなと思います」
しかし、弟は中学に進学したころから成績が急降下し、その後高校を中退してしまいます。
大学へ進学し、好きな英語を生かして翻訳や校閲の仕事をしたこともありましたが、どれも長続きしませんでした。
兄の池上さんは、中学生になると少しずつ学校でも話せるようになり、好きな読書に没頭する日々を送りました。
高校、大学と順調に進学。大学では新聞を作る活動に打ち込み、大手通信社に就職が決まりました。
大学へ進学し、好きな英語を生かして翻訳や校閲の仕事をしたこともありましたが、どれも長続きしませんでした。
兄の池上さんは、中学生になると少しずつ学校でも話せるようになり、好きな読書に没頭する日々を送りました。
高校、大学と順調に進学。大学では新聞を作る活動に打ち込み、大手通信社に就職が決まりました。

「物書きになりたい」という幼い頃からの夢を叶えた兄と、仕事が続かずひきこもりがちな弟。
両親にとっての“社会的評価”は逆転し、母親は「大企業に入れて良かったじゃない」と喜びました。
その後、池上さんは3年ほどで通信社をやめ、フリージャーナリストとして仕事をするようになりました。
駆け出しのころ、学校教育の問題を取材する中で、一人の少年に出会います。
両親にとっての“社会的評価”は逆転し、母親は「大企業に入れて良かったじゃない」と喜びました。
その後、池上さんは3年ほどで通信社をやめ、フリージャーナリストとして仕事をするようになりました。
駆け出しのころ、学校教育の問題を取材する中で、一人の少年に出会います。
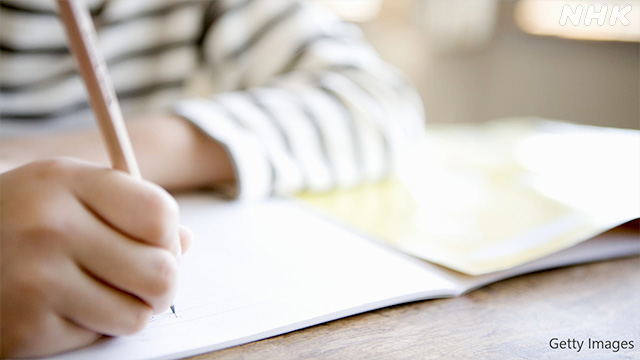
場面緘黙(かんもく)症で言葉を発することができずに不登校となり、フリースクールに通っていた中学生の男の子。
言葉は交わさなくても、伝わってくる気持ちがありました。
「どうしてこうなってしまうのだろう…」
かつての自分と重なり、夢中になって調べるうちに、さまざまな精神疾患やひきこもりの世界に触れ、のめり込んでいきました。
一方で、フリージャーナリストとして働くことを、母親はあまり快く思っていませんでした。
世間体を気にする母親からは、通信社をやめた際、「ショックです」というひとことだけ書かれたはがきが送られてきました。
両親から期待されたレールから外れて生きているという自覚があった池上さんは、次第に実家から足が遠のくようになっていきました。
「お兄ちゃんはいいな」
弟は、フリージャーナリストとして働く兄を、羨む言葉を漏らすこともあったと言います。
言葉は交わさなくても、伝わってくる気持ちがありました。
「どうしてこうなってしまうのだろう…」
かつての自分と重なり、夢中になって調べるうちに、さまざまな精神疾患やひきこもりの世界に触れ、のめり込んでいきました。
一方で、フリージャーナリストとして働くことを、母親はあまり快く思っていませんでした。
世間体を気にする母親からは、通信社をやめた際、「ショックです」というひとことだけ書かれたはがきが送られてきました。
両親から期待されたレールから外れて生きているという自覚があった池上さんは、次第に実家から足が遠のくようになっていきました。
「お兄ちゃんはいいな」
弟は、フリージャーナリストとして働く兄を、羨む言葉を漏らすこともあったと言います。
池上正樹さん
「僕は子どもの頃の体験もあって、親のプレッシャーから自分を防衛して、自分らしさを解放するために家を出て行きました。僕は『家』から逃げたところがありました。弟は両親に忠実で、親の価値観に縛られて逃げることができなかったのだと思います」
「僕は子どもの頃の体験もあって、親のプレッシャーから自分を防衛して、自分らしさを解放するために家を出て行きました。僕は『家』から逃げたところがありました。弟は両親に忠実で、親の価値観に縛られて逃げることができなかったのだと思います」
“先送り”し続けた家族
一度、池上さんは母親に頼み込まれて、弟をアシスタントとして雇ったことがありました。
しかし、金銭感覚があまりなかった弟は、事務所の備品を大量に買い込むなどしてしまい、池上さん自身の生活にも影響が及びました。
「このままでは共倒れしてしまう」
よかれと思ってやってくれているのは理解したものの、注意しても改善することなく、雇い続けるのは難しいと伝えざるを得ませんでした。
その後も、社会に居場所を見つけることができず、ひきこもりがちだった弟。
家族は問題を先送りし、話し合いの場を持つことはありませんでした。
やがて、母親ががんを患い、余命幾ばくかということがわかります。
池上さんの提案で、家族みんなで、旅行に出かけました。
母親が幼い頃に過ごした町でのひととき。しかしそこでも“先送り”は続きました。
しかし、金銭感覚があまりなかった弟は、事務所の備品を大量に買い込むなどしてしまい、池上さん自身の生活にも影響が及びました。
「このままでは共倒れしてしまう」
よかれと思ってやってくれているのは理解したものの、注意しても改善することなく、雇い続けるのは難しいと伝えざるを得ませんでした。
その後も、社会に居場所を見つけることができず、ひきこもりがちだった弟。
家族は問題を先送りし、話し合いの場を持つことはありませんでした。
やがて、母親ががんを患い、余命幾ばくかということがわかります。
池上さんの提案で、家族みんなで、旅行に出かけました。
母親が幼い頃に過ごした町でのひととき。しかしそこでも“先送り”は続きました。
池上さん
「その時は他愛もない話で、母親が亡くなったときの話はできませんでした。僕から踏み込んでもよかったのだろうけど、そのときになっても先送りになってしまいました。どこかで“いざとなったらお兄ちゃんが何とかしてくれるだろう”という期待を感じて、目を背けたかったのかもしれません」
「その時は他愛もない話で、母親が亡くなったときの話はできませんでした。僕から踏み込んでもよかったのだろうけど、そのときになっても先送りになってしまいました。どこかで“いざとなったらお兄ちゃんが何とかしてくれるだろう”という期待を感じて、目を背けたかったのかもしれません」
母親が入院してから亡くなるまでのおよそ半年間、弟は母親にかいがいしく付き添い、病院に通い詰めていました。
そして、大勢の人が訪れた葬儀。
弟は人目をはばからず泣きじゃくっていました。
そして、大勢の人が訪れた葬儀。
弟は人目をはばからず泣きじゃくっていました。

母親の死後、父親と二人暮らしになった弟は、家事の一切を担っていました。
家のことに口出しをしてこなかった父親と、弟との間にどのような関係があったのか。離れて暮らす池上さんからはわかりませんでした。
まもなく、今度は父親に脳腫瘍が見つかります。
兄弟二人はセカンドオピニオンを求めて、協力してさまざまな病院をめぐりました。
その甲斐なく、母親のおよそ1年後に亡くなりました。
晩年、声が出せなくなった父親は、2人の息子の姿をじっと見つめ、涙をながしたことがありました。
結局最後まで、自分の思いを語ることはありませんでした。
家のことに口出しをしてこなかった父親と、弟との間にどのような関係があったのか。離れて暮らす池上さんからはわかりませんでした。
まもなく、今度は父親に脳腫瘍が見つかります。
兄弟二人はセカンドオピニオンを求めて、協力してさまざまな病院をめぐりました。
その甲斐なく、母親のおよそ1年後に亡くなりました。
晩年、声が出せなくなった父親は、2人の息子の姿をじっと見つめ、涙をながしたことがありました。
結局最後まで、自分の思いを語ることはありませんでした。
池上さん
「家のことは母に任せきりで、あまりものを言わない人でしたが、優しい父でした。でも本心では、自分の思っていたような家族じゃないという思いがあったのか。あの涙が何を意味していたのか、今でもときどき考えてしまいます」
「家のことは母に任せきりで、あまりものを言わない人でしたが、優しい父でした。でも本心では、自分の思っていたような家族じゃないという思いがあったのか。あの涙が何を意味していたのか、今でもときどき考えてしまいます」
「お兄ちゃん、誰か連れてきたでしょう」
一人取り残された弟は、生きる気力そのものを失っていきました。
時折、実家を訪ねると、お酒の空き缶などのごみであふれ、雨戸を締め切った自室で寝たままの状態でいました。
それでも、池上さんが訪ねていくと起き上がり、「通信制の大学を卒業して、就職して、結婚もしたい」と口にしました。
ジャーナリズムや英語の教材を買い込んでいて、気づけば、両親が残したお金を使い果たし、多重債務を抱えていることもわかりました。
やがて、「誰かが覗(のぞ)いている」「話し声が聞こえる」などと口にするようになりました。
弟は自ら精神科の病院に入院。そこで、「統合失調症」と指摘されます。
しかし、その診断をかたくなに受け入れませんでした。
退院に際して実家を手放し、アパートで暮らし始めた弟。
池上さんが訪ねるたびに目にしたのは、封がしたままの段ボールが山積みになった暗い部屋。
デスクの照明だけで明かりを取り、机に向かう姿でした。
「今度、部屋の照明を買ってくるね」
時折、実家を訪ねると、お酒の空き缶などのごみであふれ、雨戸を締め切った自室で寝たままの状態でいました。
それでも、池上さんが訪ねていくと起き上がり、「通信制の大学を卒業して、就職して、結婚もしたい」と口にしました。
ジャーナリズムや英語の教材を買い込んでいて、気づけば、両親が残したお金を使い果たし、多重債務を抱えていることもわかりました。
やがて、「誰かが覗(のぞ)いている」「話し声が聞こえる」などと口にするようになりました。
弟は自ら精神科の病院に入院。そこで、「統合失調症」と指摘されます。
しかし、その診断をかたくなに受け入れませんでした。
退院に際して実家を手放し、アパートで暮らし始めた弟。
池上さんが訪ねるたびに目にしたのは、封がしたままの段ボールが山積みになった暗い部屋。
デスクの照明だけで明かりを取り、机に向かう姿でした。
「今度、部屋の照明を買ってくるね」

その約束を果たすため、照明器具を購入し、1人で取り付けにいった時のことでした。
正月だったので、おせち料理を持って行きました。
照明を取り付けていると、弟は、
「お兄ちゃん、誰か連れてきたでしょう。話し声が聞こえる」
と言って怒り出し、池上さんは追い出されるような形で部屋を後にしました。
それが、弟と交わした、最後の言葉となりました。
数か月後、部屋代を滞納していると連絡があり確認してもらったところ、亡くなっていることがわかりました。
「すでに腐敗しているから」と、対面することもかないませんでした。
死因は「病死」とされました。
49歳でした。
正月だったので、おせち料理を持って行きました。
照明を取り付けていると、弟は、
「お兄ちゃん、誰か連れてきたでしょう。話し声が聞こえる」
と言って怒り出し、池上さんは追い出されるような形で部屋を後にしました。
それが、弟と交わした、最後の言葉となりました。
数か月後、部屋代を滞納していると連絡があり確認してもらったところ、亡くなっていることがわかりました。
「すでに腐敗しているから」と、対面することもかないませんでした。
死因は「病死」とされました。
49歳でした。
「生きていてさえくれれば」
それから7年の時が経ちました。
その間に、高齢の親が中高年の子どもを抱え込む「8050(はちまる・ごーまる)問題」が広く知られるようになりました。
また、生きる気力を失い、命を落とす人の存在も報道されるようになり、本人とどう関わっていくべきなのか、少しずつ知見が積み上がってきています。
そうした中で、池上さんが最も強く感じるのは「生きていてさえくれれば」という思いです。
ある講演会に参加してくれた女性の当事者からの言葉。
「握手をして、“生きていてほしい”と言ってもらえませんか」
「生きていてね」と声をかけると、女性は「ありがとうございます」といいながら、大粒の涙を流しました。
その間に、高齢の親が中高年の子どもを抱え込む「8050(はちまる・ごーまる)問題」が広く知られるようになりました。
また、生きる気力を失い、命を落とす人の存在も報道されるようになり、本人とどう関わっていくべきなのか、少しずつ知見が積み上がってきています。
そうした中で、池上さんが最も強く感じるのは「生きていてさえくれれば」という思いです。
ある講演会に参加してくれた女性の当事者からの言葉。
「握手をして、“生きていてほしい”と言ってもらえませんか」
「生きていてね」と声をかけると、女性は「ありがとうございます」といいながら、大粒の涙を流しました。

この言葉を、弟にもかけ続けてあげられていたら。
「生きているだけでいい」という思いで、家族が接してあげられていたら。
生きる気力を失い、消え入るように亡くなっていった弟の命を、つなぎとめることができたのではないか。
そう思えてしかたがないといいます。
「生きているだけでいい」という思いで、家族が接してあげられていたら。
生きる気力を失い、消え入るように亡くなっていった弟の命を、つなぎとめることができたのではないか。
そう思えてしかたがないといいます。
池上正樹さん
「『生きていてね』って、その一言を言ってもらいたいけど、誰も言ってくれない。
生きていてもしかたがないと思っているし、社会から必要とされてないと思っているからこそ、その言葉が大事なのだと。
弟が生きていた時には、そこに思いが及びませんでした。今だったら言えます。
生きているだけでいいじゃん。
一日一日、ああ生きていてよかったって、それでいいじゃないって。今だったら言いますね…」
「『生きていてね』って、その一言を言ってもらいたいけど、誰も言ってくれない。
生きていてもしかたがないと思っているし、社会から必要とされてないと思っているからこそ、その言葉が大事なのだと。
弟が生きていた時には、そこに思いが及びませんでした。今だったら言えます。
生きているだけでいいじゃん。
一日一日、ああ生きていてよかったって、それでいいじゃないって。今だったら言いますね…」
8050家族の“教訓”
池上さんは自身の経験を振り返り、兄弟姉妹としてできることとしての教訓があると、教えてくれました。
◎「まずは生きることが大切」と家族が認識を持つこと
池上正樹さん
「親は『世間体』とか、『働いて自立してほしい』という思いがあり、本人もそれにとらわれてしまいがちです。『尊厳』を大事にしながら、一人になったとしても生きていけるよう支えるのが大事だという共通認識を家族が持てるといいと思います。兄弟姉妹が家族会議を取り持つなどして説得することで、関係性が改善したり、親子ともに元気になっていったりすることもあるのです」
「親は『世間体』とか、『働いて自立してほしい』という思いがあり、本人もそれにとらわれてしまいがちです。『尊厳』を大事にしながら、一人になったとしても生きていけるよう支えるのが大事だという共通認識を家族が持てるといいと思います。兄弟姉妹が家族会議を取り持つなどして説得することで、関係性が改善したり、親子ともに元気になっていったりすることもあるのです」
◎両親が存命なうちに、第三者とのつながりを持っておくこと
「親が唯一の社会の窓になっている場合、親が亡くなると生きるエネルギーそのものがなくなってしまうおそれがあります。家族以外の第三者とのつながりを作っておくことが大切です。親の病院に本人が心配して付きそうケースが多いので、そうしたタイミングを外とのつながりをつくるきっかけにすることも大事なのではないかと思います」
今、池上さんが理事を務めるKHJ全国ひきこもり家族会連合会では、月に1度、兄弟姉妹が悩みを共有したり、相談したりできる場を開いています。
また、全国の人が参加できる、オンラインでの兄弟姉妹支部の発足に向けて準備を進めています。
また、全国の人が参加できる、オンラインでの兄弟姉妹支部の発足に向けて準備を進めています。
「なぜ兄弟姉妹がケアをしたり、さまざまな負担をしたりしなければいけないのか、という不公平感に悩んでいる方も多いかと思います。『兄弟なんだから』という周囲からのプレッシャーから、誰にも相談できずにいる人もたくさんいます。悩みを共有し、どうしていけばいいか一緒に考えられる場を作っていきたいと思います」
KHJ全国ひきこもり家族連合会 兄弟姉妹の会(※NHKのサイトを離れます)

報道局社会番組部ディレクター
森田智子
ウェブサイト「#となりのこもりびと」担当
“ひきこもり”取材13年
NHKスペシャル「ドラマこもりびと」「ある、ひきこもりの死」、ETV特集「空蝉の家」など制作
森田智子
ウェブサイト「#となりのこもりびと」担当
“ひきこもり”取材13年
NHKスペシャル「ドラマこもりびと」「ある、ひきこもりの死」、ETV特集「空蝉の家」など制作
#となりのこもりびと
森田ディレクターが担当するウェブサイトはこちら
