温泉郷を襲った異変 いったい何が?
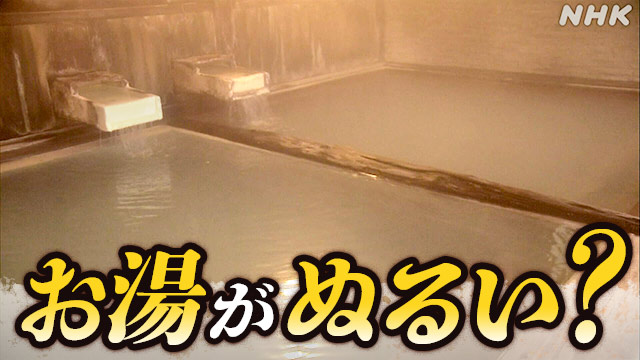
「申し訳ありませんが、ぬるくて入れません」。
青森県の温泉旅館の店主は電話口で絞り出すように答えました。源泉の温度が下がり、旅館の温泉に入れないというのです。休業を余儀なくされ、冬の温泉を楽しみにしていた客への説明に追われています。
新型コロナの行動制限が解除され全国旅行支援も再開。
旅館にとって、いよいよ復活という時に、業者の熱をも冷ます事態になっています。
(青森放送局記者 森谷日南子)
青森県の温泉旅館の店主は電話口で絞り出すように答えました。源泉の温度が下がり、旅館の温泉に入れないというのです。休業を余儀なくされ、冬の温泉を楽しみにしていた客への説明に追われています。
新型コロナの行動制限が解除され全国旅行支援も再開。
旅館にとって、いよいよ復活という時に、業者の熱をも冷ます事態になっています。
(青森放送局記者 森谷日南子)
観光客戻る!期待のタイミングで…

青森県弘前市の嶽(だけ)温泉郷です。
300年以上前に始まり、湯治場として栄えた「こじんまり」とした温泉郷で、6つの旅館があります。
異変は、この温泉郷で起こりました。
300年以上前に始まり、湯治場として栄えた「こじんまり」とした温泉郷で、6つの旅館があります。
異変は、この温泉郷で起こりました。

「(温度は)ぬるいですね、入れないです」
そう話すのは、嶽温泉旅館組合の小嶋庸平組合長です。
昨年末から急に源泉の温度が低くなってしまい、熱いお湯が出なくなってしまったと言います。
そう話すのは、嶽温泉旅館組合の小嶋庸平組合長です。
昨年末から急に源泉の温度が低くなってしまい、熱いお湯が出なくなってしまったと言います。
嶽温泉旅館組合 小嶋庸平組合長
「完全に枯れたかどうか結論づけるのは早いと思うんですが、現状、あまり期待できる温度と量が確保できていません」
「完全に枯れたかどうか結論づけるのは早いと思うんですが、現状、あまり期待できる温度と量が確保できていません」
嶽温泉郷は、6つの旅館が共同で4本の源泉を利用しています。

そのうち、最も温度の高い源泉が、80度からおよそ50度まで下がってしまったのです。
源泉が宿泊施設の浴槽にたどり着くころには38度ほどと、青森では湯冷めをしてしまうという温度です。
源泉が宿泊施設の浴槽にたどり着くころには38度ほどと、青森では湯冷めをしてしまうという温度です。

江戸時代末期に創業した小嶋さんが経営する旅館では、およそ44度の「あつい温泉」と、およそ42度の「ぬるい温泉」の2種類があり、人気を集めていました。
しかし、取材した日は、あつい温泉で36度、ぬるい温泉で34度といつもより8度も下がってしまっていました。
しかし、取材した日は、あつい温泉で36度、ぬるい温泉で34度といつもより8度も下がってしまっていました。

さらに、源泉の湯量も、以前は毎分200リットルほどありましたが、5分の1ほどに落ち込んでしまいました。
温度も下がり、湯量も減少。
嶽温泉郷にある6つの旅館のうち3つの旅館が休業し、あとの3つの旅館は日帰り入浴のみの営業など、かき入れ時の年末以降、規模を縮小して営業を続けています。
温度も下がり、湯量も減少。
嶽温泉郷にある6つの旅館のうち3つの旅館が休業し、あとの3つの旅館は日帰り入浴のみの営業など、かき入れ時の年末以降、規模を縮小して営業を続けています。
原因不明・破産に追い込まれる旅館も
なぜ今、源泉に異変が起きているのか。
温度が下がった源泉は、50年ほど前に掘られたものですが、こうしたトラブルは「今回が初めて」だといいます。
温度が下がった源泉は、50年ほど前に掘られたものですが、こうしたトラブルは「今回が初めて」だといいます。
温泉旅館組合は、当初、源泉の配管がつまって湯量が減り温度が下がったとみて調べましたが、配管に異変はみられませんでした。
原因は分からぬままです。
これ以上詳しい調査をしようにも、雪深い嶽地域は、源泉がある山奥に行くために大規模な除雪が必要で、春の雪どけを待つしかありません。
原因は分からぬままです。
これ以上詳しい調査をしようにも、雪深い嶽地域は、源泉がある山奥に行くために大規模な除雪が必要で、春の雪どけを待つしかありません。

嶽温泉旅館組合 小嶋庸平組合長
「お湯の十分な量と温度が確保できないとなると浴用施設としての営業はほぼ不可能な状況です。春くらいまでは通常の営業ができなくなるかもしれません。今後どうなるか全く予想がつきません」
「お湯の十分な量と温度が確保できないとなると浴用施設としての営業はほぼ不可能な状況です。春くらいまでは通常の営業ができなくなるかもしれません。今後どうなるか全く予想がつきません」
源泉の温度低下で、破産に追い込まれる宿泊施設も出ています。

嶽温泉を代表する創業およそ350年の老舗ホテルが、破産申請を行う方針が明らかになったのです。
新型コロナで経営がいっそう悪化、そこにきての源泉の温度低下が破産申請を決断した決め手になったとみられています。
新型コロナによる行動制限も解除され、全国旅行支援もことし1月10日から再開。
新型コロナで経営がいっそう悪化、そこにきての源泉の温度低下が破産申請を決断した決め手になったとみられています。
新型コロナによる行動制限も解除され、全国旅行支援もことし1月10日から再開。

さらに海外からの観光客もようやく戻ってくるという、観光施設にとっては待ちに待ったタイミングでの今回の異変。
取材で、たびたび嶽温泉郷に向かいましたが、目立った客の姿はなく、閑散としていました。
いつまで休業しなければならないのか、源泉は復活するのか、旅館の店主たちの肩を落とす姿を見ると胸が痛くなりました。
取材で、たびたび嶽温泉郷に向かいましたが、目立った客の姿はなく、閑散としていました。
いつまで休業しなければならないのか、源泉は復活するのか、旅館の店主たちの肩を落とす姿を見ると胸が痛くなりました。
実は全国で?
なぜこうした事態は起きているのか。
温泉の研究を行っている中央温泉研究所の大塚晃弘主任研究員に聞きました。
大塚研究員は、温泉の“目詰まり”の可能性を指摘します。
温泉の研究を行っている中央温泉研究所の大塚晃弘主任研究員に聞きました。
大塚研究員は、温泉の“目詰まり”の可能性を指摘します。

中央温泉研究所 大塚晃弘主任研究員
「急激に温度が下がったことから源泉そのもののトラブルではないと思います。地域内で複数の源泉が調子を崩しているのであれば、地域での温泉の過剰採取や気象条件が疑われますが、そうではなく、1源泉だけが温度が低下し湯量が減っているのであれば、一般的には温泉井戸の深部からの温泉湧出が物理的に阻害されているようなこと、つまり温泉が目詰まりしていると推定されます」
「急激に温度が下がったことから源泉そのもののトラブルではないと思います。地域内で複数の源泉が調子を崩しているのであれば、地域での温泉の過剰採取や気象条件が疑われますが、そうではなく、1源泉だけが温度が低下し湯量が減っているのであれば、一般的には温泉井戸の深部からの温泉湧出が物理的に阻害されているようなこと、つまり温泉が目詰まりしていると推定されます」
一方で、原因は異なると思われるものの、「源泉の温度が下がる」「温泉が出ない」現象は、全国でも起きているといいます。
中央温泉研究所 大塚晃弘主任研究員
「実は、青森県だけでなく大分県・別府温泉や北海道・ひらふ温泉でも同様の問題が発生しています。別府温泉やひらふ温泉でこのような問題が発生したのは、長い年月をかけて温泉が地域に拡大し、過剰に温泉を取り過ぎた結果、温泉の水位が下がり温度が下がったことが原因ではないかと考えています」
「実は、青森県だけでなく大分県・別府温泉や北海道・ひらふ温泉でも同様の問題が発生しています。別府温泉やひらふ温泉でこのような問題が発生したのは、長い年月をかけて温泉が地域に拡大し、過剰に温泉を取り過ぎた結果、温泉の水位が下がり温度が下がったことが原因ではないかと考えています」
そのうえで、大塚研究員はこう話します。
中央温泉研究所 大塚晃弘主任研究員
「温泉の井戸は人間が掘削して作ったものですのでどうしても寿命があります。維持していくにはメンテナンスも必要で、温泉の枯渇はどこの温泉地でも発生しえる現象です。全国には1万7000本の源泉がありますので中には調子を崩している温泉があっても不思議ではありません」
「温泉の井戸は人間が掘削して作ったものですのでどうしても寿命があります。維持していくにはメンテナンスも必要で、温泉の枯渇はどこの温泉地でも発生しえる現象です。全国には1万7000本の源泉がありますので中には調子を崩している温泉があっても不思議ではありません」
「風呂好き県」に落とす影
青森県は入浴施設の数が、人口10万人あたり16.95軒で、日本一。(2022年6月時点)。その入浴施設の多くが温泉で、車にお風呂セットを常備している人も多いといわれるほどの“風呂好き県”です。
夏のねぶた(弘前ではねぷたですが)だけではなく、冬にも温泉やスキーを目当てに、国内だけでなく海外からも、多くの観光客が訪れます。
夏のねぶた(弘前ではねぷたですが)だけではなく、冬にも温泉やスキーを目当てに、国内だけでなく海外からも、多くの観光客が訪れます。

地域の集いの場としても、観光資源としても、なくてはならない温泉に起きた異変。
取材を通して、温泉は当たり前にあるものではない、大切な資源なんだということを痛感しました。
限りある資源をどう生かしていくのか。
嶽温泉の源泉が警鐘を鳴らしているのかもしれません。
取材を通して、温泉は当たり前にあるものではない、大切な資源なんだということを痛感しました。
限りある資源をどう生かしていくのか。
嶽温泉の源泉が警鐘を鳴らしているのかもしれません。

青森放送局弘前支局記者
森谷 日南子
2019年入局
警察取材を担当後、弘前支局
現在は、行政や農業取材を担当。
森谷 日南子
2019年入局
警察取材を担当後、弘前支局
現在は、行政や農業取材を担当。