美しい写真で自然に共感してもらいたい 写真家 高砂淳二さん

自然写真の世界最高峰の賞のひとつを受賞した写真家の高砂淳二さん。
世界100か国以上を巡り、37年にわたって写真家として歩んできた高砂さんは心に残るような美しい写真を数多く撮影してきました。
時間をかけて美しい自然と向き合いたい。
そこには東北の海への思いがありました。
(おはよう日本 アナウンサー 森下絵理香)
世界100か国以上を巡り、37年にわたって写真家として歩んできた高砂さんは心に残るような美しい写真を数多く撮影してきました。
時間をかけて美しい自然と向き合いたい。
そこには東北の海への思いがありました。
(おはよう日本 アナウンサー 森下絵理香)
世界の自然を撮影し続けてきた
高砂淳二さん(60)は世界の海や大地を巡って、一瞬だけ見せる奇跡のような美しい瞬間を撮影し続けてきたカメラマンです。

「カニとアジサシ」という作品。
セーシェル諸島の砂浜で「食べる・食べられる」という関係ではないアジサシという鳥とカニが、お互いに気づいたら近くにいて、「どうしようかなと…」と目を合わせて戸惑った瞬間を捉えていて、心の中まで見て取れるような表情豊かな写真です。
セーシェル諸島の砂浜で「食べる・食べられる」という関係ではないアジサシという鳥とカニが、お互いに気づいたら近くにいて、「どうしようかなと…」と目を合わせて戸惑った瞬間を捉えていて、心の中まで見て取れるような表情豊かな写真です。

「ジェンツーペンギン」という作品。
住人のほとんどがペンギンという南米のフォークランド諸島の海辺で、夕暮れ時に海から戻ったジェンツーペンギンの群れを写しだしていて、人間が目の届かない大自然の中で続けられてきた生き物たちの営みの長い年月さえも感じさせる写真になっています。
住人のほとんどがペンギンという南米のフォークランド諸島の海辺で、夕暮れ時に海から戻ったジェンツーペンギンの群れを写しだしていて、人間が目の届かない大自然の中で続けられてきた生き物たちの営みの長い年月さえも感じさせる写真になっています。
世界的な写真賞を受賞
その高砂さんの作品が2022年10月、「ワイルドライフ・フォトグラファー・オブ・ザ・イヤー」の自然芸術部門で最優秀賞を受賞しました。

この賞は、ロンドン自然史博物館が主催するコンテストで、何万点もの作品の中から最優秀賞が選ばれる世界で最も権威のある写真賞のひとつです。
自然芸術部門の最優秀賞を日本人が受賞したのは初めてのことになります。
自然芸術部門の最優秀賞を日本人が受賞したのは初めてのことになります。

こちらが受賞した作品。
南米ボリビアにあるウユニ塩湖に降り立ったフラミンゴを写した写真です。
風が完全に止んで鏡のようになった湖面に青空が反射して天国のように美しい光景の中でフラミンゴが音符のようにも見えた奇跡的な一瞬を写し出しています。
フラミンゴは特に警戒心が強いということで、遠くに車を止めて、ゆっくりゆっくりと2時間ほどかけて近づいたということです。
ウユニ塩湖がある所は標高3700メートルと富士山の山頂ほどの高さにあるため、高山病による頭痛や立ちくらみに襲われながらも、警戒させずに自然な姿を写しだしました。
南米ボリビアにあるウユニ塩湖に降り立ったフラミンゴを写した写真です。
風が完全に止んで鏡のようになった湖面に青空が反射して天国のように美しい光景の中でフラミンゴが音符のようにも見えた奇跡的な一瞬を写し出しています。
フラミンゴは特に警戒心が強いということで、遠くに車を止めて、ゆっくりゆっくりと2時間ほどかけて近づいたということです。
ウユニ塩湖がある所は標高3700メートルと富士山の山頂ほどの高さにあるため、高山病による頭痛や立ちくらみに襲われながらも、警戒させずに自然な姿を写しだしました。
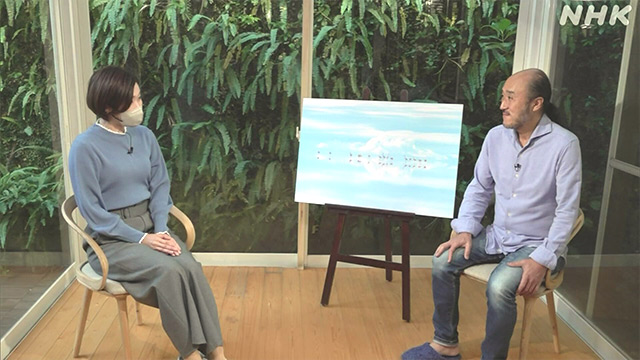
高砂淳二さん
「ウユニ塩湖にはコロナ前の10年間で6回訪れていて、遠くにいるフラミンゴは見たことがありましたが、こんなにも近くで出会ったのは初めてでした。風が止み、雲が程よくあり、フラミンゴたちがその背景と完全なハーモニーを作っているという奇跡の一瞬で、自然からの贈り物のように感じました。いろいろな問題が起きている地球上に、同時にこんな瞬間が存在するということ、そして、この地球はこんなにも美しく宝物のような天体であるということを感じさせてくれます」
「ウユニ塩湖にはコロナ前の10年間で6回訪れていて、遠くにいるフラミンゴは見たことがありましたが、こんなにも近くで出会ったのは初めてでした。風が止み、雲が程よくあり、フラミンゴたちがその背景と完全なハーモニーを作っているという奇跡の一瞬で、自然からの贈り物のように感じました。いろいろな問題が起きている地球上に、同時にこんな瞬間が存在するということ、そして、この地球はこんなにも美しく宝物のような天体であるということを感じさせてくれます」
震災後 潜れなくなった原点の海
その高砂さんは、自身の原点である東北の海に向き合えなくなった時期がありました。
高砂さんは宮城県石巻市出身で、海好きが高じて、海の中を撮影することから写真家としてのスタートを切りました。
高砂さんは宮城県石巻市出身で、海好きが高じて、海の中を撮影することから写真家としてのスタートを切りました。

2002年に撮影したこの写真は、ホヤの漁師を写したものです。海のすぐそばで暮らしてきたからこそ、自然とは恵みをもたらすもの、優しさを持つものと考えていました。
しかし、巨大な津波が人々の生活をのみ込むように破壊してしまったのです。2011年の東日本大震災です。高砂さんは当時、東京にいましたが、実家が津波で被災し、知人を亡くすなど、自然の恐ろしさを初めて知りました。
震災後の海に潜るダイバーもいましたが、高砂さんはその海に潜る気持ちになれませんでした。2年ほどは大自然や海と向き合って撮影することができず、その後、海外を巡って雄大な大地などを撮影していました。
しかし、巨大な津波が人々の生活をのみ込むように破壊してしまったのです。2011年の東日本大震災です。高砂さんは当時、東京にいましたが、実家が津波で被災し、知人を亡くすなど、自然の恐ろしさを初めて知りました。
震災後の海に潜るダイバーもいましたが、高砂さんはその海に潜る気持ちになれませんでした。2年ほどは大自然や海と向き合って撮影することができず、その後、海外を巡って雄大な大地などを撮影していました。

被災した海に潜る
震災から9年が経過した2020年、自分の気持ちに区切りをつけたいと思い、初めて震災の痕が残る宮城県の海に潜りました。場所は宮城県女川町の沿岸です。
目を背けたままだった破壊的な恐ろしさをもった「自然」も見なくてはいけないと決心がついたからです。
目を背けたままだった破壊的な恐ろしさをもった「自然」も見なくてはいけないと決心がついたからです。

水深4メートルの海には、人々の生活を感じさせる多くの物が9年たっても海底に散乱していました。
子どもが使って遊んでいたであろうおもちゃの車は、色あせることなく残されていました。陸上とは違い、海の中は風化せずに震災の爪痕が残っていたのです。
子どもが使って遊んでいたであろうおもちゃの車は、色あせることなく残されていました。陸上とは違い、海の中は風化せずに震災の爪痕が残っていたのです。

水深12メートルの海底に沈んでいた巨大な魚の養殖用の生けすは網や金属製の枠組みが亡霊のようにたたずんでいました。
そして、ホヤや貝などがびっしりとついて、年月の経過を感じさせていました。
そして、ホヤや貝などがびっしりとついて、年月の経過を感じさせていました。

ボッキリと折れた金属製の柱が海底に沈んでいましたが、柱の中の空間にはハゼの仲間が住みついていました。
ハゼは「何だオマエ!」とでも言いたそうな顔でこちらを見ています。
ハゼは「何だオマエ!」とでも言いたそうな顔でこちらを見ています。

高砂淳二さん
「自然というのは、しなやかでもあり、したたかでもあり、人がどうだったというのを関係なく、住みやすいと思えば、そこにどんどん、くっついていって住んでいる。そして飲み込みつつあるわけです。僕たちは、自然の恵みをいただいて、いろんなものに囲まれていることに感謝して生きなくちゃいけない…だけど、いつ死んでもおかしくない、覚悟して生きなくちゃいけないということを、同時に感じたんです。自分自身も、大好きな海がこんなことをしてしまったと嘆くのではなくて、そういうのも含めて覚悟して、一瞬一瞬生きていかなくちゃいけないなと、思えるようになっていきました」
「自然というのは、しなやかでもあり、したたかでもあり、人がどうだったというのを関係なく、住みやすいと思えば、そこにどんどん、くっついていって住んでいる。そして飲み込みつつあるわけです。僕たちは、自然の恵みをいただいて、いろんなものに囲まれていることに感謝して生きなくちゃいけない…だけど、いつ死んでもおかしくない、覚悟して生きなくちゃいけないということを、同時に感じたんです。自分自身も、大好きな海がこんなことをしてしまったと嘆くのではなくて、そういうのも含めて覚悟して、一瞬一瞬生きていかなくちゃいけないなと、思えるようになっていきました」
美しい写真で“自然に共感”を
高砂さんは美しいだけではない自然の姿も見たうえで、改めて美しい景色を撮影していきたいと言います。
そのことを示すものとしてカナダのセントローレンス湾の流氷で撮影したアザラシの写真を見せてくれました。
そのことを示すものとしてカナダのセントローレンス湾の流氷で撮影したアザラシの写真を見せてくれました。

高砂淳二さん
「生まれたばかりのアザラシの目は、涙が浮かんでいるように見えるでしょ。これは生理現象なのですが、私たち人間は『共感』ができる生き物だから『涙』に見えるのです。人は、地球上の他の生き物に対しても感情移入したり、その思いをシェアしたりできる。そんな思いをこうした写真で呼び覚ませればうれしいよね」
「生まれたばかりのアザラシの目は、涙が浮かんでいるように見えるでしょ。これは生理現象なのですが、私たち人間は『共感』ができる生き物だから『涙』に見えるのです。人は、地球上の他の生き物に対しても感情移入したり、その思いをシェアしたりできる。そんな思いをこうした写真で呼び覚ませればうれしいよね」
美しい写真は自然を大切にする気持ちを広げる力があると語りました。
実はこの写真の撮影から数日後、この場所の氷は全部溶けてなくなったことを高砂さんは知ります。氷に守られていたアザラシの子どもは、自立できず死んでしまったのではないか…。衝撃を受けると同時に、美しい写真を撮り続ける使命感を感じたと言います。
実はこの写真の撮影から数日後、この場所の氷は全部溶けてなくなったことを高砂さんは知ります。氷に守られていたアザラシの子どもは、自立できず死んでしまったのではないか…。衝撃を受けると同時に、美しい写真を撮り続ける使命感を感じたと言います。

高砂淳二さん
「僕自身、美しい自然を見ることで気持ちが癒されたり感動したりしながら、突き動かされて撮影を続けてこられたように、自然の美しさには人の心を動かす力があると考えています。美しさ、愛らしさ、神々しさ、そういうものを感じて、大事にしなきゃと、元々持っている意識が揺さぶられるのではないかと思うんです。僕の原点は、生まれ育った東北の海で感じた、海や自然の豊かさや包み込むような温かさで、震災で揺らいでも、その根幹は変わりませんでした。美しい景色にこだわって撮影することで、少しでも多くの人に“自然を大事にしたい”と思ってもらいたいと考えています」
「僕自身、美しい自然を見ることで気持ちが癒されたり感動したりしながら、突き動かされて撮影を続けてこられたように、自然の美しさには人の心を動かす力があると考えています。美しさ、愛らしさ、神々しさ、そういうものを感じて、大事にしなきゃと、元々持っている意識が揺さぶられるのではないかと思うんです。僕の原点は、生まれ育った東北の海で感じた、海や自然の豊かさや包み込むような温かさで、震災で揺らいでも、その根幹は変わりませんでした。美しい景色にこだわって撮影することで、少しでも多くの人に“自然を大事にしたい”と思ってもらいたいと考えています」

おはよう日本 アナウンサー
森下絵理香
2015年入局
仙台局での高砂さんの取材をきっかけにNHK潜水班でも活動。震災の痕を撮る水中撮影に同行。東北の海に向けられる思いを伝えたい
森下絵理香
2015年入局
仙台局での高砂さんの取材をきっかけにNHK潜水班でも活動。震災の痕を撮る水中撮影に同行。東北の海に向けられる思いを伝えたい