新型コロナに感染してから間もない段階で効果がある飲み薬があれば、重症者や死亡者を減らせるとして、世界各国で開発が進められてきました。
現在承認されている軽症の段階から使える飲み薬は、アメリカの製薬大手「メルク」が開発した「ラゲブリオ」と、アメリカの製薬大手「ファイザー」が開発した「パキロビッドパック」の2種類です。
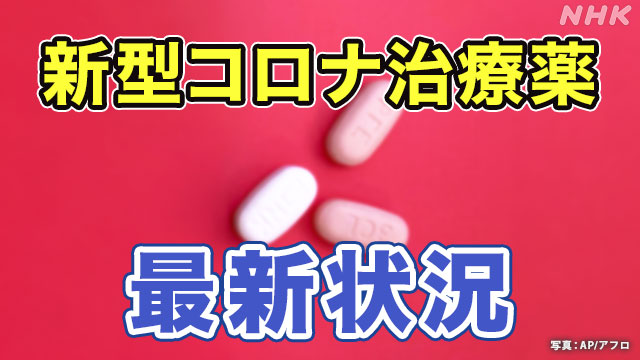
新型コロナ 国内承認の治療薬 最新状況まとめました【11/22】
新型コロナの第8波が始まったのではないか?
感染者は増加し、新たな変異ウイルスも出てきています。
そんな中22日、重症化リスクが低い患者も軽症の段階で服用できる飲み薬として、塩野義製薬の「ゾコーバ」が承認されました。
いま国内で承認されている治療薬にはどんな薬があり、どういった効果があるのか、最新の状況をまとめました。(2022年11月22日現在)
国内で承認されている新型コロナウイルスの治療薬は、2022年11月現在9種類あります。
【軽症段階で使える飲み薬】
「ラゲブリオ」

国内で初めて2021年12月24日に特例承認されたのが「ラゲブリオ」、一般名「モルヌピラビル」です。
ウイルスが細胞に侵入した後、ウイルスの設計図となる「RNA」をコピーする際に必要な酵素の働きを抑え、増殖を防ぎます。
薬の添付文書などによりますと、投与の対象となるのは、18歳以上の軽症から中等症1の患者のうち、高齢者や肥満、糖尿病などの重症化リスクがある人で、発症から5日以内に1日2回、5日間服用するとしています。
また、胎児に影響が出るおそれがあるとして、妊婦や妊娠している可能性がある女性は服用しないこととしています。
重症化リスクがある患者の入院や死亡のリスクをおよそ30%低下させる効果があるとされ、薬の服用後に有害事象が出た割合は、薬を服用したグループと偽の薬を服用したグループで変わらなかったとしています。
ウイルスが細胞に侵入した後、ウイルスの設計図となる「RNA」をコピーする際に必要な酵素の働きを抑え、増殖を防ぎます。
薬の添付文書などによりますと、投与の対象となるのは、18歳以上の軽症から中等症1の患者のうち、高齢者や肥満、糖尿病などの重症化リスクがある人で、発症から5日以内に1日2回、5日間服用するとしています。
また、胎児に影響が出るおそれがあるとして、妊婦や妊娠している可能性がある女性は服用しないこととしています。
重症化リスクがある患者の入院や死亡のリスクをおよそ30%低下させる効果があるとされ、薬の服用後に有害事象が出た割合は、薬を服用したグループと偽の薬を服用したグループで変わらなかったとしています。

厚生労働省によりますと、これまでに160万人分を確保し、2022年9月15日の時点でおよそ61万9600人に投与されているということです。
2022年9月16日からは薬の生産体制が整ったとして、一般の医薬品と同様に卸会社を通じた流通が行われています。
2022年9月16日からは薬の生産体制が整ったとして、一般の医薬品と同様に卸会社を通じた流通が行われています。
「パキロビッドパック」

ラゲブリオに続いて2022年2月10日に特例承認されたのが、アメリカの製薬大手「ファイザー」が開発した「パキロビッドパック」です。
新型コロナ向けに開発した抗ウイルス薬の「ニルマトレルビル」と、エイズの治療に使う既存の薬で抗ウイルス薬の効果を増強させる役割を担う「リトナビル」を組み合わせた薬です。
「ラゲブリオ」と同様、細胞内に侵入したウイルスの増殖を抑えるタイプの薬ですが、作用のメカニズムが異なり、ウイルスが自身のRNAをコピーして増える準備段階で働く酵素を機能しなくすることで増殖を抑えます。
会社が2021年12月に公表した臨床研究の最終的な分析結果によりますと、重症化リスクのある患者に対して発症から3日以内に投与を始めた場合には、入院や死亡のリスクが89%低下し、発症から5日以内に投与を始めた場合でも88%低下したとしています。
また、薬の服用後に有害事象が出た割合は、薬を投与した人たちと偽の薬を投与した人たちで頻度は変わらず、ほとんどが軽かったとしています。
薬の添付文書などによりますと、投与の対象は12歳以上の重症化のリスクが高い軽症から中等症1の患者で、1日2回、5日間服用するとしています。
新型コロナ向けに開発した抗ウイルス薬の「ニルマトレルビル」と、エイズの治療に使う既存の薬で抗ウイルス薬の効果を増強させる役割を担う「リトナビル」を組み合わせた薬です。
「ラゲブリオ」と同様、細胞内に侵入したウイルスの増殖を抑えるタイプの薬ですが、作用のメカニズムが異なり、ウイルスが自身のRNAをコピーして増える準備段階で働く酵素を機能しなくすることで増殖を抑えます。
会社が2021年12月に公表した臨床研究の最終的な分析結果によりますと、重症化リスクのある患者に対して発症から3日以内に投与を始めた場合には、入院や死亡のリスクが89%低下し、発症から5日以内に投与を始めた場合でも88%低下したとしています。
また、薬の服用後に有害事象が出た割合は、薬を投与した人たちと偽の薬を投与した人たちで頻度は変わらず、ほとんどが軽かったとしています。
薬の添付文書などによりますと、投与の対象は12歳以上の重症化のリスクが高い軽症から中等症1の患者で、1日2回、5日間服用するとしています。

パキロビッドパックは、一緒に飲むことが禁じられている薬がおよそ40種類あることや、腎臓の機能が低下している患者に対しても用量の調整が必要であることなどから、使用するケースが比較的少ない状態が続いています。
厚生労働省によりますと、200万人分が確保されていますが、投与されたのは2022年10月31日の時点でおよそ5万人にとどまっています。
「ラゲブリオ」と「パキロビッドパック」いずれも、ウイルスが細胞に感染する際の足がかりとなる「スパイクたんぱく質」が変異しても影響は少なく、効果は保たれると考えられています。
厚生労働省によりますと、200万人分が確保されていますが、投与されたのは2022年10月31日の時点でおよそ5万人にとどまっています。
「ラゲブリオ」と「パキロビッドパック」いずれも、ウイルスが細胞に感染する際の足がかりとなる「スパイクたんぱく質」が変異しても影響は少なく、効果は保たれると考えられています。

新型コロナの治療に詳しい愛知医科大学の森島恒雄 客員教授は「『パキロビッドパック』は一緒に飲めない薬が多いが、お薬手帳で情報を伝えてもらったり、かかりつけの医療機関で処方したりする仕組みが整えば、もっと処方できるのではないか」と話しています。
【軽症に使える抗体医薬】
新型コロナ用に開発された「抗体医薬」で、点滴や注射で投与する薬にも、軽症者に使えるものが2種類あります。
「抗体医薬」は人工的に作った抗体を投与するタイプの薬で、抗体が新型コロナウイルスの表面にある突起の部分「スパイクたんぱく質」に結合することで、ウイルスが細胞に侵入するのを阻止します。
「抗体医薬」は人工的に作った抗体を投与するタイプの薬で、抗体が新型コロナウイルスの表面にある突起の部分「スパイクたんぱく質」に結合することで、ウイルスが細胞に侵入するのを阻止します。
抗体カクテル療法「ロナプリーブ」

軽症患者向けに使える初めての薬として2021年7月に特例承認されたのが、2種類の抗体を投与する抗体カクテル療法の薬「ロナプリーブ」です。
点滴や注射で投与します。
点滴や注射で投与します。
「ソトロビマブ」

また、2021年9月には1種類の抗体を投与する「ソトロビマブ」、販売名「ゼビュディ」が特例承認されました。
点滴で投与します。
いずれも、高齢者や基礎疾患のある人など重症化するリスクがある軽症から中等症1までの患者が投与の対象で、薬の添付文書などによりますと「ロナプリーブ」は発症から7日以内に「ソトロビマブ」は発症から5日以内に1回投与します。
「ロナプリーブ」は臨床試験で、投与していない人に比べて入院や死亡のリスクがおよそ70%下げられたということです。
また、免疫力が低下し重症化するリスクがある濃厚接触者に対しては、発症予防を目的に投与することも承認されています。
厚生労働省によりますと、投与された人数は2022年10月31日の時点でおよそ4万3000人にのぼるということです。
また「ソトロビマブ」は臨床試験で、投与していない人に比べて入院や死亡のリスクがおよそ85%下げられたということです。
厚生労働省によりますと、投与された人数は2022年10月31日の時点で18万人余りにのぼるということです。
ただ、これらの抗体医薬はウイルスが変異することで「スパイクたんぱく質」の形が変わってしまうと結合しにくくなり、効果が下がってしまうという弱点があります。
特にオミクロン株に対しては、従来株と比べて効果が著しく低下したという報告が相次ぎ、厚生労働省の新型コロナの「診療の手引き」では、オミクロン株に対して「有効性が下がるおそれがあることから、ほかの治療薬が使用できない場合に使用を検討する」としています。
点滴で投与します。
いずれも、高齢者や基礎疾患のある人など重症化するリスクがある軽症から中等症1までの患者が投与の対象で、薬の添付文書などによりますと「ロナプリーブ」は発症から7日以内に「ソトロビマブ」は発症から5日以内に1回投与します。
「ロナプリーブ」は臨床試験で、投与していない人に比べて入院や死亡のリスクがおよそ70%下げられたということです。
また、免疫力が低下し重症化するリスクがある濃厚接触者に対しては、発症予防を目的に投与することも承認されています。
厚生労働省によりますと、投与された人数は2022年10月31日の時点でおよそ4万3000人にのぼるということです。
また「ソトロビマブ」は臨床試験で、投与していない人に比べて入院や死亡のリスクがおよそ85%下げられたということです。
厚生労働省によりますと、投与された人数は2022年10月31日の時点で18万人余りにのぼるということです。
ただ、これらの抗体医薬はウイルスが変異することで「スパイクたんぱく質」の形が変わってしまうと結合しにくくなり、効果が下がってしまうという弱点があります。
特にオミクロン株に対しては、従来株と比べて効果が著しく低下したという報告が相次ぎ、厚生労働省の新型コロナの「診療の手引き」では、オミクロン株に対して「有効性が下がるおそれがあることから、ほかの治療薬が使用できない場合に使用を検討する」としています。
【発症抑制に使える薬も】
抗体医薬の中には、感染する前に投与して発症を抑える目的で使えるものがあります。
「エバシェルド」

イギリスの製薬大手「アストラゼネカ」が開発した抗体医薬「エバシェルド」は、免疫の働きが低下していてワクチンを打っても効果が出ない人たちの発症抑制に使えるとして、2022年8月に特例承認されました。
この薬は、2種類の抗体を注射で投与します。
添付文書などによりますと、ワクチンの効果が不十分と考えられる人などおよそ5200人を対象に行った治験で、感染する前に投与すると発症リスクが77%抑えられ、効果は半年間続いたとしています。
また、感染した軽症から中等症のハイリスクの患者に投与することで、重症化や死亡のリスクを50%減らす効果がみられたとしています。
この薬は安定供給が難しいことから、厚生労働省は発症予防の目的で使う場合のみ、無償で配分しています。
一方で、オミクロン株に対しては「有効性が下がるおそれがあることから、ほかの治療薬が使用できない場合に使用を検討する」としています。
この薬は、2種類の抗体を注射で投与します。
添付文書などによりますと、ワクチンの効果が不十分と考えられる人などおよそ5200人を対象に行った治験で、感染する前に投与すると発症リスクが77%抑えられ、効果は半年間続いたとしています。
また、感染した軽症から中等症のハイリスクの患者に投与することで、重症化や死亡のリスクを50%減らす効果がみられたとしています。
この薬は安定供給が難しいことから、厚生労働省は発症予防の目的で使う場合のみ、無償で配分しています。
一方で、オミクロン株に対しては「有効性が下がるおそれがあることから、ほかの治療薬が使用できない場合に使用を検討する」としています。
【別の病気で開発の治療薬で軽症対象も】
「レムデシビル」

別の病気の治療薬として開発され、新型コロナへの効果もあるとして使われている薬もあり、その中には軽症の段階から使えるようになったものもあります。
もともとエボラ出血熱の治療薬として開発されていた点滴の抗ウイルス薬「レムデシビル」は、2020年5月、新型コロナの治療薬として初めて特例承認されました。
新型コロナの中等症1から重症の入院患者に使用されてきましたが、厚生労働省は2022年3月、重症化リスクのある軽症や中等症の患者に対しても適応を拡大しました。
もともとエボラ出血熱の治療薬として開発されていた点滴の抗ウイルス薬「レムデシビル」は、2020年5月、新型コロナの治療薬として初めて特例承認されました。
新型コロナの中等症1から重症の入院患者に使用されてきましたが、厚生労働省は2022年3月、重症化リスクのある軽症や中等症の患者に対しても適応を拡大しました。
【中等症以上の患者用の薬】
肺炎を起こして酸素投与が必要になった中等症2や、さらに症状が重くなった重症の患者には、体のさまざまな部位の炎症を抑える目的で免疫の過剰な働きを抑えるタイプの薬が使われます。
「デキサメタゾン」

免疫の過剰な働きを抑えるステロイド剤の「デキサメタゾン」は、2020年7月に厚生労働省が新型コロナの治療薬として推奨しました。
もともと重度の肺炎やリウマチなどの治療に使われてきた薬で、錠剤の飲み薬と点滴薬、それに注射薬があり、中等症2や重症の患者に投与されます。
もともと重度の肺炎やリウマチなどの治療に使われてきた薬で、錠剤の飲み薬と点滴薬、それに注射薬があり、中等症2や重症の患者に投与されます。
「バリシチニブ」

2021年4月に承認された「バリシチニブ」も免疫の過剰な働きを抑える薬で、中等症2以上の患者に投与されます。
もともとは、関節リウマチなどの患者に使われてきた錠剤の飲み薬で、国内ではレムデシビルと併用する場合に限られています。
もともとは、関節リウマチなどの患者に使われてきた錠剤の飲み薬で、国内ではレムデシビルと併用する場合に限られています。
「アクテムラ」

日本の製薬会社「中外製薬」などが開発した、関節リウマチの薬「アクテムラ」、一般名「トシリズマブ」も2022年1月に新型コロナの治療薬として承認されました。
点滴で過剰な免疫の働きを抑える薬で、酸素投与が必要になった中等症2以上の患者に対しステロイド剤と併用して投与するとしています。
点滴で過剰な免疫の働きを抑える薬で、酸素投与が必要になった中等症2以上の患者に対しステロイド剤と併用して投与するとしています。