カブトムシが廃棄物を減らす?双子の兄弟の挑戦

育てたカブトムシが死んでしまう。
でもそんな数々の失敗が今につながっています。
カブトムシの力でゴミを資源化するビジネス。
双子の兄弟が立ち上げたスタートアップ企業が目指すのは食料不足の解消です。
(社会部記者 黄在龍)
でもそんな数々の失敗が今につながっています。
カブトムシの力でゴミを資源化するビジネス。
双子の兄弟が立ち上げたスタートアップ企業が目指すのは食料不足の解消です。
(社会部記者 黄在龍)
カブトムシ6万匹を飼育
カブトムシを活用した事業を行う「(株)TOMUSHI」。
「かぶ・とむし」と読めます。
秋田県大館市にあるこのスタートアップ企業を立ち上げたのは、石田健佑さん(25)と陽佑さん(25)。
双子の兄弟です。
手がけるのは廃棄物の処理にカブトムシを活用し、それを販売などにつなげる循環型の事業。
「かぶ・とむし」と読めます。
秋田県大館市にあるこのスタートアップ企業を立ち上げたのは、石田健佑さん(25)と陽佑さん(25)。
双子の兄弟です。
手がけるのは廃棄物の処理にカブトムシを活用し、それを販売などにつなげる循環型の事業。

飼育しているカブトムシは、世界最大級の「ヘラクレスオオカブト」など6万匹に上ります。
東京で起業も失敗 出身地へ
秋田県大館市で生まれた健佑さんと陽佑さん。

2人が最初に起業したのは5年前、20歳のときでした。
当時、兄の健佑さんは高校卒業後に東京で就職していて、弟の陽佑さんは大学生でした。
仲間とともに東京でIT系のベンチャー企業を立ち上げましたが、半年ほどで経営は行き詰まります。
当時、兄の健佑さんは高校卒業後に東京で就職していて、弟の陽佑さんは大学生でした。
仲間とともに東京でIT系のベンチャー企業を立ち上げましたが、半年ほどで経営は行き詰まります。

当時について2人は次のように振り返ります。
「競合他社がひしめくところに参入したんですが、自分が好きなことをやるのではなく、お金を稼げるかどうかを優先してやっていたので、どうしても熱意が取引先などに伝わらなかった。事業に思い入れがないから仕事をしていてもどこか楽しくなかったですし、あっという間に飲み込まれてしまいました」
そのころ祖父が体調を崩したこともあり、2人は田舎に帰って祖父母と同居することを決めました。
祖父母の支援で“趣味”を事業化
秋田に戻っても仕事に就かず、ダラダラとした生活を送っていたある日。
子どもの頃に熱中していたカブトムシを捕りに行きました。
でも山に入っても昔のようには捕れません。
「悔しいから自分たちで飼育しよう」
「せっかくだから憧れのヘラクレスオオカブトを育てたい」
そんな2人の趣味として飼い始めたカブトムシが事業化のきっかけになりました。
子どもの頃に熱中していたカブトムシを捕りに行きました。
でも山に入っても昔のようには捕れません。
「悔しいから自分たちで飼育しよう」
「せっかくだから憧れのヘラクレスオオカブトを育てたい」
そんな2人の趣味として飼い始めたカブトムシが事業化のきっかけになりました。
弟の陽佑さん
「育てた成虫の写真をネットにアップしていたら、『すごい立派ですね』とか『どこで買えますか?』と反応があったので、それを販売して売り上げたお金でまた飼育するという単純な事業を始めたんです」
「育てた成虫の写真をネットにアップしていたら、『すごい立派ですね』とか『どこで買えますか?』と反応があったので、それを販売して売り上げたお金でまた飼育するという単純な事業を始めたんです」
2人を応援してくれたのは祖父母でした。

「もっといろんな種類のカブトムシを育てたい」と飼育にのめり込んだ2人は事業を拡大するため、祖父母に300万円を貸してほしいと頼み込みます。
最初は断られたものの毎日のように思いを伝え続けると、その熱意に根負けするように出資してくれました。
当時は住宅の1部屋を飼育部屋にしていましたが、祖父母から「家の中に大量のカブトムシがいるのは気持ち悪いし、どうせやるなら思いっきりやってほしい」と言われ、農作業小屋のリフォーム費用などさらに100万円を出してくれました。
最初は断られたものの毎日のように思いを伝え続けると、その熱意に根負けするように出資してくれました。
当時は住宅の1部屋を飼育部屋にしていましたが、祖父母から「家の中に大量のカブトムシがいるのは気持ち悪いし、どうせやるなら思いっきりやってほしい」と言われ、農作業小屋のリフォーム費用などさらに100万円を出してくれました。
祖母のアツ子さん
「最初はカブトムシを何万円も出して誰が買うのって思っていました。でも2人が夜中の3時、4時まで明かりをつけて作業している姿を見たら、本気なんだって信用しました。援助したお金はことしの夏から返してくれていて、『全部返すまで長生きしてね』と言われています」
「最初はカブトムシを何万円も出して誰が買うのって思っていました。でも2人が夜中の3時、4時まで明かりをつけて作業している姿を見たら、本気なんだって信用しました。援助したお金はことしの夏から返してくれていて、『全部返すまで長生きしてね』と言われています」
転機となったトラブル
カブトムシを育てて販売する事業を始めた2人の転機となったのは、あるトラブルでした。
幼虫に食べさせるエサを小ばえなどの雑虫に食べられてしまったのです。
自然の中にいるカブトムシの幼虫は腐葉土や朽ち木を食べて育ちますが、飼育する場合は「マット」と呼ばれる広葉樹などを粉砕して粉状にしたものが必要です。
雑虫のトラブルで「マット」を何度も買い直すことになり、経費がかさんでしまいました。
そんなとき地域の農家からこう声をかけられたといいます。
「農業で出る残りかすを活用できない?」
幼虫に食べさせるエサを小ばえなどの雑虫に食べられてしまったのです。
自然の中にいるカブトムシの幼虫は腐葉土や朽ち木を食べて育ちますが、飼育する場合は「マット」と呼ばれる広葉樹などを粉砕して粉状にしたものが必要です。
雑虫のトラブルで「マット」を何度も買い直すことになり、経費がかさんでしまいました。
そんなとき地域の農家からこう声をかけられたといいます。
「農業で出る残りかすを活用できない?」

弟の陽佑さん
「ずっと家にいてニートのような生活をしていたんですが、少しは外に出てみろと言われて農家の人たちを紹介してもらいました。エサのことを相談したら応援してくれる人がたくさんいて、農業ざんさをカブトムシのエサにできるんじゃないかってアドバイスを頂いたんです」
「ずっと家にいてニートのような生活をしていたんですが、少しは外に出てみろと言われて農家の人たちを紹介してもらいました。エサのことを相談したら応援してくれる人がたくさんいて、農業ざんさをカブトムシのエサにできるんじゃないかってアドバイスを頂いたんです」
その1つがシイタケ農家が処分に困っていた「廃菌床」(収穫を終えたあとの菌床)でした。

「廃菌床」の処分について、宮城県内でシイタケ栽培を手がけている後藤さんは次のように話します。

ほっとファーム 後藤亮一さん
「年間およそ50~80トンのシイタケを生産するのに対し、20~50トンの廃菌床が出ます。それを処分するには数十万円から100万円の費用がかかるんです。ほかの農家に引き取ってもらうこともありましたが、引き取り先を探すのも大変でしたし、とにかく処分に困っていたので助かりました」
「年間およそ50~80トンのシイタケを生産するのに対し、20~50トンの廃菌床が出ます。それを処分するには数十万円から100万円の費用がかかるんです。ほかの農家に引き取ってもらうこともありましたが、引き取り先を探すのも大変でしたし、とにかく処分に困っていたので助かりました」
有機廃棄物をカブトムシのエサに
2人が立ち上げたスタートアップ企業「トムシ」のビジネスモデルです。
・キノコ農家から廃棄物のサンプルを受け取り、エサへの加工方法を研究。
・農家の近くにカブトムシを飼育するためのプラントを建設し、カブトムシを提供。
・農家はノウハウの提供とサポートを受けて、廃棄物をエサに加工し、カブトムシを育てる。
・成虫になったカブトムシは「トムシ」が買い取り、ECサイトで数千円から3万円で販売。
・農家の近くにカブトムシを飼育するためのプラントを建設し、カブトムシを提供。
・農家はノウハウの提供とサポートを受けて、廃棄物をエサに加工し、カブトムシを育てる。
・成虫になったカブトムシは「トムシ」が買い取り、ECサイトで数千円から3万円で販売。
カブトムシの販売や農家へのコンサルタント料で今年度の売り上げは1億8000万円になる見込みです。
ただビジネスとして成立するまでには、多くの失敗がありました。
当初は有機廃棄物をエサに変えるノウハウはなかったためすべて手探りで、ひたすら“トライアンドエラー”を繰り返したといいます。
ただビジネスとして成立するまでには、多くの失敗がありました。
当初は有機廃棄物をエサに変えるノウハウはなかったためすべて手探りで、ひたすら“トライアンドエラー”を繰り返したといいます。
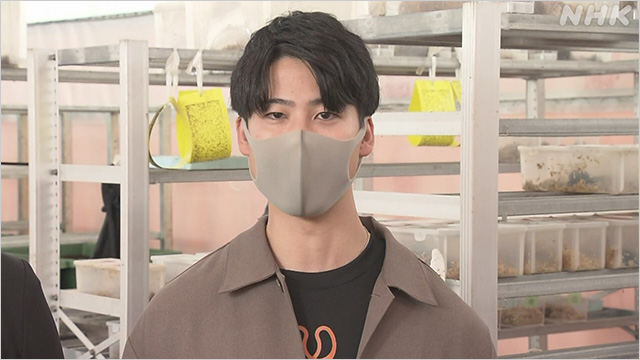
兄の健祐さん
「複数の廃棄物や発酵を促進させる菌、栄養素などを混ぜます。その配合をどうするのか、温度や時間によっても結果が大きく変わります。最初は実験してデータを取り、また実験するという研究だけで何の成果も出ませんでした。トライアンドエラーを繰り返してカブトムシを死なせてしまいました」
「複数の廃棄物や発酵を促進させる菌、栄養素などを混ぜます。その配合をどうするのか、温度や時間によっても結果が大きく変わります。最初は実験してデータを取り、また実験するという研究だけで何の成果も出ませんでした。トライアンドエラーを繰り返してカブトムシを死なせてしまいました」
弟の陽佑さん
「僕たちが大好きなカブトムシが廃棄物の問題を解決したらどれだけおもしろいかという思いで続けていましたが、やっぱり死んでしまったカブトムシを見ると本当に心が苦しかったです」
「僕たちが大好きなカブトムシが廃棄物の問題を解決したらどれだけおもしろいかという思いで続けていましたが、やっぱり死んでしまったカブトムシを見ると本当に心が苦しかったです」

研究を続けて2年。
少しずつ廃棄物を加工したエサを食べても生き残るカブトムシが出てきました。
しかも一般に販売されている「マット」を使うより成長スピードが速く、大きく育ちます。
・廃菌床の加工によってカブトムシが速く大きく育つエサを作る。
・カブトムシの交配を重ねて加工したエサをよく食べる個体を作る。
この2つのアプローチによって成長スピードを通常より4倍速くすることに成功しました。
少しずつ廃棄物を加工したエサを食べても生き残るカブトムシが出てきました。
しかも一般に販売されている「マット」を使うより成長スピードが速く、大きく育ちます。
・廃菌床の加工によってカブトムシが速く大きく育つエサを作る。
・カブトムシの交配を重ねて加工したエサをよく食べる個体を作る。
この2つのアプローチによって成長スピードを通常より4倍速くすることに成功しました。
兄の健佑さん
「実験を繰り返したことでようやくこの種類とこの種類のカブトムシは、こう加工した廃棄物のエサなら大きく育てられるということがわかってきました。ちゃんと成虫として育ったときにはものすごく感動しました」
「実験を繰り返したことでようやくこの種類とこの種類のカブトムシは、こう加工した廃棄物のエサなら大きく育てられるということがわかってきました。ちゃんと成虫として育ったときにはものすごく感動しました」

現在、会社で処理できる廃棄物は年間およそ100トンですが、各地からさまざまな廃棄物を活用できないかと連絡が来るといいます。
「廃菌床」のほかにも畜産のふん尿やブドウの絞りかす、廃棄されるサトウキビなど。
現在はおよそ30の事業者と契約を結び、加工に取り組んでいます。
「廃菌床」のほかにも畜産のふん尿やブドウの絞りかす、廃棄されるサトウキビなど。
現在はおよそ30の事業者と契約を結び、加工に取り組んでいます。
食品ロスの活用 企業と連携
「食品ロス」の活用も模索しています。
すでに企業との連携も始まっていて、そのうちの1つがJR東日本グループです。
駅ビルの飲食店やコンビニから出た食品廃棄物などを「再生可能エネルギー」として活用しているほか、リンゴのお酒の醸造工程で出る搾りかすから「高濃度アルコール」を精製する取り組みを進めていますが、まだ活用できていない部分をカブトムシの力で解決できないかと考えています。
さらに廃棄物で育てたカブトムシを駅の施設で展示・販売することも検討しているということです。
すでに企業との連携も始まっていて、そのうちの1つがJR東日本グループです。
駅ビルの飲食店やコンビニから出た食品廃棄物などを「再生可能エネルギー」として活用しているほか、リンゴのお酒の醸造工程で出る搾りかすから「高濃度アルコール」を精製する取り組みを進めていますが、まだ活用できていない部分をカブトムシの力で解決できないかと考えています。
さらに廃棄物で育てたカブトムシを駅の施設で展示・販売することも検討しているということです。

JR東日本スタートアップ 古川詩乃さん
「実際に出た食品廃棄物を微生物の力でエネルギー化するバイオマス発電なども行っているんですが、それでも出る残りかすなどを『トムシ』さんの力でゼロにできるような取り組みが一緒にできたらいいなと」
「実際に出た食品廃棄物を微生物の力でエネルギー化するバイオマス発電なども行っているんですが、それでも出る残りかすなどを『トムシ』さんの力でゼロにできるような取り組みが一緒にできたらいいなと」
「数字としての目標よりも廃棄物、無価値だったものを価値のあるものに変えていくことをスモールスタートでも始めて、駅から出たゴミを使って育てたカブトムシを駅で販売するという循環型の取り組みをグループ内でできたら素敵だと思います」
新たな挑戦 “食料不足の解消”
健佑さんと陽佑さんたちが新たな目標として挑戦しているのが、廃棄物をエサにして育てたカブトムシ自体をタンパク源にすることです。
カブトムシを昆虫食として食品化するもので、弘前大学などと共同で研究を行っています。
国連の推計によると世界の人口は2030年までにおよそ85億人に達すると予測され、牛肉や豚肉などのタンパク質の供給が足りなくなるのではないかと指摘されているため、こうした対策にも生かしたいと考えているのです。
カブトムシを昆虫食として食品化するもので、弘前大学などと共同で研究を行っています。
国連の推計によると世界の人口は2030年までにおよそ85億人に達すると予測され、牛肉や豚肉などのタンパク質の供給が足りなくなるのではないかと指摘されているため、こうした対策にも生かしたいと考えているのです。

将来的にはカブトムシを大量に育てるためにファームを全国展開し、自動化やシステム化によってさらにコストを下げていくことにしています。
兄の健佑さん
「廃棄物で困ったら『トムシ』に相談しようという受け皿になり、効率の一番いい方法で処理するソリューションを提供できる企業になれたらと思います。そして子どもたちがカブトムシを見たときに、ただかっこいいだけでなく世の中の役に立っているんだと思ってもらえるよう、自分たちもカブトムシとともに成長してきたいと考えています」
「廃棄物で困ったら『トムシ』に相談しようという受け皿になり、効率の一番いい方法で処理するソリューションを提供できる企業になれたらと思います。そして子どもたちがカブトムシを見たときに、ただかっこいいだけでなく世の中の役に立っているんだと思ってもらえるよう、自分たちもカブトムシとともに成長してきたいと考えています」
取材後記
カブトムシを安定して繁殖させる技術やノウハウを確立させ、飼育数は2023年春にはおよそ8万匹、2024年春には15万匹まで増やせる見通しです。
一方で食品化にあたっては、コストやカブトムシのにおいをどう抑えるのかなど課題も多くあります。
「なぜ難しい挑戦をするんですか」と尋ねると、陽佑さんはこう答えました。
「事業を始めた当初、『所詮ペットだろ。社会に貢献していない』と言われて悔しい思いをしました。カブトムシでも社会に貢献できるということを証明したいんです」
彼らの原動力はこのカブトムシへの偏愛とも言える愛情、そして探究心と行動力です。
好きなことを仕事にしていてうらやましいと感じつつ、一歩ずつでも課題解決につなげていってほしいと期待せずにはいられませんでした。
一方で食品化にあたっては、コストやカブトムシのにおいをどう抑えるのかなど課題も多くあります。
「なぜ難しい挑戦をするんですか」と尋ねると、陽佑さんはこう答えました。
「事業を始めた当初、『所詮ペットだろ。社会に貢献していない』と言われて悔しい思いをしました。カブトムシでも社会に貢献できるということを証明したいんです」
彼らの原動力はこのカブトムシへの偏愛とも言える愛情、そして探究心と行動力です。
好きなことを仕事にしていてうらやましいと感じつつ、一歩ずつでも課題解決につなげていってほしいと期待せずにはいられませんでした。


社会部記者
黄 在龍
新潟局・福岡局を経て現所属
去年、息子とカブトムシを捕まえて感動しました
黄 在龍
新潟局・福岡局を経て現所属
去年、息子とカブトムシを捕まえて感動しました