原発の新増設検討も 方針転換の理由は?

政府は、8月24日、来年夏以降に原発7基の再稼働を追加で目指す方針を明らかにしました。これまで「想定していない」としてきた原発の新増設についても方針を転換し、次世代原子炉の開発・建設を検討する考えです。政府がここにきて原発政策を前に進めようとしているのはなぜなのでしょうか。(経済部記者 五十嵐圭祐)
再稼働目指す原発7基とは?

8月24日のGX=グリーントランスフォーメーション実行会議で政府が示したのは、まず、原子力規制委員会の審査に合格しているものの、再稼働できていない原発7基について、来年夏以降に再稼働を目指すという方針です。
対象となるのは、以下の7基の原発です。
対象となるのは、以下の7基の原発です。

▽福井県にある関西電力高浜原発の1号機と2号機
▽宮城県にある東北電力女川原発2号機
▽島根県にある中国電力島根原発2号機
▽新潟県にある東京電力柏崎刈羽原発の6号機と7号機
▽茨城県にある日本原子力発電の東海第二原発
このうち、女川2号機と高浜1、2号機、それに島根2号機の合わせて4基は、これまでに地元の合意を得ています。
一方、柏崎刈羽の6、7号機と東海第二原発については「地元理解に向けて国が全面に立って対応する」としています。
▽宮城県にある東北電力女川原発2号機
▽島根県にある中国電力島根原発2号機
▽新潟県にある東京電力柏崎刈羽原発の6号機と7号機
▽茨城県にある日本原子力発電の東海第二原発
このうち、女川2号機と高浜1、2号機、それに島根2号機の合わせて4基は、これまでに地元の合意を得ています。
一方、柏崎刈羽の6、7号機と東海第二原発については「地元理解に向けて国が全面に立って対応する」としています。

国内に36基(廃炉が決まっている原発を除く)ある原発のうち、福島の事故のあと新たな基準に基づいて再稼働した実績があるのは10基。
定期点検中の原発やテロ対策施設の完成が遅れている原発もあり、9月5日の時点で実際に稼働しているのはこのうちの6基となっています。
政府はことし7月、電力の需給ひっ迫が予想されるこの冬までに最大で9基の原発の稼働を進める考えを示していました。
来年の夏以降は、こうした再稼働の実績がある原発10基に7基が加わることになります。
政府はさらに、原発の運転期間の延長も検討する方針です。
定期点検中の原発やテロ対策施設の完成が遅れている原発もあり、9月5日の時点で実際に稼働しているのはこのうちの6基となっています。
政府はことし7月、電力の需給ひっ迫が予想されるこの冬までに最大で9基の原発の稼働を進める考えを示していました。
来年の夏以降は、こうした再稼働の実績がある原発10基に7基が加わることになります。
政府はさらに、原発の運転期間の延長も検討する方針です。

福島の事故以降、原発の運転期間は原子炉等規制法で40年までと規定され、原子力規制委員会の認可を受ければ1回にかぎり最長で20年の延長、つまり60年まで運転できると定められています。
一方で、新しい規制基準のもとで審査が長期化し、中には10年以上稼働できないままになっている原発もあります。
こうした稼働していない期間の扱いについても議論を深めたいとしています。
政府は、去年10月に閣議決定したエネルギー基本計画で、2030年度の原発の電源構成比率を「20%から22%」としています。
ただ、これを実現するには20基以上の稼働が必要な計算になります。
発電全体に占める原発の割合は2020年度は、3.9%となっています。
一方で、新しい規制基準のもとで審査が長期化し、中には10年以上稼働できないままになっている原発もあります。
こうした稼働していない期間の扱いについても議論を深めたいとしています。
政府は、去年10月に閣議決定したエネルギー基本計画で、2030年度の原発の電源構成比率を「20%から22%」としています。
ただ、これを実現するには20基以上の稼働が必要な計算になります。
発電全体に占める原発の割合は2020年度は、3.9%となっています。
なぜ 追加の再稼働目指す?
政府がこのタイミングで原発政策を前に進めようとしているのはなぜなのか。
背景には、日本の深刻な電力需給の状況があります。
福島の事故以降、日本の電力は火力発電に依存してきました。
一方で、電力の自由化や再生可能エネルギーの拡大によって、採算が悪い老朽化した火力発電所の休止や廃止が相次ぎ、火力発電の供給力は低下しています。
背景には、日本の深刻な電力需給の状況があります。
福島の事故以降、日本の電力は火力発電に依存してきました。
一方で、電力の自由化や再生可能エネルギーの拡大によって、採算が悪い老朽化した火力発電所の休止や廃止が相次ぎ、火力発電の供給力は低下しています。

この夏は6月から記録的な暑さが連日続き、電力の需要が急増。
政府は全国で7年ぶりに節電要請を行い、無理のない範囲で節電への協力を呼びかけています。
老朽化して廃止も見込まれていた火力発電所を国の指示によって再稼働させ、必要な供給力をなんとか確保している綱渡りの状況です。
政府は全国で7年ぶりに節電要請を行い、無理のない範囲で節電への協力を呼びかけています。
老朽化して廃止も見込まれていた火力発電所を国の指示によって再稼働させ、必要な供給力をなんとか確保している綱渡りの状況です。
特にことしの冬はさらに厳しい電力需給が見込まれていて、ひっ迫した状況が常態化するおそれもあります。
経済産業省の幹部は、「夏と冬のたびに停電の心配をしなければならない途上国のような状態だ」と話していました。
こうした中で懸念されるのはロシアによるウクライナへの侵攻の長期化です。
資源大国ロシアは、世界最大の天然ガス輸出国です。
このロシアが今、制裁を強める欧米各国や日本に対し、エネルギーを武器に対抗措置を次々に講じています。
ロシアが天然ガスの供給を絞ったことで世界はエネルギーの争奪戦に突入し、天然ガスの価格は跳ね上がりました。
経済産業省の幹部は、「夏と冬のたびに停電の心配をしなければならない途上国のような状態だ」と話していました。
こうした中で懸念されるのはロシアによるウクライナへの侵攻の長期化です。
資源大国ロシアは、世界最大の天然ガス輸出国です。
このロシアが今、制裁を強める欧米各国や日本に対し、エネルギーを武器に対抗措置を次々に講じています。
ロシアが天然ガスの供給を絞ったことで世界はエネルギーの争奪戦に突入し、天然ガスの価格は跳ね上がりました。

日本にとっても、天然ガスの調達先であるロシア極東の開発プロジェクト「サハリン2」をめぐって、ロシアが揺さぶりをかけてきています。
エネルギー資源のほとんどを輸入に頼る日本は、このように、他国の思惑によってエネルギーの安定供給が脅かされるという危機に直面しています。
エネルギー資源のほとんどを輸入に頼る日本は、このように、他国の思惑によってエネルギーの安定供給が脅かされるという危機に直面しています。
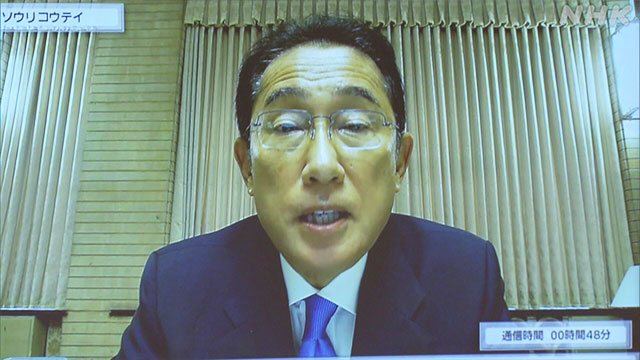
岸田総理大臣は、8月24日のGX実行会議で、「ロシアによるウクライナ侵略でエネルギーの需給構造に大きな地殻変動が起こっている中、電力需給ひっ迫という足元の危機克服のため、今後数年間を見据え、あらゆる政策を総動員して不測の事態に備えていく」と述べました。
政府は、可能なかぎり原発依存度を低減するという方針は変わらないとしていますが、電力をめぐる危機的な状況を乗り切るため、そして脱炭素に向けた取り組みを進めるためにも原発の活用が不可欠だとしています。
政府は、可能なかぎり原発依存度を低減するという方針は変わらないとしていますが、電力をめぐる危機的な状況を乗り切るため、そして脱炭素に向けた取り組みを進めるためにも原発の活用が不可欠だとしています。
新増設の検討も そのわけは?
そしてもう1つ注目されるのが、次世代原子炉の開発・建設を検討すると表明したことです。
政府は福島の事故以降、一貫して、「原発の新増設は想定していない」と説明してきました。
それだけに今回、新増設を検討することについては、「唐突感が拭えない」などという声もあがっています。
政府が足元で原発の再稼働を進めることに加えて、次世代原子炉の開発・建設の検討にまで踏み込んだのはなぜなのか。
そこには原子力産業の見通しが立たず、縮小が続いていることへの危機感がありました。
政府は福島の事故以降、一貫して、「原発の新増設は想定していない」と説明してきました。
それだけに今回、新増設を検討することについては、「唐突感が拭えない」などという声もあがっています。
政府が足元で原発の再稼働を進めることに加えて、次世代原子炉の開発・建設の検討にまで踏み込んだのはなぜなのか。
そこには原子力産業の見通しが立たず、縮小が続いていることへの危機感がありました。
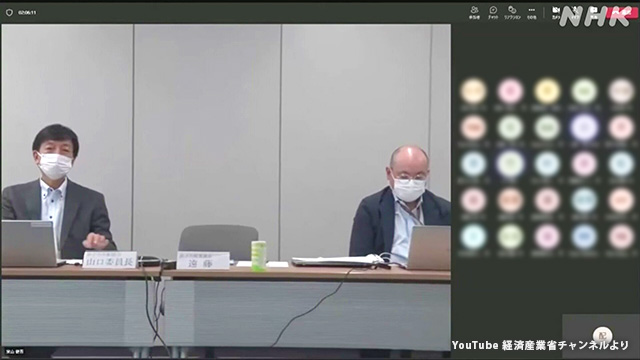
経済産業省は8月25日に開かれた「総合資源エネルギー調査会」の「原子力小委員会」で中間論点整理の案を示し、この中で「短中期の判断の積み重ねだけでは、原子力に携わる多くのステークホルダー(利害のある関係者)にとって、持続的活用の見通しは確かなものとならないのではないか」と指摘しています。
さらに「多くの企業などが中長期的な事業の予見性をもてないまま、将来を見据えた設備投資や人材投資に踏み切れない状況が続き、将来の選択としての原子力は危機にひんしているのではないか」としています。
日本電機工業会によると、原子力産業の従事者は2011年度で1万3582人でしたが、震災後は減少傾向が続き、2020年度は約1万153人と25%減っています。
経済産業省の担当者は、「このまま原発の新増設が行われなければ、原発産業への投資が縮小し、人材が流出することは避けられない。原発を将来のエネルギーの選択肢として残すためにも原発新増設に向けた検討が必要だ」と話していました。
さらに「多くの企業などが中長期的な事業の予見性をもてないまま、将来を見据えた設備投資や人材投資に踏み切れない状況が続き、将来の選択としての原子力は危機にひんしているのではないか」としています。
日本電機工業会によると、原子力産業の従事者は2011年度で1万3582人でしたが、震災後は減少傾向が続き、2020年度は約1万153人と25%減っています。
経済産業省の担当者は、「このまま原発の新増設が行われなければ、原発産業への投資が縮小し、人材が流出することは避けられない。原発を将来のエネルギーの選択肢として残すためにも原発新増設に向けた検討が必要だ」と話していました。
原発政策を進める上での課題は
日本のエネルギー政策にとって大きな節目ともいえる今回の政府の発表。

ただ、甚大な被害をもたらした福島の事故の痛手はいまなお日本社会に重くのしかかっています。
廃炉や処理水をめぐる対応、そして地元の復興に向けても課題が山積しています。
さらに、原発政策をめぐっては高レベル放射性廃棄物の最終処分地が、いまだ決まっていないという問題もあります。
政府は原発の新増設などの具体的な方向性については年内をめどにまとめるとしていますが、福島の教訓や課題に向き合いながら、国民に対して丁寧に説明することが求められます。
廃炉や処理水をめぐる対応、そして地元の復興に向けても課題が山積しています。
さらに、原発政策をめぐっては高レベル放射性廃棄物の最終処分地が、いまだ決まっていないという問題もあります。
政府は原発の新増設などの具体的な方向性については年内をめどにまとめるとしていますが、福島の教訓や課題に向き合いながら、国民に対して丁寧に説明することが求められます。

経済部記者
五十嵐圭祐
平成24年入局
横浜局、秋田局、札幌局を経て経済部
現在、エネルギー業界を担当
五十嵐圭祐
平成24年入局
横浜局、秋田局、札幌局を経て経済部
現在、エネルギー業界を担当