コオロギに熱視線!進化する昆虫食

「“昆虫=うわっ”となる印象を変えたい」
この夏、企業の間で取り組みが広がっています。たんぱく質が豊富で栄養価が高い食材として知られる昆虫食。この「コオロギ」をそのまま食べると思い込んでいませんか?(経済部記者 佐野裕美江)
この夏、企業の間で取り組みが広がっています。たんぱく質が豊富で栄養価が高い食材として知られる昆虫食。この「コオロギ」をそのまま食べると思い込んでいませんか?(経済部記者 佐野裕美江)
コオロギに熱い視線!
まず訪れたのは、東京都内で子どもたちに大人気の職業体験テーマパーク「キッザニア」。

夏休み中の子どもたちが体験していたのは「コオロギパウダー」を使ったポップコーンづくり。
茶色っぽいパウダーがコオロギから作られたもの。コオロギの形はまるでありません。
茶色っぽいパウダーがコオロギから作られたもの。コオロギの形はまるでありません。

出来たてのポップコーンが入った紙袋に、オリーブオイルとコオロギパウダー、塩を入れて、シャカシャカ振って完成です。
そのお味は…。
そのお味は…。

小学2年生 男の子
「なんか…ふつうのポップコーン。コオロギっていう味はしない!でも僕の好きな塩のポップコーンとはちょっと違う」
小学4年生 女の子
「映画館にある塩のポップコーンと同じくらいおいしいけど、ちょっと香りが違う。コーヒーみたいな感じ」
「なんか…ふつうのポップコーン。コオロギっていう味はしない!でも僕の好きな塩のポップコーンとはちょっと違う」
小学4年生 女の子
「映画館にある塩のポップコーンと同じくらいおいしいけど、ちょっと香りが違う。コーヒーみたいな感じ」
実は栄養満点 たんぱく質は牛肉や鶏肉の3倍以上
では、昆虫はたくさん種類がいる中でなぜ、コオロギなのでしょうか??
今回、子どもたちへの体験で使われたコオロギパウダーを提供したのは、徳島県でコオロギの養殖と商品開発・販売を行う「グリラス」です。3年前に設立されました。
コオロギに目をつけた理由の1つは、栄養価の高さです。
今回、子どもたちへの体験で使われたコオロギパウダーを提供したのは、徳島県でコオロギの養殖と商品開発・販売を行う「グリラス」です。3年前に設立されました。
コオロギに目をつけた理由の1つは、栄養価の高さです。

この会社によると、乾燥コオロギ100グラム当たりのたんぱく質の質量は、およそ76グラム。ニワトリや牛の3倍以上。
それ以外にも、現代人に不足しがちなビタミンやミネラル、食物繊維をはじめ、数多くの栄養が詰まっているといいます。
それ以外にも、現代人に不足しがちなビタミンやミネラル、食物繊維をはじめ、数多くの栄養が詰まっているといいます。
将来の食料危機を救う!?世界市場は14倍以上の予測も
注目される理由はほかにもあります。
国連によると今後、世界的に人口が増加し、2030年には2019年から10%増えておよそ85億人になり、重要な栄養素である牛肉や豚肉などのたんぱく質の供給が間に合わなくなるという指摘もあります。
日本能率協会総合研究所の推計によると、世界の昆虫食市場は2025年度にはおよそ1000億円と、2019年度の実績の70億円の14倍以上になる見込みです。
日本の市場についてのデータは現時点ではありませんが、まだ決して大きいとは言えません。この会社では食料危機にも備えて、たんぱく質を摂取できる新たな食材として広めようとしているんです。
国連によると今後、世界的に人口が増加し、2030年には2019年から10%増えておよそ85億人になり、重要な栄養素である牛肉や豚肉などのたんぱく質の供給が間に合わなくなるという指摘もあります。
日本能率協会総合研究所の推計によると、世界の昆虫食市場は2025年度にはおよそ1000億円と、2019年度の実績の70億円の14倍以上になる見込みです。
日本の市場についてのデータは現時点ではありませんが、まだ決して大きいとは言えません。この会社では食料危機にも備えて、たんぱく質を摂取できる新たな食材として広めようとしているんです。

川原さん
「まずはコオロギって食べ物なんだな、おいしいんだなと思ってもらいたい。そのうえで、たんぱく質危機の問題は、今のお子さんたちが直面していくものになるかもしれないので、いざという時に、少しでも経験や知識としても力になれたらうれしい」
「まずはコオロギって食べ物なんだな、おいしいんだなと思ってもらいたい。そのうえで、たんぱく質危機の問題は、今のお子さんたちが直面していくものになるかもしれないので、いざという時に、少しでも経験や知識としても力になれたらうれしい」
昆虫のイメージ「気持ち悪い」嫌悪感のルーツは?
しかし、課題があるといいます。
インターネットでトレンド調査を行っている「日本トレンドリサーチ」がことし2月に男女800人にアンケート調査を行った結果、69.9%が昆虫を食べたことがないと回答しました。
このうち、およそ9割が「食べたいと思わない」と回答。
インターネットでトレンド調査を行っている「日本トレンドリサーチ」がことし2月に男女800人にアンケート調査を行った結果、69.9%が昆虫を食べたことがないと回答しました。
このうち、およそ9割が「食べたいと思わない」と回答。

理由を見てみると、「気持ち悪い」「虫嫌いだから」「見てるだけで無理」など、昆虫の外見やイメージが、食と結び付かないという人が多いようです。
なぜ、このようなイメージを持つ人が多いのか。専門家に取材すると昆虫が嫌いだというルーツは私たちの祖先にあるという指摘も聞かれました。
なぜ、このようなイメージを持つ人が多いのか。専門家に取材すると昆虫が嫌いだというルーツは私たちの祖先にあるという指摘も聞かれました。

深野 准教授
「子どもに比べて大人のほうが虫嫌いが多いことで知られています。その多くは虫に対して嫌悪の感情を抱くことが関係していることがわかっています。この嫌悪の感情は私たちの祖先が狩猟採集をしていた時代に感染症を避ける役割があって生き延びる上で重要な働きをしていたと考えられます」
「子どもに比べて大人のほうが虫嫌いが多いことで知られています。その多くは虫に対して嫌悪の感情を抱くことが関係していることがわかっています。この嫌悪の感情は私たちの祖先が狩猟採集をしていた時代に感染症を避ける役割があって生き延びる上で重要な働きをしていたと考えられます」
年間1600万匹養殖 見学可能な施設オープン
全国でも珍しいコオロギの養殖を行っている様子を見学できる工場が長野県茅野市に今月11日にオープンしました。

昔からイナゴなどの昆虫を食べる文化が根付いている長野県。夏休み中の家族連れなどが次々と訪れていました。
コオロギはいったいどんな環境で育てているのか…。
コオロギはいったいどんな環境で育てているのか…。

棚に均等に並べられた衣装ケースのような透明の容器。
1200平方メートルある建物にケースがなんと4000箱。年間1600万匹のコオロギを養殖できる規模だそうです。
鳴き声が響きわたっていて、においは土のようなにおいがするくらいです。
1200平方メートルある建物にケースがなんと4000箱。年間1600万匹のコオロギを養殖できる規模だそうです。
鳴き声が響きわたっていて、においは土のようなにおいがするくらいです。
短期間の飼育サイクル
飼育されているコオロギは沖縄や奄美諸島などの暖かい地域に生息する「フタホシコオロギ」。
コオロギは、ふ化してから、40日から45日でメスが土の中に産卵。産卵したあとのタイミングでケースの中のコオロギを加工用に収穫するそうです。
その後、ふ化して幼虫が誕生し…と、このサイクルを繰り返すんです。
その後、ふ化して幼虫が誕生し…と、このサイクルを繰り返すんです。
IT技術でスマート養殖
工場を案内してくれたのは、コオロギの養殖事業を行う会社「クリケットファーム」の坪井大輔代表取締役です。
実はIT企業の経営者。本業を生かし、工場ではIT技術を駆使したスマート養殖を行っているんです。
工場内に設置されたセンサーで24時間365日、温度と湿度を管理しています。
工場内に設置されたセンサーで24時間365日、温度と湿度を管理しています。

飼育ケースには個別のQRコードを配置。
スマートフォンで、そのケースにいるコオロギをいつから飼育し始めたのか、AIで分析して把握したコオロギの個体のサイズ、エサの情報などを確認できるようになっています。
坪井さんによると、国内産のコオロギの価格の相場は1キロ当たり1万円から1万5000円と、主産地の東南アジアのおよそ2倍から3倍。
世界のコオロギ市場、たんぱく市場で戦っていくためにさらなるIT化を進めるべく、今後は、自動でエサや水をコオロギに与えるロボットも導入する予定だということです。
スマートフォンで、そのケースにいるコオロギをいつから飼育し始めたのか、AIで分析して把握したコオロギの個体のサイズ、エサの情報などを確認できるようになっています。
坪井さんによると、国内産のコオロギの価格の相場は1キロ当たり1万円から1万5000円と、主産地の東南アジアのおよそ2倍から3倍。
世界のコオロギ市場、たんぱく市場で戦っていくためにさらなるIT化を進めるべく、今後は、自動でエサや水をコオロギに与えるロボットも導入する予定だということです。
清潔な場所で育つコオロギ 重要なのは水
坪井さんは、コオロギを養殖するケースの中の環境にこだわっています。

当初、コオロギを大量に養殖するノウハウがなかった中、試行錯誤の末、気付いたポイントは水。
コオロギが飲む水は、土にしみこませる方法を編み出しました。
水が余って腐敗することを防ぐなどの工夫をしています。
坪井さんは、コオロギを養殖する環境の衛生面にこだわりつつ、家族連れや観光客などに現場を見てもらうことで、コオロギを食品として受け入れてもらう一歩にしたいと考えています。
コオロギが飲む水は、土にしみこませる方法を編み出しました。
水が余って腐敗することを防ぐなどの工夫をしています。
坪井さんは、コオロギを養殖する環境の衛生面にこだわりつつ、家族連れや観光客などに現場を見てもらうことで、コオロギを食品として受け入れてもらう一歩にしたいと考えています。
工場を見学した30代女性
「虫は苦手だけれど、においも全然ないしイメージと全然違った。食べることについては、虫だけでは難しいかもしれないが、ほかの食材と組み合わせたり、わからないように配合されている形であれば試したいなと思った」
「虫は苦手だけれど、においも全然ないしイメージと全然違った。食べることについては、虫だけでは難しいかもしれないが、ほかの食材と組み合わせたり、わからないように配合されている形であれば試したいなと思った」
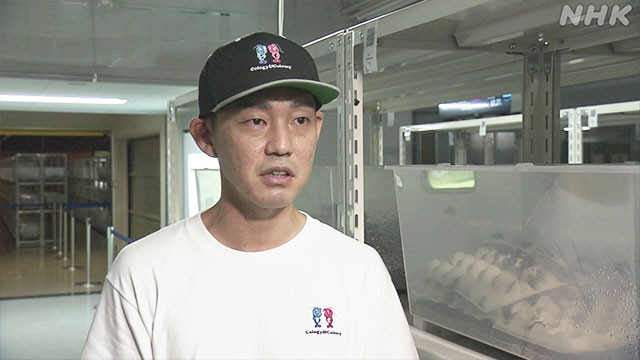
坪井代表取締役
「工場見学は、養殖のノウハウがわかってしまうので正直隠すところだと思うが、昆虫=ゲテモノ、汚い、臭い、特に畜産とかもそういうイメージ持たれるケースが多いので、そこを払拭(ふっしょく)しないと口に入れてもらえない。衛生面がきちっとしていてきれいな環境で育てられているのを知ってもらって、“昆虫=うわっ”となる印象を変えて、食べる抵抗をなくすことに取り組んでいきたい。昆虫食という言葉自体もアップデートしていく必要がある」
「工場見学は、養殖のノウハウがわかってしまうので正直隠すところだと思うが、昆虫=ゲテモノ、汚い、臭い、特に畜産とかもそういうイメージ持たれるケースが多いので、そこを払拭(ふっしょく)しないと口に入れてもらえない。衛生面がきちっとしていてきれいな環境で育てられているのを知ってもらって、“昆虫=うわっ”となる印象を変えて、食べる抵抗をなくすことに取り組んでいきたい。昆虫食という言葉自体もアップデートしていく必要がある」
市場規模、広がるのか!?

坪井さんの会社では、大手食品メーカーなどからの注文が相次いでいて、今回取材した企業以外にも、コオロギパウダーを使ったチョコやパンなどの商品の販売が行われるなど購入できる機会も増えてきています。
コスト面などの課題もあるということですが、コオロギが食品として当たり前となる時代が来るかもしれません。
コスト面などの課題もあるということですが、コオロギが食品として当たり前となる時代が来るかもしれません。

経済部記者
佐野 裕美江
2016年入局
青森放送局を経て現職
流通業界を担当
好きな虫はシャクトリムシ
佐野 裕美江
2016年入局
青森放送局を経て現職
流通業界を担当
好きな虫はシャクトリムシ