日本の地熱発電がすごい!? 世界3位の資源量 可能性にかける町

ウクライナ情勢の影響で世界はエネルギーの争奪戦に突入。石油や天然ガスに恵まれず、そのほとんどを輸入に頼る日本への影響は甚大だ。実はそんな日本にも、世界第3位の資源量を誇るエネルギー源がある。それが地熱だ。火山の多い日本は、アメリカ、インドネシアに次ぐ規模となっている。火山と温泉地に囲まれた九州の山奥にその“先進地”があった。(福岡放送局記者 早川俊太郎)
ビル・ゲイツが注目?
熊本県の阿蘇の山奥に、あのビル・ゲイツやジェフ・ベゾスも出資する投資ファンドの支援を受ける地熱発電の会社があるという。
なぜ投資先として目を付けたのか、それを探るため、われわれはその温泉地に向かった。
到着したのは、熊本県小国町にある「わいた温泉郷」。
その一角にある木造で歴史を感じる高級旅館だった。
なぜ投資先として目を付けたのか、それを探るため、われわれはその温泉地に向かった。
到着したのは、熊本県小国町にある「わいた温泉郷」。
その一角にある木造で歴史を感じる高級旅館だった。

出迎えてくれた旅館の社長で発電会社の経営者でもある熊谷和昭さん。
早速その現場を案内してもらった。
旅館の裏にそびえる急な山道を登ると、見えてきたのはモクモクと立ちのぼる蒸気。
それほど大きくはない高さ5メートルほどの発電設備だった。
早速その現場を案内してもらった。
旅館の裏にそびえる急な山道を登ると、見えてきたのはモクモクと立ちのぼる蒸気。
それほど大きくはない高さ5メートルほどの発電設備だった。

この旅館では、温泉の井戸から出る蒸気を使って、ことし2月に地熱発電に乗り出したという。
発電した200世帯分の電力は、クリーンエネルギーとして福岡市のマンションに供給されていた。
日本での地熱発電の歴史は長いが、その開発地はどうしても温泉地と近くなり、掘削をしたり蒸気を取り出したりすることで温泉の湯量が減ってしまうなどの影響を懸念し、開発業者と温泉組合が対立する構図が各地で起きてきた。
発電した200世帯分の電力は、クリーンエネルギーとして福岡市のマンションに供給されていた。
日本での地熱発電の歴史は長いが、その開発地はどうしても温泉地と近くなり、掘削をしたり蒸気を取り出したりすることで温泉の湯量が減ってしまうなどの影響を懸念し、開発業者と温泉組合が対立する構図が各地で起きてきた。
しかし、それにしても温泉旅館がみずから地熱発電を手がけるとは驚きだ。
熊谷さんにそのわけを率直に聞いてみると…。
熊谷さんにそのわけを率直に聞いてみると…。
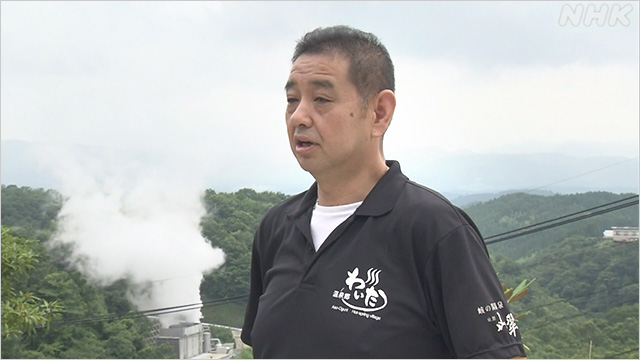
熊谷和昭さん
「実はこの地域も約30年前、賛成派と反対派で町が二分されて、事業者の計画が頓挫した経験があるんです。温泉への影響を懸念する住民も多くいました。地域の盆踊りさえ開けないほどでした。結局、その計画は中止されました。その後、温泉に影響を与えない新しい発電方法が開発され、地域全体で地熱発電に取り組む仕組みを作ったことで、いまは町の住民全員が賛成しています」
「実はこの地域も約30年前、賛成派と反対派で町が二分されて、事業者の計画が頓挫した経験があるんです。温泉への影響を懸念する住民も多くいました。地域の盆踊りさえ開けないほどでした。結局、その計画は中止されました。その後、温泉に影響を与えない新しい発電方法が開発され、地域全体で地熱発電に取り組む仕組みを作ったことで、いまは町の住民全員が賛成しています」
温泉に優しい新技術
温泉に影響を与えない新しい発電方法は「バイナリー発電」だ。
従来の地熱発電ではかなり高温の水蒸気が必要となり、発電を終えて温度が冷えた水は地中に戻される。
その際に地下の源泉の温度が下がってしまう懸念があった。
バイナリー発電は水よりも沸点の低いガスを媒介させることで温泉地であまった蒸気をそのまま活用できる。
地下の源泉に直接影響を与えないようにする技術だ。
従来の地熱発電ではかなり高温の水蒸気が必要となり、発電を終えて温度が冷えた水は地中に戻される。
その際に地下の源泉の温度が下がってしまう懸念があった。
バイナリー発電は水よりも沸点の低いガスを媒介させることで温泉地であまった蒸気をそのまま活用できる。
地下の源泉に直接影響を与えないようにする技術だ。

この技術の登場で住民の懸念が解消されたという。
わいた温泉郷では2011年、地熱発電会社「わいた会」を設立。
住民全員が株主となった会社だ。
温泉の湧出量や温度をデジタル管理し、温泉に影響が出ていないかどうかを地域全体でモニタリングするシステムを導入した。
わいた会以外の発電事業者もこのシステムを使うことができるように開放し、いまではこの温泉地には7か所で地熱発電が行われている。
わいた温泉郷では2011年、地熱発電会社「わいた会」を設立。
住民全員が株主となった会社だ。
温泉の湧出量や温度をデジタル管理し、温泉に影響が出ていないかどうかを地域全体でモニタリングするシステムを導入した。
わいた会以外の発電事業者もこのシステムを使うことができるように開放し、いまではこの温泉地には7か所で地熱発電が行われている。
熊谷和昭さん
「そのまま大気に放出されていた蒸気を有効活用できます。発電によって収入も得られますし、この地区の取り組みが1つのモデルになればいいなと思います」
「そのまま大気に放出されていた蒸気を有効活用できます。発電によって収入も得られますし、この地区の取り組みが1つのモデルになればいいなと思います」
業務スーパー創業者“常識破り”の地熱発電
温泉旅館の取材のあと、地熱発電の世界でいま注目を集めているある人物とわいた温泉郷で出会った。
全国チェーン「業務スーパー」の創業者、沼田昭二さん(68)。
全国チェーン「業務スーパー」の創業者、沼田昭二さん(68)。

地熱発電の開発に果敢に挑戦する“常識破り”の発想に驚いた。
沼田さんの案内で車に乗って山道を進み続けると、対向車との離合も難しい細い道になってきた。
道には大きな石がごろごろ。
そこを乗り越えるたびに座席から腰が浮き上がって不安になる道だった。
しばらく進むと開けた場所となり、突然、高さ40メートルの巨大なやぐらが飛び込んできた。
沼田さんの案内で車に乗って山道を進み続けると、対向車との離合も難しい細い道になってきた。
道には大きな石がごろごろ。
そこを乗り越えるたびに座席から腰が浮き上がって不安になる道だった。
しばらく進むと開けた場所となり、突然、高さ40メートルの巨大なやぐらが飛び込んできた。
ここが、沼田さんが第二の創業と位置づけ、人生をかけて挑む現場だ。

沼田昭二さん
「日本の地熱発電の有望地は、北海道と東北、そして九州ですが、中でも九州は一番、地熱発電に適した地域です。比較的浅い地層に地熱に必要な水蒸気が多くあります。地熱発電になぜ取り組むのかというと、エネルギー問題を抱える日本の次世代の子どもたちのためにはいまやらなければならないと考えるからです」
「日本の地熱発電の有望地は、北海道と東北、そして九州ですが、中でも九州は一番、地熱発電に適した地域です。比較的浅い地層に地熱に必要な水蒸気が多くあります。地熱発電になぜ取り組むのかというと、エネルギー問題を抱える日本の次世代の子どもたちのためにはいまやらなければならないと考えるからです」
沼田さんは地熱発電を手がける新たな会社を2016年に設立。
わいた温泉郷の山あいの土地で最初の地熱発電所の建設に向けた準備を進めている。
現在は、水蒸気を地中から取り出すための掘削作業を行っている。
事業費はなんと100億円にのぼるという。
そのうち50億円は自分のポケットマネーから出しているそうだ。
もはや趣味の世界ではない。
大きなビジネスチャンスがあるからこそ、本気で資金を出しているのだ。
これまでに、地下700メートルまで掘り進め、発電用の井戸のうち1本はすでに完成。
残るもう1本の掘削作業も大詰めを迎えていた。
わいた温泉郷の山あいの土地で最初の地熱発電所の建設に向けた準備を進めている。
現在は、水蒸気を地中から取り出すための掘削作業を行っている。
事業費はなんと100億円にのぼるという。
そのうち50億円は自分のポケットマネーから出しているそうだ。
もはや趣味の世界ではない。
大きなビジネスチャンスがあるからこそ、本気で資金を出しているのだ。
これまでに、地下700メートルまで掘り進め、発電用の井戸のうち1本はすでに完成。
残るもう1本の掘削作業も大詰めを迎えていた。

順調にいけば、発電設備の建設に移るという。
この日は土曜日だったが、ボーリングの熟練技術者たちが掘削用のパイプを操作しながら急ピッチで作業にあたっていた。
発電設備の稼働開始は2024年4月の計画。
8000世帯分の電力を生み出し、年間で約14億円の売電収入を見込んでいるという。
この日は土曜日だったが、ボーリングの熟練技術者たちが掘削用のパイプを操作しながら急ピッチで作業にあたっていた。
発電設備の稼働開始は2024年4月の計画。
8000世帯分の電力を生み出し、年間で約14億円の売電収入を見込んでいるという。
高いハードルを工夫で乗り越える
沼田さんが力を入れるのは地熱発電の従来のハードルの克服だ。
まず大事なのは「採算性」だという。
地熱発電はまず、採掘によって十分な熱と量の水蒸気を掘り当てなければならない。
沼田さんによると、その成功確率は5本から10本掘って1本程度。
しかも、1回の採掘ごとに1億円の費用がかかるという。
採掘するためには、やぐらの組み立てのために大型のクレーン車を現場に運ばなければならない。
そのための新たな道の整備なども必要となるからだ。
そこで行ったのが自作の掘削機の開発だった。
まず大事なのは「採算性」だという。
地熱発電はまず、採掘によって十分な熱と量の水蒸気を掘り当てなければならない。
沼田さんによると、その成功確率は5本から10本掘って1本程度。
しかも、1回の採掘ごとに1億円の費用がかかるという。
採掘するためには、やぐらの組み立てのために大型のクレーン車を現場に運ばなければならない。
そのための新たな道の整備なども必要となるからだ。
そこで行ったのが自作の掘削機の開発だった。

みずから作ってしまうとは…。
ショベルカーにも似た自走式の掘削機で、狭い悪路でも移動することができる。
やぐらの組み立ては不要。
現地に到着すればすぐに掘削作業を始めることができるのが大きな特徴だ。
これによって工程の短縮につながり、採掘コストは半分程度まで抑えられるようになったという。
もう1つのハードルが、発電所の設計がオーダーメードになってしまうこと。
地熱発電所をつくる場合、まずは水蒸気を採掘によって地中から見つけ出し、その量にあわせた規模の発電所をいちから設計するのが従来のやり方だった。
水蒸気が多ければ、それにあわせた発電所の規模にすることで発電量を最大限にするためだ。
沼田さんはその常識をあえて破ったという。
水蒸気が出てから設計の完成までにかかる期間は通常で2年以上。
その時間と労力がむだなコストだと考えた。
このため、水蒸気の量が多くても、あえて小さめの発電所にする仕組みを導入した。
この比較的小さな発電所で設計を“標準化”すれば、それを全国どこでも同じ設計で効率的に展開できる。
ショベルカーにも似た自走式の掘削機で、狭い悪路でも移動することができる。
やぐらの組み立ては不要。
現地に到着すればすぐに掘削作業を始めることができるのが大きな特徴だ。
これによって工程の短縮につながり、採掘コストは半分程度まで抑えられるようになったという。
もう1つのハードルが、発電所の設計がオーダーメードになってしまうこと。
地熱発電所をつくる場合、まずは水蒸気を採掘によって地中から見つけ出し、その量にあわせた規模の発電所をいちから設計するのが従来のやり方だった。
水蒸気が多ければ、それにあわせた発電所の規模にすることで発電量を最大限にするためだ。
沼田さんはその常識をあえて破ったという。
水蒸気が出てから設計の完成までにかかる期間は通常で2年以上。
その時間と労力がむだなコストだと考えた。
このため、水蒸気の量が多くても、あえて小さめの発電所にする仕組みを導入した。
この比較的小さな発電所で設計を“標準化”すれば、それを全国どこでも同じ設計で効率的に展開できる。

そう、店舗の設計を標準化して全国に展開する。
まさにスーパーの戦略と同じ発想だ。
まさにスーパーの戦略と同じ発想だ。
沼田昭二さん
「地熱発電のハードルは工夫で乗り越えることができます。日本は地熱発電のポテンシャルがありながら生かし切れていません。エネルギー価格が高騰する中、この現実をどう変えていくのか、皆さんも考えるべきだと思う」
「地熱発電のハードルは工夫で乗り越えることができます。日本は地熱発電のポテンシャルがありながら生かし切れていません。エネルギー価格が高騰する中、この現実をどう変えていくのか、皆さんも考えるべきだと思う」
日本のポテンシャル
地熱の資源量が世界3位の日本。
しかし、まだまだ活用しきれていないという指摘もある。
しかし、まだまだ活用しきれていないという指摘もある。

発電できる量=設備容量でみると、日本は8位にとどまっている。
逆に言えば、まだまだ伸びしろがあるということだ。
再生可能エネルギーといえば、太陽光発電が代表選手だが、夜間は発電ができず、天候によって左右されるという弱い面がある。
これに対して、地熱発電は24時間、発電量が一定の“安定性”が大きなメリットとされる。
実際に、原子力と同じベースロード電源と位置づけられている。
もちろん地熱発電にも、1つ1つの発電能力が小さく、数をそろえなければ代替電力としての力は足りないといった弱点もある。
ただそれでも、限られた“純国産エネルギー”としてその可能性をきちんとみる必要がありそうだと、帰り道の車窓の先にいくつも立ちのぼる蒸気を見ながら考えた。
逆に言えば、まだまだ伸びしろがあるということだ。
再生可能エネルギーといえば、太陽光発電が代表選手だが、夜間は発電ができず、天候によって左右されるという弱い面がある。
これに対して、地熱発電は24時間、発電量が一定の“安定性”が大きなメリットとされる。
実際に、原子力と同じベースロード電源と位置づけられている。
もちろん地熱発電にも、1つ1つの発電能力が小さく、数をそろえなければ代替電力としての力は足りないといった弱点もある。
ただそれでも、限られた“純国産エネルギー”としてその可能性をきちんとみる必要がありそうだと、帰り道の車窓の先にいくつも立ちのぼる蒸気を見ながら考えた。

福岡放送局記者
早川俊太郎
名古屋局、経済部などを経て2021年より福岡局
地域経済や消費生活取材を担当
早川俊太郎
名古屋局、経済部などを経て2021年より福岡局
地域経済や消費生活取材を担当