私が性に依存したわけ ~先生には悩みを打ち明けられたのに

精神疾患を患っていた母が次に襲われたのは、がんでした。
家事に加え、幼いきょうだいの世話。
母親の代わりとなった中学3年生の私に、父はこう言い続けました。
「長女なのに何でやらないんだ」
誰にも相談できない中で、私が頼ったのは“憧れの先生”でした。
でも今はそのことを後悔しています。
同じ苦しみを抱える誰かのためになればと、はるかさん(仮名・30代)が自身の経験を語ってくれました。
(首都圏局記者 石川由季)
家事に加え、幼いきょうだいの世話。
母親の代わりとなった中学3年生の私に、父はこう言い続けました。
「長女なのに何でやらないんだ」
誰にも相談できない中で、私が頼ったのは“憧れの先生”でした。
でも今はそのことを後悔しています。
同じ苦しみを抱える誰かのためになればと、はるかさん(仮名・30代)が自身の経験を語ってくれました。
(首都圏局記者 石川由季)
精神科に入院した母
母親の様子が変わったのは、小学4年生の頃でした。
もともと潔癖だった行動が少しずつエスカレートしていったのです。
それまでは外出先から帰ると手や足を洗えば家に入ることができていたのが、お風呂に入らないとダメになりました。
「強迫性障害」という精神疾患でした。
この症状を理由に、両親はけんかが絶えなくなります。
ある日、怒鳴り声と大きな物音を聞いて様子を見に行くと、包丁を持つ母の腕を父が力づくで押さえつけていました。
そのときのあざが母の腕にずっと残っていたのは、今でもはっきりと覚えています。
今だったら考えられないくらい父親が強い家庭で、父には絶対に意見を言うことはできませんでした。
もともと潔癖だった行動が少しずつエスカレートしていったのです。
それまでは外出先から帰ると手や足を洗えば家に入ることができていたのが、お風呂に入らないとダメになりました。
「強迫性障害」という精神疾患でした。
この症状を理由に、両親はけんかが絶えなくなります。
ある日、怒鳴り声と大きな物音を聞いて様子を見に行くと、包丁を持つ母の腕を父が力づくで押さえつけていました。
そのときのあざが母の腕にずっと残っていたのは、今でもはっきりと覚えています。
今だったら考えられないくらい父親が強い家庭で、父には絶対に意見を言うことはできませんでした。

「精神科に行ったほうがいい」
父の言葉で母は入院することになりました。
当時は精神疾患への偏見も強く、家族以外にこの話をすることはありませんでした。
父の言葉で母は入院することになりました。
当時は精神疾患への偏見も強く、家族以外にこの話をすることはありませんでした。
「長女なのになぜ家事をやらない」
その後も処方された薬を大量に飲んだり、リストカットをしたりすることもあった母。症状は私が中学生になる頃にはさらに悪化しました。
そして別の病魔も襲います。がんです。
このとき私は中学3年生で、年の離れた妹はまだ小学生でした。
父は夜勤もある仕事で、自分が母の代わりとなって本格的に家事や妹たちの世話を担わざるを得なくなりました。
そして別の病魔も襲います。がんです。
このとき私は中学3年生で、年の離れた妹はまだ小学生でした。
父は夜勤もある仕事で、自分が母の代わりとなって本格的に家事や妹たちの世話を担わざるを得なくなりました。

とにかく家のことを回すのに必死でした。
本を見て必死に覚えた料理。
毎日たまっていく洗濯物。
掃除はやらなくても生きていけると考え、家には物が散乱していました。
そこに追い打ちをかけたのが、父の言葉でした。
「長女なのになぜ家事をやらないんだ」
受験生で勉強もしないといけなかったのに「家事は女がやるもの」と叱られてばかり。
どうして私だけが…。
日に日にそんな思いが募る一方で、どこにも居場所がないという孤独を強く感じていました。
本を見て必死に覚えた料理。
毎日たまっていく洗濯物。
掃除はやらなくても生きていけると考え、家には物が散乱していました。
そこに追い打ちをかけたのが、父の言葉でした。
「長女なのになぜ家事をやらないんだ」
受験生で勉強もしないといけなかったのに「家事は女がやるもの」と叱られてばかり。
どうして私だけが…。
日に日にそんな思いが募る一方で、どこにも居場所がないという孤独を強く感じていました。

憧れの先生との出会い
母ががんの治療のために長く入院するようになっても、私に過度の負担がかかっていることを相談できる人はいませんでした。
入院したことは近所の人や友人、学校の先生も知っていましたが、表面的なやりとりだけで終わっていました。
「つらい気持ちを表に出してはいけない」
当時、私は成績も学年でトップクラス。運動部にも所属し、いわゆる“優等生タイプ”の生徒でした。
感情を表に出すことで生活が荒れ、今までうまく進んでいた人生の軌道を外れてしまうのが怖かったのです。
それでも負担はどんどん蓄積していき、家に帰りたくないと思う気持ちが増していきました。
そんなときに出会ったのが、塾で英語を教えてくれていた男の先生でした。当時30代だったと思います。
入院したことは近所の人や友人、学校の先生も知っていましたが、表面的なやりとりだけで終わっていました。
「つらい気持ちを表に出してはいけない」
当時、私は成績も学年でトップクラス。運動部にも所属し、いわゆる“優等生タイプ”の生徒でした。
感情を表に出すことで生活が荒れ、今までうまく進んでいた人生の軌道を外れてしまうのが怖かったのです。
それでも負担はどんどん蓄積していき、家に帰りたくないと思う気持ちが増していきました。
そんなときに出会ったのが、塾で英語を教えてくれていた男の先生でした。当時30代だったと思います。

距離を縮めるきっかけになったのは「英語の日記」でした。
どうしたら先生のように英語を話せるようになるのか尋ねたら、日記を書くようアドバイスされました。
塾のカリキュラムにはありませんでしたが、毎週書いた日記を添削してもらうようになり、個人的に話をする機会が増えていきました。
当時は先生を尊敬していて、その経験や華やかな経歴を聞くにつれ、こう感じていました。
「自分がいるのはまだスタートライン。ここから絶対に挽回できる、頑張ればなんとかなる」
どうしたら先生のように英語を話せるようになるのか尋ねたら、日記を書くようアドバイスされました。
塾のカリキュラムにはありませんでしたが、毎週書いた日記を添削してもらうようになり、個人的に話をする機会が増えていきました。
当時は先生を尊敬していて、その経験や華やかな経歴を聞くにつれ、こう感じていました。
「自分がいるのはまだスタートライン。ここから絶対に挽回できる、頑張ればなんとかなる」
孤独だった私が向かった先生の家
先生と勉強以外の話をすることも多くなりました。
入院中の母の話も親身に聞いて具体的にアドバイスをくれたので、「大変だね」としか言葉が返ってこない友だちとは違う対応に信頼感が高まります。
次第に先生に誘われて公園や喫茶店でも2人で会うようになり、一度家に遊びに行った日には、海外で撮った写真を見せてもらいました。
ただそのときに芸術作品だと言われ、女の人のヌード写真も見せられました。
そして中学校の卒業式が終わったある日、「うちに泊まりに来なよ」と連絡が来ました。
家にいたら家事やきょうだいの世話をしなければいけない
少しでもやっていなければ父に怒られる
現実から逃げたくなった私は夜中に自宅を抜け出して先生の家に泊まり、言われるがままにしました。
当時15歳。
初めての性行為でした。
そこには「もう、いいや」と自分の現状をすべて消し去りたいという思いがありました。
入院中の母の話も親身に聞いて具体的にアドバイスをくれたので、「大変だね」としか言葉が返ってこない友だちとは違う対応に信頼感が高まります。
次第に先生に誘われて公園や喫茶店でも2人で会うようになり、一度家に遊びに行った日には、海外で撮った写真を見せてもらいました。
ただそのときに芸術作品だと言われ、女の人のヌード写真も見せられました。
そして中学校の卒業式が終わったある日、「うちに泊まりに来なよ」と連絡が来ました。
家にいたら家事やきょうだいの世話をしなければいけない
少しでもやっていなければ父に怒られる
現実から逃げたくなった私は夜中に自宅を抜け出して先生の家に泊まり、言われるがままにしました。
当時15歳。
初めての性行為でした。
そこには「もう、いいや」と自分の現状をすべて消し去りたいという思いがありました。

交際していない人と性行為を繰り返すように
先生との関係はそれっきりで終わりました。
ただ交際していない複数の人と、性行為を繰り返すようになりました。
家庭で私に過度の負担がのしかかる状況が変わらない中で、「性行為をするその瞬間だけは誰かに依存できる」。
心から頼れる人がいない中で、そう感じていました。
一方で、それは自傷行為を繰り返すような感覚でもありました。
誰にも迷惑はかけていない。悪いこともしていない。
お金をもらっているわけでもない。誰かの何かを奪っているわけでもない。
精神のバランスを保つためにはしかたのないこと、そう自分に言い聞かせていたんです。
ただ交際していない複数の人と、性行為を繰り返すようになりました。
家庭で私に過度の負担がのしかかる状況が変わらない中で、「性行為をするその瞬間だけは誰かに依存できる」。
心から頼れる人がいない中で、そう感じていました。
一方で、それは自傷行為を繰り返すような感覚でもありました。
誰にも迷惑はかけていない。悪いこともしていない。
お金をもらっているわけでもない。誰かの何かを奪っているわけでもない。
精神のバランスを保つためにはしかたのないこと、そう自分に言い聞かせていたんです。
SOSを出せない子どもたちに知ってほしいこと

これまで胸に秘めてきたという自身の経験を語ってくれた、はるかさん(仮名・30代)。
取材のきっかけは、NHKのヤングケアラー特設サイトに意見を寄せてくれたことでした。
はるかさんは最近になって「ヤングケアラー」という言葉を知ったとき、塾の先生との一連の出来事を思い返したといいます。
取材のきっかけは、NHKのヤングケアラー特設サイトに意見を寄せてくれたことでした。
はるかさんは最近になって「ヤングケアラー」という言葉を知ったとき、塾の先生との一連の出来事を思い返したといいます。
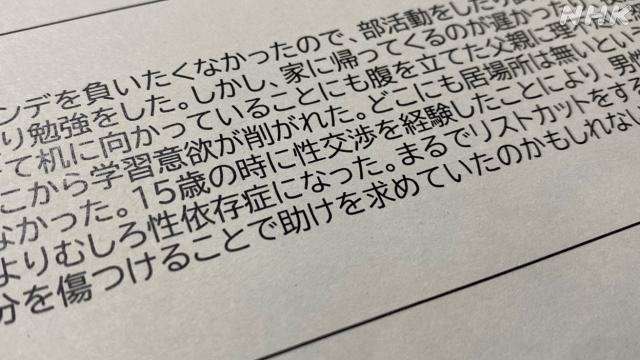
取材を受けたときには時折涙を浮かべ、何度もことばを詰まらせながら当時のことを振り返りました。
はるかさん
「急に襲われたわけではないし、塾の先生からすれば“同意のもと”だったと思います。でもその前に家に行った段階で“芸術作品”と言ってヌード写真を見せられたりしたので、性行為をほのめかされたというか、うまく丸め込まれたんだと思います。私の家の状況を知っていたので、嫌な目にあっても親には話さないということをわかっていたんじゃないかなって」
「急に襲われたわけではないし、塾の先生からすれば“同意のもと”だったと思います。でもその前に家に行った段階で“芸術作品”と言ってヌード写真を見せられたりしたので、性行為をほのめかされたというか、うまく丸め込まれたんだと思います。私の家の状況を知っていたので、嫌な目にあっても親には話さないということをわかっていたんじゃないかなって」
だからこそ誰にも相談できずに苦しんでいる子どもたちが同じ目に遭わないよう、“つけ込んでくる大人もいる”ということを知ってほしいと話しました。
はるかさん
「もちろん子どものことをちゃんと考えてくれる人もたくさんいると思いますが、インターネットを通じていろいろな人とつながれる時代になったからこそ、悪意を持った大人もいるということを知っておいてほしい。当時の私はどこに助けを求めればいいのかわからなかったけど、もっと助けを求めてよかったんだと今は思っています。行政や支援団体などしっかりとした相談・支援機関につながってほしいです」
「もちろん子どものことをちゃんと考えてくれる人もたくさんいると思いますが、インターネットを通じていろいろな人とつながれる時代になったからこそ、悪意を持った大人もいるということを知っておいてほしい。当時の私はどこに助けを求めればいいのかわからなかったけど、もっと助けを求めてよかったんだと今は思っています。行政や支援団体などしっかりとした相談・支援機関につながってほしいです」
専門家「生きるための手段」
15歳のときの経験をきっかけに、性行為を繰り返すようになったというはるかさん。
医療機関の診断は受けていませんが、こうした行動についてさまざまな依存症の治療に携わってきた専門家は次のように話します。
医療機関の診断は受けていませんが、こうした行動についてさまざまな依存症の治療に携わってきた専門家は次のように話します。
赤城高原ホスピタル 竹村道夫 院長
「摂食障害やアルコール依存症、境界性パーソナリティ障害などの患者の治療にあたってきたが、性行為に依存する人もいました。その中には機能不全に陥った家族の中で幼少期を過ごしていたというケースも少なくありません」
「摂食障害やアルコール依存症、境界性パーソナリティ障害などの患者の治療にあたってきたが、性行為に依存する人もいました。その中には機能不全に陥った家族の中で幼少期を過ごしていたというケースも少なくありません」
一方、精神保健福祉士の資格を持つ杏林大学の加藤雅江教授も性行為を繰り返す女性に会ったことがあるといいます。
加藤教授は30年にわたって大学病院に勤務し、救命救急センターで搬送されてくる若い女性患者などのサポートにあたった経験があります。
加藤教授は30年にわたって大学病院に勤務し、救命救急センターで搬送されてくる若い女性患者などのサポートにあたった経験があります。
杏林大学 加藤雅江教授
「はるかさんは家族の中で役割を持つことはできても、彼女そのままの存在を肯定してくれるような温かい感情のやり取りがなかったのかもしれません。うれしい、悲しい、つらいということを言葉として発して、相手がそれを受け止め共感してくれる体験を繰り返すといろんな感情があっていいことを知り、いろんな気持ちを持つ自分を受け入れていくことができます。一方でそういう体験が少ないと自分の感情に鈍くなり、つらさや恐怖を感じてしまうことが苦しいので何も感じないようにして自分を守ります」
「はるかさんは家族の中で役割を持つことはできても、彼女そのままの存在を肯定してくれるような温かい感情のやり取りがなかったのかもしれません。うれしい、悲しい、つらいということを言葉として発して、相手がそれを受け止め共感してくれる体験を繰り返すといろんな感情があっていいことを知り、いろんな気持ちを持つ自分を受け入れていくことができます。一方でそういう体験が少ないと自分の感情に鈍くなり、つらさや恐怖を感じてしまうことが苦しいので何も感じないようにして自分を守ります」

そのうえで性に依存したことについて、「生きるための手段」だったのではないかと指摘しました。
杏林大学 加藤雅江教授
「性的に求められることこそが自分の存在を認める唯一の理由となり、愛されていることであると誤解してしまうケースは少なくありません。はるかさんが“自傷行為をするように性行為をしていた”と話したということですが、リストカットやオーバードーズといった行為は、死なないようにする“生きるための手段”という一面もあるんです」
「性的に求められることこそが自分の存在を認める唯一の理由となり、愛されていることであると誤解してしまうケースは少なくありません。はるかさんが“自傷行為をするように性行為をしていた”と話したということですが、リストカットやオーバードーズといった行為は、死なないようにする“生きるための手段”という一面もあるんです」
安心して過ごせる“居場所”を
加藤教授が当時のはるかさんのような子どもたちに必要だと話したのは、そのままの存在を肯定してくれ、安心して過ごすことができる居場所です。
加藤教授自身が仲間とともに開催している「子ども食堂」。
家庭や学校にいるのが苦しくなったときに少しの時間だけでもいられる場、そして地域の大人たちとつながれる場になることを目指しています。
加藤教授自身が仲間とともに開催している「子ども食堂」。
家庭や学校にいるのが苦しくなったときに少しの時間だけでもいられる場、そして地域の大人たちとつながれる場になることを目指しています。

「ヤングケアラーを支援している」とか「生活が苦しい家庭の子どもを支援している」と言うと来るのをためらってしまう子がいるため、こう伝えているといいます。
「誰でも来ることができる場所だよ」
「誰でも来ることができる場所だよ」
杏林大学 加藤雅江教授
「大人に頼ってもいいんだと思ってもらえるような働きかけをしていきたいし、ヤングケアラーと言われる子どもたちに、『相談したら対応してもらえた』という経験をしてほしい。何か困ったときに相談に来ようと思ってもらえる居場所づくりを続けていきたいと思っています」
「大人に頼ってもいいんだと思ってもらえるような働きかけをしていきたいし、ヤングケアラーと言われる子どもたちに、『相談したら対応してもらえた』という経験をしてほしい。何か困ったときに相談に来ようと思ってもらえる居場所づくりを続けていきたいと思っています」
取材後記
はるかさんは信頼できるパートナーと出会い、生まれ育った街を離れたことで、当時のことを思い出す時間も減り、穏やかな日々を過ごせているといいます。
子どもを育てる中で、同じような思いをする子どもたちを減らしたいという思いが強くなり、今回、取材を受けてくれました。
はるかさんが、性行為を繰り返すきっかけとなった先生との出来事。
「先生と生徒」「大人と未成年」という上下の関係がある中で、SOSを出しにくいと分かっていながら関係を迫ったのだとしたら、それは気持ちを踏みにじる行為です。
ヤングケアラーを支援する場は少しずつ増えてきていますが、生きづらさを感じている子どもたちのSOSが適切な機関や団体につながる必要性を改めて強く感じました。
子どもを育てる中で、同じような思いをする子どもたちを減らしたいという思いが強くなり、今回、取材を受けてくれました。
はるかさんが、性行為を繰り返すきっかけとなった先生との出来事。
「先生と生徒」「大人と未成年」という上下の関係がある中で、SOSを出しにくいと分かっていながら関係を迫ったのだとしたら、それは気持ちを踏みにじる行為です。
ヤングケアラーを支援する場は少しずつ増えてきていますが、生きづらさを感じている子どもたちのSOSが適切な機関や団体につながる必要性を改めて強く感じました。

首都圏局 記者
石川由季
平成24年入局 大津局、宇都宮局を経て現所属。
ヤングケアラーなど福祉関連の取材を続ける。
石川由季
平成24年入局 大津局、宇都宮局を経て現所属。
ヤングケアラーなど福祉関連の取材を続ける。