東京ブラックホール “秘録” バブルの時代

バブルの象徴と言われた女性がいる。
「アッコちゃん」と言われる伝説の人、川添明子さん。当時、大学生だった彼女に男たちは夢中になった。「地上げの帝王と呼ばれた」不動産会社社長、ユーミンを世に送り出した音楽プロデューサー…。
バブル崩壊から30年あまり。今回彼女が初めてテレビのインタビューに応じ、「まるでプリティ・ウーマンのようだった」というバブルの時代の体験を赤裸々に語った。
バブルの時代に国が行った世論調査。「日常生活に悩みや不安を感じていない」と答えた国民は、51パーセント。調査が始まった昭和33年から現在に至るまで、この調査で「不安を感じていない」という回答が半数を超えたのは、この時期だけである。
日本迷走の元凶とも言われるバブル。しかし、それは本当に空虚な繁栄だったのか。あの時代には何があり、今の私たちは何を失ったのか。
バブルの時代を象徴する人々の“秘録”とも言えるロングインタビューから探っていく。
(NHKスペシャル「東京ブラックホール 取材班」)
「アッコちゃん」と言われる伝説の人、川添明子さん。当時、大学生だった彼女に男たちは夢中になった。「地上げの帝王と呼ばれた」不動産会社社長、ユーミンを世に送り出した音楽プロデューサー…。
バブル崩壊から30年あまり。今回彼女が初めてテレビのインタビューに応じ、「まるでプリティ・ウーマンのようだった」というバブルの時代の体験を赤裸々に語った。
バブルの時代に国が行った世論調査。「日常生活に悩みや不安を感じていない」と答えた国民は、51パーセント。調査が始まった昭和33年から現在に至るまで、この調査で「不安を感じていない」という回答が半数を超えたのは、この時期だけである。
日本迷走の元凶とも言われるバブル。しかし、それは本当に空虚な繁栄だったのか。あの時代には何があり、今の私たちは何を失ったのか。
バブルの時代を象徴する人々の“秘録”とも言えるロングインタビューから探っていく。
(NHKスペシャル「東京ブラックホール 取材班」)
センター街を抜けるのに2時間 バブルの象徴「アッコちゃん」

「アッコちゃん」とよばれた川添明子はバブルの象徴だった。
作家の林真理子が彼女や関係者に行ったインタビューをもとに当時の日本を描いた小説「アッコちゃんの時代」。タイトルは川添明子のニックネームからとった。
当時、大学生だったアッコはとにかくモテた。渋谷に出れば男たちが次々と彼女に声をかけて来る。今やはやらなくなったナンパである。
作家の林真理子が彼女や関係者に行ったインタビューをもとに当時の日本を描いた小説「アッコちゃんの時代」。タイトルは川添明子のニックネームからとった。
当時、大学生だったアッコはとにかくモテた。渋谷に出れば男たちが次々と彼女に声をかけて来る。今やはやらなくなったナンパである。
川添明子さん
「お茶しないとか、どこ行くのとか。あと、夜明けのソフト食べようとか。センター街を突っ切るのに2時間ぐらいかかったこともありました。急いでいるときはそういう所を避けて歩いていました」
「お茶しないとか、どこ行くのとか。あと、夜明けのソフト食べようとか。センター街を突っ切るのに2時間ぐらいかかったこともありました。急いでいるときはそういう所を避けて歩いていました」
ディスコに通うようになったきっかけもバブルの時代“らしい”ものだった。
川添さん
「街を歩いていたら、券をもらって、『ソフトクリーム食べられるよ』って言われて、面白そうだし食べに行こうかなという感じでディスコに行きました。そうしたら、ただで入れてくれるんです」
「街を歩いていたら、券をもらって、『ソフトクリーム食べられるよ』って言われて、面白そうだし食べに行こうかなという感じでディスコに行きました。そうしたら、ただで入れてくれるんです」

当時、多くのディスコは富裕層の男性客が集まることを当て込み、アッコのように若く美しい女性はタダで利用することができた。
目的に合わせてディスコをはしごすることもアッコの日常になっていった。
目的に合わせてディスコをはしごすることもアッコの日常になっていった。
川添さん
「六本木にメイキャップっていうディスコがあって、そこに行くとメイクもしてくれるし、あと、焼き鳥ディスコとか、お寿司ディスコとか、サラダディスコとかお腹がすくとディスコをハシゴしていましたね」
「六本木にメイキャップっていうディスコがあって、そこに行くとメイクもしてくれるし、あと、焼き鳥ディスコとか、お寿司ディスコとか、サラダディスコとかお腹がすくとディスコをハシゴしていましたね」
その華やかな美貌で六本木でも瞬く間に評判になったアッコ。ディスコでは上客向けのVIP席に招かれるようになっていった。
彼女が踊るだけで、店には男たちが殺到し、売り上げが上がったと言う。
彼女が踊るだけで、店には男たちが殺到し、売り上げが上がったと言う。
川添さん
「お店の“売上協力隊”みたいになっていましたね。VIP席に行って、男の人に『何飲みたい?』って聞かれたら『ピンクのドンペリ!』って言って、『何食べたい?』って聞かれたら『メロン!』みたいな。帰りには男の人からタクシー代が女の子一人一人に渡されるんです。大体1人2万ずつくらいでしたね」
「お店の“売上協力隊”みたいになっていましたね。VIP席に行って、男の人に『何飲みたい?』って聞かれたら『ピンクのドンペリ!』って言って、『何食べたい?』って聞かれたら『メロン!』みたいな。帰りには男の人からタクシー代が女の子一人一人に渡されるんです。大体1人2万ずつくらいでしたね」
“地上げの帝王”と呼ばれた早坂太吉氏など名のある男たちが、まだ二十歳そこそこのアッコに夢中になった。
当時のアッコを知る友人はその魅力をこう語る。
当時のアッコを知る友人はその魅力をこう語る。
「魔性の女に見えないところが魔性なんですよ。当時はアッコの魔力にやられちゃった男がどれほどいたか」

アッコ本人は、少し違った目線で自分を客観的に見ていた。
川添さん
「私には、すごい自分好きな人、つまりナルシストが寄ってくるんです。だから友達から“ナルシスホイホイ”って呼ばれていました。お友達から『あの人自慢するから嫌い』っていう言葉はよく聞いたんですけど、私は男の人の自慢話が好きなんですよ」
「私には、すごい自分好きな人、つまりナルシストが寄ってくるんです。だから友達から“ナルシスホイホイ”って呼ばれていました。お友達から『あの人自慢するから嫌い』っていう言葉はよく聞いたんですけど、私は男の人の自慢話が好きなんですよ」
男たちは自分の成功談をアッコに飽くことなく語った。

アッコに熱をあげた男の中でも、高級レストランの御曹司にして音楽プロデューサーでもあった川添象郎氏の財力は桁外れだった。
アッコをプライベートジェットでヨーロッパ旅行に連れ出すなど、彼女のために湯水のようにお金を使った。
そして、その後ふたりは結婚した。
アッコをプライベートジェットでヨーロッパ旅行に連れ出すなど、彼女のために湯水のようにお金を使った。
そして、その後ふたりは結婚した。

川添さん
「川添はプロデューサーだからなんでしょうけど、お洋服買うのも、全部トータルで買ってくれるんですよ。だからもう映画の『プリティ・ウーマン』の主人公になった気分でした。お金は一種のエネルギーだと思うんです。好きな人に自分のエネルギーを使う行為、要するに好きだという表現を形で表しているのがプレゼントだったりお金だったりするわけで、嫌いな人にはそのエネルギーは与えないから」
「川添はプロデューサーだからなんでしょうけど、お洋服買うのも、全部トータルで買ってくれるんですよ。だからもう映画の『プリティ・ウーマン』の主人公になった気分でした。お金は一種のエネルギーだと思うんです。好きな人に自分のエネルギーを使う行為、要するに好きだという表現を形で表しているのがプレゼントだったりお金だったりするわけで、嫌いな人にはそのエネルギーは与えないから」
トランプのカジノで勝負をした日本人

バブルの時代、株式市場の時価総額は600兆円、世界の市場の4割以上を占めていた。株式時価総額で測る世界の企業ランキングの50社中、32社までが日本企業だった。
膨れ上がった日本人の“カネ”を狙っていた人物もいた。
アメリカ前大統領のドナルド・トランプ氏。
運営するトランプ・プラザ・ホテル・アンド・カジノの最高責任者だったジョン・オドンネル氏が今もバブル時代の“伝説”として語られるトランプ氏と日本人の賭けの舞台裏を語った。
膨れ上がった日本人の“カネ”を狙っていた人物もいた。
アメリカ前大統領のドナルド・トランプ氏。
運営するトランプ・プラザ・ホテル・アンド・カジノの最高責任者だったジョン・オドンネル氏が今もバブル時代の“伝説”として語られるトランプ氏と日本人の賭けの舞台裏を語った。

当時、アメリカのカジノの関係者たちは一晩で100万ドル以上のお金を使えるお客を“ホエール”と呼んでいた。その中でも、とりわけ有名な日本人がいた。
地上げで巨万の富を築いた不動産業の柏木昭男氏。
地上げで巨万の富を築いた不動産業の柏木昭男氏。
オドンネル氏
「私たちは日本や香港を含む極東のギャンブラーを招致する戦略をたてていました。柏木氏は“ホエール”の中でも特別で、世界中でとても有名でした。一回のプレーで1000万ドルも勝ったり負けたりするという評判を持っていました。ですから、柏木氏にトランプのカジノに来てもらうため、われわれはとてもアグレッシブに彼を追いかけていました」
「私たちは日本や香港を含む極東のギャンブラーを招致する戦略をたてていました。柏木氏は“ホエール”の中でも特別で、世界中でとても有名でした。一回のプレーで1000万ドルも勝ったり負けたりするという評判を持っていました。ですから、柏木氏にトランプのカジノに来てもらうため、われわれはとてもアグレッシブに彼を追いかけていました」

トランプ氏からカジノの経営を任されていたオドンネル氏は、柏木氏から巨額の資金を得るために、彼の勝敗記録やギャンブルのクセを調べていた。
そして、“勝っている時でも必ずしもやめないこと”、また“一度カジノを訪れれば数日間滞在して賭けを行う”という彼の特徴を把握していた。
そして、“勝っている時でも必ずしもやめないこと”、また“一度カジノを訪れれば数日間滞在して賭けを行う”という彼の特徴を把握していた。
オドンネル氏
「多くの人は知らないかもしれませんが、業界の人なら知っているとおり、勝負が長くなればなるほど、カジノ側が有利になります。たとえカジノにとって勝率の低いバカラでも、柏木氏が一日8~10時間、4日か5日プレーすれば、私たちは彼からお金を奪えると、かなり自信を持っていました」
「多くの人は知らないかもしれませんが、業界の人なら知っているとおり、勝負が長くなればなるほど、カジノ側が有利になります。たとえカジノにとって勝率の低いバカラでも、柏木氏が一日8~10時間、4日か5日プレーすれば、私たちは彼からお金を奪えると、かなり自信を持っていました」
バブルで膨れ上がった柏木氏の資金に目をつけていたトランプ氏。彼は顧客と会うことを嫌うとされているが、オドンネル氏がアレンジした柏木氏との面会を行ってまで信頼を得ようとした。
ねらいはいうまでもなく柏木氏が持つ“巨額の金”だった。
ねらいはいうまでもなく柏木氏が持つ“巨額の金”だった。
オドンネル氏
「トランプ氏が柏木氏に会う時間を取ったことが、柏木氏からのリスペクトを得る上でプラスになったと思います。ドナルド・トランプ氏は、貿易の不均衡があるとか、何かと理由をつけて、日本をバッシングしていましたが、日本人が多くのお金を持っていることも知っていました。率直に言ってドナルドは当時、苦境にありました。資金集めをするために日本に行くこともあったのですから..」
「トランプ氏が柏木氏に会う時間を取ったことが、柏木氏からのリスペクトを得る上でプラスになったと思います。ドナルド・トランプ氏は、貿易の不均衡があるとか、何かと理由をつけて、日本をバッシングしていましたが、日本人が多くのお金を持っていることも知っていました。率直に言ってドナルドは当時、苦境にありました。資金集めをするために日本に行くこともあったのですから..」
柏木氏は招きに応じて、トランプ氏のカジノを訪問する。
最初の訪問は2日間。予定より短い滞在となったが柏木氏が600万ドル勝った。
最初の訪問は2日間。予定より短い滞在となったが柏木氏が600万ドル勝った。
オドンネル氏
「カジノ側が600万ドル負けたことを伝えると、ドナルドは不満そうでした。そしてご存じのとおり、ドナルドは責任のなすりつけをするのが好きです。柏木氏を招くという決定に彼も関わっていたにもかかわらず、『だからやめろと言っただろう』と言い始めました。つまり、彼は600万ドルの損失を私のせいにしたのです」
「カジノ側が600万ドル負けたことを伝えると、ドナルドは不満そうでした。そしてご存じのとおり、ドナルドは責任のなすりつけをするのが好きです。柏木氏を招くという決定に彼も関わっていたにもかかわらず、『だからやめろと言っただろう』と言い始めました。つまり、彼は600万ドルの損失を私のせいにしたのです」

まもなく柏木氏の2度目の訪問、つまりトランプ側にとっては絶好のリベンジの機会が訪れる。
オドンネル氏
「4日間滞在させることができれば、われわれカジノはお金を取り戻せる可能性が高いと考えていました。実際にまさにそうなりました。ゲームの早い段階で、柏木氏は負け始めたのです」
「4日間滞在させることができれば、われわれカジノはお金を取り戻せる可能性が高いと考えていました。実際にまさにそうなりました。ゲームの早い段階で、柏木氏は負け始めたのです」
柏木氏は以前に勝った600万ドルを失った。その時点で、トータルの勝敗はイーブン。
柏木氏はプレーを続け、さらに400万ドル負けを重ねた。つまりその時点で、2回目の訪問だけで柏木氏は1000万ドルを失っていた。
しかし、彼はまだプレーを続けるつもりだった。自由に使えるお金が200万ドル残っていたからだ。
だが、柏木氏は挽回するチャンスを得られなかった。
柏木氏はプレーを続け、さらに400万ドル負けを重ねた。つまりその時点で、2回目の訪問だけで柏木氏は1000万ドルを失っていた。
しかし、彼はまだプレーを続けるつもりだった。自由に使えるお金が200万ドル残っていたからだ。
だが、柏木氏は挽回するチャンスを得られなかった。
オドンネル氏
「ドナルド・トランプが賭けを打ち切ったからです。彼は400万ドル勝っている状況で『もういい、この男を追い出せ』と言ったのです」
「ドナルド・トランプが賭けを打ち切ったからです。彼は400万ドル勝っている状況で『もういい、この男を追い出せ』と言ったのです」

このときの訪問で1000万ドル、日本円にして15億円を失った柏木氏。その後、バブルが崩壊し彼は巨額の借金を背負うことになる。
そして、トランプのカジノを訪問してから2年後の1992年、自宅の台所でメッタ斬りになった姿で発見された。
そして、トランプのカジノを訪問してから2年後の1992年、自宅の台所でメッタ斬りになった姿で発見された。
俳優 山田孝之がバブルの時代を生きる

2022年、誰もがマスクをつけ街を歩く姿がもはや日常になった日本。その現代を生きる俳優の山田孝之さんが今回バブルの時代を“追体験”した。
「東京ブラックホール」。
いまから5年前に放送が始まったNHKスペシャルは今回で3回目。終戦直後の1945年~1946年を扱った第一回放送の「戦後ゼロ年」、最初の東京オリンピックが行われた1964年を扱った第二回「破壊と創造の1964年」。
番組に共通するのは、俳優の山田孝之さんが、21世紀の若者にふんし、時空を超えて当時の映像の中に入り込み、追体験していく構成である。
1983年に生まれた山田さんはバブルの当時6歳。鹿児島県薩摩川内市で、両親は喫茶店を営んでいた。その街までバブルの波は届いていなかったという。
「東京ブラックホール」。
いまから5年前に放送が始まったNHKスペシャルは今回で3回目。終戦直後の1945年~1946年を扱った第一回放送の「戦後ゼロ年」、最初の東京オリンピックが行われた1964年を扱った第二回「破壊と創造の1964年」。
番組に共通するのは、俳優の山田孝之さんが、21世紀の若者にふんし、時空を超えて当時の映像の中に入り込み、追体験していく構成である。
1983年に生まれた山田さんはバブルの当時6歳。鹿児島県薩摩川内市で、両親は喫茶店を営んでいた。その街までバブルの波は届いていなかったという。
山田孝之さん
「“バブル”っていう感覚はないんです。時代っていうより、うちの家庭は、何もなかった気がします。世代としては、自分たちの親もしくは、おじいちゃんですよね。その人たちが見ると『自分たちはこんなにがつがつしてたんだ』と、素に戻れるという感じがします」
「“バブル”っていう感覚はないんです。時代っていうより、うちの家庭は、何もなかった気がします。世代としては、自分たちの親もしくは、おじいちゃんですよね。その人たちが見ると『自分たちはこんなにがつがつしてたんだ』と、素に戻れるという感じがします」

昭和天皇が崩御したこの年、宮内庁坂下門は弔問の人たちでごった返していた。この時代の映像の中に入り込んだ山田さんは、キャバクラで働く同世代の若者に出会い、アパートで暮らしながら当時を生きる人たちと出会っていく。高給ディスコでは1本200万円ものワインまで登場した。
大企業に勤めるサラリーマンはタクシー代はすべて経費で落とせた。1万円札をひらひらさせながらのタクシー争奪戦がおこり、運転手が客を選べる時代だった。
大企業に勤めるサラリーマンはタクシー代はすべて経費で落とせた。1万円札をひらひらさせながらのタクシー争奪戦がおこり、運転手が客を選べる時代だった。
バブルの時代には行きたくない
2022年に生きる山田さんはそんなバブルの時代に違和感を抱いた。
山田さん
「元気っていうか、何かすごい刺激物を与えられ続けて、みんなぶっ飛んじゃってたみたいな感じに見えました。これまで、別のドラマでも、バブルのさなかの、なんか“調子乗っちゃってる”設定のキャラクターを演じたこととかはあるんですけど…。その時代に行きたくないですね。絶対合わないです。その人たちと、感覚が。やっぱり、欲がすごすぎて。僕も欲はあるけど、なんか、その時代は『奪ってでも』頂点に上り詰めるみたいな…。要は人の上に行きたいっていう感覚がちょっとわからなくて、本当にあの時代にいたら、僕はなんかまず友達できないだろうなあ、と思うんです」
「元気っていうか、何かすごい刺激物を与えられ続けて、みんなぶっ飛んじゃってたみたいな感じに見えました。これまで、別のドラマでも、バブルのさなかの、なんか“調子乗っちゃってる”設定のキャラクターを演じたこととかはあるんですけど…。その時代に行きたくないですね。絶対合わないです。その人たちと、感覚が。やっぱり、欲がすごすぎて。僕も欲はあるけど、なんか、その時代は『奪ってでも』頂点に上り詰めるみたいな…。要は人の上に行きたいっていう感覚がちょっとわからなくて、本当にあの時代にいたら、僕はなんかまず友達できないだろうなあ、と思うんです」

国の世論調査で「日常生活に悩みや不安を感じていない」と答えた国民は過半数を超え、コロナ禍の現代とは全く違う“希望”を多くの人たちが持っていたバブルの時代。
一方でその時代を追体験した山田さんが感じたのは“息苦しさ”だったという。
一方でその時代を追体験した山田さんが感じたのは“息苦しさ”だったという。

山田さん
「もちろんどの時代も、みんながみんなではないでしょうけど、なんか息苦しかっただろうなって思いますね。とにかくみんな横見て、競い合って、上見てっていう…。あの時代は立ち止まったり、振り返ったりすることがよしとされなさそうなので。『一回ちょっとみんな落ち着いてさ、休憩しようよ』っていうと、『はっ?お前何言ってんの?』みたいな。そういう時代だから、疲れていた人が多いんじゃないかなって思います」
「もちろんどの時代も、みんながみんなではないでしょうけど、なんか息苦しかっただろうなって思いますね。とにかくみんな横見て、競い合って、上見てっていう…。あの時代は立ち止まったり、振り返ったりすることがよしとされなさそうなので。『一回ちょっとみんな落ち着いてさ、休憩しようよ』っていうと、『はっ?お前何言ってんの?』みたいな。そういう時代だから、疲れていた人が多いんじゃないかなって思います」
経済を動かすためにオフィスビルには深夜まで煌々と明かりがついていた。都心の地価は高騰し多くのサラリーマンは長い通勤時間がかかる郊外に家を求めた。終電を逃すと次の日の仕事のためにカプセルホテルに泊まる人たち…。
1989年のサラリーマンの労働時間は、今と比べて、年間400時間も多かった。
1989年のサラリーマンの労働時間は、今と比べて、年間400時間も多かった。
バブル崩壊に抗おうとした証券マン ウォール街との闘い

サラリーマンが働き続けた1989年の年末はまさにバブルのピークだった。
12月29日、東京株式市場の終値は、史上最高値となる3万9000円に迫った。市場関係者の中には、「数年後には10万円も夢ではない」と豪語する者もいた。
しかし、バブルの“終わり”は1990年とともにやってきた。年明早々、日経平均は二日連続で下落。2月には史上二番目の下げ幅となる1596円安を記録し、あっという間に3月には3万円の大台を割った。
当時、野村投信でトレーダーをしていた近藤駿介氏。
「売り」一色の相場のなかで、暴落を何とか食い止めようと、大量の「買い」注文を出していた。
12月29日、東京株式市場の終値は、史上最高値となる3万9000円に迫った。市場関係者の中には、「数年後には10万円も夢ではない」と豪語する者もいた。
しかし、バブルの“終わり”は1990年とともにやってきた。年明早々、日経平均は二日連続で下落。2月には史上二番目の下げ幅となる1596円安を記録し、あっという間に3月には3万円の大台を割った。
当時、野村投信でトレーダーをしていた近藤駿介氏。
「売り」一色の相場のなかで、暴落を何とか食い止めようと、大量の「買い」注文を出していた。

あれから32年。バブル崩壊に直面した当時の緊張感と今に続くトラウマを近藤氏が語った。
近藤駿介さん
「漠然とした根拠のなき自信っていうのが、当時の日本人はみんな持ってたんですね。みんな10万円を目指してると思ったし、それを取り巻くエコノミストであるとか、もう全員が上を向いてたんですね。だから弱気な人が一人もいない中で、何でマーケットが下がるんだっていう、何か狐につままれたような感覚でいました」
「漠然とした根拠のなき自信っていうのが、当時の日本人はみんな持ってたんですね。みんな10万円を目指してると思ったし、それを取り巻くエコノミストであるとか、もう全員が上を向いてたんですね。だから弱気な人が一人もいない中で、何でマーケットが下がるんだっていう、何か狐につままれたような感覚でいました」
近藤が勤めていた野村投信は当時、日本最大の機関投資家だった。
野村の「買い」に対抗する投資家がいるということ自体、彼らには想像がつかない事態だった。
野村の「買い」に対抗する投資家がいるということ自体、彼らには想像がつかない事態だった。
近藤さん
「80年代までだったら、野村が大量の買いを市場で入れたっていったら、まあ『提灯がつく』っていうんですけど、皆さん投資家は一斉に同じ方向に動いたんですよ。でもそのときの先物市場に関しては、野村がいくら買いを入れても、誰もついてこなかった。つまり、相場を戻せなかったんですよね」
「80年代までだったら、野村が大量の買いを市場で入れたっていったら、まあ『提灯がつく』っていうんですけど、皆さん投資家は一斉に同じ方向に動いたんですよ。でもそのときの先物市場に関しては、野村がいくら買いを入れても、誰もついてこなかった。つまり、相場を戻せなかったんですよね」
近藤氏たち野村投信の相手はウォール街だった。バブル崩壊を虎視眈々とねらっていたアメリカの証券各社は示し合せたかのように、激しい売りを浴びせていた。
彼らは当時日本でまだ浸透していなかった『裁定取引』という複雑な手法を使っていた。
裁定取引とは、先物と現物を同時に売買しながら、その価格差を利益にする手法である。暴落によって先物と現物の価格差が広がるタイミングを狙って裁定取引を仕掛け、巨額の利益を上げていた。
彼らは当時日本でまだ浸透していなかった『裁定取引』という複雑な手法を使っていた。
裁定取引とは、先物と現物を同時に売買しながら、その価格差を利益にする手法である。暴落によって先物と現物の価格差が広がるタイミングを狙って裁定取引を仕掛け、巨額の利益を上げていた。

当時、日本株に「売り」を仕掛けた金融機関グループの一つモルガン・スタンレーの幹部だったジャック・ワッズワース氏。
はじめから勝負は見えていたと語った。
はじめから勝負は見えていたと語った。
ジャック・ワッズワース氏
「当時、日本の株式市場は過大評価されていました。暴落は当然の帰結だったのです。しかも、日本の投資家で裁定取引を理解している人はほとんどいませんでした。暴落しているときに買い続ければ、大損することは間違いないのにね。私たちは正しい側にいて、野村が間違った側にいたのです。残念ですがね」
「当時、日本の株式市場は過大評価されていました。暴落は当然の帰結だったのです。しかも、日本の投資家で裁定取引を理解している人はほとんどいませんでした。暴落しているときに買い続ければ、大損することは間違いないのにね。私たちは正しい側にいて、野村が間違った側にいたのです。残念ですがね」

当時、裁定取引のリスクに気づかなかった近藤氏。負けるはずがないと信じていた野村投信の役員たちからは「外資系が先物売ってるんだったら、“締め上げてやれ”」という指示が出ていたという。
近藤さん
「締め上げてやれば、相手はギブアップすると。つまり資金の量では野村は負けることはないと思ってたんですよ。でも、売り物のかたまりを買ってもまだ売り物が出てくる。不気味でした。誰が売ってきてるんだと。だからもう何が起きてるのか正確にわかっていない。見えないとこから弾が飛んでくるっていう、形でしたからね」
「締め上げてやれば、相手はギブアップすると。つまり資金の量では野村は負けることはないと思ってたんですよ。でも、売り物のかたまりを買ってもまだ売り物が出てくる。不気味でした。誰が売ってきてるんだと。だからもう何が起きてるのか正確にわかっていない。見えないとこから弾が飛んでくるっていう、形でしたからね」

野村がいくら買っても“売り”が続く状態となったマーケット。実は資金調達の方法もウォール街には大きなアドバンテージがあった。
野村の資金調達は顧客から投資信託という形でお金を集める方法。近藤氏によれば、バブル最盛期の89年には毎月1千億円以上集め、当時の日本ではスタンダードな手段だったという。
一方でアメリカの資金調達は全く違っていた。
野村の資金調達は顧客から投資信託という形でお金を集める方法。近藤氏によれば、バブル最盛期の89年には毎月1千億円以上集め、当時の日本ではスタンダードな手段だったという。
一方でアメリカの資金調達は全く違っていた。
近藤さん
「銀行系の金融機関は、例えばJPモルガンとかは、いくらでもファイナンスで資金調達ができちゃうんですよ。世界で一番信用が高い金融機関の銀行間取引は、もう1日に、何兆円という規模で、やり取りがなされてます。そこで『1千億買いたい』って言ったら、1千億すぐ調達できてしまう。一方で、投資信託だとお客様から資金を調達しないといけない。だから、集めようと思ってもすぐに集められないんですよ」
「銀行系の金融機関は、例えばJPモルガンとかは、いくらでもファイナンスで資金調達ができちゃうんですよ。世界で一番信用が高い金融機関の銀行間取引は、もう1日に、何兆円という規模で、やり取りがなされてます。そこで『1千億買いたい』って言ったら、1千億すぐ調達できてしまう。一方で、投資信託だとお客様から資金を調達しないといけない。だから、集めようと思ってもすぐに集められないんですよ」
当時のウォール街との戦いを近藤氏は太平洋戦争に例えて振り返った。
近藤さん
「機関銃に竹槍で向かう、いや原爆に竹槍ですかね、そういう構図にはなっていたわけですね。ただ、当時は真剣だったんですよ。今の人から見ると、愚かだと思うかもしれないけど、気がつかなかったんです」
「機関銃に竹槍で向かう、いや原爆に竹槍ですかね、そういう構図にはなっていたわけですね。ただ、当時は真剣だったんですよ。今の人から見ると、愚かだと思うかもしれないけど、気がつかなかったんです」
近藤氏の同僚の中には病気になる人も相次ぎ、そのうちの何人かは数年後に亡くなった。近藤氏自身も今も薬が手放せないという。
近藤さん
「悪いことばっかり考える日が何か月も続いた。『朝起きたとき、どういうふうになってるんだ』っていうことを考えると眠れなくなって安定剤を飲んで寝る…。あれから三十数年経ちましたが、今でもそれがないと眠れないですね」
「悪いことばっかり考える日が何か月も続いた。『朝起きたとき、どういうふうになってるんだ』っていうことを考えると眠れなくなって安定剤を飲んで寝る…。あれから三十数年経ちましたが、今でもそれがないと眠れないですね」
バブル崩壊を見たアッコちゃん

バブル崩壊の波はアッコにも訪れていた。
川添明子さん
「銀行も潰れたじゃないですか。父は銀行のOBだったので、2日ぐらい寝込んでいました。持っていた株も全部なくなっちゃって」
「銀行も潰れたじゃないですか。父は銀行のOBだったので、2日ぐらい寝込んでいました。持っていた株も全部なくなっちゃって」
周りでバブルを謳歌していた人々も次々と姿を見せなくなった。
川添さん
「『ああ、あの人もやっぱりいなくなっちゃったんだ』とか、逆に『えーっあの人が』みたいなこともありますけど、次々いなくなっていく。何かこう胸が酸っぱくなるというか。お祭りの後の屋台を片してる風景を見るみたいな感じでした」
「『ああ、あの人もやっぱりいなくなっちゃったんだ』とか、逆に『えーっあの人が』みたいなこともありますけど、次々いなくなっていく。何かこう胸が酸っぱくなるというか。お祭りの後の屋台を片してる風景を見るみたいな感じでした」
まるで、1929年の大恐慌後の時代を描いた、フィッツジェラルドの「バビロン再訪」の冒頭のような描写である。およそ百年前のアメリカも、この成長は永遠に続くという夢に酔っていた。バブルの象徴だったアッコはその時代をこう振り返る。
川添さん
「本当に日本が初めてお金持ちになって、戦後ずっと、頑張って、頑張って、頑張ってきて、『やっとお金持ちなった。わーい』って、遊んじゃったらはじけた、そんな時代でした。ただ、その時代はみんなが『楽しみたい』ってあがいてたんだと思います。何か知恵を出して楽しくしようと、遊んでる側も店側も考えてもっと楽しむ、そういうことにエネルギーを使っていました。だから楽しかったんじゃないかなと」
「本当に日本が初めてお金持ちになって、戦後ずっと、頑張って、頑張って、頑張ってきて、『やっとお金持ちなった。わーい』って、遊んじゃったらはじけた、そんな時代でした。ただ、その時代はみんなが『楽しみたい』ってあがいてたんだと思います。何か知恵を出して楽しくしようと、遊んでる側も店側も考えてもっと楽しむ、そういうことにエネルギーを使っていました。だから楽しかったんじゃないかなと」
バブルは、確かにイノセントな時代だった。その時代をくぐり抜けて、日本の社会は成熟を目指すことになった。
しかし何をもって、「成熟」とするかは難しい。今の日本で目につくのは、「成熟」よりも「あきらめ」かもしれない。
しかし何をもって、「成熟」とするかは難しい。今の日本で目につくのは、「成熟」よりも「あきらめ」かもしれない。

バブルの時代に結婚し、子どもを産み、現在はさまざまなビジネスを展開するアッコこと川添明子氏。
現代まで長く続く日本の迷走の元凶とも言われるバブル。
そして新型コロナウイルスの感染拡大。
「不安」を抱える“現代”をバブルの時代と対比しながら独特の目線で見ている。
現代まで長く続く日本の迷走の元凶とも言われるバブル。
そして新型コロナウイルスの感染拡大。
「不安」を抱える“現代”をバブルの時代と対比しながら独特の目線で見ている。
川添さん
「日本は賢くなったんじゃないかって思います。バブルによって。『あんなことしていたらダメだ』というのを学んだんじゃないですか。バブルの時はただもう右へ倣えみたいな感じがあって、隣の人がお金借りているから、オレも借りちゃえみたいな、そんな感じでした。一方で“現代”は、自信がない、みんな冒険しなくなっちゃった。日本は、清潔だし、物価も安いし、安全だし、人が親切だし、何で今、そんなに元気ないんですかって言いたいです。なのに、何してんですか?って。今は、つまらない。遊ぶ側もお店側も、この知恵を出して、何か楽しませようっていうのがないと感じます」
「日本は賢くなったんじゃないかって思います。バブルによって。『あんなことしていたらダメだ』というのを学んだんじゃないですか。バブルの時はただもう右へ倣えみたいな感じがあって、隣の人がお金借りているから、オレも借りちゃえみたいな、そんな感じでした。一方で“現代”は、自信がない、みんな冒険しなくなっちゃった。日本は、清潔だし、物価も安いし、安全だし、人が親切だし、何で今、そんなに元気ないんですかって言いたいです。なのに、何してんですか?って。今は、つまらない。遊ぶ側もお店側も、この知恵を出して、何か楽しませようっていうのがないと感じます」
現代は“十分平和で潤っている”

番組の撮影でバブルの時代に入り込み、その映像の中から“帰ってきた”俳優の山田孝之さんは、アッコと違う目で現代を見るようになったという。
それは、活力が失われたと言われる2022年も、そう悪くはないのではないか、という感覚だった。
それは、活力が失われたと言われる2022年も、そう悪くはないのではないか、という感覚だった。
山田さん
「なんかバブルの時代よりは今の世代のほうが気楽に生きられてるんじゃないか、ちょっと安心して生きられるんじゃないかなとは思います。僕の学生時代よりもっと前にバブルがあった。いま考えると、バブルがはじけて下がったところから“上がっているんじゃなか”って、すごく思ってます。国の借金のこととか…いろんな数字はありますけど。それでも、人から奪ったりもせずにみんな食べていけて、もう一般的に生きていけてるから、十分平和で潤ってるんじゃないかと思っています」
「なんかバブルの時代よりは今の世代のほうが気楽に生きられてるんじゃないか、ちょっと安心して生きられるんじゃないかなとは思います。僕の学生時代よりもっと前にバブルがあった。いま考えると、バブルがはじけて下がったところから“上がっているんじゃなか”って、すごく思ってます。国の借金のこととか…いろんな数字はありますけど。それでも、人から奪ったりもせずにみんな食べていけて、もう一般的に生きていけてるから、十分平和で潤ってるんじゃないかと思っています」
4月下旬。バブルの時代の証言者たちにインタビューを行った取材班は多摩美術大学を訪れていた。学生たちに取材や番組制作の過程を直に伝えたかったからだ。
過去の映像と現代の俳優を合成するVFXの手法、時代や風俗を表現するためのロケーションや工夫など、現代にバブルの時代を甦らせる「東京ブラックホールIII」の舞台裏を語った。
集まった大学生は当時のアッコと同世代。
バブル当時、まだ生まれていなかった現代の若者たちが、放送や記事を通じて出会う“時代の証言者たち”の言葉から、今を生きる何かのヒントを見つけてくれたらと願うばかりである。
山田孝之さんが、バブルという狂乱の時代を追体験したNHKスペシャル「東京ブラックホールIII 1989-1990 魅惑と罪のバブルの宮殿」
過去の映像と現代の俳優を合成するVFXの手法、時代や風俗を表現するためのロケーションや工夫など、現代にバブルの時代を甦らせる「東京ブラックホールIII」の舞台裏を語った。
集まった大学生は当時のアッコと同世代。
バブル当時、まだ生まれていなかった現代の若者たちが、放送や記事を通じて出会う“時代の証言者たち”の言葉から、今を生きる何かのヒントを見つけてくれたらと願うばかりである。
山田孝之さんが、バブルという狂乱の時代を追体験したNHKスペシャル「東京ブラックホールIII 1989-1990 魅惑と罪のバブルの宮殿」
詳しくはこちら

多摩美術大学での学生たち、出演した伊原六花さん、番組のディレクターとのトークイベントについての記事はこちらから
NHKのサイトを離れます
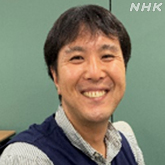
丸山 拓也
2007年入局、鹿児島局、制作局、仙台局などを経て、2022年から制作局。クローズアップ現代やNHKスペシャルなど、ドキュメンタリー番組を中心に担当。
2007年入局、鹿児島局、制作局、仙台局などを経て、2022年から制作局。クローズアップ現代やNHKスペシャルなど、ドキュメンタリー番組を中心に担当。

大久保 圭祐
2009年入局、仙台局、制作局を経て現プロジェクトセンター勤務。
過去にプロフェッショナル仕事の流儀、クローズアップ現代、NHKスペシャルなどを担当。
2009年入局、仙台局、制作局を経て現プロジェクトセンター勤務。
過去にプロフェッショナル仕事の流儀、クローズアップ現代、NHKスペシャルなどを担当。