“カルビ”も“ツナ”も大豆から 代替食品の可能性は?

“畑のお肉”といえば、そう、大豆です。昔からあるこのたとえ。聞いたことあると思いますが、いま、たとえではなく、“お肉”の新ジャンルになろうとしています。「代替肉」とか「植物肉」と呼ばれています。ホンモノに代わる?それともホンモノを超える?可能性はどうなのでしょうか。(おはよう日本 おはBizキャスター 布施谷博人 ディレクター 天城亮太郎)
世界で盛り上がる代替肉
ずいぶん前から、大豆やえんどう豆などのたんぱく質でできた「代替肉」のことが気になっていました。
アメリカのフードテック企業が、見た目も、味も、牛肉のミンチそっくりの代替肉を開発。
スーパーでは、ホンモノの肉と一緒に売られている…。
大手のバーガーチェーンで代替肉バーガーの販売が始まった…。
そんなニュースが、海外から次々と発信されていたからです。
アメリカのフードテック企業が、見た目も、味も、牛肉のミンチそっくりの代替肉を開発。
スーパーでは、ホンモノの肉と一緒に売られている…。
大手のバーガーチェーンで代替肉バーガーの販売が始まった…。
そんなニュースが、海外から次々と発信されていたからです。

そうこうしているうちに日本でも「代替肉」を見ることが増えてきました。
この間、立ち寄ったバーガー店のメニューにあるのを発見しましたし、スーパーの棚でも、ハンバーグやミートボールなどを、ちらほら見かけるようになってます。
この間、立ち寄ったバーガー店のメニューにあるのを発見しましたし、スーパーの棚でも、ハンバーグやミートボールなどを、ちらほら見かけるようになってます。
開発の最前線に潜入!
では、日本では、どんな動きが出ているのだろう?
ということで先日、新潟県長岡市に向かいました。
そこに創業1年あまりの代替肉ベンチャーの研究拠点があったからです。
「ネクストミーツ」という会社です。
ということで先日、新潟県長岡市に向かいました。
そこに創業1年あまりの代替肉ベンチャーの研究拠点があったからです。
「ネクストミーツ」という会社です。

開発の最前線を見たいとお願いしたところ、創業者の白井良さんとチームのみなさんが迎えてくれました。
ベンチャーらしく、少々雑然とした研究室が印象的でした。
ベンチャーらしく、少々雑然とした研究室が印象的でした。
この会社を取材したのは、作っているモノが、ユニークだったからです。
代替肉というと、やはりバーガーのパティのようなミンチ状のものが多いのですが、この会社は、肉の形をした製品づくりがこだわりです。
焼き肉のカルビ、ハラミに似せたスライス状の商品もあれば、厚みのある代替チキンもあります。
フライパンで“肉”をジューッと加熱すると、しっかり焼き色もつきます。
代替肉というと、やはりバーガーのパティのようなミンチ状のものが多いのですが、この会社は、肉の形をした製品づくりがこだわりです。
焼き肉のカルビ、ハラミに似せたスライス状の商品もあれば、厚みのある代替チキンもあります。
フライパンで“肉”をジューッと加熱すると、しっかり焼き色もつきます。

ためしに代替カルビをひと口。
弾力ある歯ごたえは、ホンモノのようでした。
弾力ある歯ごたえは、ホンモノのようでした。
ちょっと変わったところでは、代替ツナの缶詰も販売していますし、黄色があざやかな代替タマゴも開発中です。

代替タマゴであれば、卵アレルギーに悩む人でも食べることができます。
代替肉が地球を救う?
なぜ、いま代替肉なのか。
健康志向や食の多様化もありますが、それ以上に、地球環境や食料問題に対する意識の高まりがあります。
白井さんも、地球環境の課題をビジネスで解決したいと模索する中で、この代替肉にたどりついたといいます。
例えば、牛肉1キロを生産するのに、11キロの穀物がエサとして消費されています。
飼育には大量の水も使い、牛の「げっぷ」が温室効果ガスの発生源にもなっていると指摘されます。
健康志向や食の多様化もありますが、それ以上に、地球環境や食料問題に対する意識の高まりがあります。
白井さんも、地球環境の課題をビジネスで解決したいと模索する中で、この代替肉にたどりついたといいます。
例えば、牛肉1キロを生産するのに、11キロの穀物がエサとして消費されています。
飼育には大量の水も使い、牛の「げっぷ」が温室効果ガスの発生源にもなっていると指摘されます。

ならば肉のかわりに植物性タンパクを食べた方が、環境負荷ははるかに小さく、将来の食料危機への備えにもなる。
そう考えたといいます。
「現在、世界の食肉市場の規模はざっくり200兆円。仮に1%が代替肉に置き換われば2兆円の市場が生まれる」。
そういう読みもあったそうです。
そう考えたといいます。
「現在、世界の食肉市場の規模はざっくり200兆円。仮に1%が代替肉に置き換われば2兆円の市場が生まれる」。
そういう読みもあったそうです。
“肉”の食感、どう再現
では、代替肉はどうやって作っているのでしょう。
“牛肉”も“鶏肉”も主原料は大豆パウダーです。
“牛肉”も“鶏肉”も主原料は大豆パウダーです。

それをエクストルーダーという加工用の機械で、練って、加熱・加圧、そして“お肉”風の形に成形します。
その際、「熱、圧力、水分量」を微妙に調整するのがノウハウだそうです。
それぞれの数値を変えると、分子結合の状態が変わり、原料は同じなのに、いかにも牛や鶏といった食感を作り出せるのだそうです。
その際、「熱、圧力、水分量」を微妙に調整するのがノウハウだそうです。
それぞれの数値を変えると、分子結合の状態が変わり、原料は同じなのに、いかにも牛や鶏といった食感を作り出せるのだそうです。

例えば“鶏肉”は筋繊維のような形状がしっかりと再現されていました。

「爆速」で世界へ
こうした肉質感を出せるようになるまで3年間、ひたすら研究を続け、商品化のめどがついたことから去年、会社を設立。
現在は13種類の商品を販売。
スーパーや焼き肉チェーンにも販路を広げ、シンガポールなど海外にも進出しています。
現在は13種類の商品を販売。
スーパーや焼き肉チェーンにも販路を広げ、シンガポールなど海外にも進出しています。
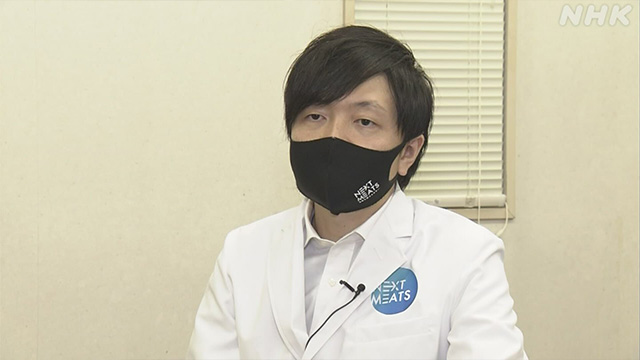
白井さん
「日本ブランドとして一気に世界に出ていく。これを“爆速”でやる。いま作っているのは、肉に似せたモノですが、いずれは、肉を超えるモノを作りたい。肉の代替品ではなく、新しい食べ物として定着していくといいなと思っています」
「日本ブランドとして一気に世界に出ていく。これを“爆速”でやる。いま作っているのは、肉に似せたモノですが、いずれは、肉を超えるモノを作りたい。肉の代替品ではなく、新しい食べ物として定着していくといいなと思っています」
まだ、もの珍しい代替肉が、世界の食卓でごく普通に食べられるようになれば。
白井さんが目指す未来です。
白井さんが目指す未来です。
海の幸も大豆から
ところで、大豆から作られるのは“肉”だけではありません。
海の高級食材“ウニ”も登場しています。
海の高級食材“ウニ”も登場しています。

開発したのは、1950年創業の「不二製油」。
パームやヤシなどを原料に、食用油やチョコレート用の油脂をつくるメーカーです。
業務用チョコレートの販売では世界トップ3に入る大手です。
大豆のたんぱく質の可能性に早くから注目して、研究・開発を続け、大豆ハンバーグやシューマイなどの原料になる、たんぱく素材を生産してきました。
蓄積した技術で、大豆からコクのある豆乳クリームをつくる特許も持っています。
この特許技術を使って開発したのが「代替ウニ」です。
ウニのねっとりとした舌触りを再現しました。
パームやヤシなどを原料に、食用油やチョコレート用の油脂をつくるメーカーです。
業務用チョコレートの販売では世界トップ3に入る大手です。
大豆のたんぱく質の可能性に早くから注目して、研究・開発を続け、大豆ハンバーグやシューマイなどの原料になる、たんぱく素材を生産してきました。
蓄積した技術で、大豆からコクのある豆乳クリームをつくる特許も持っています。
この特許技術を使って開発したのが「代替ウニ」です。
ウニのねっとりとした舌触りを再現しました。
こちらはウニドリア。

開発した「代替ウニ」。
さまざまな料理にアレンジが可能です。
さまざまな料理にアレンジが可能です。
日本らしい代替食材
会社では、代替食品への関心が世界で高まる中、ウニのような“日本らしい食材”を作ってビジネスを拡大しようとしています。
代替ウニは、本物と比べ日持ちがよいため、すでに飲食店やホテルなどから引き合いがきています。

鈴木さん
「日本なりの植物性食品を展開していけば、きっとおもしろいものができてくる。非常に手応えを感じています」
「日本なりの植物性食品を展開していけば、きっとおもしろいものができてくる。非常に手応えを感じています」
今はホンモノの代わりという意味で「代替食品」と言われています。
ホンモノを超えるかはともかく、そのうち「きのうは動物のお肉だったので、きょうは大豆の“お肉”で」と、ホンモノと並ぶ食品になる可能性はありそうです。
おいしく食べて、社会課題の解決にもつながる。
そんな技術が日本から広がるといいなと感じます。
ホンモノを超えるかはともかく、そのうち「きのうは動物のお肉だったので、きょうは大豆の“お肉”で」と、ホンモノと並ぶ食品になる可能性はありそうです。
おいしく食べて、社会課題の解決にもつながる。
そんな技術が日本から広がるといいなと感じます。

おはよう日本 おはBizキャスター(経済部デスク)
布施谷 博人
平成5年入局
経済部で金融の現場や財務省を取材
アメリカ・ワシントンに駐在しTPPや金融政策を取材した
布施谷 博人
平成5年入局
経済部で金融の現場や財務省を取材
アメリカ・ワシントンに駐在しTPPや金融政策を取材した

ディレクター
天城 亮太郎
平成27年入局
松江放送局を経て経済番組を担当
eスポーツやフードテックなど最新のトレンドや技術を取材
天城 亮太郎
平成27年入局
松江放送局を経て経済番組を担当
eスポーツやフードテックなど最新のトレンドや技術を取材