緊急事態宣言で保育所はどうなる?自治体で対応分かれる
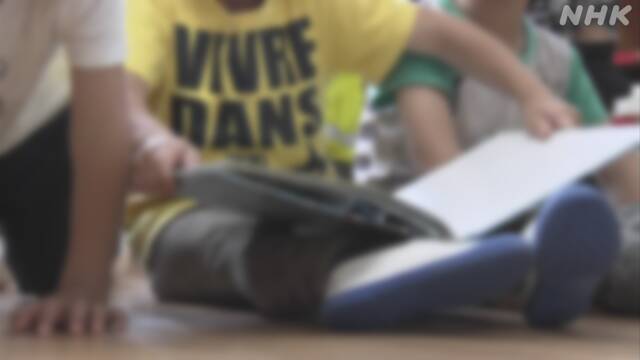
緊急事態宣言を受けて、国が保育所の受け入れを縮小するよう求める中、都内の62の自治体に「認可保育所」の対応を取材したところ、46の自治体が保護者に通園の自粛を要請するのにとどめている一方、12の自治体では「原則休園」とするなど、自治体によって対応が分かれていることがわかりました。
「自粛要請」が最多
NHKでは「認可保育所」の対応について、都内の62の市区町村に取材しました。その結果、9日時点で通園の「自粛要請」が46自治体と最も多く、次いで「原則休園」が12自治体、「平時と同じ」が2自治体、「検討中」が2自治体と自治体によって対応がわかれていることがわかりました。
「原則休園」でも柔軟に対応
ただし「原則休園」とした12の自治体でも、保護者が子どもの面倒を見ることが難しい場合は、引き続き保育所で子どもを預かることにしているということです。
その場合ほとんどの自治体は、ふだん通園している保育所を開けて子どもを預かることにしていますが、渋谷区では区内の8つの保育所だけを開けて子どもを集めて対応するということです。
その場合ほとんどの自治体は、ふだん通園している保育所を開けて子どもを預かることにしていますが、渋谷区では区内の8つの保育所だけを開けて子どもを集めて対応するということです。
預かる子どもは保護者の職業で
またどのような家庭の場合に保育所で子どもを預かるかについても、自治体の対応は分かれています。
保護者の職業を医療関係者の場合や警察や消防、インフラ関係など社会機能の維持に必要な職種に限る自治体がある一方で、例えば墨田区では、「世帯全員の保護者が仕事を継続しなければならない場合」としているほか、文京区では、「職種にかかわらず保護者から申し出があれば原則として受け入れる」とするなど、職種を限定しない自治体もあります。
保護者の職業を医療関係者の場合や警察や消防、インフラ関係など社会機能の維持に必要な職種に限る自治体がある一方で、例えば墨田区では、「世帯全員の保護者が仕事を継続しなければならない場合」としているほか、文京区では、「職種にかかわらず保護者から申し出があれば原則として受け入れる」とするなど、職種を限定しない自治体もあります。
保護者から切実な声も
自治体の担当者によりますと、保護者からは「会社に行けないのでなんとか子どもを預かってほしい」という切実な声がある一方で、「会社を休んで自宅で保育を行うためにも『休園』など明確な対応をとってほしい」といった声も多く寄せられているということです。
また休園や自粛の判断についての統一的な基準が無く、自治体ごとに対応が分かれているため、保護者からは「なぜ同じ都内なのに住んでいる地域で対応が異なるのか」といった問い合わせがあり、対応に苦慮している自治体もあります。
また休園や自粛の判断についての統一的な基準が無く、自治体ごとに対応が分かれているため、保護者からは「なぜ同じ都内なのに住んでいる地域で対応が異なるのか」といった問い合わせがあり、対応に苦慮している自治体もあります。
保育現場からは困惑の声も
保育の現場では行政から示された子どもの受け入れ基準があいまいで、それぞれの保育所に判断が任されていることに困惑の声も上がっています。
このうち、東京 世田谷区の尾山台保育園では、区から示されている「仕事が休める家庭は登園の自粛をお願いする」という方針も踏まえて極力自宅での保育をお願いするなどしています。
園内での感染を防ぐためにも、預かる子どもの人数を減らさざるをえないと考えていますが、保護者からは「在宅勤務をしているが子どもの世話と仕事が両立できないので預かってほしい」といった声もあり、対応に苦慮しているということです。
また「園内では子どもが大勢で過ごしているので感染が心配だ」といった声や、「感染のリスクを減らすために自宅で保育を行おうと思っても保育園を『休園』にしてくれないと仕事が休めない。しっかり基準をつくってほしい」といった声も寄せられているということです。
2歳の娘を保育園に通わせている男性は、「在宅勤務をしていますが、来週から保育園を休ませることにしました。こういう状況で園も大変だと思うので、家で子どもの面倒を見るのは大変ですが協力したいと思います」と話していました。
遠山拓郎園長は「区から、どういった人なら受け入れるといった具体的な方針が示されていないので、こちらでなんとか保護者に協力をお願いしています。保育士の中には自分の子どもを保育所に預けられなくなる人もいて、このままでは保育園の体制を維持するのも難しいです。休園するならするで、方針を打ち出してもらい、本当に保育が必要な人に届くようにしたいです。早くしっかりとした基準を示してほしいと切実に願っています」と話していました。
このうち、東京 世田谷区の尾山台保育園では、区から示されている「仕事が休める家庭は登園の自粛をお願いする」という方針も踏まえて極力自宅での保育をお願いするなどしています。
園内での感染を防ぐためにも、預かる子どもの人数を減らさざるをえないと考えていますが、保護者からは「在宅勤務をしているが子どもの世話と仕事が両立できないので預かってほしい」といった声もあり、対応に苦慮しているということです。
また「園内では子どもが大勢で過ごしているので感染が心配だ」といった声や、「感染のリスクを減らすために自宅で保育を行おうと思っても保育園を『休園』にしてくれないと仕事が休めない。しっかり基準をつくってほしい」といった声も寄せられているということです。
2歳の娘を保育園に通わせている男性は、「在宅勤務をしていますが、来週から保育園を休ませることにしました。こういう状況で園も大変だと思うので、家で子どもの面倒を見るのは大変ですが協力したいと思います」と話していました。
遠山拓郎園長は「区から、どういった人なら受け入れるといった具体的な方針が示されていないので、こちらでなんとか保護者に協力をお願いしています。保育士の中には自分の子どもを保育所に預けられなくなる人もいて、このままでは保育園の体制を維持するのも難しいです。休園するならするで、方針を打ち出してもらい、本当に保育が必要な人に届くようにしたいです。早くしっかりとした基準を示してほしいと切実に願っています」と話していました。
ネット上でもさまざまな声
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、ネット上では、保育所に子どもを預けることをめぐって、さまざまな声が上がっています。
SNSには「感染のリスクが高いなか、子どもを預けることが、子どもにとっても保育士にとっても心配です。どうか保育園を休園に」、「幼稚園、保育所は、完全なる3密です。今すぐ休園しないと」などといった、感染のリスクを心配する声が上がっています。
一方で、休園や利用自粛を求める動きに対して、「しかたないのは理解するけど、在宅勤務に対する理解度が低いなと思い知らされる」といった、仕事への影響を懸念する声も上がっています。
SNSには「感染のリスクが高いなか、子どもを預けることが、子どもにとっても保育士にとっても心配です。どうか保育園を休園に」、「幼稚園、保育所は、完全なる3密です。今すぐ休園しないと」などといった、感染のリスクを心配する声が上がっています。
一方で、休園や利用自粛を求める動きに対して、「しかたないのは理解するけど、在宅勤務に対する理解度が低いなと思い知らされる」といった、仕事への影響を懸念する声も上がっています。